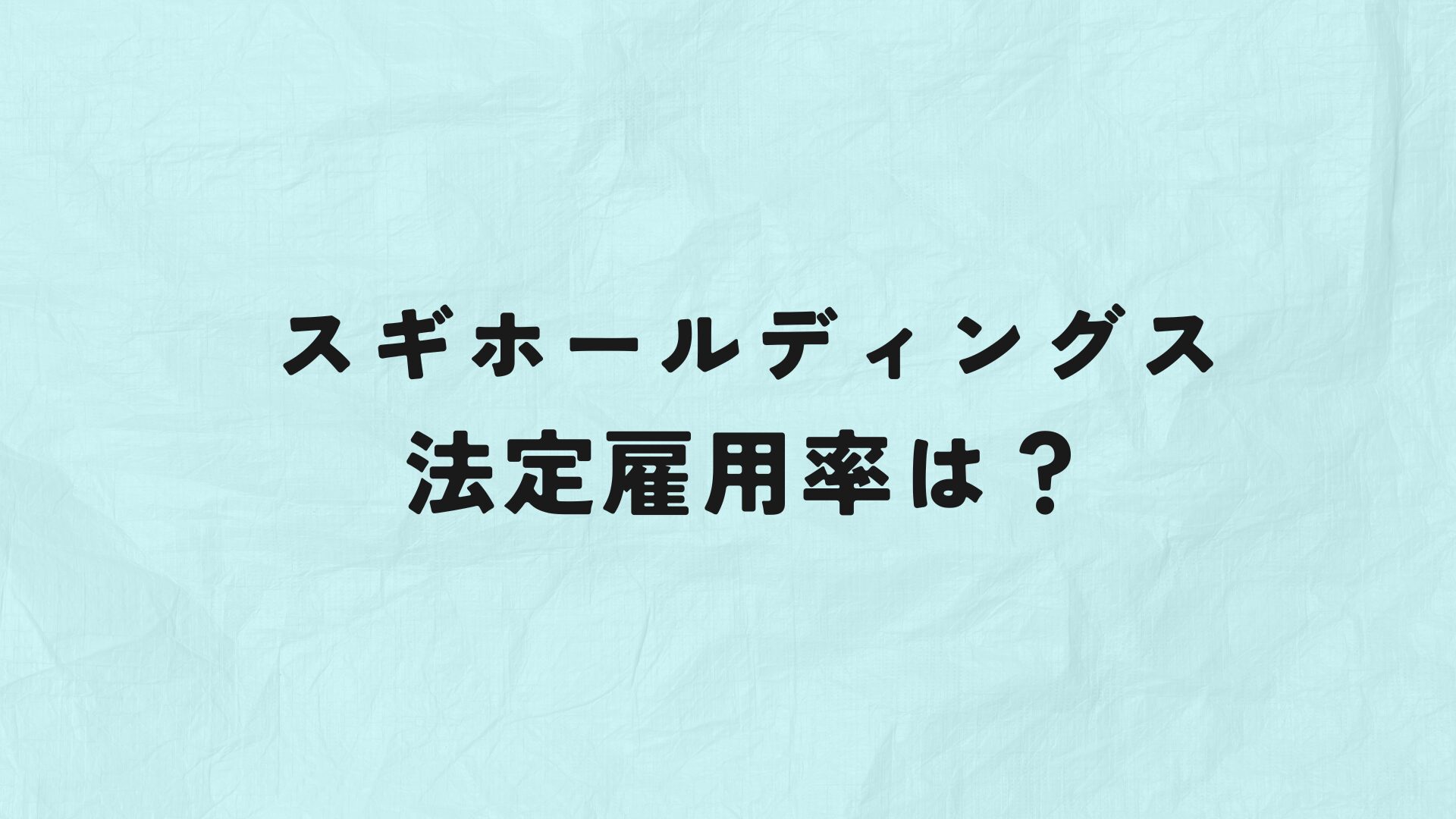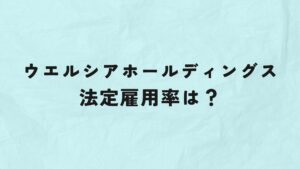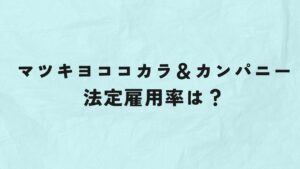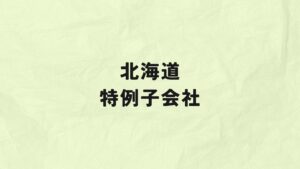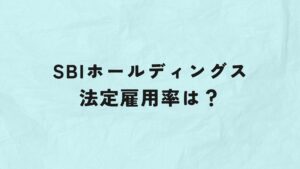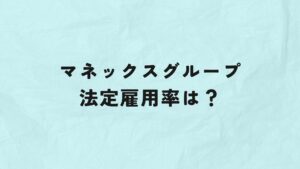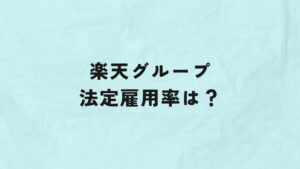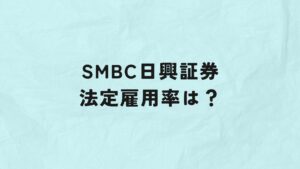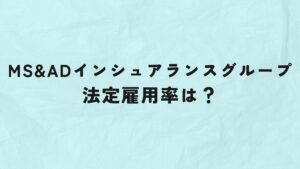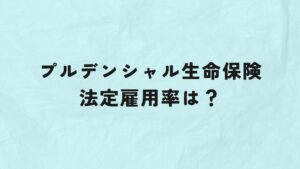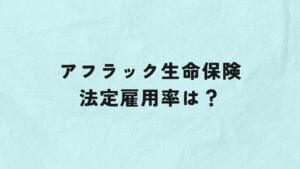「スギホールディングスは法定雇用率を達成しているの?」そんな疑問をわかりやすく解説します。
スギホールディングス株式会社とは?

会社概要
| 会社名 | スギホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県大府市横根町新江62番地の1 |
| 設立 | 1982年3月(スギ薬局創業1976年) |
| 代表 | 代表取締役社長 杉浦 克典 |
| 資本金 | 154億3,400万円 |
| 従業員数 | 11,820名(2025年2月末現在) |
| 上場市場 | プライム市場(7649) |
| 公式サイト | https://www.sugi-hd.co.jp/ |
主な事業内容
スギホールディングスは、ドラッグストア「スギ薬局」を中心に、調剤薬局、在宅医療、介護サービスなど幅広い事業を展開しています。医薬品・化粧品・日用品の販売に加え、地域包括ケアに貢献する「医療モール」型の店舗展開や在宅訪問サービスなど、地域の健康を支えるトータルヘルスケア企業を目指しています。
グループの規模と特徴
グループ全体で全国1,600店舗以上を展開しており、中部・関西・関東エリアを中心に成長を続けています。調剤併設率は業界トップクラスで、ヘルスケアと在宅医療分野の強化を特徴としています。
また、地域に密着した店舗運営により、患者・顧客との信頼関係を重視する経営スタイルが特色です。
グループ会社
| 会社名 | 事業領域 | 公式サイト |
|---|---|---|
| スギ薬局株式会社 | ドラッグストア事業 | https://www.drug-sugi.co.jp/ |
| スギメディカル株式会社 | 医療コンサルティング | https://www.sugi-hd.co.jp/sugi-medical/ |
| 株式会社Sトレーディング | 海外事業 | https://www.strading.co.jp/ |
| スギナーシングケア株式会社 | 訪問看護・介護支援 | https://www.sugi-nursingcare.co.jp/ |
| 株式会社DCPソリューション | 医師開業支援 | https://dcp-sol.com/ |
| 株式会社MCS | 医療スタッフの人材支援 | https://www.mcs-cadical.co.jp/ |
| 株式会社CoMediCs | 医療機関支援・コンサルティング | https://www.comedics.co.jp/ |
| スギスマイル株式会社 | 障害者雇用推進(特例子会社) | https://www.sugi-smile.co.jp/ |
| スギウェルネス株式会社 | 疾病予防支援 | https://www.sugi-wellness.co.jp/ |
上記に加えて、ひかりファーマ、薬日本堂、ファルマシステムズなど、個別に異なる事業領域の関連会社も多数存在します。
スギホールディングスの障害者雇用について
障害者雇用に関する基本方針
スギホールディングスでは、企業理念である「まごころを込めたサービス」を実現するために、多様な人材が活躍できる環境づくりを重視しています。特にダイバーシティ&インクルージョンの推進を掲げ、障害のある方の雇用と定着を重要な経営課題のひとつと位置づけています。
店舗での接客やバックヤード業務、本社部門での事務作業など、個々の適性に合わせた幅広い職域を用意し、長く安心して働ける環境づくりを進めています。
スギホールディングスに特例子会社はあるの?

スギホールディングスには、障害者雇用を専門に担うスギスマイル株式会社があります。2019年に愛知県大府市に設立された特例子会社で、障害のある社員が安心して働き続けられる環境を提供することを目的としています。
スギスマイルは、従業員一人ひとりの能力や適性に応じた業務を割り振り、グループ全体のバックオフィス業務や店舗支援を担っています。設立以来、スギホールディングスの障害者雇用を支える中核的な存在となっています。
| 会社名 | スギスマイル株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県大府市横根町新江62番地の1(スギホールディングス本社内) |
| 設立 | 2019年4月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 販促物・名札の制作、清掃、消耗品のセット作業、事務補助、軽作業など |
| 公式サイト | https://www.sugi-smile.co.jp/ |
スギスマイルでは、主に以下のような業務が行われています。
- 店舗で使用する名札や販促物の制作・発送
- 商品の袋詰め、販促用サンプルのセット作業
- 社内の文書スキャンやデータ入力といった事務補助業務
- オフィスや共用スペースの清掃、整理整頓
また、採用にあたっては特別支援学校や就労支援機関と積極的に連携し、入社後はジョブコーチや支援スタッフが定着を支援する体制を整えています。
単に雇用するだけでなく、「定年まで安心して働き続けられる会社」を目指しており、障害のある社員がキャリアを積み重ねられる仕組みを用意している点も特徴です。
具体的な雇用の取り組み事例
スギスマイルでは、特別支援学校や就労支援機関と連携して、採用から職場定着まで一貫したサポートを行っています。入社後は、社内のジョブコーチや支援スタッフが個別にフォローを行い、安心して働き続けられる体制を整えています。
また、店舗では障害のある従業員が商品の補充・整理、カゴやカートの回収、バックヤードでの仕分け作業などに従事しており、顧客や地域社会に貢献する形で活躍の場を広げています。
法定雇用率とは?
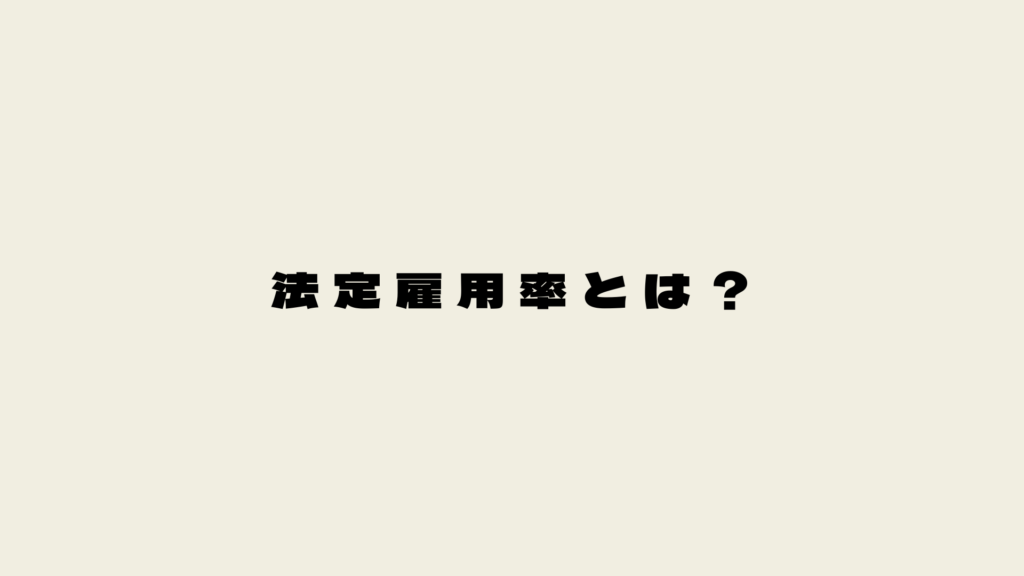
法定雇用率の定義と仕組み
法定雇用率とは、企業や行政機関が雇用する従業員の総数に対して、一定割合以上の障害者を雇用することを義務づけた制度です。障害者雇用促進法に基づき定められており、「障害のある方の雇用機会を確保し、社会参加を促進する」ことを目的としています。
この制度は1986年から本格的に運用され、経済や雇用環境の変化に合わせて数年ごとに段階的に引き上げられてきました。民間企業・国や自治体・教育委員会など、組織の区分ごとに定められる雇用率は異なります。
対象企業と義務内容
民間企業では、常用労働者が43.5人以上いる場合に法定雇用率が適用されます。
雇用率を満たしていない場合は「障害者雇用納付金」(不足人数1人あたり月額5万円)を納める義務があり、逆に基準を超えて雇用している企業には調整金や奨励金が支給される仕組みがあります。
さらに、基準を長期にわたって満たしていない場合は企業名の公表や行政指導の対象となることもあり、企業経営にとっても大きな影響を与える制度となっています。
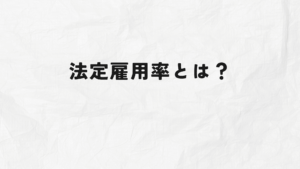
計算方法と対象労働者
必要な障害者の雇用人数は、常用労働者数 × 法定雇用率で算出されます。
例えば、従業員が10,000人の場合、現在(2024年4月以降)の法定雇用率2.5%を適用すると250人以上の障害者雇用が必要です。2026年7月からは2.7%となるため、必要人数は270人以上に増えます。
また、算定対象となる労働者の範囲やカウント方法には以下のルールがあります。
- 週30時間以上勤務:1人としてカウント
- 週20時間以上30時間未満勤務:0.5人としてカウント
- 重度身体障害者・重度知的障害者(短時間勤務):1人としてカウント
- 精神障害者も2018年以降、雇用率算定に含まれるようになった
- 在宅勤務(テレワーク)など多様な就労形態も一定条件で算入可能
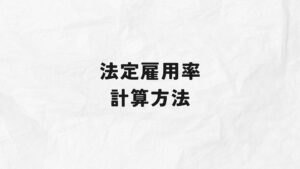
法定雇用率の推移
近年の法定雇用率の推移は以下のとおりです。
| 施行時期 | 民間企業の法定雇用率 |
|---|---|
| 2018年4月~ | 2.2% |
| 2021年3月~ | 2.3% |
| 2024年4月~ | 2.5% |
| 2026年7月~ | 2.7%(予定) |
このように、法定雇用率は社会状況に合わせて引き上げられており、今後も障害者雇用の拡大が求められることが明らかです。
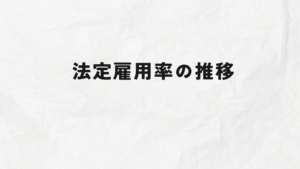
スギホールディングスの法定雇用率は?
直近の障害者雇用率
スギホールディングス全体の具体的な障害者雇用率は公表されていません。ただし、2019年に設立された特例子会社スギスマイル株式会社において、多数の障害者雇用が進められています。
スギスマイルでは、名札や販促物の制作、清掃、軽作業、事務補助などを障害のある社員が担当し、グループ全体の雇用率向上に大きく貢献しています。
法定雇用率達成状況
スギホールディングスのグループ従業員数は約12,000人とされています。
現在の法定雇用率2.5%(2024年4月〜)に基づく必要な雇用人数は300人以上、さらに2026年7月からの2.7%では324人以上となります。
今後の取り組み予定
2026年以降も段階的な法定雇用率の引き上げが予定されており、さらなる雇用機会の拡大が求められます。
スギホールディングスでは、特例子会社での体制強化だけでなく、店舗や本部での職域開拓、支援機関との連携強化を進めることで、障害のある方が長く安心して働ける環境づくりを推進していくことが期待されます。
スギホールディングスの法定雇用率は?

直近の障害者雇用率
スギホールディングスの最新の公開データによると、2023年度(2024年2月期)の障害者雇用率は2.43%となっています。過去の推移を見ると、2020年度は2.80%、2021年度は2.58%、2022年度は2.36%と推移しており、直近は2.4%前後で推移していることがわかります。
この数値は、2024年4月から引き上げられた法定雇用率2.5%にはわずかに届いていない水準です。ただ2024年以降の数字は出ていませんので達成している可能性も考えられます。こちらは今後、最新情報が出次第更新をしていきます。
今後の取り組み予定
2026年以降の法定雇用率引き上げに備え、さらなる雇用拡大が求められます。特例子会社での体制強化に加え、店舗や本部での新しい職域づくり、支援機関との連携を通じて、障害のある方が安心して長く働ける仕組みづくりが期待されます。
『流通業界』各社の法定雇用率について
「流通業界の各社は法定雇用率を達成しているのか?」会社ごとにまとめていますので是非ご覧ください。