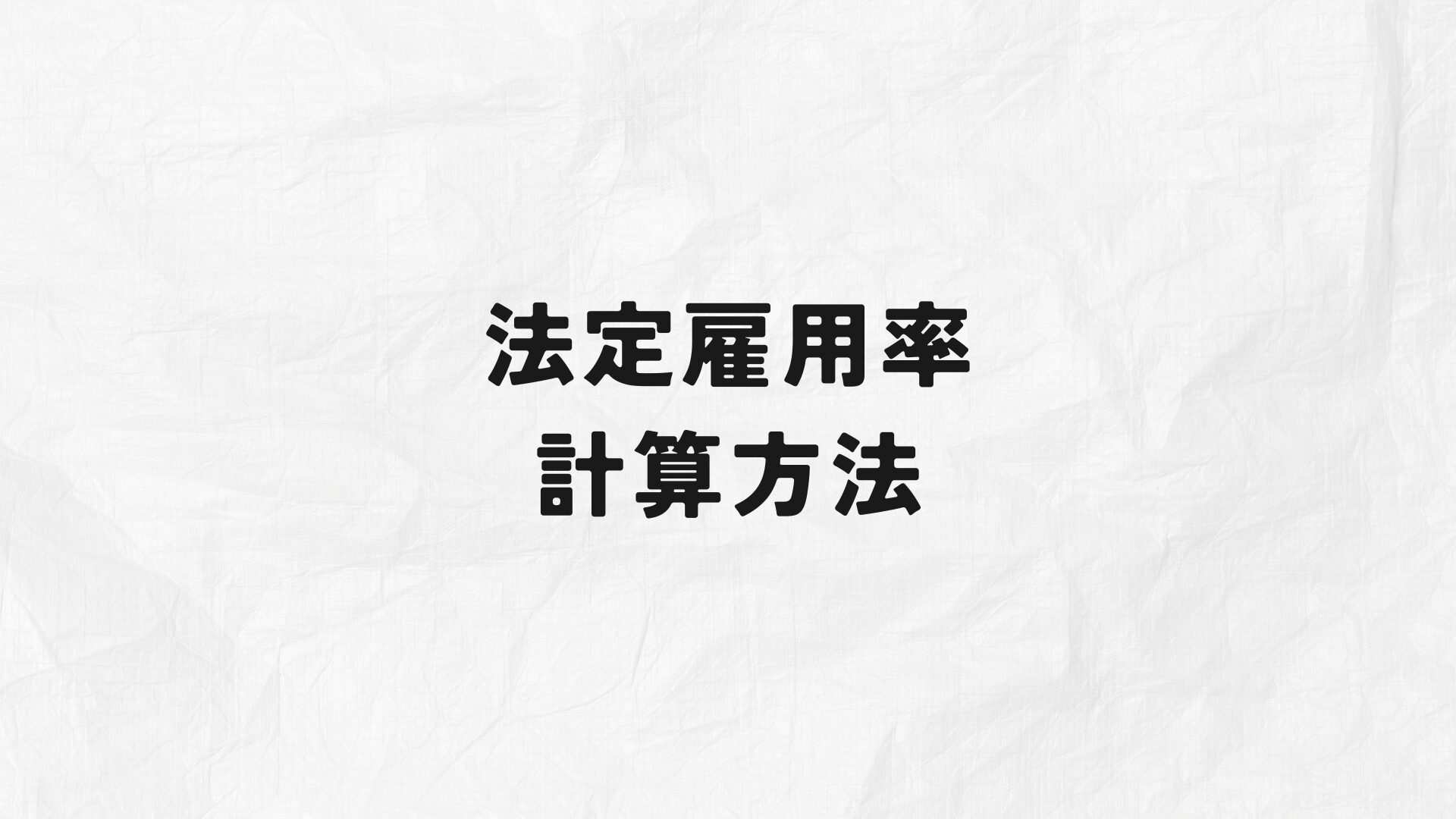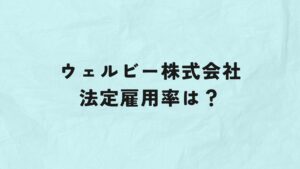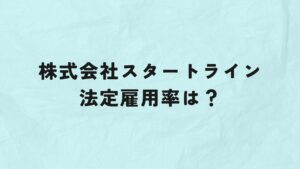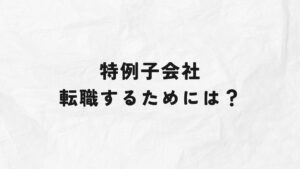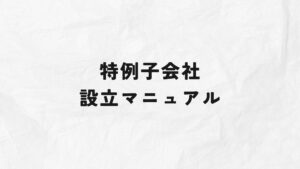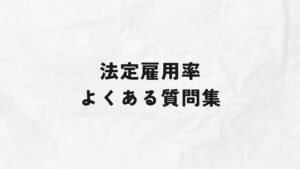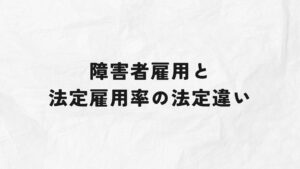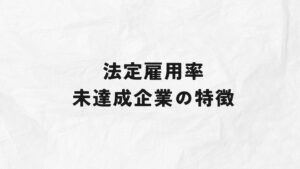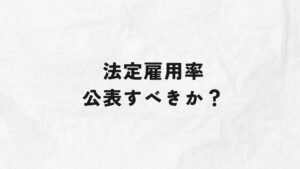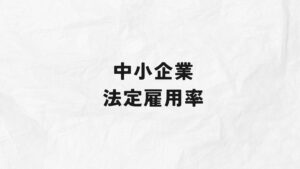「自社は法定雇用率を満たしているのか?」そう思っても、いざ調べようとすると「計算方法が難しそう…」と感じたことはありませんか?
この記事では、法定雇用率の計算方法を【初心者向け】にやさしく解説します。企業の人事担当者の方や、雇用管理を任されている方が、自社の状況を正しく把握し、今後の対策に活かせるように徹底解説していきます。
法定雇用率とは?
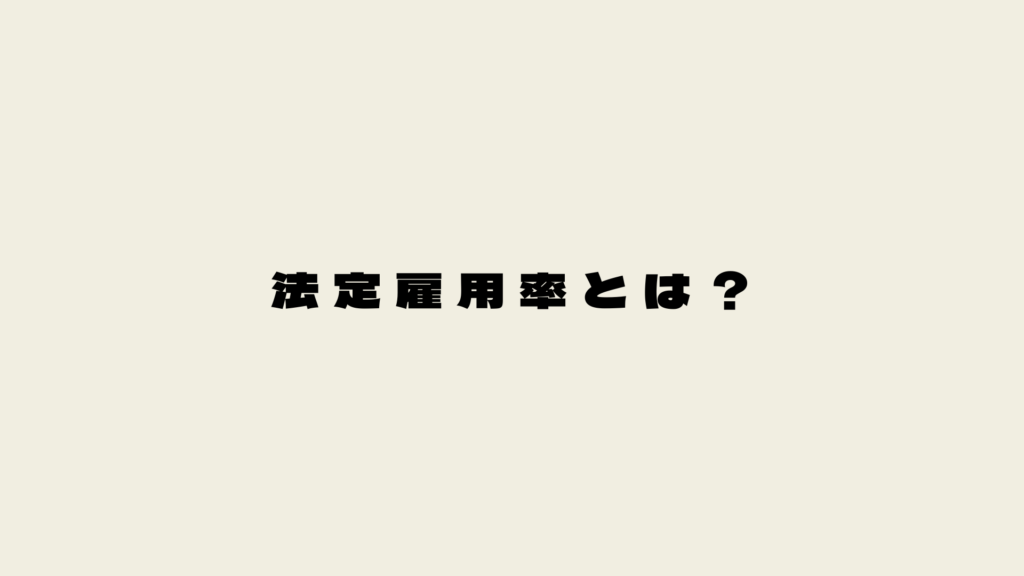
まずは法定雇用率は何か?という基礎知識からみていきましょう。
法定雇用率の基本定義
法定雇用率とは、「障害者雇用促進法」によって定められた、企業が雇用しなければならない障害者の割合を示す数値になります。この制度は、障害のある方が働く機会を確保し、社会参加を後押しすることを目的としています。
つまり、「一定以上の従業員がいる企業は、必ず一定数以上の障害者を雇用しなければならない」という義務があり、これを「法定雇用率」と呼びます。
現在の法定雇用率(2024年時点)
2024年4月から、法定雇用率は以下のように改定されています。
| 対象 | 法定雇用率 |
|---|---|
| 民間企業 | 2.5% |
| 国・地方公共団体 | 2.6% |
| 都道府県などの教育委員会 | 2.9% |
特に常時雇用する労働者が43.5人以上の企業は、法定雇用率に基づいて障害者を雇用することが義務となります。満たしていない場合は、納付金(罰則)を支払う必要があるなど、さまざまな影響があります。
2026年にはさらに引き上げ予定
厚生労働省の発表により、2026年4月には民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決まっています。企業側には、今後ますます障害者雇用への対応が求められる流れです。
障害者の人数は年々増えているため、今後の法定雇用率はさらに上がる可能性があるとも言われています。
法定雇用率の対象となる企業とは?
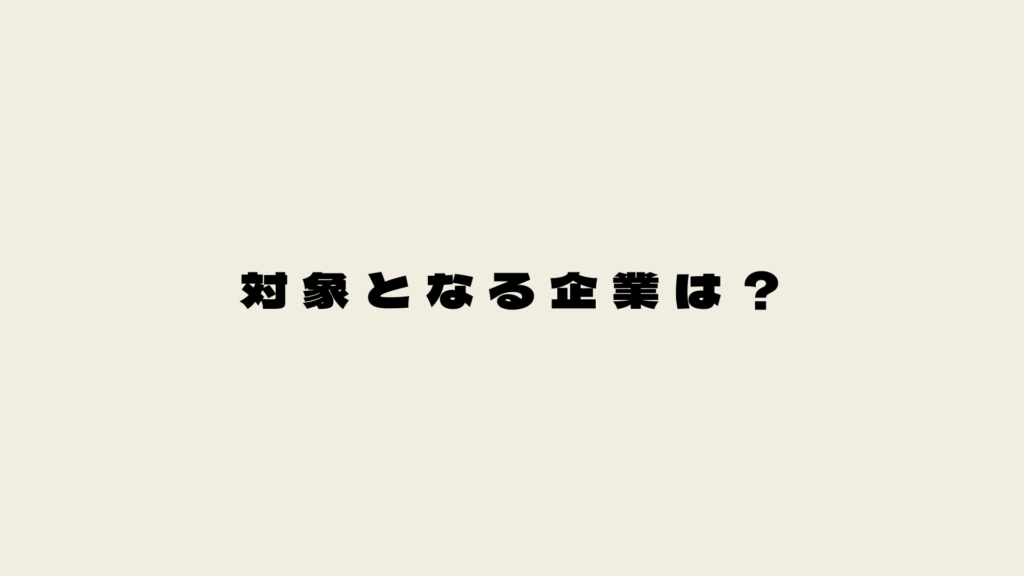
常時雇用する労働者数が基準
法定雇用率の適用対象となるのは、常時雇用する労働者が43.5人以上の企業です。
この「常時雇用する労働者」とは、正社員だけでなく、契約社員やパートタイム労働者など、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上雇用が見込まれる人を含みます。
「常時雇用する労働者」は、企業全体の雇用状況を反映して計算されるため、支店や工場などが複数ある場合は、法人単位での集計が必要です。
例えば、全国に事業所などを展開している会社は事業所単位での労働者数ではなく、全国の「常時雇用する労働者」をカウントします。その数が43.5名を超える会社に関しては、障害者雇用をする義務があるのです。
正社員・パートの扱い方
法定雇用率を計算する際は、正社員だけでなくパートタイムの従業員も対象になります。
ただし、パートタイムや短時間勤務の方は1人分としてカウントされないため、「0.5人分」として換算されるのが一般的です。具体的には、以下のような扱いになります。
- 週30時間以上勤務する労働者:1人としてカウント
- 週20時間以上30時間未満勤務する労働者:0.5人としてカウント
- 週20時間未満:原則として対象外
そのため、パートやアルバイトが多い企業では、実際の従業員数よりも「常用労働者数(換算後の人数)」が少なくなる傾向があります。正確な把握のためには、雇用形態ごとに就業時間や契約期間を整理しておくことが重要です。
法定雇用率の計算方法と基本公式
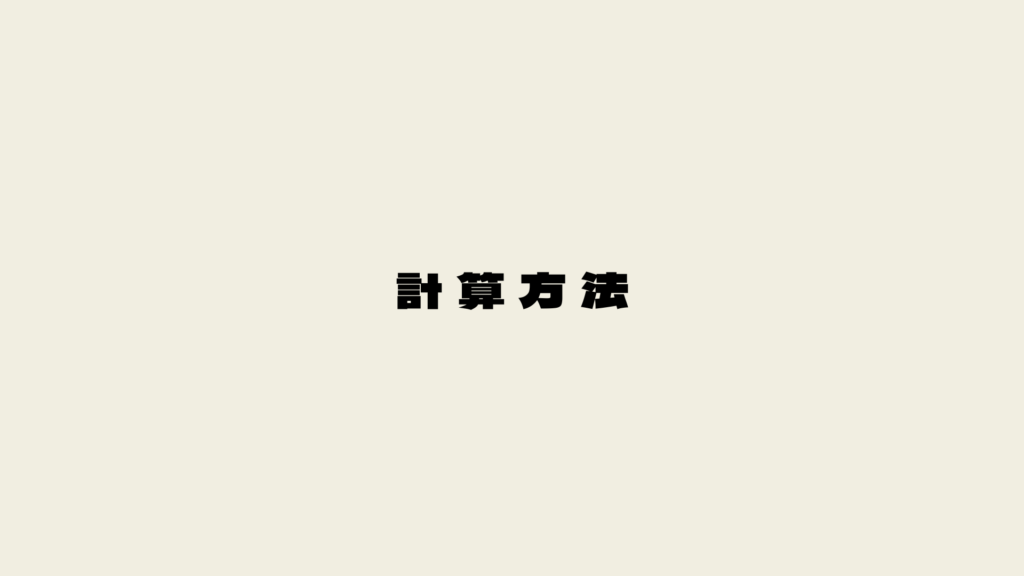
基本の公式
法定雇用率の計算式はこちらです。
必要な障害者の数 = 常時雇用する労働者数 × 法定雇用率(2.5%)
ただし、小数点以下は切り捨てになりますので理解しておきましょう。
法定雇用率の計算例(2024年時点/法定雇用率2.5%)
企業の従業員数に対して、法定雇用率をかけると「必要な障害者雇用人数」が算出されます。ただし小数点以下は切り捨てで計算されるため、1.9人と出ても「1人いれば達成」となります。
| 常時雇用労働者数 | 法定雇用率での計算 | 切り捨て後 | 必要な雇用人数 |
|---|---|---|---|
| 39人 | 39 × 2.5% = 0.975人 | 0人 | 義務なし(43.5人未満) |
| 50人 | 50 × 2.5% = 1.25人 | 1人 | 1人の雇用で達成 |
| 79人 | 79 × 2.5% = 1.975人 | 1人 | 1人の雇用で達成 |
| 80人 | 80 × 2.5% = 2.0人 | 2人 | 2人の雇用で達成 |
| 199人 | 199 × 2.5% = 4.975人 | 4人 | 4人の雇用で達成 |
| 200人 | 200 × 2.5% = 5.0人 | 5人 | 5人の雇用で達成 |
このように、法定雇用率の判断では「必要な人数の小数点以下は切り捨て」となるため、たとえ「1.99人必要」と計算されても、1人雇っていれば達成扱いになります。
但し、計算間違いなどの可能性もあるので余裕をもって採用するのがポイントになってきます。
【具体例】従業員数別の法定雇用率の計算例
ここでは、従業員数に応じて、実際にどれくらいの障害者を雇用すれば法定雇用率を満たすのか、具体例でわかりやすく見ていきましょう。2025年7月現在、民間企業に求められる法定雇用率は2.5%です。
従業員数50人の企業
50人 × 2.5% = 1.25人
障害者雇用数は「1名以上」が必要になります。
※小数点以下は切り捨てのため、実際には1名雇用でOKとされます。
従業員数100人の企業
100人 × 2.5% = 2.5人
この場合、必要な雇用人数は「2名」となります。
※2.5人の小数点以下を切り捨て。
従業員数200人の企業
200人 × 2.5% = 5人
この場合、必要な雇用人数は「5名」となります。
従業員数500人の企業
500人 × 2.5% = 12.5人
この場合、小数点以下は切り捨てになるため必要な雇用人数は「12名」となります。
パートタイム労働者がいる場合の法定雇用率の計算例
法定雇用率の計算では、パートタイムや短時間勤務の従業員もカウントされますが、週の労働時間によって「1人として数えるかどうか」が異なります。以下のルールの確認になります。
- 週30時間以上勤務:1人としてカウント
- 週20時間以上30時間未満勤務:0.5人としてカウント
- 週20時間未満勤務:対象外
以下では、実際のケースに沿って具体的に計算してみましょう。
ケース①:正社員30人、パート20人(週25時間勤務)
- パート20人 × 0.5人換算 = 10人
- 常用労働者数 = 正社員30人 + パート換算10人 = 40人
- 40 × 2.5% = 1.0人 → 切り捨て不要
➡ 障害者1人の雇用で達成となります。
ケース②:正社員80人、パート40人(週28時間勤務)
- パート40人 × 0.5 = 20人
- 常用労働者数 = 80 + 20 = 100人
- 100 × 2.5% = 2.5人 → 切り捨て → 2人
➡ 2人以上の障害者雇用で達成となります。
ケース③:正社員100人、パート60人(週18時間勤務)
- パート60人は週20時間未満のためすべて対象外
- 常用労働者数 = 正社員100人
- 100 × 2.5% = 2.5人 → 切り捨て → 2人
➡ この場合も障害者2人以上の雇用で達成です。
ケース④:正社員40人、パート10人(週32時間勤務)
- パート10人 × 1人換算 = 10人
- 常用労働者数 = 40 + 10 = 50人
- 50 × 2.5% = 1.25人 → 切り捨て → 1人
➡ 障害者1人以上の雇用で達成となります。
ポイントまとめ
パートタイム従業員が多い企業では、労働時間による換算の違いが法定雇用率に大きく影響します。見かけの人数ではなく、「換算後の常用労働者数」で正確に把握することが大切です。
どのタイミングで従業員の計算をするの?
法定雇用率の達成状況を判断する際、「いつの時点の従業員数を使って計算するのか」は重要なポイントです。これは企業にとって納付金の対象になるかどうかを左右するため、正確に理解しておく必要があります。
納付金制度では「各月末時点」の人数を基準にする
障害者雇用納付金制度では、毎月末の時点における常時雇用労働者数をもとに、年間の平均を算出して判断します。つまり、「年1回まとめて判断」ではなく、「毎月の人数を記録」しておくことが必要になってくるのです。
実際の流れ(納付金の対象企業の場合)
- 毎月末時点の労働者数・障害者数を記録
- 年度末に12か月分の平均を算出
- 平均値で法定雇用率を満たしているかを判定
たとえば、ある月だけ障害者が多く在籍していても、年間平均で不足していれば「未達成」扱いになります。一時的な対応ではなく、継続的な雇用が求められているということです。
対象外企業(従業員43.5人未満)の場合は?
従業員が43.5人未満の企業には納付金制度が適用されないため、法定雇用率の義務は発生しません。ただし、従業員数が増えて基準を超えると、翌年度から義務対象になる可能性があります。そのため、企業規模が拡大している段階では、早めに人員構成の確認と準備をしておくのが安心です。
ポイントまとめ
- 計算の基準は「各月末の人数」
- 年1回のチェックではなく「12か月平均」で判定
- 一時的に達成していても、平均で未達なら「未達成」扱い
よくある計算ミスと注意点
法定雇用率を正しく計算するには、制度上のルールをしっかり理解しておく必要があります。ここでは、実際によくある「計算ミス」や「見落としやすいポイント」を3つご紹介します。
社員数の集計ミス
法定雇用率の計算に使う「常時雇用する労働者数」には、正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトも含まれます。そのため、正社員数だけで計算してしまうと、必要な障害者数が実際よりも少なく見積もられてしまうケースがあります。
また、計算の基準となる人数は月末時点の在籍者であり、産休・育休中の社員や長期休職中の方も含まれる場合があります。社内の人事台帳や勤務実績をもとに、実際にカウントすべき人が正しく反映されているかを確認しましょう。
パートの換算漏れ
週20時間以上勤務しているパートタイム従業員は、0.5人として常用労働者数にカウントされます。ところが、「パートは人数に含めなくていい」と思い込んでいたり、労働時間が曖昧なまま集計してしまったりすることがあります。
特に、週20時間前後の勤務形態の人がいる場合には、契約書や勤怠表をもとにしっかり確認することが大切です。
在宅勤務・派遣社員の扱い
最近では、在宅勤務やテレワークが一般化しており、働き方に関係なく週20時間以上・1年以上雇用見込みがあればカウント対象となります。「在宅だから対象外」と思って除外してしまうのは誤りです。
また、派遣社員については、雇用主が派遣元企業であるため、原則として派遣先企業では人数に含まれません。ただし、受け入れ実態が「常用的」なものであれば例外的にカウント対象となるケースもあるため、社労士など専門家に確認するのが確実です。
ポイントまとめ
- 正社員以外の雇用形態も含めて集計する
- パートタイムの勤務時間に注意(20時間が境目)
- 在宅勤務者も対象になることを忘れずに
- 派遣社員は原則除外だが、実態次第で例外もあり
法定雇用率が未達成のデメリットは?
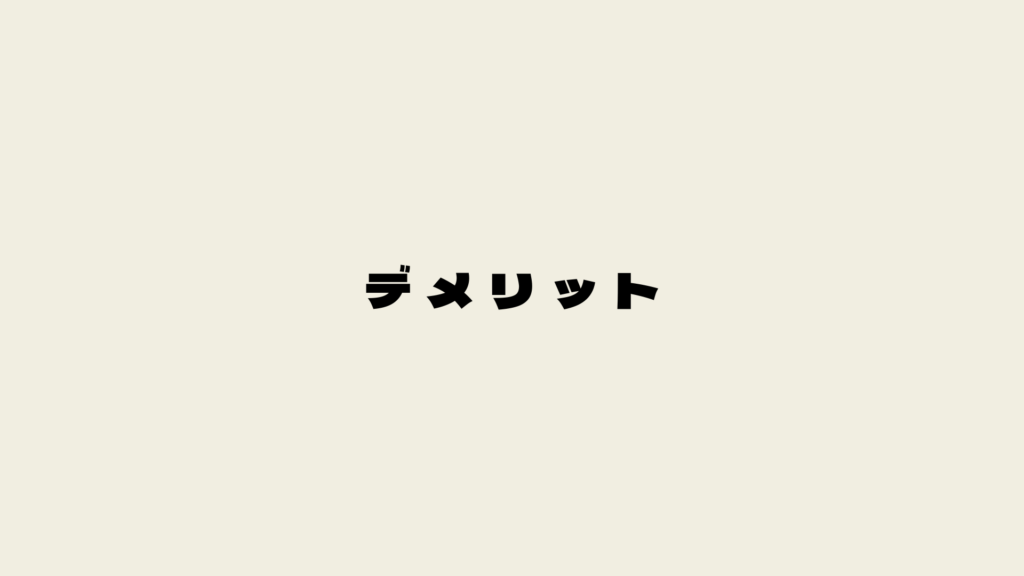
法定雇用率を達成していない場合、企業には経済的な負担や社会的な影響などのデメリットがあります。実際にどのようなペナルティやリスクがあるのかを3つの視点から解説します。
納付金制度の概要
障害者雇用率が未達成の企業(常用労働者数が43.5人以上の企業)には、障害者雇用納付金制度が適用されます。これは不足人数1人あたり月額5万円(年間60万円)
例えば、2人不足していた場合は…
- 5万円 × 2人 × 12か月 = 年間120万円の納付
10人不足していた場合は…
- 5万円 × 10人 × 12か月 = 年間600万円の納付
この納付金は「罰金」ではなく、「制度運営のための拠出金」とされていますが、企業にとっては明確な経済的負担になります。
行政指導・企業名の公表リスク
一定期間にわたって法定雇用率を達成せず、改善の兆しも見られない場合、厚生労働省からの行政指導や企業名の公表される場合があります。
特に、上場企業や大手企業の場合は、イメージや株価への影響も考慮する必要があります。「法定雇用率を守っていない会社」というレッテルを貼られることで、採用活動や取引先との信頼関係にも影響を及ぼす可能性があります。
ESG評価や社会的信用の低下
最近では、企業の社会的責任(CSR)やESG(環境・社会・ガバナンス)への対応が重視される時代です。
障害者雇用に消極的な企業は、投資家・取引先・求職者からの信頼を損なうリスクもあります。 逆に言えば、法定雇用率をしっかり達成し、プラスαの雇用や職場環境整備に取り組んでいる企業は、社会的評価が高まりやすい傾向にあります。
ポイントまとめ
- 未達成企業には「納付金(月5万円×人数)」が課される
- 改善が見られない場合は行政指導や企業名の公表も
- ESG・CSRの観点から、社会的信用を落とすリスクもある
法定雇用率を超えている企業のメリット
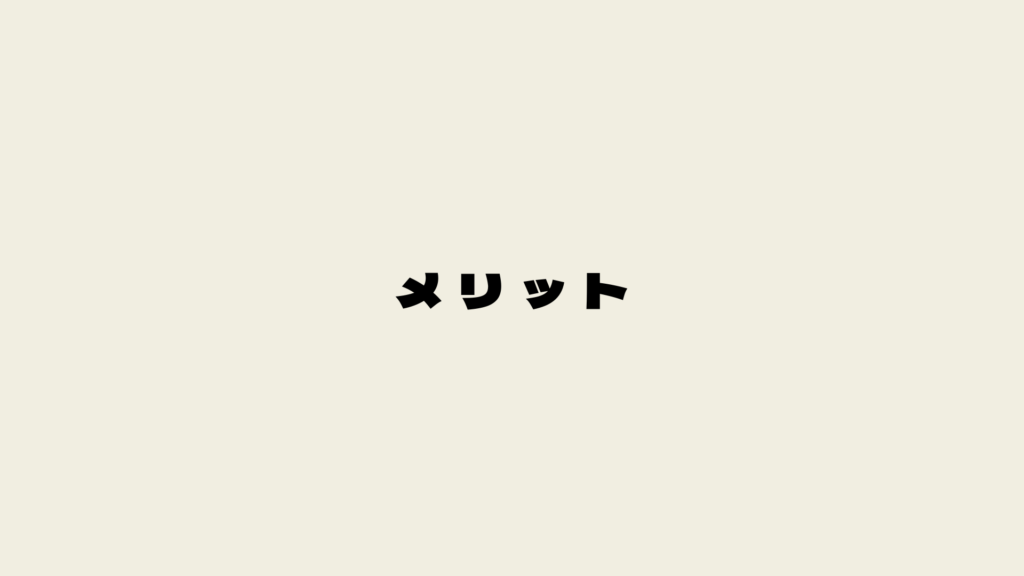
法定雇用率は「最低限守るべき基準」ですが、それを上回る水準で障害者を雇用している企業には、さまざまなメリットがあります。ここでは、制度的なインセンティブと、企業ブランディングの2つの観点から解説します。
調整金・報奨金の支給
法定雇用率を上回って障害者を雇用している企業には、「障害者雇用調整金」や「報奨金」が支給される制度があります。
- 障害者雇用調整金: 常用労働者100人超の企業が対象
- 報奨金: 常用労働者100人以下の中小企業が対象
これらは、法定雇用率を上回って雇用している人数に応じて、月額・年額で支給される仕組みです。例えば中小企業の場合、障害者1人あたり月額27,000円(年額324,000円)
支給には申請が必要ですが、国や自治体からの経済的支援を受けながら、雇用の幅を広げられるのは大きなメリットです。
採用ブランディング・CSR向上
障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業は、社外へのイメージアップ効果も期待できます。特に最近では、就活生や転職希望者、取引先が「ダイバーシティ」「ESG経営」を重視する傾向が強まっており、
- 採用サイトやIR資料でのアピール
- 自治体・メディアでの紹介や表彰
- SDGs活動の一環としての評価
といった形で、「社会的に評価される企業」としてのポジションづくりにもつながります。
ポイントまとめ
- 法定雇用率を超えると「調整金・報奨金」が受け取れる
- 中小企業でも経済的メリットがある
- 採用・広報・企業価値向上にもつながる
法定雇用率を達成するための実務対策
法定雇用率の達成は、単なる「数合わせ」ではなく、働く場としての受け入れ体制を整えることが重要です。ここでは、実際に多くの企業が取り組んでいる3つの対策をご紹介します。
採用活動の工夫(求人媒体・条件設定)
まずは「障害のある方との出会いの場を広げること」が第一歩です。ハローワークだけでなく、障害者専門の求人媒体や紹介事業者を活用することで、マッチする人材と出会いやすくなります。
- dodaチャレンジ・atGPなど、障害者専門の転職サービス
- 就労支援施設からの紹介(職業センター、福祉事業所など)
また、募集条件をあらかじめ柔軟に設定しておくことも重要です。
- 勤務時間の相談OK
- 在宅勤務・通院配慮あり
- 業務内容は面接時に相談可
このような記載をすることで、応募のハードルがぐっと下がります。
社内体制の見直し・環境整備
採用後に定着してもらうには、社内全体での理解と仕組みづくりが欠かせません。
- 配属部署での受け入れ研修の実施
- 相談窓口やメンター制度の設置
- 障害特性に応じた業務調整やマニュアル整備
特に、精神・発達障害のある方の場合は、業務内容の明確化や声かけの工夫などが離職防止につながります。社内全体での意識共有が、結果として法定雇用率の安定的な達成につながります。
外部支援の活用(就労移行支援・定着支援)
採用活動や職場定着においては、外部の専門支援機関と連携することで、企業側の負担を大幅に軽減できます。
- 就労移行支援事業所: 就職前の訓練や職場実習を提供
- 定着支援サービス: 就職後の定期的なフォロー(面談・報告)
- 職業センター: アセスメント・職域設計のアドバイス
こうした支援機関は、障害者本人だけでなく、企業側へのサポートも積極的に行ってくれるのが特長です。「初めての障害者雇用で不安…」という企業こそ、気軽に相談してみるとよいでしょう。
ポイントまとめ
- 専門媒体や支援機関を活用して母集団を広げる
- 社内体制を整えることで定着率が上がる
- 外部支援と連携することで、コストと手間を減らせる
法定雇用率の推移と今後の動向
法定雇用率は、一度決まったらずっと同じというわけではありません。障害者の就労環境の整備や社会のニーズに合わせて、段階的に引き上げられてきた経緯があります。ここでは、過去の推移と今後の予定について整理します。
法定雇用率の過去推移
| 施行年 | 民間企業の法定雇用率 | 改正内容 |
|---|---|---|
| 2013年4月 | 2.0% | 初めて精神障害者が算定対象に |
| 2018年4月 | 2.2% | 精神障害者の義務対象化 |
| 2021年3月 | 2.3% | 段階的引き上げ |
| 2024年4月 | 2.5% | 最新の引き上げ |
| 2026年4月予定 | 2.7% | さらなる引き上げ予定 |
このように、障害者の就労促進とともに、少しずつ段階的に雇用率が引き上げられていることがわかります。
2026年以降の制度変更予定
厚生労働省は2023年に発表した中長期方針において、2026年4月に法定雇用率を2.7%へ引き上げると明記しています。対象となるのは民間企業で、従業員数43.5人以上の企業ではより高い障害者雇用が求められることになります。
この引き上げにより、たとえば従業員数が199人の企業では、
- 2024年:199人× 2.5% =0.975人→必要なし
- 2026年:199人× 2.7% =1.053人→切り捨てて1人必要
500名の企業の場合、
- 2024年:500人×2.5%=12.5人→切り捨てて12人必要
- 2026年:500人×2.7%=13.5人→切り捨てて13人必要
199名の場合は今までは障害者雇用の必要性はなかったのですが、2026年7月以降は1名の障害者雇用が必要になってきます。従業員数によっては増えない場合もありますが、できるだけ早いタイミングで計算しておくことをオススメします。
今後のポイントまとめ
- 法定雇用率は今後も少しずつ引き上げられる見込み
- 2026年4月には2.7%へ(民間企業)
- 早めの雇用・社内体制づくりが将来のリスク回避につながる
よくある質問(Q&A)

Q1. パートでもカウントされる?
はい、週20時間以上勤務し、かつ1年以上の雇用が見込まれるパートはカウントされます。ただし、週30時間未満であれば0.5人として換算されます。
Q2. 在宅勤務者も対象になる?
勤務形態に関係なく、週20時間以上・1年以上の雇用が見込まれる場合は在宅勤務者も対象となります。
Q3. 法定雇用率の計算ツールはある?
厚生労働省や自治体のホームページなどで、障害者雇用率計算ツールが公開されています。常用労働者数を入力するだけで、必要な障害者数がわかる便利なツールです。
Q4. 雇用義務のない企業でも雇用した方がいい?
義務がない企業でも、助成金の活用や社会的評価の向上などのメリットがあります。将来的に規模拡大を目指す場合も、早めの準備が有効です。
Q5. 精神障害者もカウントされる?
はい、2018年4月以降、精神障害者も法定雇用率の算定対象となっています。身体・知的・精神のすべての障害種別が含まれます。
Q6. 特例子会社を設立すれば雇用率はどうなる?
認定を受けた特例子会社に雇用された障害者も、親会社の雇用率に算入することができます。
Q7. 障害者手帳があれば全員対象?
原則として、障害者手帳を持っている人が対象です。ただし、雇用契約上の条件(労働時間や見込み期間など)も満たす必要があります。
Q8. 雇用率を超えて雇ったら何か特典はある?
はい、報奨金制度(中小企業向け)や、調整金制度(大企業向け)により、障害者1人あたり数十万円の支給が受けられることがあります。
Q9. 派遣社員はカウント対象?
原則として派遣元(派遣会社)の雇用扱いになるため、派遣先企業ではカウントされません。ただし、長期的・常用的な勤務実態がある場合は例外的に含まれることもあります。
Q10. 離職したらすぐ未達成になる?
年間の平均人数で判断されるため、一時的に人数が減っても即「未達成」にはなりません。ただし、長期間にわたり不足していると納付金の対象になる可能性があります。
Q11. アルバイトはカウントされる?
週20時間以上かつ1年以上の雇用が見込まれる場合は、アルバイトも対象になります。雇用契約の内容や就業実態に応じて判断されます。
Q12. 達成していない場合、助成金は受け取れない?
多くの助成金制度では法定雇用率の達成が要件となっているため、未達成だと支給されない可能性があります。
Q13. 1社で何人以上雇えば「良い企業」と言える?
業種や規模によって異なりますが、法定雇用率を上回る雇用+定着支援の体制が整っていれば、社外から高く評価される傾向にあります。
Q14. 雇用率は年度途中で変わる?
原則として年度単位(4月~翌年3月)で平均を算出します。法改正がある場合は、施行日(たとえば2026年4月)以降に新しい率が適用されます。
Q15. 個人事業主にも雇用義務はある?
原則として法人が対象であり、個人事業主は法定雇用率の義務対象にはなりません。ただし、従業員数が多い場合は任意雇用や社会的責任として取り組む事例もあります。
まずは正確な人数の把握が大切!
この記事のおさらい
- 法定雇用率の計算は「従業員数」と「障害者数」の正しい把握がカギ
- パート・在宅勤務者・派遣などのカウント方法にも注意が必要
- 未達成によるリスク(納付金・社会的評価低下)を避けるためにも、早めの対策が重要
- 法定雇用率は今後さらに引き上げられる予定(2026年は2.7%)
社労士や外部機関に相談するのも有効
法定雇用率の達成や障害者雇用に不安がある場合は、社労士・就労支援機関・職業センターなど外部の専門機関に相談するのがおすすめです。
採用から定着、制度利用や助成金の活用まで、自社だけで抱え込まずにサポートを得ることで、より現実的かつ継続的な雇用につながります。
まずは「今、自社には何人の障害者雇用が必要なのか?」を正しく知ることから始めましょう。できるだけ早いタイミングで2.7%になった場合の計算をして、早めに備えることが法定雇用率をクリアするために必要になってきます。