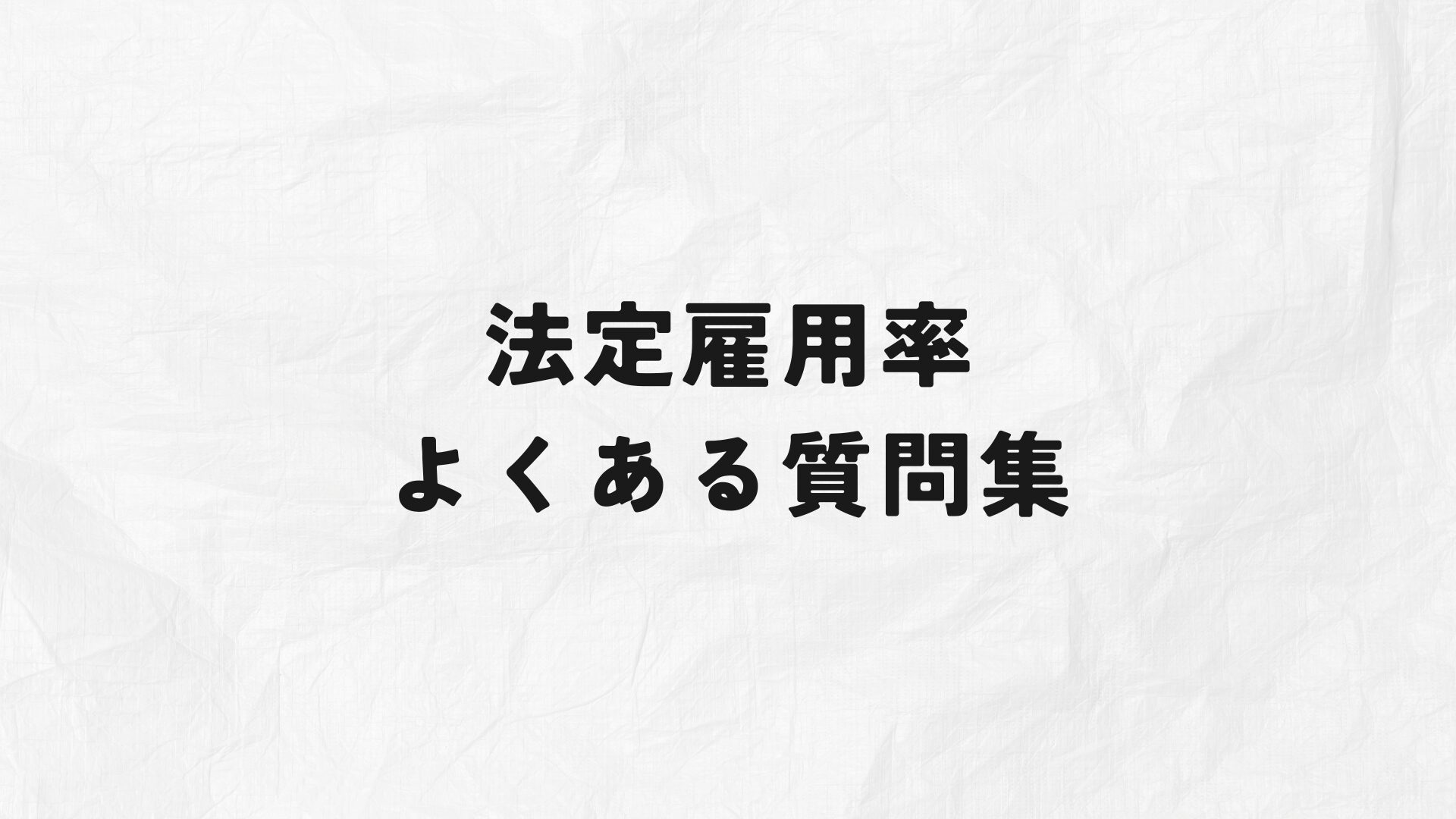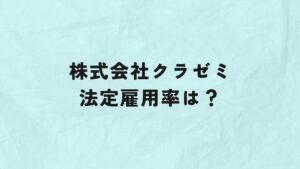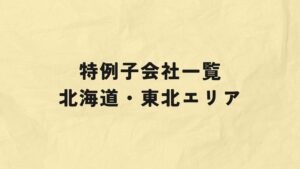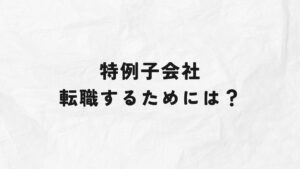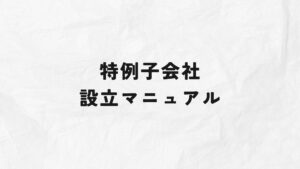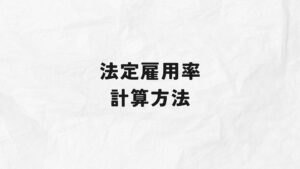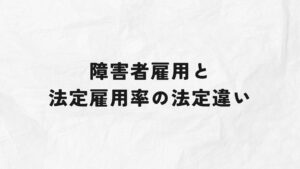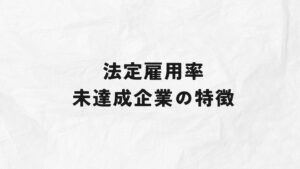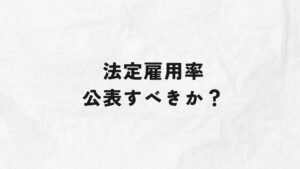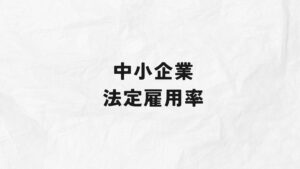法定雇用率について「何から調べたらいいかわからない」「難しくてよくわからない」という声を多く聞きます。この記事では、初心者の方でも安心して読めるように、よくある質問をジャンル別にわかりやすくまとめました。
法定雇用率の基本知識についての質問
まずは法定雇用率の基礎知識についてのよくある質問です。これを近いできていれば一般的な知識は身に付きますよ。
Q1. 法定雇用率って何ですか?
A. 法定雇用率とは、企業に対して障害者を一定割合以上雇用することを義務づけた制度です。法律(障害者雇用促進法)に基づいて設定されています。
Q2. そもそもなぜ法定雇用率があるの?
A. 障害のある人の雇用を促進し、すべての人が働ける社会を実現するためです。企業には社会的責任が求められています。
Q3. 法定雇用率の「法律的な根拠」は?
A. 「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づいて制度が設けられています。
Q4. いつから制度が始まったの?
A. 法定雇用率の制度は1976年に導入されました。当初は努力義務でしたが、1987年から法的義務になりました。
Q5. 誰がこの制度を決めているの?
A. 厚生労働省が制度設計や数値の見直しを行い、国として運用しています。
Q6. 法定雇用率はどのくらい?
A. 2025年現在、民間企業の法定雇用率は2.5%です。2026年からは2.7%に引き上げられる予定です。
Q7. 法定雇用率は誰がチェックするの?
A. 各都道府県のハローワークが企業の雇用状況を確認し、報告を受け付けています。
Q8. 企業が守らないとどうなるの?
A. 一定規模以上の企業が未達成だと、障害者雇用納付金の支払い義務が発生したり、行政指導の対象になることがあります。
Q9. 法定雇用率は企業の規模によって違うの?
A. 法定雇用率そのものは同じですが、義務の対象となる企業は「従業員数43.5人以上の事業主」とされています。
Q10. 法定雇用率っていつ見直されるの?
A. 法定雇用率は概ね5年ごとに見直され、社会情勢や障害者の雇用状況に応じて変更されることがあります。
対象となる企業の条件についての質問
どんな会社が対象になるのかの質問をまとめてあります。
Q11. 法定雇用率が適用される企業はどんな会社?
A. 原則として、常時43.5人以上の従業員を雇用している事業主に適用されます。全国一律の基準です。
Q12. 43.5人ってどういう意味?
A. 「常時雇用している労働者」が43.5人以上いる事業主が対象です。43人だと対象外、44人だと対象になるという意味です。
Q13. パートやアルバイトも従業員数に含まれますか?
A. 一定の条件を満たせば含まれます。週の労働時間が20時間以上で、かつ1年以上雇用見込みがある人は「0.5人」でカウントされます。
Q14. 複数の事業所がある場合はどうカウントする?
A. 法定雇用率の適用は「企業単位(法人単位)」で判断されます。事業所ごとではなく全体の従業員数で判断します。
Q15. 公務員も法定雇用率の対象ですか?
A. はい。国や地方公共団体にも法定雇用率の達成が義務づけられており、それぞれ異なる基準が設けられています。
Q16. 医療法人や学校法人なども対象?
A. はい、常時43.5人以上の従業員がいれば、医療法人・学校法人・社会福祉法人なども対象になります。
Q17. 非正規雇用が多い企業でも対象になりますか?
A. 正社員でなくても、労働時間など一定の基準を満たす非正規雇用者も従業員数にカウントされます。そのため対象になる可能性は十分あります。
Q18. 一時的に従業員が減ったら義務はなくなりますか?
A. 一時的に従業員数が減っても、恒常的な雇用状況に基づいて判断されるため、すぐに対象外にはなりません。
Q19. 法人でなくても対象になりますか?
A. はい。個人事業主であっても、常時43.5人以上を雇用していれば対象となります。
Q20. グループ会社全体で見るの?それとも単体?
A. 原則として、法定雇用率の判断は「それぞれの法人単位」で行われます。ただし、特例子会社制度を使う場合はグループ単位での特例もあります。
障害者の定義と対象者の範囲についての質問
障害者の定義って何になるの?対象者は誰?このあたりの質問になります。
Q21. 法定雇用率の対象になる「障害者」とは?
A. 身体障害者、知的障害者、精神障害者のうち、障害者手帳などで認定されている方が対象です。
Q22. 精神障害や発達障害の方も対象になりますか?
A. はい。精神障害者保健福祉手帳を持っている方、発達障害の方なども対象になります(2018年から常時カウント対象に)。
Q23. 身体障害者手帳がなくても対象になりますか?
A. 原則として手帳の所持が必要です。手帳がない場合はカウント対象になりません。
Q24. 障害者年金を受給していれば対象になりますか?
A. 年金の受給有無ではなく、障害者手帳の所持が基準になります。
Q25. 短時間勤務の障害者も雇用率にカウントされる?
A. はい。週20時間以上30時間未満であれば「0.5人」、30時間以上で「1人」としてカウントされます。
Q26. 在宅勤務の障害者も対象ですか?
A. はい。在宅勤務でも、勤務実態があり、手帳所持などの条件を満たしていればカウント対象となります。
Q27. 派遣社員の障害者はどちらの会社がカウントするの?
A. 雇用契約を結んでいる派遣元(派遣会社)がカウントします。派遣先企業ではありません。
Q28. 業務委託契約をしている障害者は対象になりますか?
A. 業務委託契約は「雇用」ではないため、法定雇用率の対象にはなりません。
Q29. 外国籍の障害者もカウントされますか?
A. 日本国内に居住し、障害者手帳を所持している場合は、国籍を問わずカウントされます。
Q30. 同じ人が複数の障害を持っている場合はどうなる?
A. 複数の障害があっても、原則として1人分または0.5人分でのカウントとなります。重度障害者の場合は加算制度があります(例:1人で2人分としてカウントなど)。
法定雇用率の計算方法についての質問
意外と理解が難しいのが計算方法です。計算方法に関しての質問と回答になります。
Q31. 法定雇用率ってどうやって計算するの?
A. 法定雇用率は、「常時雇用している労働者」に対して「雇用している障害者数」の割合で計算します。例:従業員100人 × 2.5% = 2.5人の障害者雇用が必要。
Q32. 計算の「分母」と「分子」って何ですか?
A. 分母は常時雇用している従業員数(一定の条件あり)、分子はその中でカウント対象となる障害者数です。
Q33. 障害者1人は何人分として数えるの?
A. 週30時間以上勤務:1人、週20〜30時間未満:0.5人。重度障害者で一定条件を満たせば1人で2人分になります。
Q34. 精神・知的・身体障害者でカウントの違いはありますか?
A. 基本的には同じですが、重度障害者(身体1・2級、知的A判定など)は加重(2人分)でカウントできます。
Q35. 重度障害者はどう数えるの?
A. 重度障害者を「週30時間以上勤務」させた場合、1人で2人分としてカウント可能です(短時間勤務は1人分)。
Q36. 在宅勤務者は対象になりますか?
A. はい。雇用契約があり、勤務実態があれば在宅勤務でもカウント対象です。
Q37. パートタイム勤務でもカウントされる?
A. 週20時間以上かつ1年以上の雇用見込みがある場合、0.5人としてカウントされます。
Q38. 日雇いの人は対象になりますか?
A. 原則として、日雇いや短期契約のみの人は「常時雇用」には含まれないため、対象にはなりません。
Q39. 計算の対象になる「事業主」とは?
A. 原則として、法人単位での判断になります。グループ会社や事業所ごとではなく、法人全体でカウントします。
Q40. 小数点以下の人数はどう扱えばいい?
A. 法定雇用率に基づく「必要な雇用人数」の小数点以下は切り捨てで計算されます。たとえば2.9人と出た場合は「2人」が必要人数となります。
法定雇用率の達成基準と確認方法についての質問
Q41. 法定雇用率の「達成」とはどんな状態?
A. 企業が法律で定められた人数以上の障害者を雇用している状態です。対象者のカウント方法に沿って、雇用率が基準以上になっていれば「達成」とされます。
Q42. 法定雇用率を達成しているかどうか、どうやって確認するの?
A. 雇用している障害者の人数と、法定雇用率に基づく必要人数を照らし合わせて確認します。自社での算定またはハローワークへの報告書を通じて把握できます。
Q43. 雇用率の達成状況はいつの時点で判断するの?
A. 原則として、各年6月1日時点での状況で判断されます(障害者雇用状況報告書の基準日)。
Q44. 障害者雇用状況報告書とは?
A. 毎年6月1日時点の障害者雇用の状況をハローワークに報告するための書類です。常時43.5人以上の従業員がいる事業主に義務づけられています。
Q45. 報告はどこに提出すればいいの?
A. 管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出します。電子申請も可能です。
Q46. 提出しないとどうなる?
A. 正当な理由なく未提出の場合は、行政指導や勧告の対象となる場合があります。企業の信頼にも影響します。
Q47. 達成しているかどうか通知してもらえるの?
A. ハローワーク側で通知されるケースは基本的にありません。自社で計算・報告することが原則です。
Q48. 年の途中で雇用率を下回った場合はどうなる?
A. 年1回の報告時点で判断されますが、継続的に雇用率を維持する努力が求められます。突発的な退職などへの対応も重要です。
Q49. 誤って報告した場合はどうすればいい?
A. 内容に誤りがあった場合は、早めにハローワークに連絡し、修正報告などの対応を相談しましょう。
Q50. 雇用率の達成状況を社内で共有するべき?
A. はい。経営層や人事部門だけでなく、全社的に理解を深めることで継続的な取り組みにつながります。社内報や会議などで共有する企業も増えています。
未達成の場合のペナルティとリスクについての質問
Q51. 法定雇用率を達成していないとどうなるの?
A. 未達成の事業主には、納付金の支払い義務や、行政からの指導・勧告の対象となることがあります。
Q52. 納付金ってどれくらいの金額?
A. 不足1人あたり月額5万円(年間60万円)を支払う必要があります。常用労働者数100人を超える企業が対象です。
Q53. 納付金はどんな企業でも発生するの?
A. 常用労働者数が100人を超える企業で、法定雇用率を未達成の場合に納付義務が発生します。中小企業には猶予があります。
Q54. 行政指導って具体的に何をされるの?
A. 厚生労働省やハローワークから、障害者雇用に向けた計画提出や改善勧告を受ける場合があります。
Q55. 勧告を受けたのに改善しないとどうなる?
A. 最悪の場合、企業名の公表に至ることがあります。これは社会的信用に大きく関わる重大なリスクです。
Q56. 企業名の公表って実際にされているの?
A. はい。毎年、厚労省が未達成企業名を一部公表しています。大手企業が名指しされるケースもあります。
Q57. 未達成でも罰金はないの?
A. 罰金という刑事罰はありませんが、「納付金」は実質的に経済的負担となります。
Q58. 納付金を払えば達成しなくてもいいの?
A. いいえ。納付金はあくまで未達成に対するペナルティであり、雇用の努力義務は継続します。
Q59. 複数年にわたって未達成の場合は?
A. 継続的に未達成が続けば、指導が強化されることもあります。対策計画の提出や実績の報告が求められます。
Q60. 社内的なリスクもありますか?
A. はい。採用ブランディングの低下や社員からの不信感、取引先や投資家からの評価低下などが考えられます。
達成に向けた企業の対応策についての質問
Q61. 法定雇用率を達成するにはまず何をすればいい?
A. 自社の現在の雇用率と対象者の人数を正しく把握することが第一歩です。そのうえで採用計画を立てましょう。
Q62. 障害のある方を採用する方法は?
A. ハローワーク、障害者就労支援機関、民間求人サイト、職業紹介所などを通じて募集できます。
Q63. 採用してもすぐに辞めてしまう…どう対策すれば?
A. 面接時の相互理解、業務内容の調整、定着支援体制の構築が重要です。社内に相談窓口やメンター制度を設ける企業も増えています。
Q64. 職場の受け入れ体制はどう整えるべき?
A. バリアフリー対応やICT支援機器の導入、就労支援員との連携などが効果的です。社内の意識改革も重要です。
Q65. 合理的配慮って具体的には何をすればいい?
A. 例:勤務時間の柔軟化、通院配慮、作業マニュアルの工夫、周囲への周知など。個別の事情に応じて柔軟に対応します。
Q66. 既存社員の理解をどう促せばいい?
A. 障害者雇用に関する社内研修や講話、成功事例の共有などが有効です。「ともに働く」意識を高めることがカギです。
Q67. 外部の支援機関は活用できる?
A. はい。就労移行支援事業所、特例子会社、地域の障害者就業・生活支援センターなどがサポートしてくれます。
Q68. 障害のある方にどんな仕事を任せるべき?
A. 一般事務、清掃、軽作業、IT支援、顧客対応補助など、個々の能力に応じた職務設計が求められます。
Q69. 業務の切り出しってどうやるの?
A. 業務工程を棚卸しし、マニュアル化・簡素化できる作業を抽出していきます。障害者雇用に強いコンサルなどに相談するのもおすすめです。
Q70. 自社だけでの対応が難しい場合は?
A. 特例子会社との連携、外部委託、支援付き雇用制度などを活用することで、実現可能な体制づくりができます。
助成金・納付金・報奨金制度についての質問
Q71. 障害者雇用に関する助成金にはどんな種類があるの?
A. 「特定求職者雇用開発助成金」「障害者トライアル雇用助成金」「職場支援助成金」などがあります。目的や雇用形態に応じて使い分けが可能です。
Q72. 助成金はどんな企業でももらえるの?
A. 一定の条件(雇用保険加入、雇用形態、対象者の要件など)を満たしていれば、中小企業でも大企業でも受給可能です。
Q73. 助成金はどうすれば申請できる?
A. 労働局やハローワークを通じて申請します。事前に計画書の提出が必要なケースもあるため、早めの準備が重要です。
Q74. 納付金って何?なぜ払うの?
A. 法定雇用率を達成していない企業が、障害者雇用の機会損失に対して支払う制度です。1人不足あたり月額5万円(年額60万円)が基本です。
Q75. 納付金制度の対象になるのはどんな企業?
A. 常用労働者が100人を超える企業で、障害者の法定雇用率を満たしていない場合に納付義務が生じます。
Q76. 報奨金ってどういう制度ですか?
A. 一定以上の障害者を雇用し、かつ継続雇用している企業に支給される「障害者雇用納付金制度に基づく報奨金制度」があります。
Q77. 調整金と報奨金の違いは?
A. 「調整金」は障害者を多数雇用している企業への支援金、「報奨金」は要件を満たした優良事業主への奨励金です。
Q78. 調整金はいくら支給されるの?
A. 不足人数分の納付金が財源となり、障害者を多数雇用する企業に1人あたり月額27,000円(年額324,000円)が支給されます(一定条件あり)。
Q79. 助成金や報奨金は併用できる?
A. 内容によっては併用可能ですが、重複支給が制限される場合もあります。個別に制度の要綱を確認することが必要です。
Q80. 助成金・調整金・納付金制度の最新情報はどこで確認できる?
A. 厚生労働省の公式サイトや、各都道府県労働局のページで随時更新されています。また、社会保険労務士に相談するのもおすすめです。
特例子会社とその活用についての質問
Q81. 特例子会社って何ですか?
A. 特例子会社とは、障害者の雇用促進を目的として設立され、一定の基準を満たすことで親会社と一体で雇用率を算定できる制度上の子会社です。
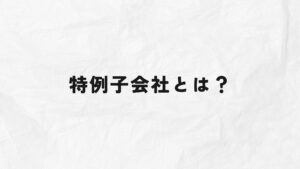
Q82. 特例子会社を作ると何がメリット?
A. 障害者雇用を集中して実施できることで、支援体制や設備を整えやすくなり、親会社とあわせた雇用率達成がしやすくなります。
Q83. どんな会社でも特例子会社を作れるの?
A. 原則として可能ですが、厚生労働大臣の認可を得る必要があり、一定の基準(障害者の雇用割合や支援体制など)を満たす必要があります。
Q84. 認可の条件にはどんなものがある?
A. 雇用される障害者の割合が一定以上であること、職場支援体制が整っていることなどが求められます。具体的には障害者が全従業員の20%以上などの基準があります。
Q85. 特例子会社で働く人はどうカウントされる?
A. 特例子会社の障害者は、親会社(グループ企業)全体の雇用率計算に含めることができます。
Q86. 特例子会社を持っている有名企業は?
A. トヨタ、NTT、みずほフィナンシャルグループ、パナソニックなど、多くの大手企業が特例子会社を設立しています。
Q87. 子会社を設立しなくても連携はできる?
A. はい。既存の特例子会社や就労支援機関と業務委託契約を結ぶ形で連携することも可能です。
Q88. 特例子会社を設立するにはどれくらいのコストがかかる?
A. 設立費用や運営費は規模によりますが、一定の初期投資が必要です。助成金や専門家の支援を活用することで負担軽減が可能です。
Q89. 障害者の支援体制はどう整備されているの?
A. 多くの特例子会社では、ジョブコーチ、産業医、専任の支援担当者などを配置しており、安心して働ける環境が整えられています。
Q90. 特例子会社以外に似たような仕組みはある?
A. 就労継続支援A型・B型などの福祉サービス事業所と提携する方法もありますが、法定雇用率の達成に直接カウントされるのは雇用契約がある場合に限られます。
エリア別特例子会社記事一覧

法定雇用率ナビに掲載をしているエリア別の特例子会社記事になります。ぜひ参考にしてください。
- 北海道エリア・東北エリアの特例子会社一覧
- 関東エリアの特例子会社一覧
- 中部エリアの特例子会社一覧
- 近畿エリアの特例子会社一覧
- 中国エリアの特例子会社一覧
- 四国エリアの特例子会社一覧
- 九州エリア・沖縄エリアの特例子会社一覧
法定雇用率の推移と今後の見通しについての質問
Q91. 法定雇用率は昔から変わってないの?
A. いいえ。法定雇用率は社会の変化に応じて何度も見直されてきました。たとえば1998年は1.6%、2024年には2.5%と段階的に引き上げられています。
Q92. 法定雇用率が上がる理由は何ですか?
A. 障害者の就労支援の充実や、社会的包摂の流れ、障害者数の増加などが主な理由です。企業における多様性確保も重視されています。
Q93. 今の法定雇用率は何%?
A. 2024年4月現在、民間企業の法定雇用率は2.5%です。国や地方公共団体は2.6〜2.8%と若干高めに設定されています。
Q94. 法定雇用率は今後どうなる予定?
A. 2026年4月から、民間企業の法定雇用率は2.7%に引き上げられることが決まっています。
Q95. これからも雇用率は上がっていくの?
A. はい。長期的には3.0%超えも視野に入れた制度設計が検討されています。社会的受容や雇用環境の整備がカギとなります。
Q96. なぜ企業側には負担が増えるのに引き上げるの?
A. 社会全体で障害者の活躍を支える必要があるためです。国際的にも多様性・インクルージョンが重視されており、日本も制度を強化しています。
Q97. 障害者の雇用率は実際どれくらい?
A. 令和5年(2023年)の実雇用率の平均は約2.3%で、未達成企業も多く存在しています。
Q98. 業種によって達成率は違うの?
A. はい。製造業や小売業では比較的達成率が高く、IT・金融・建設などはやや遅れがちという傾向があります。
Q99. 過去に達成率が上がった要因は?
A. 精神障害者のカウント開始(2018年)や支援制度の充実、助成金活用などが後押しになっています。
Q100. 今から何を準備すべき?
A. 雇用計画の見直し、採用ルートの確保、職場環境整備、助成金制度の確認などを早めに進めておくと安心です。
中小企業や個人事業主の対応びついての質問
Q101. 中小企業でも法定雇用率の対象になりますか?
A. はい。常時43.5人以上の従業員がいれば、中小企業でも法定雇用率の対象になります。
Q102. 社員が40人前後の小規模事業所でも対策すべき?
A. すぐに義務対象にならなくても、将来に備えて障害者雇用の理解や準備を進めておくのは非常に有効です。
Q103. 個人事業主も対象になる?
A. はい。法人かどうかに関係なく、常時43.5人以上を雇用していれば対象になります。
Q104. 人手不足で障害者を採用する余裕がない場合は?
A. 外部支援の活用、業務の切り出し、合理的配慮など工夫次第で可能なこともあります。一人から始める企業も多いです。
Q105. 障害者雇用に不安がある場合はどうすれば?
A. 就労移行支援事業所やハローワーク、社労士など専門機関と連携することで、不安を解消しながら進められます。
Q106. 中小企業向けの助成金制度はありますか?
A. はい。中小企業向けの優遇措置や、初めて雇用する場合の助成金などが多数用意されています。
Q107. 業務が少なくても雇用する意味はありますか?
A. はい。業務量に合わせた就業時間の調整や在宅勤務も可能です。小さな雇用でも社会的評価や企業文化に良い影響があります。
Q108. 就労継続支援A型やB型との違いは?
A. A型・B型は福祉的支援の場であり、企業の直接雇用とは異なります。法定雇用率の達成には「雇用契約」が必要です。
Q109. 自社に合う障害者雇用の形がわからない
A. 企業の業種や規模によって最適な雇用形態は異なります。地域の障害者就業・生活支援センターなどで相談が可能です。
Q110. 社内に障害者を迎えることで周囲の負担が増えないか心配です
A. 正しい理解と適切な配慮があれば、負担よりも多様性の広がりや職場の改善につながることが多いです。
法定雇用率と障害者雇用の違い
Q111. 法定雇用率と障害者雇用って何が違うの?
A. 法定雇用率は「企業に義務づけられた雇用割合」のこと、障害者雇用はその取り組み全体を指します。前者は制度、後者は行動です。
Q112. 法定雇用率を守っていれば障害者雇用は十分?
A. 達成は最低ラインです。数値を満たすだけでなく、働きやすい職場づくりや定着支援などの中身も重要です。
Q113. 障害者雇用は法定雇用率のためだけに行うもの?
A. いいえ。企業の社会的責任(CSR)やダイバーシティ推進の一環として、自発的に取り組む企業も多くあります。
Q114. 法定雇用率未達でも障害者雇用していれば問題ない?
A. 雇用していても、換算方法や条件を満たしていないと法定雇用率にはカウントされません。要件を確認することが大切です。
Q115. 「障害者雇用に熱心な企業」と「法定雇用率を満たしている企業」はイコール?
A. 必ずしも一致しません。法定雇用率を上回っていても、配慮や支援が不十分な場合もあります。制度と実態の両方が重要です。
Q116. 障害者雇用は任意?義務?
A. 常時43.5人以上の事業主には法的義務があります。ただし、それ未満の企業でも障害者雇用に取り組むことはできます。
Q117. 「障害者雇用推進企業」になるにはどうすればいい?
A. 雇用率の達成はもちろん、職場の配慮、社内体制、外部支援の活用などを含めた総合的な取り組みが評価されます。
情報公開についての質問
Q118. 法定雇用率の達成状況は公表すべき?
A. 法的義務ではありませんが、公表することで企業の社会的責任やダイバーシティへの姿勢を示すことができ、信頼獲得につながります。
Q119. 公表すると企業評価は上がる?
A. はい。投資家や求職者からの信頼度が高まり、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営の一環としてもプラスに評価されやすいです。
Q120. 逆に未達成を隠すとリスクになる?
A. 情報公開を求められた際に隠したり曖昧にすると、企業姿勢が疑われ、ネガティブな印象を与えるリスクがあります。
Q121. 企業の法定雇用率達成状況はどこで見られる?
A. 厚生労働省が一部の未達成企業名を毎年公表しています。また、有価証券報告書やCSRレポートに記載されている企業もあります。ただ、現時点で法定雇用率の達成・未達成を掲げている企業は多くありません。
Q122. 自社の達成状況を公開する場合、どう発信すればよい?
A. 採用ページ、IR資料、社内報などでの掲載が効果的です。数字だけでなく、取り組み内容や今後の計画も添えると好印象です。
他社事例・先進企業の取り組みについての質問
Q123. 実際に取り組んでいる企業は?
A. トヨタ、スターバックス、リクルート、サントリー、NTTなど、多くの大手企業が積極的に障害者雇用を進めています。特例子会社を設立している例も多いです。
Q124. どんな工夫で成功している?
A. 例として、業務の切り出し、ICT活用、メンター制度の導入、ジョブコーチとの連携などがあります。社内理解を深める取り組みも成功のカギです。
Q125. 特例子会社以外で工夫している企業の例は?
A. 小売業では店舗内軽作業、IT企業ではデータ入力や検証業務など、業種に合わせて独自のポジションを創出している企業もあります。
Q126. 中小企業でうまくいっている事例はある?
A. はい。就労支援事業所と連携し、少人数から無理なくスタートして定着率を上げている事例が各地で報告されています。
Q127. 他社事例はどこで調べられる?
A. 厚生労働省や都道府県労働局の事例集、障害者職業総合センターの報告書、または企業のCSRレポート・採用ページなどに掲載されています。
求職者・障害者目線についての質問
Q128. 法定雇用率を達成している会社の見つけ方は?
A. 企業の採用サイトやCSRレポート、IR資料に掲載されていることがあります。また、厚労省の障害者雇用データベースや「リタリコ仕事ナビ」などでも情報収集が可能です。ただ、各社情報を出しているケースが少ないため現時点で達成している企業かどうかを見分けるのは難しいです。
Q129. 障害があるけど、働ける会社はある?
A. はい。多くの企業が障害者雇用に取り組んでおり、配慮のある職場も増えています。就労支援機関やハローワークを通じて探すのがおすすめです。
Q130. 障害者枠での採用と一般枠、何が違うの?
A. 障害者枠では、配慮が前提となった働き方が整えられており、定着支援も受けやすいです。一方で、業務内容や給与条件に差が出ることもあります。
Q131. 「障害者に優しい会社」はどうやって見分ける?
A. 採用ページの内容、社員の声、支援体制の記載、職場見学の対応などから、配慮の姿勢が読み取れる企業も多いです。面接時に質問するのも大切です。
Q132. 働く前に相談できる窓口はある?
A. はい。就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センター、地域若者サポートステーションなど、無料で相談できる窓口が全国にあります。
まとめ
法定雇用率は、単なる数字や義務ではありません。障害のある方の社会参加を支え、多様性ある職場づくりを進めるための「入り口」です。法定雇用率に関するよくある質問をジャンル別に整理し、初心者の方でも理解しやすいよう解説しました。
これから制度に対応する企業も、すでに取り組んでいる企業も、「正しく知ること」から始めることが重要です。
まずは自社の現状把握から。 必要であれば、社労士や支援機関に相談することも選択肢のひとつです。