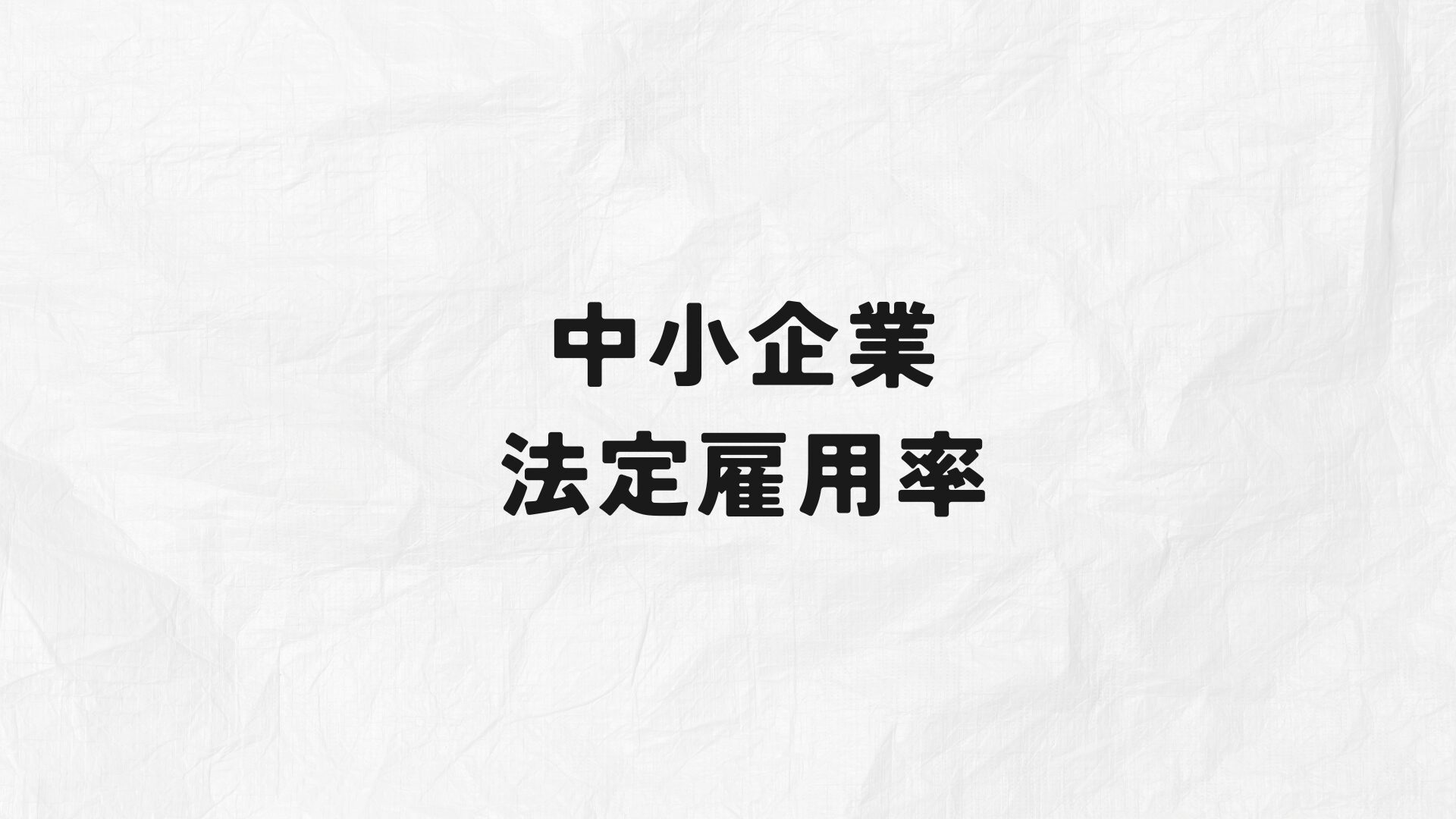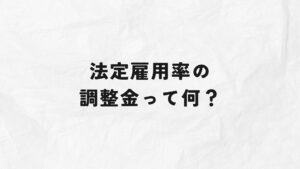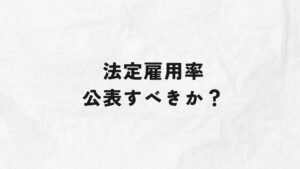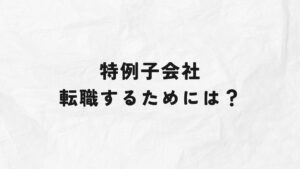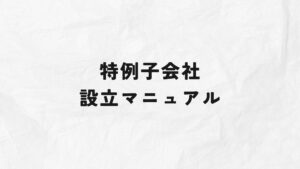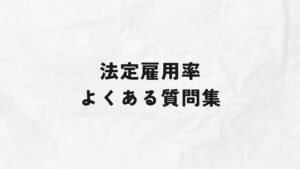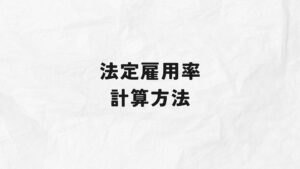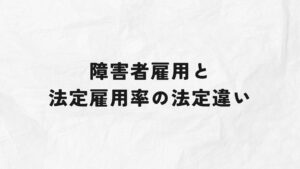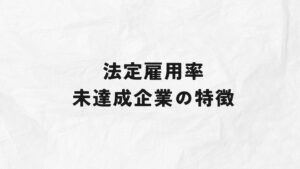「法定雇用率ってウチみたいな中小企業にも関係あるの?」「達成してないけど、罰則あるの?」そんな不安を抱えている中小企業の経営者・人事の方に向けて、法定雇用率の基本から、未達成リスク、実際の対応方法、活用できる助成金制度まで、初心者でもわかるように解説していきます。
法定雇用率とは?中小企業にも関係ある制度
法定雇用率の基本をカンタンに解説
「法定雇用率(ほうていこようりつ)」とは、企業が一定割合の障害者を雇用することを義務付けた制度です。これは、障害者の就労機会を確保し、誰もが働きやすい社会をつくることを目的として、「障害者雇用促進法」によって定められています。
この制度では、従業員の数に応じて「何人の障害者を雇用しなければならないか」が決まります。2025年時点の法定雇用率は2.5%ですが、2026年7月には2.7%へ引き上げられる予定です。
つまり、従業員が100人いる企業の場合、2024年時点では2.5人(=3人に切り上げ)、2026年以降は2.7人(=3人)の障害者を雇用する義務があることになります。
このルールは、大企業だけでなく、中小企業にも適用される場合があります。自社が対象かどうかを確認することが、適切な対応の第一歩です。
なぜ法定雇用率が必要なのか?
障害のある方の中には、働く意欲や能力があっても、就職の機会に恵まれない人が多くいます。その背景には「雇用する側の理解不足」や「働く環境の整備が不十分」といった課題がありました。
法定雇用率は、そうした社会的な課題を解決するために作られた制度です。企業に一定数の雇用を義務づけることで、障害のある方の就労を推進し、誰もが活躍できる職場づくりを目指しています。
また、最近ではSDGs(持続可能な開発目標)やダイバーシティ経営への注目も高まっており、障害者雇用は企業価値を高める取り組みとしても重要視されています。
法定雇用率の対応は「義務」であると同時に、「信頼される企業づくり」への第一歩とも言えます。
法定雇用率の現在の数値と推移
2025年現在の法定雇用率
2025年時点における民間企業の法定雇用率は2.5%です。企業が常用雇用する従業員のうち、2.5%以上を障害者として雇用することが法律で義務づけられていることを意味します。
この2.5%という基準は2021年から適用されており、次回の改定はすでに決定しています。2026年4月からは2.7%へ引き上げられる予定であり、企業は早めの準備が求められます。
なお、法定雇用率は民間企業だけでなく、国や地方公共団体、教育委員会にも適用されています。
それぞれの法定雇用率は以下の通りです(2025年時点)。
- 国および地方公共団体:2.6%
- 都道府県などの教育委員会:2.9%
このように、民間と公共機関とでは適用される割合が異なります。
民間企業は自社の従業員規模に応じて雇用義務の人数を正確に把握することが重要です。
法定雇用率の今後の動向
法定雇用率は2026年以降もさらに引き上げられる可能性が高いと見られています。実際、過去の推移を見ても数年ごとに段階的に引き上げられており、企業側の対応力が強く求められています。
この引き上げの背景には、以下のような社会的な事情があります。
- 障害者の求職者数・就労希望者数の増加
- 少子高齢化による労働力人口の減少
- 多様性・インクルージョンを重視する経営の広がり
特に近年は、SDGs(持続可能な開発目標)やESG経営などへの意識の高まりもあり、障害者雇用は社会貢献にとどまらず企業価値の向上にも直結すると考えられています。
そのため、制度改正を待ってから動くのではなく、今のうちから採用体制や社内の受け入れ環境を整えておくことが、中小企業にとってもリスク回避と成長のチャンスになります。
中小企業が法定雇用率の対象になる条件
対象となる「45.5人以上」とは?
法定雇用率の対象となるのは、常時雇用している従業員が45.5人以上の企業です。「45.5人」というのは少し中途半端に見えるかもしれませんが、これは法定雇用率2.5%における最小の雇用義務者数「1人」が必要となる基準人数として定められています。
- 従業員 45人 × 2.5% = 1.125 → 雇用義務なし(切り捨て)
- 従業員 46人 × 2.5% = 1.15 → 雇用義務あり(切り上げで1人)
このように、常用雇用労働者が45.5人を超えると、障害者1人以上の雇用義務が発生します。「うちはまだ小さいから関係ない」と思っている中小企業も、従業員が増えると対象になる可能性があるため、早めのチェックが重要です。
パート・アルバイトの換算方法
法定雇用率の対象人数を計算する際には、正社員だけでなくパートやアルバイトも含めてカウントされます。ただし、短時間労働者は労働時間に応じて0.5人などとして換算される仕組みです。
- 週30時間以上勤務のパート:1人分としてカウント
- 週20時間以上30時間未満のパート:0.5人としてカウント
つまり、フルタイム以外の従業員も合算して常用雇用労働者数を正しく把握しないと、実際には対象なのに見落としていたというケースも起こり得ます。自社の労働者がどのくらいの割合で対象になるのか、一度、雇用状況を棚卸ししておくのがおすすめです。
45.5人未満でも「努力義務」がある
従業員が45.5人未満の場合は、法的な雇用義務は発生しません。
しかし、これで「まったく関係ない」というわけではありません。厚生労働省では規模に関係なく、障害者雇用に積極的に取り組むことが望ましいとしています。
そのため、対象企業でなくても「努力義務」が課されていると考えるべきです。また、助成金の対象になる場合もあり、小規模でも障害者を雇用するメリットは少なくありません。
今後の雇用率引き上げや制度改正を見据えて、早いうちから社内体制を整えておくことが、持続的な経営の土台になります。
とはいえ、45.5人以下の企業は義務ではありませんので、45.5人以下の会社はほぼ障害者雇用をしていないと考えてよいでしょう。
大企業と中小企業で未達成率はどう違う?
大企業と中小企業での達成率・未達成率をみていきましょう。
【最新データ】企業規模別の達成・未達成率比較(2024年)
厚生労働省の令和6年(2024年6月1日)の「障害者雇用状況」報告によると、民間企業全体の法定雇用率達成企業の割合は46.0%で、未達成企業が54.0%を占めています。
| 企業規模(従業員数) | 実雇用率 | 達成率(割合) | 未達成率(割合) |
|---|---|---|---|
| 40.0~43.5人 | 2.10% | 33.3% | 66.7% |
| 43.5~100人未満 | 1.95% | 45.4% | 54.6% |
| 100~300人未満 | 2.19% | 49.1% | 50.9% |
| 300~500人未満 | 2.29% | 41.1% | 58.9% |
| 500~1,000人未満 | 2.48% | 44.3% | 55.7% |
| 1,000人以上 | 2.64% | 54.7% | 45.3% |
このデータからは、企業規模が小さいほど達成率は低く、未達成率は高くなる傾向がわかります。特に従業員数40〜100人未満の中小企業では、未達成企業が半数以上を占めています。
また、未達成企業のうち57.6%は、障害者を1人も雇用していない企業でした。これは障害者雇用に取り組んでいない企業も多いということを指しています。障害者雇用は採用、面接、定着などで配慮しなけれればいけないことが多く、もともと接点がない会社にはハードルが高いと言われています。
「法定雇用率は気にしない」「罰則で対応すればよい」と考えている企業も多いのが現状です。
中小企業が達成しづらい3つの理由
中小企業で達成率が低くなりやすい背景は、主に以下の3点です。
- 「あと0.5人でもアウト」な計算の厳しさ
小規模企業ではたった1人雇えないだけで未達成になるため、1人の雇用状況が結果に直結します。 - 採用後のフォロー体制が弱い
人事担当者が複数役割を担い、制度理解や社内整備が追いつかないケースが多くあります。 - 制度や助成金への理解不足
法改正(2024年4月の2.5%引き上げなど)や支援制度の情報が届いておらず、「コストがかかりそう」と敬遠されがちです。
しかし、未達成企業の大多数はあと一歩の状況であること、公的支援や民間サービスが充実していることを考えると、中小企業こそ早めに一歩を踏み出すことで、状況を改善しやすいという利点もあります。
自社が対象かどうかを簡単に確認する方法
常用労働者数のカウント方法
まず最初に確認すべきなのが、自社の「常用労働者数」が45.5人以上かどうかです。この人数を超えると、障害者を1人以上雇用する義務が発生します。
「常用労働者数」とは、正社員だけでなく一定の条件を満たすパート・アルバイトも含めた全従業員数です。具体的には、以下のような計算になります。
- 週30時間以上勤務:1人としてカウント
- 週20時間以上30時間未満:0.5人としてカウント
- 週20時間未満:基本的にカウント対象外
このように、労働時間によってカウント数が変わるため、従業員の勤務実態を正確に把握することが重要です。判断に迷う場合は、労務担当者やハローワークに相談するのも一つの手です。
雇用義務数の計算式と具体例
常用労働者数が把握できたら、次は自社が何人の障害者を雇用する必要があるかを計算します。2026年4月以降は法定雇用率が2.7%に引き上げられる予定ですので、それを踏まえた計算例を紹介します。
計算式:
従業員数 × 2.7% → 小数点は切り上げ
例:
- 従業員数:60人
- 60 × 2.7% = 1.62 → 切り上げて2人必要
小数点が出た場合は必ず切り上げになります。たとえば、1.01人でも2人雇用義務があるということになります。
なお、重度障害者を雇用した場合は「2人分」としてカウントされるなど、加算措置もあります。「常用労働者数 × 法定雇用率(2.5%または2.7%)」の計算によって、自社が義務対象かどうか、そして必要な人数がすぐに確認できます。
6. 法定雇用率を未達成だったときのリスクとは?
納付金制度(月5万円/人)について
法定雇用率を達成していない場合、一定規模以上の企業には「障害者雇用納付金制度」が適用されます。これは、障害者を雇用していない企業が、雇用している企業を財政的に支える仕組みです。
対象となるのは、常用労働者が100人を超える企業で、障害者の不足人数に応じて毎月納付金を支払う必要があります。
【具体的な納付金額】
- 不足1人あたり:月額5万円(年間60万円)
- 例えば、2人不足している場合 → 月10万円(年間120万円)の納付が必要
納付金は雇用の義務違反に対する罰金ではなく、障害者雇用を行っている企業への調整金や助成金の財源として使われます。ただし、金額が企業にとって大きな負担になることは事実です。
中小企業(常用労働者100人以下)の場合、納付金は原則として免除されていますが、将来的に対象範囲が拡大する可能性もあります。
社名公表・行政指導の可能性も
法定雇用率を長期間にわたって未達成のまま放置していると、行政による指導や勧告、最終的には企業名の公表といった厳しい措置が取られることもあります。厚生労働省では、以下のようなステップで対応しています。
- まずはハローワークなどを通じた指導・助言
- 是正が見られない場合 → 報告徴収・勧告
- さらに悪質な場合 → 社名公表(厚労省HPに掲載)
実際に、毎年数社が「障害者の雇用義務を著しく怠っている企業」として社名が公表されています。一度公表されてしまうと、企業イメージや取引先との関係に深刻な影響を及ぼす可能性もあるため、注意が必要です。
社名公表の対象となる可能性が高い企業の特徴
- 常用労働者が100人を超えている企業
原則として、社名公表の対象はこの規模以上の企業に限定されます。 - 障害者を一人も雇用していない企業
実雇用率が0%の企業は、行政から強く問題視されます。 - 行政の指導・助言に従わず改善が見られない企業
計画提出や採用活動を行わないなど、誠実な対応がない場合です。 - 同業他社と比べて著しく雇用状況が悪い企業
「業種全体で雇用が進んでいる中で自社だけがゼロ」という場合など。 - 過去に是正指導を受けており、再び未達成となっている企業
繰り返し対応を怠っている場合、悪質と判断されやすくなります。
中小企業であっても「指導対象」になることは十分にあり得ますので、制度への理解と早めの対応が重要です。とはいえ、現時点では行政指導が入っていない会社は公表の心配はありません。
ただ、ここまで国が障害者雇用に重点をおいていると、どこかのタイミングで法定雇用率の公表の義務化になるい可能性も十二分に考えられます。x
中小企業が法定雇用率を達成するには?
よくある課題とその対応策
中小企業が法定雇用率を達成するうえで、次のような課題を抱えているケースが多く見られます。
- 障害者を雇いたくても応募が来ない
地域や業種によっては、ハローワークに求人を出してもなかなか応募がないという声もあります。 - どんな仕事を任せたらいいかわからない
業務が多能工型であったり、障害の特性に合わせて仕事を切り出す経験がないため、受け入れをためらう企業もあります。 - 社内にサポート体制がない
定着支援のノウハウがなく、「入社してもすぐ辞めてしまった」という不安から踏み出せないケースも少なくありません。
こうした課題に対しては、以下のような対応策が現実的です。
- ハローワークの専門相談員や、障害者就業・生活支援センターに相談(無料)
- 就労移行支援事業所や特例子会社と連携し、採用前の実習を受け入れる
- 業務を細分化して「できる範囲の仕事」を切り出す
- 社内に相談窓口やメンター制度を設け、定着を支援する体制をつくる
重要なのは、「完璧な体制ができてから採用する」のではなく、まずは一歩踏み出してから、徐々に整えていくというスタンスです。
成功事例に学ぶ工夫
ここでは、実際に中小企業が法定雇用率を達成した事例をご紹介します。同じような悩みを持っていた企業が、どう工夫して乗り越えたのかが参考になります。
事例1:製造業(従業員60人)
工場内の「部品の検品・梱包」というルーティン業務を切り出して、障害者1名を雇用。職場の理解を深めるために、社内研修を実施したところ、現場からの協力も得られるようになり、定着率も向上しました。
事例2:小売業(従業員80人)
在庫管理や清掃業務などをパートタイムで任せる形で障害者を採用。本人の希望を踏まえて週3日勤務からスタートし、徐々に業務を拡大。社内のメンター制度を設けたことで、安心して働き続けられるようになりました。
事例3:IT企業(従業員50人)
就労移行支援事業所と連携し、在宅でできるデータ入力業務を用意。試用期間中にスキルや特性を確認し、マッチした人材を本採用。リモート勤務でも十分に戦力になることが社内でも評価されています。
このように、業務の工夫・支援制度の活用・柔軟な雇用形態などを取り入れることで、中小企業でも十分に法定雇用率を達成することが可能です。
最初は小さな工夫からで構いません。社内の「理解」と「協力」こそが成功のカギなってきます。
中小企業向けの助成金・支援制度を活用しよう
代表的な助成金制度
障害者の雇用に取り組む中小企業に対しては、さまざまな助成金制度が用意されています。費用面の負担を軽減しながら、採用・定着支援を行うためにも、ぜひ活用したい制度です。
- 特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者など、就職が困難な人をハローワーク等の紹介で雇用した場合に支給。〈例〉重度障害者を継続雇用した場合、最大240万円(1年目120万+2年目120万) - 障害者トライアル雇用助成金
障害者を一定期間(原則3か月)試行的に雇用する制度。対象者1人につき最大月額4万円(最大12万円)支給。 - 障害者職場支援推進助成金
雇用した障害者のために社内の環境整備・サポート体制の構築を行った場合に支給される制度。〈例〉支援担当者(ジョブコーチ)配置のための研修や社内研修に対する補助など。
これらの助成金は、単独で使うだけでなく、組み合わせて活用することも可能です。「採用」「定着」「体制整備」といった目的別に支援が用意されている点がポイントです。
助成金活用の流れと注意点
助成金を受け取るには、所定の手続きやタイミングを守ることが必須です。以下は一般的な流れです。
- ハローワークや労働局で制度説明を受ける
不明点があれば、事前相談がベストです(無料) - 申請前に「計画書」や「申請書類」を提出
多くの制度は雇用前に申請が必要です。 - 対象者の採用・就労スタート
- 所定の期間終了後に実績報告を提出
- 審査後、助成金が支給される
注意点
- 事前申請が原則:採用後に申請しても受理されない場合があります
- 書類不備に注意:雇用契約書や出勤記録など、証拠書類の保存が必要です
- 対象者要件に合致しているかの確認:障害者手帳の有無や紹介元など
助成金は正しく準備すれば確実に活用できる制度です。とはいえ、助成金を申請から受け取るまではかなり細かくハードルが高いといえます。人事担当者が無理するのではなく、障害者雇用に強いコンサルタントに相談するなどして進めるのが賢いやり方です。
専門機関や外部サービスの活用方法
公的支援機関(ハローワーク等)
中小企業が障害者雇用に取り組むうえで、最も手軽に相談できるのがハローワークです。全国に設置されており、無料で相談・求人掲載・マッチング支援などを受けることができます。
- ハローワーク(公共職業安定所)
専門の「障害者職業相談員」がおり、採用から助成金の相談まで幅広く対応。 - 障害者就業・生活支援センター
障害者本人だけでなく、企業に対しても支援を行う地域密着型の機関。採用後のフォローや職場定着支援も得意としています。 - 地域障害者職業センター
職場適応訓練や評価、職務分析など、専門的なアドバイスが得られる機関。
「誰に相談したらいいかわからない」というときは、まずはハローワークに相談するのが第一歩です。必要に応じて、これらの専門機関とも連携してサポートを受けられるようになっています。
就労移行支援や特例子会社との連携
障害者雇用を円滑に進めるためには、民間の専門サービスを活用するのも有効です。特に以下のような事業者や制度が注目されています。
- 就労移行支援事業所
働きたい障害者に対して、就職に向けたトレーニングや職場体験などを提供する事業所。企業と連携して実習受け入れやマッチング支援を行ってくれる場合もあります。 - 特例子会社
障害者雇用を目的として設立された企業グループ内の子会社で、雇用率のカウント対象にもなります。中小企業が単独で雇用が難しい場合、外部委託や連携により雇用義務を一部達成することが可能なケースもあります。 - 民間の障害者雇用コンサルティング会社
制度対応・業務設計・助成金申請までトータルで支援してくれるサービスも増えています。
これらの外部機関を上手に活用することで、自社内に専門知識がなくても、雇用の第一歩を踏み出しやすくなります。
「人がいないから無理」ではなく、「人を借りてでも始められる」が、いまの障害者雇用の現実です。
よくある質問(FAQ)
Q1:パートでもカウントされるの?
はい、労働時間が週20時間以上あれば、パートタイム労働者も法定雇用率の対象としてカウントされます。ただし、週20〜30時間未満の場合は「0.5人」として換算されます。
Q2:在宅勤務の障害者でも対象になる?
はい、在宅勤務でも就労実態があれば法定雇用率のカウント対象になります。雇用契約・勤務実態・業務指示が明確であれば問題ありません。
Q3:1人雇えば達成になる?
企業の常用労働者数によって異なります。たとえば、従業員が60人であれば、2.5%の法定雇用率により1.5人 → 切り上げて2人必要となるため、1人では未達成となります。
Q4:雇った後の定着支援は?
障害者就業・生活支援センターやジョブコーチ支援を活用することで、職場定着の支援が受けられます。また、企業側でメンター制度や相談窓口を設けるのも効果的です。
Q5:法定雇用率は今後も上がるの?
はい、すでに2026年7月に2.7%へ引き上げが決まっており、将来的にもさらに上がる可能性があります。
Q6:障害者手帳がない人もカウントできる?
基本的には障害者手帳を持っている人がカウント対象ですが、特定の難病患者などは例外的に対象となることもあります。
Q7:精神障害者も雇用対象になるの?
はい、身体・知的・精神いずれの障害も対象です。精神障害者手帳を持つ方も法定雇用率の対象となります。
Q8:雇用義務の人数はどうやって計算するの?
常用労働者数 × 法定雇用率(現在は2.5%)で計算し、小数点は切り上げます。
Q9:障害者を1人雇うと助成金がもらえる?
条件を満たせば複数の助成金が利用可能です。例:特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金など。
Q10:定着率を上げるコツは?
仕事内容の明確化・社内理解の促進・相談体制の整備がポイントです。定着支援には外部機関の協力も有効です。
Q11:達成していないとどんな罰則がある?
常用労働者100人超の企業は納付金(月5万円/人)が発生します。さらに、長期未達成で改善が見られない場合は社名公表のリスクもあります。
Q12:障害者の仕事はどんな内容が多い?
職種によりますが、軽作業、事務補助、清掃、データ入力などがあります。本人の希望やスキルに合わせた仕事の調整が大切です。
Q13:障害者に配慮すべきことは?
コミュニケーション方法、勤務時間、作業手順、環境面など、個別の特性に応じた配慮が求められます。無理に特別な設備を整える必要はありません。
Q14:実習や試用期間は設けられる?
はい、就労移行支援やトライアル雇用制度などを活用して、雇用前に実習を行うことが可能です。
Q15:中小企業でも社名公表されるの?
原則として従業員100人超の企業が対象ですが、中小企業でも行政指導や是正勧告の対象
まとめ|法定雇用率対応は中小企業の経営戦略にもなる
この記事のまとめ
ここまで、中小企業における法定雇用率への対応について、基本から実務、支援制度まで幅広く解説してきました。
最後に、ポイントを3つにまとめておさらいしましょう。
- 中小企業も対象となる場合がある
従業員が45.5人を超えると、障害者雇用の義務が発生します。 - 未達成率は高いが、対策すれば改善できる
採用・定着の工夫や、外部機関の協力を得れば、中小企業でも十分に達成可能です。 - 助成金や外部支援を上手に活用すれば、経済的にも負担を軽減できる
制度を理解し、段階的に進めることでリスクを抑えつつ実現できます。
法定雇用率は「ただの義務」ではなく、企業の社会的信頼や、経営の持続性を高めるチャンスにもなり得ます。
まずは「自社が対象か」をチェックしよう
記事を読んで「うちもそろそろ考えなきゃ」と感じた方は、まずは常用労働者数を確認することから始めてみましょう。
従業員数 × 法定雇用率(2024年時点で2.5%、2026年から2.7%)で、必要な雇用人数がすぐに分かります。
そのうえで、ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどの専門機関に相談すれば、採用から支援制度まで一緒に考えてくれます。「制度が難しそう」と思っていた方も、意外と身近なサポートがあると気づいてもらえるはずです。
小さな一歩が、企業と社会の未来を大きく変えるかもしれません。