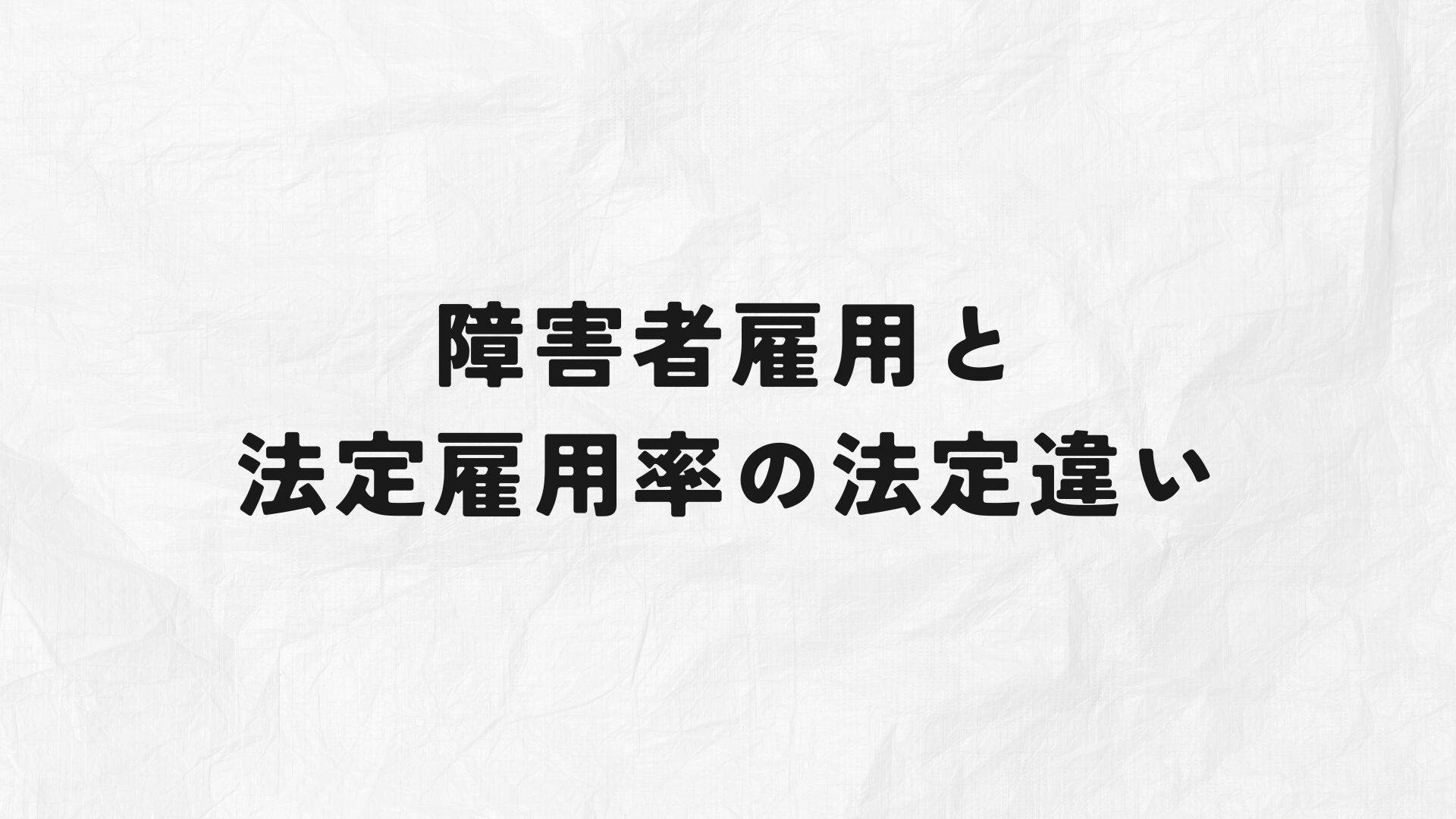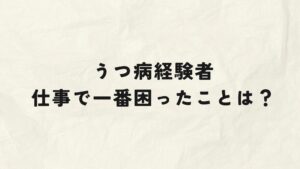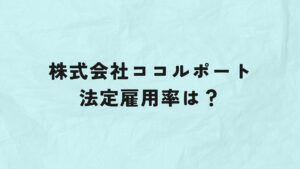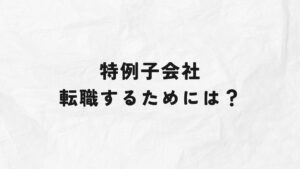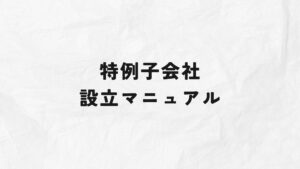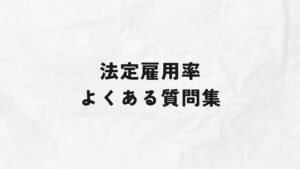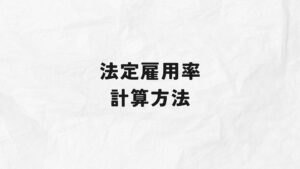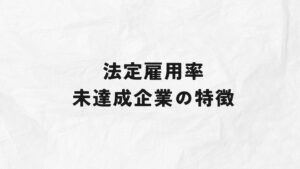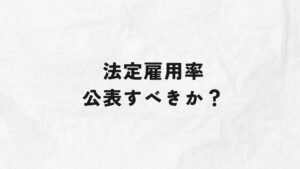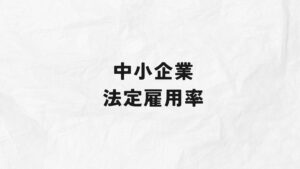「障害者雇用」と「法定雇用率」──よく耳にする言葉ですが、意味の違いを正しく説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか?
企業にとっては義務でもあり、社会的責任でもある障害者雇用。しかし、「とりあえず法定雇用率を満たせばいい」と考えてしまうと、大切な本質を見失ってしまうかもしれません。
この記事では、「障害者雇用」と「法定雇用率」の違いをわかりやすく整理しながら、初心者の方にも理解しやすいように基礎から丁寧に解説します。また、制度の背景や企業の取り組み事例、未達成時のリスクまでわかりやすく紹介していきます。
障害者雇用と法定雇用率の違いとは?
そもそも「障害者雇用」とは何か
「障害者雇用」とは、障害のある人が自分の力を活かして働けるよう、企業や行政が仕事の機会を提供することです。たとえば、車いすを使っている人が働きやすいように段差のない職場環境を整えたり、精神的な不調がある方が無理なく働けるように配慮した働き方を導入するなども含まれます。
つまり、障害のある方が「安心して」「長く」働けるように支援すること全体を「障害者雇用」と呼びます。
法定雇用率とは何を意味する?
一方で「法定雇用率」とは、企業が障害のある方を一定の割合で雇うよう法律で決められている基準のことです。
2025年時点では、従業員が43.5人以上いる企業は、2.5%以上の割合で障害者を雇う必要があります(2026年からは2.7%に引き上げ予定)。従業員100人の会社は2.5名(切り上げで3名)、従業員1000人の会社は25名の障害者の方を雇用する義務があります。
この「数字の目標」が法定雇用率です。
混同しがちなポイントと明確な違い
この2つは混同されがちですが、まとめるとこんな感じです。
障害者雇用:障害のある方を雇い、働きやすい環境をつくる取り組み全体
法定雇用率:その取り組みの中で、最低限守らなければならない「雇用割合」のこと
つまり、「障害者雇用」は広い意味を持つ言葉で、「法定雇用率」はその中の一つのルール。障害者雇用=目的、法定雇用率=そのためのルール、と理解するとわかりやすくなります。
法定雇用率の基本をおさらい
なぜ法定雇用率が定められているのか
障害のある人が働きやすい社会をつくるためには、「企業が積極的に雇用に取り組むこと」が欠かせません。しかし、任意に任せてしまうと、障害者の就職先がなかなか増えないという課題がありました。
そこで国は、企業に対して「一定割合の障害者を雇うこと」を法律で義務づけました。これが法定雇用率です。これは、障害者の就労の機会を守るための最低ラインであり、企業の社会的責任を果たすための基準でもあります。
最新の法定雇用率(2024年→2026年)
法定雇用率は時代とともに少しずつ引き上げられています。2024年と2026年の改定内容は以下の通りです。
- 2024年4月~:民間企業の法定雇用率は 2.5% に引き上げ
- 2026年7月~:さらに 2.7% に引き上げ予定
この変更は、「障害者の雇用数が年々増えていること」や「多様な働き方の実現」を背景としています。今後も社会状況に応じて法定雇用率が見直される可能性があるため、企業としては継続的に制度を把握しておくことが大切です。
対象となる企業とその基準
法定雇用率の適用対象となるのは、従業員が43.5人以上いる企業です(2024年現在)。これを超える企業は、法定雇用率に基づいて障害者を雇用する義務があります。
たとえば、従業員が100人の企業であれば…
- 100人 × 2.5%(2024年時点)=2.5人 → 少なくとも3人の雇用が必要
- 2026年になると → 100人 × 2.7%=2.7人 → やはり3人必要
また、雇用率の算出では、短時間勤務の社員も一定条件で換算対象になります。たとえば週20時間以上働くパート社員は0.5人としてカウントされるなど、雇用形態に応じて細かなルールがあります。
制度を正しく理解することで、意図せず未達成になってしまうリスクを避けることができます。
障害者雇用の具体的な形
一般就労と福祉的就労の違い
障害者雇用には、大きく分けて「一般就労」と「福祉的就労」の2つの形があります。
一般就労とは、企業や官公庁などで他の従業員と同じように働く形です。給料が支払われ、雇用契約が結ばれている点が特徴です。障害者雇用のうち、法定雇用率のカウント対象となるのは、この一般就労にあたります。
一方で福祉的就労は、就労継続支援A型・B型や生活介護など、福祉サービスの一環として行われる働き方です。主に「一般企業で働くのはまだ難しい」という人が対象で、訓練や支援を受けながら、ステップアップを目指す場となります。
ポイント:福祉的就労は法定雇用率の対象外です。就労支援の段階と捉えるとわかりやすいでしょう。
雇用形態の種類(正社員・パート・特例子会社など)
障害者雇用は、さまざまな雇用形態で行われています。正社員として長期雇用される方もいれば、パートや契約社員として柔軟に働く方もいます。企業側は、障害のある方の希望や特性に応じて、無理のない働き方を選べるよう配慮することが求められます。
また、障害者雇用を専門的に行う「特例子会社」という制度もあります。これは、障害者のために特別な支援体制を整えた子会社で、親会社の法定雇用率の達成にもカウントできる仕組みです。
LITALICOやゼネラルパートナーズなどは、障害者雇用に特化した事業を展開しており、さまざまな雇用形態に対応しています。
在宅勤務やテレワークも対象?
近年では、テレワークや在宅勤務という新しい働き方も広がっており、障害者雇用でも積極的に導入され始めています。
結論から言うと、一定の条件を満たせば、在宅勤務も法定雇用率の対象となります。
- 雇用契約が正式に結ばれていること
- 定期的な業務の指示や報告が行われていること
- 就労の実態が確認できること
テレワークは、通勤に不安がある方や、身体的・精神的な理由で在宅の方が働きやすいという方にとって、大きな可能性を広げる選択肢となっています。
今後、障害者雇用とテレワークはさらに親和性を高めていくと考えられます。
法定雇用率の計算方法
従業員数のカウント方法
法定雇用率の対象になるかどうか、また何人の障害者を雇えばよいかを判断するには、まず「従業員数」のカウント方法を知っておく必要があります。
ここで言う「従業員数」とは、常時雇用されている労働者を指します。
- 正社員(フルタイム)
- 契約社員・嘱託社員
- 週30時間以上働くパートタイム労働者
逆に、季節雇用や日雇い労働者、一時的な派遣スタッフなどは、原則としてカウントされません。この従業員数をもとに、法定雇用率をかけて「障害者を何人雇うべきか」を算出します。
カウントに含まれる障害者とは
では、「障害者」としてカウントされるのはどのような方でしょうか?法定雇用率における対象者は、主に以下のとおりです。
- 身体障害者手帳を持っている方
- 知的障害者(療育手帳などで確認)
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
特に注意が必要なのは、「精神障害者」については、2018年4月から正式にカウント対象となった点です。
また、対象となるには、ハローワークへの雇用状況報告で適切に申告されていることが条件になります。申請が漏れていると、雇っていてもカウントされない場合があるので要注意です。
パートタイム・短時間労働者の扱い
障害者の中には、体調や通院の関係などで短時間勤務を希望する方も少なくありません。このような方でも、一定の条件を満たせば法定雇用率のカウント対象となります。
- 週20時間以上30時間未満 → 0.5人としてカウント
- 週30時間以上 → 1人としてカウント
たとえば、週20時間働いているパートの障害者2人は、「1人分」としてカウントされます。短時間勤務が主流の業界や企業でも、柔軟な雇用をしながら法定雇用率を達成することは十分可能です。実際に、多くの企業がパートや在宅勤務を組み合わせて雇用数を満たしています。
法定雇用率を達成している企業の取り組み
成功企業の取り組み事例(ゼネラルパートナーズ・manabyなど)
法定雇用率を安定的に達成している企業は、「障害者だから特別扱いする」のではなく、「その人が力を発揮できる環境をつくる」ことを大切にしています。
たとえば、ゼネラルパートナーズは就労支援事業や教育サービスを通じて、障害者雇用を「社会課題の解決」として積極的に取り組んでいます。自社でも障害のあるスタッフが活躍できるよう、業務を細分化したり、個別のサポート体制を整えるなど、現場レベルでの配慮が徹底されています。
また、manabyはITスキルの習得支援を軸にした就労移行支援事業を展開しており、「在宅訓練→在宅就労」といった新しい働き方を提案。障害者が自宅で安心してスキルを磨き、そのまま企業へとステップアップできる環境づくりをしています。


中小企業でもできる工夫
「うちは大企業じゃないから難しい…」と思う中小企業の方も多いかもしれません。しかし、工夫次第で法定雇用率を無理なく達成している中小企業もたくさんあります。
- 業務の一部を障害者向けに切り出して簡略化する
- 週20時間程度の短時間勤務からスタートする
- 在宅でできるPC業務を導入する
このように、「できることから始める」ことが大切です。障害者雇用の経験がない企業でも、就労移行支援事業所や地域のハローワークと連携することで、マッチングやサポート体制が整います。
障害者から見た「働きやすい会社」とは
障害のある方が「ここで働きたい」「ここなら安心して続けられる」と思える会社には、いくつかの共通点があります。
- 話しやすい上司や相談できる窓口がある
- 体調やペースに配慮した柔軟な勤務制度
- 業務マニュアルや指示がわかりやすい
- 「できないこと」より「できること」に目を向けてくれる
こうした環境を整えることは、障害者にとってだけでなく、すべての従業員にとって働きやすい職場づくりにもつながります。
法定雇用率を「義務」と捉えるのではなく、「組織の質を高めるチャンス」として活かすことが、これからの企業経営に求められています。
法定雇用率と企業価値の関係
ESGやSDGsの文脈での評価
近年、企業経営において「利益」だけでなく、「社会的責任」や「環境への配慮」なども重視されるようになっています。その代表例が、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)です。
障害者雇用は、これらの考え方と深くつながっています。特に「誰一人取り残さない社会」を目指すSDGsの観点からは、障害のある方を含む多様な人材の雇用は重要なテーマです。
企業が法定雇用率をしっかり達成し、障害者が働きやすい環境を整えることは、社会からの評価を高める要素になります。
IRや投資家へのアピール材料に
上場企業や大手企業にとっては、投資家への情報開示(IR)も重要な取り組みです。近年では、障害者雇用の状況やダイバーシティ施策を積極的に公開する企業も増えており、それが投資家からの信頼獲得につながるケースも多くなっています。
たとえば、ESG評価機関のレポートで「障害者雇用の取り組み」がポジティブに評価されたり、社会貢献性の高い企業としてサステナブル投資の対象になることもあります。
つまり、法定雇用率の達成は「義務」の範囲を超え、企業価値を高める戦略的な取り組みとして活用できるのです。
採用力・ブランディングにも影響
法定雇用率の達成や障害者雇用への積極的な姿勢は、採用活動や企業ブランディングにも良い影響を与えます。
現代の求職者、特に若い世代は「企業がどんな社会貢献をしているか」「働きやすい職場かどうか」を重視する傾向が強くなっています。そのため、ダイバーシティやインクルージョンに力を入れている企業は、「人が集まる会社」として注目されやすくなります。
また、企業のホームページや採用ページで、障害者雇用の取り組みをしっかり伝えることで、信頼感や共感を生み、良い人材との出会いにつながることも少なくありません。
よくある誤解とその解消
「障害者を雇うのは大変」という誤解
障害者雇用について、「コストがかかる」「業務の調整が難しそう」といった不安の声をよく耳にします。しかし実際は、正しい知識と準備があれば、決して「大変すぎる」ものではありません。
たとえば、すべての業務を任せる必要はなく、一部業務の切り出しやマニュアル化で十分に活躍できる場面も多くあります。また、国や自治体からは助成金制度や専門家による無料支援も充実しており、ひとりで抱え込む必要はありません。
「特別扱いする」のではなく、「一緒に働く仲間として必要な配慮をする」という視点が大切です。
「法定雇用率だけ満たせばいい」は本当?
法定雇用率を満たすことは、確かに企業にとっての「最低限の義務」です。しかし、それだけで「良い企業」とは言えません。
雇用人数だけをクリアしていても、職場環境が整っていない、仕事を与えていない、形だけの雇用であれば、本質的な意味での障害者雇用とは言えないのです。
逆に、法定雇用率を上回って積極的に取り組んでいる企業は、社内外からの評価も高まり、ESG・SDGs文脈での価値も向上します。「数字だけ」ではなく「中身のある雇用」が今、求められています。
採用後のサポート体制の重要性
障害者雇用で最も大切なのは、「採用して終わり」ではないという意識です。採用後に必要なのは、定着支援や相談しやすい社内環境の整備。
- 定期的な面談・フィードバック
- 業務量や勤務時間の柔軟な調整
- 専門知識を持った社内担当者の配置(障害者職業生活相談員など)
また、外部の就労移行支援事業所やハローワークとも連携することで、企業単独では難しい支援もカバーできます。採用はあくまでも最初のハードルで「安心して長く働ける環境づくり」こそが、障害者雇用の成功のカギなのです。
まず何から始めればよい?
社内体制の整備
障害者雇用をはじめるにあたって、最初に取り組みたいのが社内体制の見直しです。いきなり採用活動を始めるのではなく、まずは「受け入れ準備」を整えることが重要です。
- 業務の切り出しやマニュアル化
- 相談できる担当者(メンター)の配置
- 職場環境のバリアフリー化や配慮事項の確認
また、社内で障害者職業生活相談員を任命しておくと、採用後のサポートがスムーズになります。こうした整備があることで、企業側も従業員側も安心してスタートできます。
外部支援・助成金の活用
障害者雇用に関しては、国や自治体から豊富な支援制度が用意されています。
- トライアル雇用助成金:お試し雇用の期間に支給される
- 特定求職者雇用開発助成金:継続的な雇用を行った際に支給
- 職場改善助成金:バリアフリー設備の導入などに使える
こうした制度を活用することで、費用面の負担を軽減しつつ、安心して障害者雇用に取り組むことができます。また、就労移行支援事業所との連携によって、企業に合った人材をマッチングしてもらうことも可能です。
無料で相談できる窓口
「何から始めたらいいのかわからない…」という場合は、無料で相談できる公的機関を活用するのがおすすめです。
- ハローワーク:障害者雇用専門の担当者が常駐
- 地域障害者職業センター:職場適応支援などのアドバイスが可能
- 就労移行支援事業所:候補者の紹介や実習の受け入れ相談も可能
これらの機関では、制度の説明や支援内容、雇用事例の紹介なども丁寧に対応してくれます。まずは話を聞いてみるだけでも、きっと大きな一歩になります。
法定雇用率を超える企業になるために
プラスαの雇用が与える価値
法定雇用率は「最低限のライン」ですが、それを上回って雇用する企業も増えてきています。なぜなら、障害者雇用は義務であると同時に、企業価値を高める戦略にもなり得るからです。
たとえば、社内の多様性が広がることで、チームの創造力や柔軟性が高まり、業務の効率化やサービス向上につながることもあります。また、CSR(企業の社会的責任)やESG評価の観点からも、プラスαの雇用は社会からの信頼を得る大きなアピールポイントになります。
採用だけでなく「定着率」にも目を向ける
障害者雇用の本質は、「雇うこと」ではなく「安心して働き続けてもらうこと」にあります。
せっかく採用しても、職場環境や業務内容が合っていなければ、早期退職につながることも。定着率を高める工夫がとても重要です。
- 定期的な面談やキャリア相談
- 体調に合わせた勤務時間の調整
- スモールステップでの業務習得
- 職場全体の理解促進(社内研修や啓発)
こうした取り組みは、障害のある社員だけでなく、他の社員の働きやすさにもつながるため、企業全体のエンゲージメント向上にも効果的です。
障害者雇用=企業の戦略的資産
障害者雇用を「法令対応」や「社会貢献」としてだけ捉えるのは、もったいない考え方です。
むしろ、多様な人材の活用は、変化の多い現代社会において、企業が生き残るための「戦略的資産」とも言えます。たとえば、障害のある方の視点から新しいサービスが生まれたり、業務の見直しによって無駄の削減や効率化が進むこともあります。
「障害者雇用を進めたことで、会社全体が変わった」「職場の雰囲気が良くなった」といった声も多く、実際に組織文化の向上にもつながっているのです。
これからの時代、法定雇用率を「超える企業」こそが、信頼され、選ばれる存在になっていくでしょう。
まとめ|障害者雇用と法定雇用率の理解が企業の未来を変える
- 障害者雇用=取り組み全体、法定雇用率=法律上の数値基準
- 法定雇用率は「義務」だが、その先にあるのは企業価値の向上
- まずは自社の現状を把握し、小さな一歩から。
障害者雇用は、単に法律を守るだけの取り組みではありません。多様な人材を受け入れ、共に働くという姿勢は、企業の柔軟性や信頼性を高め、長期的な成長の土台になります。
「うちはまだ準備ができていない」と感じている企業こそ、今が見直しのチャンスです。社内の意識改革から始めるだけでも、障害者雇用の第一歩になります。