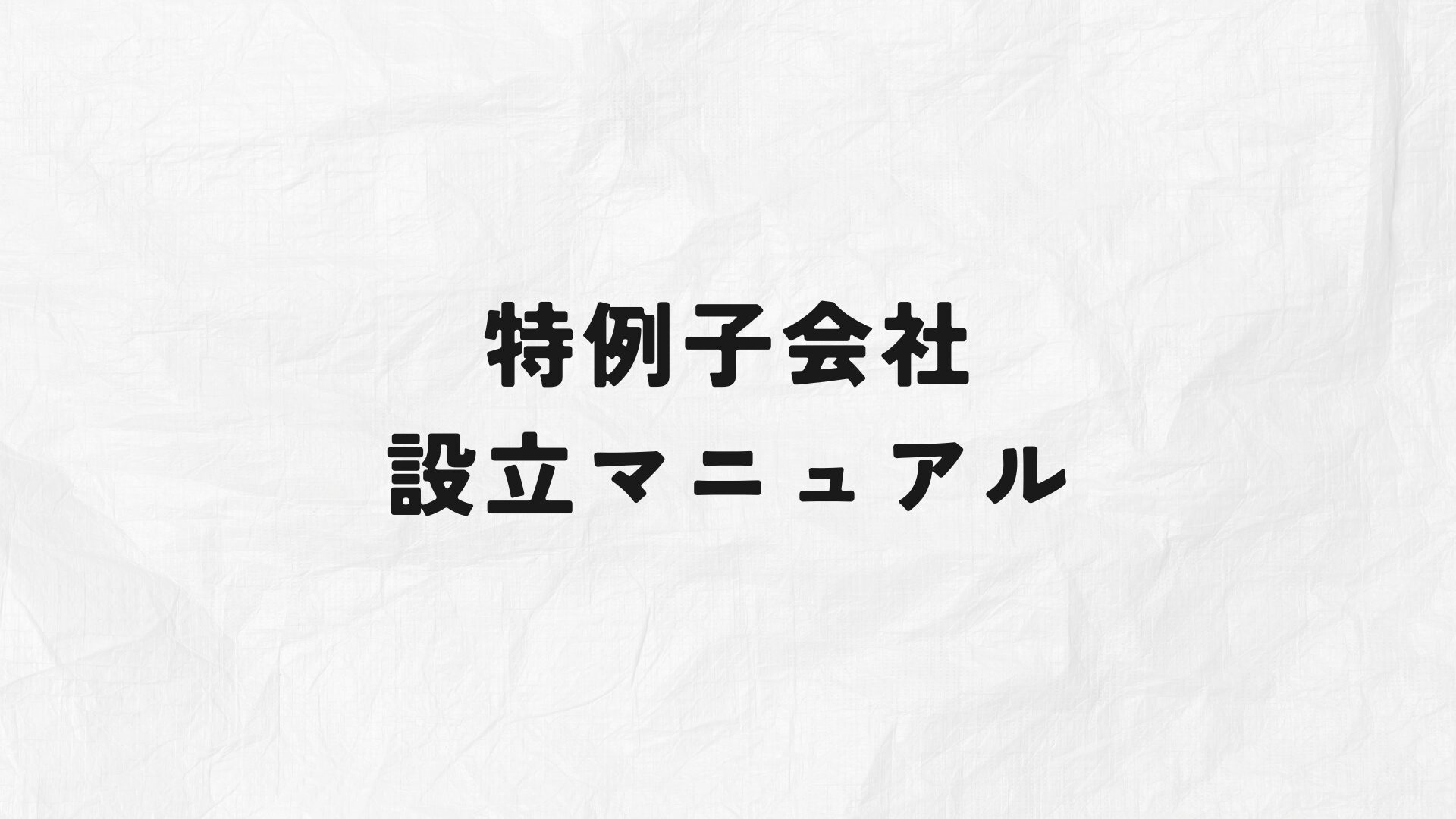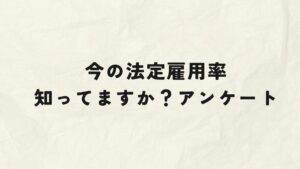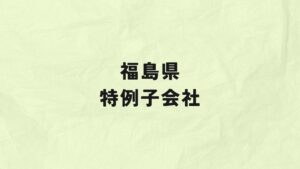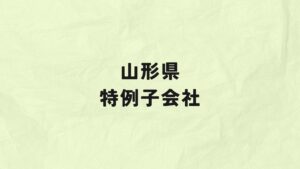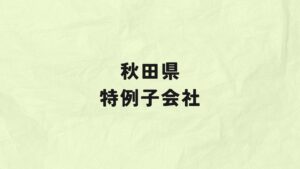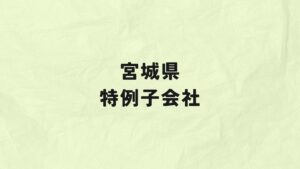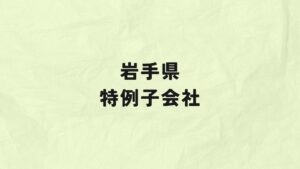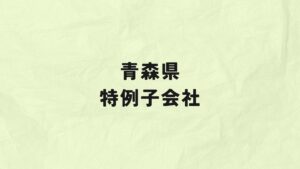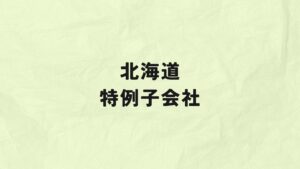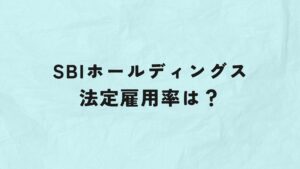「障害者雇用を進めたいけれど、社内に十分な受け入れ体制がない…」
そんな悩みを抱える企業にとって、有効な選択肢のひとつが「特例子会社」の設立です。
特例子会社とは、障害のある方を安定して雇用することを目的とした、グループ会社内の特別な子会社のこと。障害者雇用促進法にもとづいて認定を受ければ、親会社を含む企業グループ全体で法定雇用率を満たすことができるというメリットがあります。
実際に大企業だけでなく、中小企業や地域密着型の会社でも特例子会社を活用する動きが広がっており、雇用の多様性や社会的責任(CSR・ESG)を果たす手段として注目が高まっています。
とはいえ、「設立までにどんな準備が必要なのか?」「認定を受けるには何をすればいいのか?」「助成金は使えるのか?」といった疑問や不安を感じる方も多いはず。
本記事では、特例子会社の設立を考えている企業向けに、基礎知識から設立手順、必要書類、よくある失敗例、助成金制度までをわかりやすく解説していきます。
人事・総務部門の方はもちろん、経営層の皆さまも、ぜひこの記事を参考にして頂ければ幸いです。
特例子会社とは?基礎知識と背景を解説
特例子会社ってなに?
特例子会社(とくれいこがいしゃ)とは、障害のある人たちを安定して雇用することを目的とした、親会社のグループ会社のことです。かんたんに言えば、「障害のある方を安心して働けるようにサポートするための、特別な会社」と思ってください。
厚生労働省から「特例子会社」として認定されることで、親会社やグループ全体での障害者雇用率にカウントできるという特徴があります。
どうしてできたの?
特例子会社の仕組みは、障害のある方の働く機会を増やすために作られました。企業には「障害のある人を一定の割合で雇いましょうね」という決まり(=法定雇用率)がありますが、実際には「社内に受け入れ体制がない」「配慮が難しい」という理由でうまく進まないことも…。
そこで、障害者雇用に特化した子会社を作り、そこでまとめて雇うことで、障害のある人も安心して働けて、企業も法律を守れるようにしたのが「特例子会社」なんです。
どんな会社が使ってるの?
特例子会社は、トヨタやソニー、ユニクロ(ファーストリテイリング)など、大手企業を中心に導入が進んでいます。でも、最近では中小企業やベンチャー企業でも、グループ内に設立する動きが少しずつ広がってきています。
実は2025年時点で、全国に500社以上の特例子会社があるんです。
ふつうの子会社と何が違うの?
一見ふつうの子会社と同じように見えますが、特例子会社にはいくつか特別なルールがあります。
- 障害のある人が働きやすいよう、環境を整える必要がある
- 支援員(ジョブコーチなど)を配置して、仕事のサポートをする
- 親会社と連携しながら、雇用全体をコーディネートする
こうした点が、ふつうの子会社と違うところです。
「障害者のために特化した雇用の場をつくる」という明確な目的があるのがポイントです。
これからもっと増えるってほんと?
はい、本当です。今後は企業の社会的責任(CSR)や多様性の推進(ダイバーシティ&インクルージョン)といった観点からも、特例子会社のニーズが高まっていくと考えられています。
また、障害者雇用の義務がより厳しくなる方向にあるため、対策のひとつとして注目されているんです。
次の章では、そんな特例子会社を作ることでどんなメリットがあるのか?をわかりやすく紹介していきます!特例子会社についてさらに詳しく知りたい方は下記を参考にしてください。
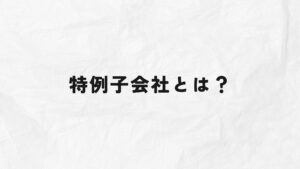
エリア別特例子会社記事一覧

法定雇用率ナビに掲載をしているエリア別の特例子会社記事になります。ぜひ参考にしてください。
- 北海道エリア・東北エリアの特例子会社一覧
- 関東エリアの特例子会社一覧
- 中部エリアの特例子会社一覧
- 近畿エリアの特例子会社一覧
- 中国エリアの特例子会社一覧
- 四国エリアの特例子会社一覧
- 九州エリア・沖縄エリアの特例子会社一覧
特例子会社を設立するメリット
「特例子会社って、なんとなく良さそうだけど… 実際に作るとどんなメリットがあるの?」ここでは、特例子会社を設立することで得られる主な5つのメリットを、初心者向けにわかりやすく紹介します。
1. グループ全体で法定雇用率をクリアできる
企業には「一定割合以上、障害のある方を雇用しましょうね」という法律上のルール(法定雇用率)があります。
ですが、「本社では雇用が難しい」「事業所によって状況が違う」というケースも多いですよね。
そんなとき、特例子会社があるとその会社で雇用した障害者の人数を、グループ全体の達成率にカウントできるんです。つまり、グループの中で障害者雇用を集中的に行うことで、全体の雇用率を効率よくクリアできるというわけです。
2. 専門的な支援ができて、職場定着率がアップ
特例子会社では、障害のある方が安心して長く働けるような体制づくりが前提です。
- 支援員(ジョブコーチ)による日々のサポート
- 働きやすい職場レイアウトや配慮
- ひとりひとりの特性に合わせた業務設計
こうした取り組みによって、「雇って終わり」ではなく、無理なく定着して働き続けられる職場を作ることができます。
3. 社会的評価・ブランド価値が上がる
最近は、障害者雇用や多様性にしっかり取り組む企業が投資家や消費者から選ばれる時代になっています。特例子会社を設立し、しっかりと運営している企業は、
- ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の対象になりやすい
- SDGsへの取り組みを対外的にアピールできる
- 採用面でも好印象につながる
といった社会的な信頼やブランド価値の向上にもつながります。
4. 助成金や支援制度が利用できる
特例子会社を設立する際には、国や自治体からの助成金を活用できる場合があります。
- 特例子会社等設立奨励金
- 職場適応援助(ジョブコーチ)制度
- 設備改修費用に対する補助金
などがあり、費用面の負担を軽くすることが可能です。「お金の面が心配…」という企業でも、上手に活用すればスムーズなスタートが切れます。
5. 組織の多様性が進み、社員の意識も変わる
障害のある方と一緒に働くことで、社内のコミュニケーションや考え方にも変化が生まれます。「お互いに助け合う」「相手の立場を考える」そんな姿勢が自然と根づいていくんですね。
結果として、
- 社員のエンゲージメントが向上
- やさしい会社づくりにつながる
- 離職率の低下やチーム力の強化にも好影響
といった副次的なメリットも期待できます。特例子会社は「法律を守るため」だけでなく、企業にとっても、社会にとっても良いことがたくさんある制度なんです。
特例子会社を設立する際のデメリット・注意点
ここまで読んで、「特例子会社、すごく良さそう!」と感じた方も多いと思います。ですが、メリットばかりではなく、注意すべきポイントやデメリットもちゃんと知っておくことが大切です。
ここでは、設立を検討する際に知っておきたい5つの注意点を、わかりやすく解説します。
1. 設立には時間と手間がかかる
特例子会社をつくるには、しっかりとした準備が必要です。業務内容を決めたり、施設を整えたり、申請書類を用意したりと、数か月~1年ほどの期間がかかるケースもあります。
特に初めての方にとっては、「どこから手をつければいいの?」と戸惑うかもしれません。そのため、専門家や支援機関と連携することが成功のカギになります。
2. ランニングコストがかかる
特例子会社では、障害のある方が安心して働けるよう、支援スタッフの配置や職場環境の整備などが求められます。そのため、通常の子会社と比べると人件費や設備投資がかかる傾向があります。
助成金をうまく使えば負担を軽くできますが、中長期的な運営コストの見通しも立てておくと安心です。
3. 事業とのマッチングが重要
「とりあえず作る」ではうまくいきません。大切なのは、自社の業務内容と、障害者雇用がきちんとマッチしているかどうか。
- マニュアル化しやすい作業があるか?
- 勤務時間や配慮が必要な業務に適しているか?
- 他部署との連携はスムーズにできるか?
といった視点で、「この仕事なら安心して任せられる」環境を整えることが必要です。
4. 社内理解と協力がカギ
特例子会社の成功には、親会社や他部署の理解と協力が欠かせません。「障害者雇用はあっちの部署がやること」ではなく、グループ全体で取り組む姿勢が大切です。
- 社内説明会や研修の実施
- 障害者雇用の意義の共有
- 部門間の情報共有・連携体制の構築
といった、全社的な意識づけが必要になります。
5. 認定後も運営が続く
認定されたからといって終わりではありません。むしろそこからが本番です。定期的な報告や雇用状況の確認、業務改善や社員サポートなど、長く運営していく体制づくりが求められます。
「作っただけ」で終わらせず、継続的に見直しや改善ができる仕組みを考えておくことが大切です。
以上が、特例子会社設立における代表的な注意点です。メリットがたくさんある一方で、本気で取り組むからこそ価値がある制度とも言えますね。
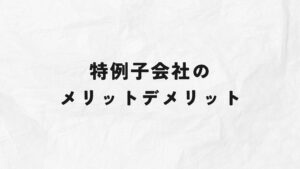
設立までの流れとスケジュール
ここからは、実際に特例子会社を設立するためのステップを、わかりやすく順番に紹介していきます。「まず何をする?」「どこに相談するの?」など、初心者の方でも安心して進められるように解説しますね。
全体の流れをざっくり確認!
特例子会社の設立は、ざっくり以下のようなステップで進んでいきます:
- 社内で設立の意思決定をする
- 障害者雇用に適した業務を選ぶ
- 事業計画・雇用計画を立てる
- 設備や支援体制を整える
- 厚生労働省へ申請・審査を受ける
- 認定されたら事業をスタート!
ではここから、それぞれのステップをくわしく見ていきましょう!
STEP1|社内体制をつくって、意思決定する
まずは「特例子会社を作るぞ!」という社内での意思統一が必要です。経営陣や人事部門が中心となって、
- なぜ設立するのか?(目的)
- どんな組織で進めるか?(プロジェクトチーム)
- スケジュール感や予算
といったことを話し合い、社内での理解と協力体制を固めていきましょう。
STEP2|どんな業務で雇うかを決める
次に、「どんな仕事を特例子会社でやってもらうか?」を考えます。ポイントは、障害のある方にとって“取り組みやすい業務”を選ぶこと。
よく選ばれている業務例は…
- 印刷や発送作業
- 名刺の作成やデータ入力
- 清掃・リネン業務
- 社内システムのチェック
「社内にある単純作業を集めて子会社に移す」という考え方もアリです!
STEP3|事業計画と人員配置を考える
業務内容が決まったら、次は具体的な計画を作ります。
- いつ、どこに、どんな子会社を作るのか?
- 何人くらい雇用する予定か?
- 障害のある方は何人? 支援スタッフは?
- お金はいくらかかる?(予算計画)
これらを整理して、厚生労働省に提出する「事業計画書」や「雇用計画書」にまとめていきます。
STEP4|設備・支援体制を整える
特例子会社には、障害のある方が安心して働ける環境が必要です。
- バリアフリー対応(トイレや通路など)
- 静かな作業スペースや個別ブース
- 支援員の配置・育成
この段階で、福祉施設や支援団体、社労士などの専門家に相談するのもおすすめです。
STEP5|厚生労働省に申請する
準備が整ったら、いよいよ「特例子会社にしてください」と厚生労働大臣に申請します。申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 特例子会社認定申請書
- 事業計画書
- 雇用・支援体制に関する資料
- 就業規則や組織図
内容に不備がなければ、約1〜2か月で認定通知が届くのが一般的です。
STEP6|事業スタートと運営開始!
無事に認定されたら、いよいよ事業のスタートです!最初は少人数から始めて、少しずつ雇用を拡大していく企業が多いですよ。
- 毎年の雇用状況報告
- 職場改善や研修の実施
- 社内との連携強化
など、“つくって終わり”ではなく、“育てていく”ことが大切です。
ここでは本当に簡単な流れのみを記載しています。実際にスタートさせようとすると各ステップごとに悩みや問題が出てくることでしょう。その場合は自社内だけで完結しようとせずに特例子会社設立に強い専門家(障害者雇用に強いコンサル会社)などに相談すると良いでしょう。
なかなか企画~特例子会社設立まで自社内で完結する会社は多くありません。会社を1つ作るイメージですのでできる限り外部のリソースも使いながら進めていくのが賢いやり方です。
設立に必要な書類一覧と作成ポイント
特例子会社の設立には、厚生労働省へ提出するための書類がいくつか必要です。「書類ってむずかしそう…」と思う方も多いですが、ポイントを押さえれば大丈夫!ここでは、必要な書類と、それぞれの作成ポイントをわかりやすく解説していきます。
主な提出書類一覧
特例子会社の認定申請に必要な書類は、おおよそ以下の通りです。
- ① 特例子会社認定申請書
- ② 事業計画書
- ③ 雇用管理体制図
- ④ 就業規則(案)
- ⑤ 親会社との関係がわかる資料(登記簿、出資比率など)
- ⑥ 障害者の雇用予定者一覧
- ⑦ 支援体制に関する資料
では、それぞれの書類のポイントをかんたんに見ていきましょう。
① 特例子会社認定申請書
特例子会社の認定をお願いする、いわば「申込み用紙」です。フォーマットは厚生労働省のウェブサイトでダウンロードできます。
企業名、所在地、資本金、代表者、障害者雇用の概要などを記入します。記載ミスや記入漏れがあると、申請が遅れる原因になるので要注意です。
ただ、厚生労働省のページにはそこまで詳しい情報が記載されておりません。まずは障害者雇用に強いコンサル会社などに相談するのが良いでしょう。
② 事業計画書
この書類はとても重要です!「この子会社でどんな事業をやって、どんなふうに障害者を雇用していくのか」を明確に示す必要があります。
- 事業の目的
- 業務内容(できるだけ具体的に)
- 障害のある方の配置予定
- 売上・支出の見込み
難しく聞こえるかもしれませんが、「誰が・どこで・何を・どうやってやるのか?」を具体的に書けばOKです。
③ 雇用管理体制図
どんな人が、どの立場で、誰を支援するのか――支援体制を図にまとめる資料です。
- ジョブコーチや支援員の配置
- 直属の上司や指導係の関係
- 本社との連絡体制(人事部との連携)
できれば図や表を使って、ひと目でわかるようにするのがおすすめです。
④ 就業規則(案)
特例子会社で働く人たちのためのルールブックです。一般的な会社と同じ形式でOKですが、障害のある方への配慮も盛り込んでおくと安心です。
- 勤務時間や休憩時間の柔軟な設定
- 体調に合わせた勤務対応
- 支援スタッフへの相談窓口
⑤ 親会社との関係がわかる資料
親会社とのつながりが明確であることを証明するための資料です。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 出資比率を示す資料
「この子会社は、親会社としっかりつながっています」ということが伝わる内容にしましょう。
⑥ 障害者の雇用予定者一覧
どんな方を、どの部署で、どんな仕事で雇う予定なのかを整理した一覧表です。
氏名や障害の種別を書く必要はありませんが、人数や業務内容、支援体制などの全体像を明記することがポイントです。
⑦ 支援体制に関する資料
特例子会社では、「雇って終わり」ではなく、しっかりサポートできる体制があるかが大事です。
- 支援員(ジョブコーチ)の配置予定
- 研修計画
- 本人との定期面談の仕組み
具体的な運用方法を記載しておくと、審査でもプラス評価につながります。
書類の準備はちょっと大変ですが、「障害のある人が安心して働ける会社をつくりたい」という想いを伝える場でもあります。不安がある場合は、社会保険労務士や就労支援機関に相談しながら進めるのもおすすめですよ。
こちらも必要な書類は記載しているものの、自社内で完結しようとすると相当な時間と労力がかかることが予想されます。書類は認定されるうえではかなり重要事項になりますので専門家に依頼をするのが良いでしょう。
特例子会社設立に活用できる助成金
「特例子会社を作るにはお金がかかるんじゃ…」
そんな不安を感じている方も多いと思います。でもご安心ください。国や自治体では、特例子会社の設立をサポートするための助成金制度を用意しています。
ここでは、活用しやすい代表的な助成金と、それぞれのポイントをわかりやすく紹介します!
1. 特例子会社等設立奨励金
特例子会社を新たに設立する企業向けに、設備整備費や運営準備費などをサポートしてくれる助成金です。
- 対象:新たに特例子会社を設立し、障害のある方を継続的に雇用する企業
- 支給内容:最大数百万円単位での支給実績あり(年度や人数により異なる)
- 用途:備品購入・施設改修・教育訓練費・ジョブコーチの配置など
この制度は厚生労働省(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)が管轄しています。
詳細はこちら(厚生労働省)
2. 障害者トライアル雇用奨励金
正式雇用の前に、一定期間のお試し雇用(トライアル雇用)を行うことで、助成金が受け取れる制度です。
- 対象:ハローワークなどを通じて、障害のある方を試行的に雇用する場合
- 支給額:1人あたり月4万円(最大3か月間)
- メリット:雇用前に相性や業務の適性を確認できる
「いきなり本採用は不安…」という企業にもおすすめの制度です。
3. 職場適応援助者(ジョブコーチ)制度
障害のある方がスムーズに職場に慣れるように、専門の支援員=ジョブコーチが職場内でサポートしてくれる制度です。
- 対象:障害者を雇用した企業(特例子会社含む)
- 内容:外部の支援機関からジョブコーチを派遣 or 自社で配置
- 助成金:自社育成型ジョブコーチには研修費・配置費の助成あり
ジョブコーチは、職場定着率を高める強力な味方になります!
詳細はこちら(厚生労働省)
4. 障害者雇用安定助成金(職場環境改善コース)
すでに雇用している障害のある方が長く働けるように職場環境を改善する取り組みに対する助成金です。
- 対象:職場の設備改善・就業支援機器の導入など
- 例:パーティションの設置、ICT機器の導入、音声ソフトの導入 など
- 助成額:費用の1/2〜3/4など(条件による)
「採用した後のサポート費用」にも活用できるので、特例子会社の運営にもぴったりです。
詳細はこちら(厚生労働省)
5. 自治体独自の支援制度
都道府県や市区町村によっては、独自の支援制度や補助金を用意している場合もあります。
- 事業所の新設に対する補助
- 障害者雇用を行う企業への奨励金
- アドバイザー派遣や制度説明会
地元のハローワークや商工会議所に相談してみると、意外な支援が見つかることもありますよ。
助成金は「知らなかった…」だけで損をしてしまうこともあるので、早めに調べて準備するのがポイントです!また、助成金の情報に関しても独自で情報収集するのは難しいため、専門家などに協力してもらうことをオススメします。
設立事例から学ぶ成功パターンと失敗談
「うまくいく会社って、どんな工夫をしてるの?」
「逆に、失敗した会社ってどこでつまずいたの?」
特例子会社の設立・運営においては、実際の事例から学ぶことがとても大切です。
ここでは、実際の企業で見られた成功例と失敗例を、初心者にもわかりやすくご紹介します。
成功事例①:大手製造業A社|軽作業の切り出しで雇用を創出
A社は、自動車部品を製造する大手メーカー。これまでは障害者雇用が本社では難しく、法定雇用率の達成に悩んでいました。そこで倉庫の一角に特例子会社を設立し、本社から以下の業務を切り出しました:
- 部品の袋詰め
- 検品・ラベル貼り
- 出荷前の最終チェック
結果として、知的障害のある方を中心に10名以上の雇用を創出。支援スタッフも配置し、業務も安定化しました。
社内でも「仕事の役に立っている」との声が増え、他部署との交流イベントも活発化。職場全体が明るくなったそうです。
成功事例②:中小IT企業B社|データ入力業務に特化した子会社
B社は、社員50名ほどの中小企業。障害者雇用には不安を感じていましたが、在宅・リモートワークに対応できる業務を特例子会社化することに。
主に行っているのは、
- アンケート結果の入力
- 画像の分類・タグ付け
- 簡単なWebチェック作業
ITツールを活用しながら、精神障害のある方や発達障害のある方でも働きやすい環境を整えたことがポイント。作業効率もアップし、今ではグループ内の他部署からも業務を請け負うほどになりました。
失敗事例①:C社|業務設計が甘く、仕事がない状態に…
C社では、「障害者雇用しなきゃ!」と急いで特例子会社を設立。
しかし、「どんな仕事をやってもらうか」が明確に決まっていなかったため、最初から仕事がほぼゼロという状態に。
従業員は毎日出社しても手持ち無沙汰で、離職者が続出…。数ヶ月後には運営の見直しを迫られました。
この失敗から学べるのは、「事前に業務を切り出しておくことの大切さ」です。
失敗事例②:D社|社内の理解不足で孤立化
D社は支援体制や業務設計には力を入れていましたが、本社や他部署との連携がほとんどなかったのが問題でした。
結果として、特例子会社の存在が“よく知られていない”状態に。業務の依頼も少なく、従業員のモチベーションも下がってしまいました。
このケースでは、社内全体で障害者雇用を「自分ごと」にする意識づけが欠けていたと言えます。
成功のカギは「準備・連携・理解」
これらの事例からわかるように、特例子会社を成功させるには次の3つがとても重要です。
- 準備:業務の明確化・支援体制の整備
- 連携:親会社や他部署とのスムーズな関係構築
- 理解:社内全体の意識づけ・交流の促進
「作って終わり」ではなく、「育てる会社」として運営していく姿勢が、成功する特例子会社の共通点になります。
よくある質問(FAQ)

ここでは、特例子会社の設立を考えている方からよく寄せられる疑問や不安を、わかりやすくまとめました。初めての方でも理解しやすいように、できるだけかんたんな言葉でお答えしていきます!
Q1. 特例子会社って、誰でも作れるの?
いいえ、誰でも作れるわけではありません。親会社が出資していて、障害者を一定割合以上雇用する計画があることなど、一定の要件を満たす必要があります。
Q2. 設立にどれくらいの時間がかかる?
会社設立の準備から申請・認定までを含めると、半年~1年程度が一般的です。書類の準備や職場環境づくりに時間がかかることもあります。
Q3. 特例子会社に認定されると、どんなメリットがあるの?
グループ全体で法定雇用率を達成できたり、助成金を活用できたりします。また、社会的評価の向上や職場の多様性促進といったメリットもあります。
Q4. 障害のある方は、どんな仕事をしているの?
- 印刷・封入・発送作業
- データ入力・Webチェック
- 清掃・リネン管理
など、マニュアル化された作業や集中力が求められる業務が多いです。
Q5. 精神障害や発達障害の方も対象になる?
はい、対象になります。身体・知的・精神のいずれの障害も対象ですが、それぞれに配慮のポイントが異なるため、支援体制をしっかり整える必要があります。
Q6. いきなりたくさん雇わないとダメ?
いいえ、小さな規模から始めることも可能です。「まずは3人からスタートして、少しずつ増やす」という企業も多いです。
Q7. 支援員(ジョブコーチ)は必須?
法律上は必須ではありませんが、職場定着率を高めるうえでは非常に有効です。外部支援機関の利用や、自社内での育成も可能です。
Q8. 申請書類ってむずかしい?
内容は多いですが、要点を押さえればそれほど難しくありません。不安な場合は、社労士や専門機関に相談するのがおすすめです。
Q9. 認定が下りないこともある?
はい、要件を満たしていない場合は認定されないこともあります。事前にハローワークや障害者就労支援センターに相談するのが安全です。
Q10. 一度認定されたら、ずっとそのまま?
いいえ、定期的な報告義務があります。雇用状況に大きな変更があれば、再審査や認定の見直しが行われることもあります。
Q11. どんな企業規模でも設立できる?
中小企業でも設立可能です。ただし、親会社が雇用義務のある企業(常時43.5人以上)である必要があります。
Q12. 在宅勤務でも特例子会社にできる?
はい、業務内容や支援体制によっては在宅型の特例子会社も可能です。IT業界や事務系の仕事で実例があります。
Q13. 利用できる助成金には何がある?
- 特例子会社等設立奨励金
- ジョブコーチ制度
- トライアル雇用奨励金
などがあります。条件により受給額が変わるため、早めの確認がポイントです。
Q14. 特例子会社は税制上の優遇があるの?
直接的な減税制度は多くありませんが、助成金の非課税措置や、社会的信用による間接的な経済効果は期待できます。
Q15. どこに相談すればいいの?
以下のような機関がおすすめです。
- 地域のハローワーク
- 障害者就業・生活支援センター
- 社会保険労務士
- 障害者雇用の実績があるコンサル会社
「相談無料」の窓口も多いので、ぜひ気軽に活用してください。
設立をサポートしてくれる外部機関・専門家
「特例子会社の設立、ひとりで全部やるのは大変そう…」
そう感じた方も多いと思います。でも安心してください!特例子会社の設立・運営をサポートしてくれる外部機関や専門家がたくさんあります。
ここでは、相談先としておすすめの5つの窓口をご紹介します。
1. 社会保険労務士(社労士)
障害者雇用や労務管理に詳しい社労士は、とても心強い存在です。
- 申請書類の作成サポート
- 就業規則の整備
- 助成金の申請代行
特に「障害者雇用に強い社労士」や「特例子会社の経験がある事務所」を選ぶと安心です。
2. ハローワーク(公共職業安定所)
地域のハローワークでは、障害者雇用に関する専用窓口があります。特例子会社の設立についても、事前相談が可能です。
- 雇用率の確認
- 求人の出し方
- 助成金の案内
まずはハローワークに相談するのが最初の一歩としておすすめです。
3. 障害者就業・生活支援センター
「働くこと」と「生活」を支えるための地域の支援拠点です。障害のある方の就労支援だけでなく、企業側の受け入れサポートも行っています。
- 就労前後のアドバイス
- 職場見学や実習の受け入れサポート
- 継続雇用に向けたフォロー
地域密着型のため、顔の見える関係で長く付き合えるのがメリットです。
4. 障害者雇用支援の専門コンサル会社
障害者雇用や特例子会社に特化したコンサルティング会社もあります。ノウハウが豊富で、計画段階からトータルで支援してくれるのが特徴です。
- 設立準備のアドバイス
- 書類作成や業務設計支援
- 運営スタート後のフォローアップ
スピーディに進めたい・自社にリソースがないという場合には特におすすめです。
5. 地方自治体(都道府県・市区町村)
自治体によっては、独自の障害者雇用支援制度や補助金を用意していることがあります。
- 特例子会社向けの説明会・セミナー
- 専門アドバイザーの派遣
- 助成金制度の案内
市役所や都道府県庁の障害福祉課・雇用労働課などに問い合わせてみましょう。
このように、特例子会社の設立は外部の力を借りながら進めるのが一般的です。「相談する=弱みを見せる」ではなく、成功への第一歩ととらえて、ぜひ気軽に声をかけてみてくださいね。
設立後にやるべきことリスト
特例子会社を設立したら、それで終わり…ではありません!むしろ大切なのは、運営スタート後にどんな取り組みをしていくかです。
ここでは、設立後に取り組むべきことを、わかりやすいチェックリスト形式でまとめました。
1. 雇用状況の定期報告
特例子会社は、毎年、雇用状況を厚生労働省に報告する義務があります。「障害者を何人雇っているか」「どのような業務をしているか」などをまとめて提出します。
2. 職場環境の見直しと改善
運営が始まったら、実際に働く人の声をもとに、環境をアップデートしていくことが大切です。
- 照明や音環境の調整
- 作業スペースのレイアウト改善
- 道具やマニュアルの工夫
小さな改善の積み重ねが、働きやすさと定着率アップにつながります。
3. 定期的な面談・サポート体制の強化
障害のある方が安心して働き続けるためには、定期的なコミュニケーションが不可欠です。
- 月1回の面談で困りごとをキャッチ
- 支援員・上司との連携強化
- 必要に応じて支援機関と連携
「気軽に相談できる環境づくり」が大切ですね。
4. スキルアップ・キャリア支援
雇用して終わりではなく、成長できる場の提供も大切です。
- 簡単な研修制度(例:パソコン操作)
- 資格取得支援
- 社内ステップアップ制度の導入
本人のやる気や成長が、企業全体の活力にもつながります。
5. 評価制度や表彰制度の導入
頑張りを見える形で認めることで、モチベーションアップにつながります。
- 年1回の表彰式
- がんばりポイント制度
- 社内報での紹介 など
「ありがとう」「すごいね」が伝わる会社づくりを目指しましょう。
6. グループ会社との交流や理解促進
特例子会社が孤立しないよう、親会社や他部署とのつながりを保つことも重要です。
- 業務連携の強化
- 社内報やSNSでの紹介
- 交流イベント(例:一緒に社内清掃活動)
「グループの一員として見てもらえる」ことで、働く側の誇りや安心感にもつながります。
7. 社会発信・ブランディング
特例子会社での取り組みは、企業ブランディングにもつながる資産です。
- 採用ページでの紹介
- CSRレポートへの掲載
- 自治体・メディアへの情報提供
しっかり発信することで、信頼される会社づくりにつながっていきます。
このように、特例子会社は“つくる”だけでなく、“育てていく”ことが大切です。継続的に改善しながら、みんなが気持ちよく働ける場を作っていきましょう!
まとめ|特例子会社設立は“戦略的社会貢献”
ここまで、特例子会社の設立について、ゼロからやさしく解説してきました。少し長い記事でしたが、最後に大事なポイントを一緒に振り返ってみましょう。
- 特例子会社とは、障害のある方の雇用を支えるために設立される「グループ内の特別な子会社」。
- 法定雇用率の達成だけでなく、企業ブランディングや社内の多様性推進にもつながる。
- 設立には要件・準備・支援体制が必要ですが、外部の専門家や支援機関に頼ることで進めやすくなる。
- 助成金や制度も豊富で、費用面の不安もカバー可能。
- 設立後の運営や職場づくりが、何よりも重要。
特例子会社の設立は、「企業の社会的責任(CSR)」を果たす手段であると同時に、戦略的に“良い会社づくり”を進めるチャンスでもあります。
最初はわからないことばかりでも、ひとつずつ準備すれば、きっと実現できます。まずは社内で話し合うところから、あるいは専門家に相談してみることから始めると良いでしょう?