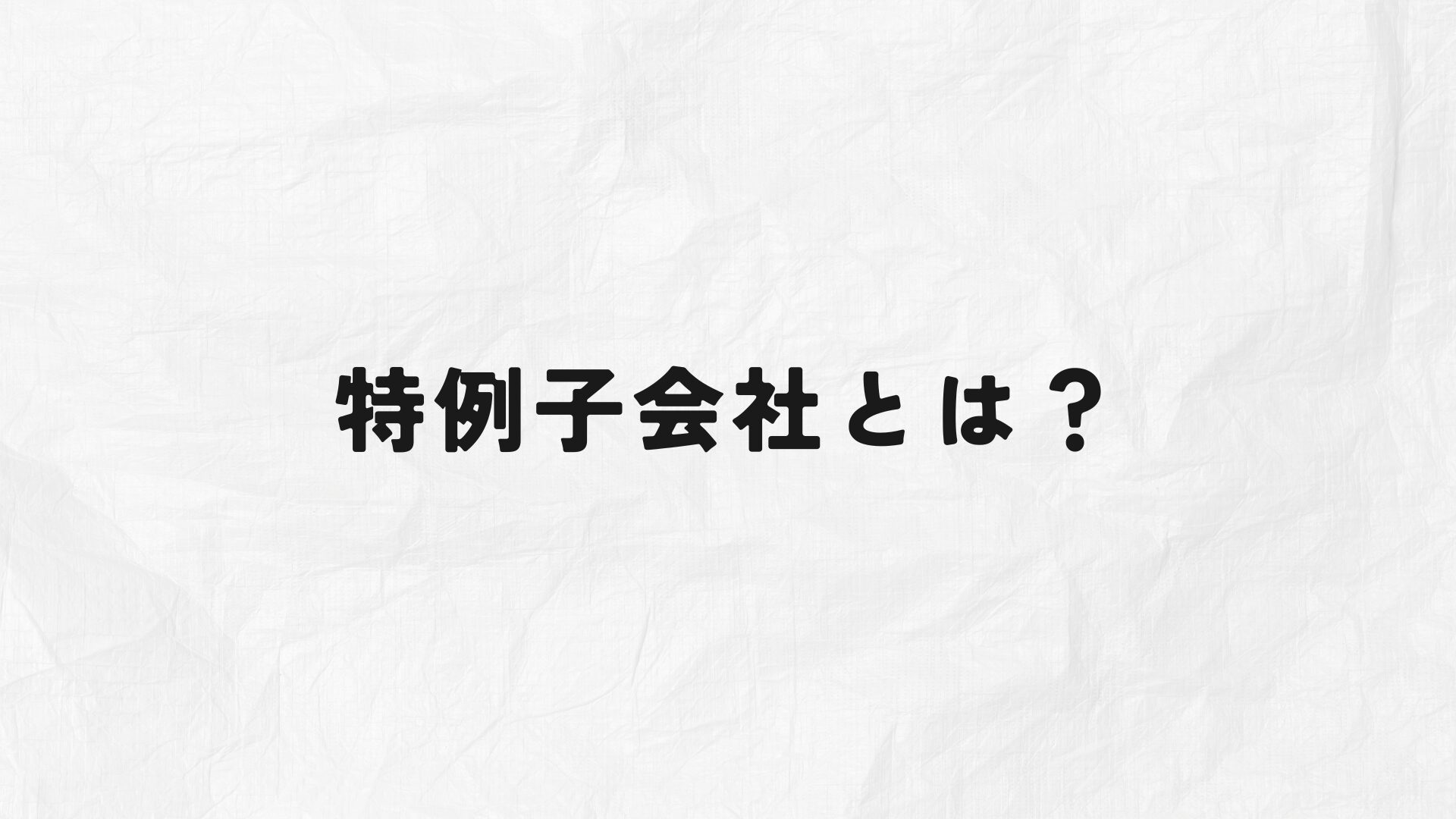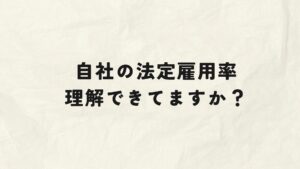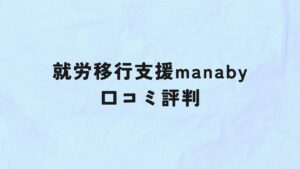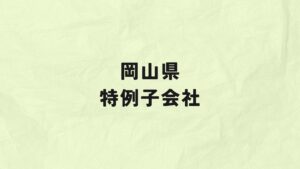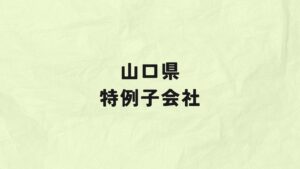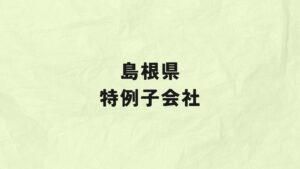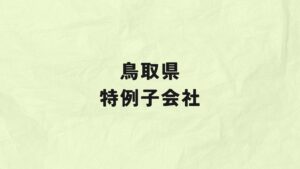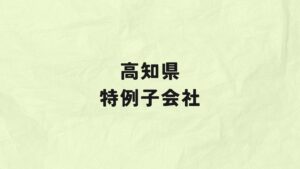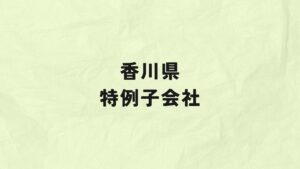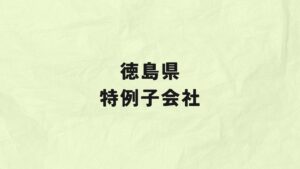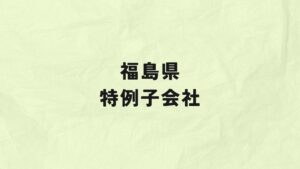「特例子会社って聞いたことあるけど、正直よくわからない…」「結局、何をやっている会社?」「何で特例子会社を作る必要があるの?」
この記事では特例子会社の意味・設立の仕組み・メリット・企業事例まで、初心者にもわかりやすく解説します。障害者雇用を考えている企業の方にも役立つ情報をまとめました。
特例子会社とは?定義と基本の仕組み

特例子会社の定義
「特例子会社」とは、障害のある方を安定的に雇用することを目的として設立された企業グループ内の子会社のうち、厚生労働大臣から「特例子会社」として認定された会社のことです。
この制度では、親会社(または関連会社)と特例子会社の障害者雇用数を合算できるため、法定雇用率の達成を目指す企業にとって大きなメリットがあります。
つまり簡単に言うと、障害者が働きやすいように配慮された子会社であり、企業全体で障害者雇用をより積極的に進めるための制度です。
通常の子会社との違い
一般的な子会社と特例子会社の大きな違いは、「障害者雇用を目的として設立されているかどうか」です。通常の子会社は、事業拡大や分社化のために設立され、雇用する人に障害があるかどうかは特に関係ありません。
特例子会社は障害のある人が安心して働ける職場づくりが前提となっており、以下のような特徴があります。
- 障害特性に配慮した作業内容や勤務時間
- 職場内にサポートスタッフ(ジョブコーチなど)を配置
- バリアフリー対応や通勤支援の整備
こうした環境整備がきちんと行われ、一定の条件を満たしたうえで、国の認定を受けることで「特例子会社」として正式に登録されます。特例子会社を作ることは比較的費用が掛かりますので、現時点では大企業が作っているケースが多いです。
制度ができた背景と目的
日本では、障害のある人の働く機会を確保するため、企業に対して「法定雇用率」という基準が設けられています。これは、一定以上の従業員を抱える企業に、障害者を一定割合以上雇用するよう義務づける制度です。
しかし、一般の企業内では、障害特性への理解や職場環境の整備が進んでいないケースも多く、「障害のある人が安心して働ける場所を別に用意したい」というニーズが高まりました。
そこで1987年に導入されたのが「特例子会社制度」です。この制度の目的は次の2つです。
- 障害者が長く安心して働ける職場を増やす
- 企業が柔軟に法定雇用率を達成できるようにする
現在では多くの大企業が特例子会社を設立しており、雇用創出の重要な仕組みとして定着しています。
特例子会社のメリットとは?
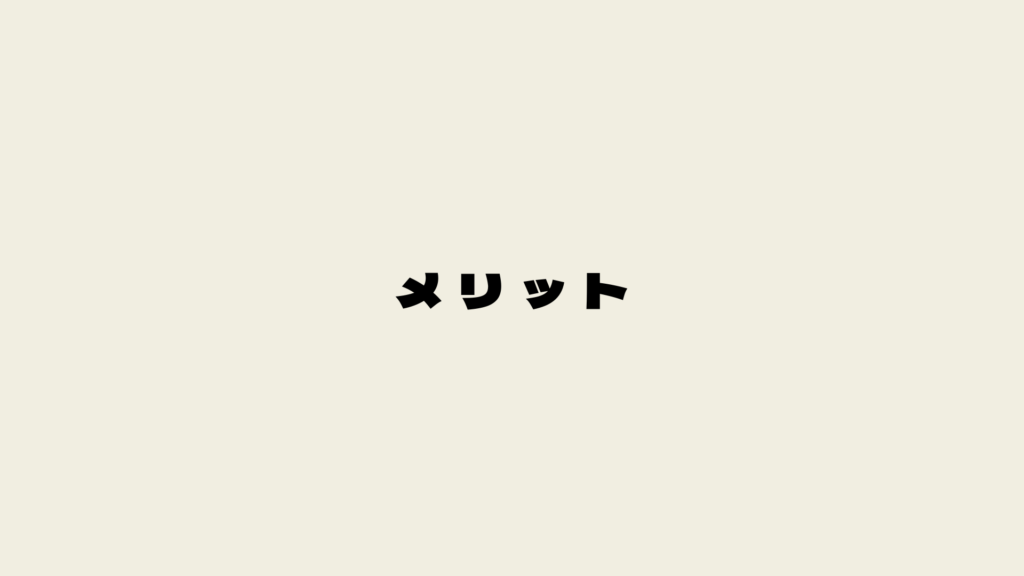
障害者雇用のカウントが合算できる
特例子会社を設立し、厚生労働大臣の認定を受けることで、親会社と特例子会社の障害者雇用者数を合算できるようになります。これにより、企業グループ全体で法定雇用率(現在2.5%※)の達成を目指すことが可能になります。
たとえば、本社では障害者に適した業務が少なく雇用が難しい場合でも、特例子会社に適切な業務や環境を整備することで、全体としてバランスのとれた雇用を実現できます。
本社と特例子会社で業務・環境を分けることができるのは大きな理由の1つです。障害者雇用は採用までも大変ですが、定着(長く働いてもらうこと)がさらに難しいと言われています。切り分けることによって、長く続けてもらえる環境を作りやすくなると考えられています。
働きやすい環境整備がしやすい
特例子会社は、障害のある方が安心して働ける環境をつくることが前提で設立されます。
- 作業工程や業務内容の調整
- 出勤時間・勤務時間の柔軟な設定
- ジョブコーチの配置や支援スタッフの常駐
- 静音室・休憩スペース・バリアフリー化
親会社とは別の職場環境を用意できるため、個々の障害特性に合った職場設計が可能です。結果として、長期雇用・定着率の向上にもつながります。
社会的評価・企業イメージ向上
障害者の雇用促進に積極的な企業は、社会的責任(CSR)やSDGsの観点から高く評価されます。特例子会社の設立は、単なる義務達成ではなく、「誰もが働きやすい社会づくりに貢献している」という強いメッセージになります。
特例子会社の運営は、次のような点でも企業にとってプラスとなります。
- 株主・顧客・取引先からの信頼性向上
- 採用におけるブランドイメージの強化
- ESG投資への対応
特に近年は、サステナビリティ経営を重視する流れの中で、障害者雇用への取り組みが注目されています。法定雇用率も2026年度には2.7%に引き上げられる予定ですのでさらに障害者を雇用する重要度が増してくると考えてよいでしょう。
障害者雇用を積極的にしているか一目でわかる
特例子会社を設立し、公式に認定されている企業は、厚労省の公開リストに掲載されます。つまり、誰が見ても「この企業は障害者雇用に積極的だ」とわかる状態になります。
- 学生や求職者に向けた採用活動
- 官公庁・自治体との連携や入札
- 企業間の取引や業務提携
また、特例子会社の紹介ページを企業サイトで発信することで、具体的な取り組み事例をPRしやすくなり、より信頼感を高めることができます。メリットは今もありますが、法定雇用率が2.7%に上がる、国がさらに障害者雇用に力をいれるなどすると今よりも大きなメリットがでてきます。
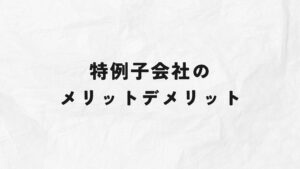
設立するための要件とは?
特例子会社を作るためにはどんな条件が必要かみていきましょう。
厚生労働省の認可条件
特例子会社を設立するには、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。単に障害者を多く雇えば自動的に「特例子会社」となるわけではなく、一定の基準を満たしたうえで申請しなければなりません。
具体的には、以下のような条件があります。
- 親会社との人的・経営的関係があること
- 障害者の雇用が安定して行われていること
- 雇用される障害者が自立して働けるよう配慮されていること
- 支援体制(職業指導員・生活支援員等)が整っていること
ということは「特例子会社を作りたい!」といってもすぐに作れるわけではありません。特に「障害者雇用が安定しているか」「自立して働けるように配慮されているか」「支援体制が整っているか」は長く障害者雇用を続けていないとクリアしづらいポイントです。
流れとしては、申請して認可を受けると、厚生労働省から「特例子会社認定通知書」が交付され、正式に特例子会社として運営が可能になります。
障害者の雇用割合
特例子会社として認められるには、全従業員のうち一定割合以上を障害者が占めていることが必要です。具体的な基準は以下の通りです。
- 常時雇用する従業員の20%以上が障害者であること
- 障害者のうち、重度障害者の割合が一定基準以上であること
また、以下のような障害者手帳を持つ方が対象となります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
障害者雇用促進法の対象となる範囲に従い、正確な人数カウントと継続的な雇用が求められます。
法定雇用率が未達成の場合は罰則を支払えばいいですが、特例子会社を作る(維持する)場合は。上記の割合を守ることが前提です。ですからさらに厳しい基準をクリアしていないと特例子会社を作ることは難しいといえます。
職場環境や支援体制の基準
特例子会社の認可においては、単に障害者を多く雇えばよいのではなく、障害者が安心して働ける職場づくりができているかが問われます。
- バリアフリー設計(トイレ・通路・エレベーターなど)
- 業務内容の配慮(作業負担や精神的ストレスを軽減)
- 職業生活支援員・ジョブコーチの配置
- 定期面談・相談体制の整備
また、職場で困りごとが起きたときにすぐに相談できるよう、管理者や支援スタッフとの距離が近い体制も評価されます。「障害者の方がいかに働きやすい環境を作れるか」ここを考えられない&実行できない会社は特例子会社を作ることはできません。
このような支援体制があることで、障害のある従業員が安心して長く働ける環境が実現でき、企業としての社会的責任も果たすことができます。
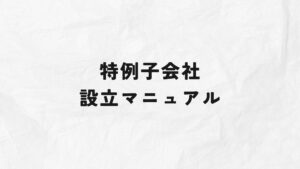
どんな企業が特例子会社を設立している?
上場企業の事例(10社)
現在、日本では多くの上場企業が特例子会社を設立し、障害者雇用の推進に取り組んでいます。以下はその代表的な事例です。
- トヨタグループ|株式会社トヨタループス
清掃・軽作業・社内メール便・文書管理などを中心に、全国拠点で障害者雇用を展開。 - ANAホールディングス|ANAウイングフェローズ・ヴィ王子株式会社
空港関連業務の一部(事務、清掃、制服管理など)を障害者が担当。 - 株式会社LIXIL|株式会社LIXIL WING
郵便物の仕分け・清掃・データ入力業務を行い、全国で障害者約200名が活躍。 - 富士通株式会社|富士通エフサス・クリエ株式会社
IT関連業務(ソフトウェア検証、印刷・発送業務など)で障害者を雇用。 - 株式会社ニトリホールディングス|ニトリビジネス
ピッキング・商品検品・発送作業などを実施。全国に障害者雇用拠点を拡大中。 - ソフトバンク株式会社|ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社
コールセンターやデータ入力業務を担う子会社として展開。 - 日本郵政グループ|JPビジネスサービス株式会社
郵便物の仕分け、書類のデジタル化、庶務業務を実施。全国に複数拠点あり。 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ|MUFGユニバーサルサポート株式会社
文書整理・コピー業務・データ入力を担い、銀行内支援業務を担当。 - アサヒグループホールディングス|アサヒビジネスソリューションズ株式会社
経理・データ処理・ラベル貼付など幅広い業務を担当。 - 日立製作所|株式会社日立ゆうあんどあい
各種事務補助業務、印刷・郵送関連業務などを障害者が中心となって担う。
これらの企業は、特例子会社を単なる「雇用の場」ではなく、事業部門の一部として位置づけている点が特徴です。
そのため、継続的な人材育成やキャリア形成支援にも力を入れています。
中小企業による設立例も
特例子会社は大企業だけのものと思われがちですが、近年では中小企業グループによる設立も増えています。その背景には、次のような理由があります。
- 法定雇用率の達成義務(従業員43.5人以上)
- 助成金や支援制度の充実
- 地域密着型の雇用を推進したいという思い
たとえば、福祉系法人が関連会社として清掃業務の特例子会社を設立した事例や、IT系中小企業がデータ入力専用子会社を立ち上げたケースなどがあります。
中小企業にとっては、「限られたリソースで効率よく法定雇用率を達成する手段」として有効な選択肢になっています。
職種・業務内容の傾向
特例子会社で行われる業務は、障害特性に配慮しながらも生産性やビジネス性を保った仕事が選ばれています。主な職種・業務は以下のようなものがあります。
- オフィス内作業(書類整理、データ入力、名刺管理など)
- 清掃・美化活動
- 印刷・封入・発送業務
- 軽作業(組み立て、梱包、仕分けなど)
- 農業・園芸(企業内ファームを活用するケースも)
- IT関連作業(ホームページ更新、画像処理、テスト業務など)
最近では、知的障害や発達障害の方が得意とする分野を活かし、業務の幅が広がってきている点も注目されています。たとえば、繰り返し作業の正確性や集中力を活かしたIT検証作業などが一例です。
企業によっては、業務の一部を委託部門として切り出すのではなく、1つの事業として独立採算型で運営しているところもあり、持続可能な障害者雇用の形として進化しています。
エリア別特例子会社記事一覧

法定雇用率ナビに掲載をしているエリア別の特例子会社記事になります。ぜひ参考にしてください。
- 北海道エリア・東北エリアの特例子会社一覧
- 関東エリアの特例子会社一覧
- 中部エリアの特例子会社一覧
- 近畿エリアの特例子会社一覧
- 中国エリアの特例子会社一覧
- 四国エリアの特例子会社一覧
- 九州エリア・沖縄エリアの特例子会社一覧
特例子会社の仕事内容とは?
清掃・事務・ITサポートなど
特例子会社で行われている仕事は、障害のある方の特性に配慮しながらも、企業活動に欠かせない実務ばかりです。単なる軽作業ではなく、「会社の一部として機能する業務」が多く存在します。
【業務の一例】
- 清掃業務(オフィス・工場・施設内の清掃や整備)
- 一般事務(書類整理、ファイリング、資料作成補助、コピー業務など)
- 郵便・印刷関連(封入・宛名貼付・仕分け・発送処理など)
- パソコン業務(データ入力、アンケート集計、名刺管理、情報更新など)
- ITサポート(Web画像処理、ソフトウェア検証、マニュアル作成など)
- 軽作業(組み立て・検品・梱包・ラベル貼りなど)
こう見ると、定型的な業務・ルーティン業務が多いのがわかります。実は障害者雇用の方は決まった業務をスピーディーに行うのは得意な方が多く、一般社員と比べても早いスピードで処理できることは珍しくありません。
近年では、精神障害・発達障害・知的障害のある方も活躍しやすい職場設計が進んでおり、幅広い業務分野での就業が可能になっています。
業種別の実例紹介
特例子会社は業種を問わず設立されており、それぞれの業界に合った業務が行われています。以下は代表的な業種別の実例です。
- 製造業:部品の検品・袋詰め・ラベル貼付・組み立て補助など(例:自動車・電機メーカー系特例子会社)
- IT業界:ソフトウェアのテスト・マニュアル作成・画像データ加工(例:富士通、NECなど)
- 小売・流通業:商品仕分け、伝票整理、ネット通販の発送補助(例:ニトリ、イオンなど)
- 金融業界:書類の電子化、名刺管理、文書整理、庶務業務(例:三菱UFJ、みずほなど)
- 航空・交通業界:制服管理、機内誌封入、清掃、備品整理(例:ANA、JR系企業など)
- 農業:野菜や花の栽培・収穫・出荷作業(企業内ファーム型の事例も多数)
このように、障害者が働ける仕事は「限定的」と思われがちですが、工夫次第でさまざまな職種が可能であり、多くの企業が業務を切り出して活用しています。
合理的配慮と業務設計
特例子会社では、障害のある方が安心して長く働けるように「合理的配慮」を行うことが前提になっています。これは単に「手助けする」ということではなく、働く上での不利を減らす工夫のことです。
- 静かな場所での作業(感覚過敏の方に配慮)
- マニュアルを画像や動画で用意(読み書きに困難がある方への支援)
- スモールステップで仕事を細分化(集中力が持続しにくい方向け)
- 時間を柔軟に調整(通院・体調への配慮)
- ジョブコーチや支援員による日々のサポート
こうした配慮を前提に業務が設計されているため、自分の得意を活かして働くことができる職場が実現しています。また企業側にとっても、作業の品質・正確さ・定着率の高さなど、多くのメリットがあります。
制度上の注意点・デメリット
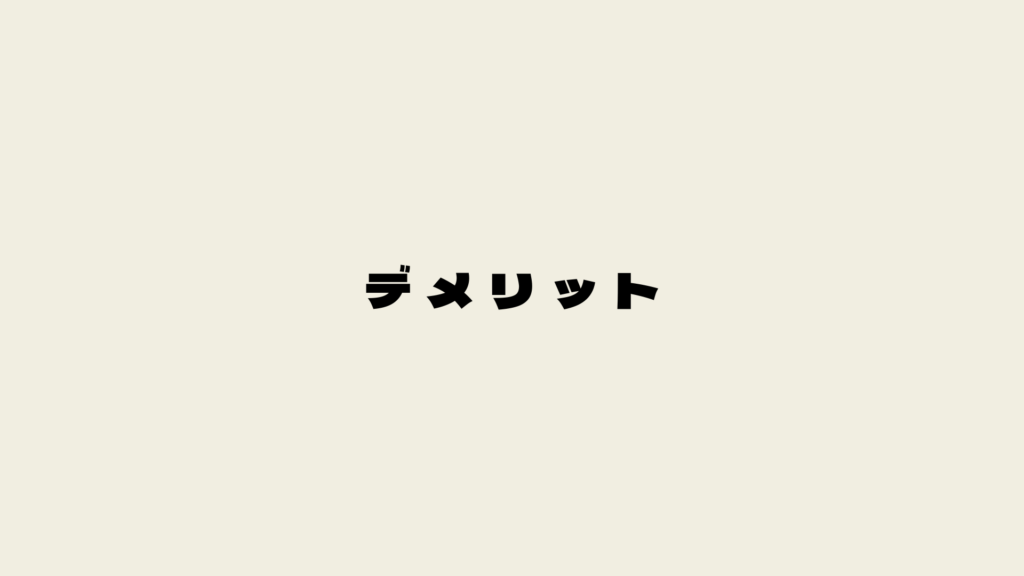
メリットだけではなく、デメリットや注意点も認識しておくことが大事です。
設立・運営に手間とコストがかかる
特例子会社の設立には、厚生労働省の認可取得をはじめとした多くの手続きが必要です。また、障害のある方が安心して働ける環境をつくるために、職場の設備改修・人員配置・サポート体制の整備など、初期投資がかかるケースも少なくありません。
さらに、運営後も以下のようなコストが発生します。
- ジョブコーチや支援員の人件費
- 作業マニュアルや研修資料の作成
- 定期的な面談・個別支援計画の実施
- 安全衛生・メンタルヘルス対策などの維持費
もちろん、これらに対する補助金や助成制度もありますが、制度活用のノウハウがないと運用負担が大きくなるという点は、事前に理解しておく必要があります。
「障害者雇用=手間がかかる」と認識している方も多くおり、「採用して良かった」と思えるようになるのはいろいろな問題点をクリアした後と通常の採用~教育よりも大変といわれています。
事業としての独立性が求められる
特例子会社は、単に「雇用の場を用意する」だけでなく、事業として持続可能であることが重視されます。つまり、特例子会社も1つのビジネスとして成り立たせる必要があるのです。
- 収益構造の構築(社内業務請負や外部委託業務の受注など)
- 従業員一人ひとりの戦力化とキャリア形成
- 品質・納期管理などの業務責任の明確化
障害者雇用の場でありながら、「あくまで企業としての価値提供が必要」という点は、福祉施設とは大きく異なるポイントです。
認定の更新と管理体制の維持
特例子会社としての認定は一度取得すれば終わりではなく、定期的な報告や実態の確認、場合によっては認定の更新が求められます。
- 障害者雇用率の維持(20%以上)
- 障害特性に応じた職務配置や業務設計
- 支援員・管理者の人材確保と育成
- 勤務状況・健康状態のモニタリングと対応
これらを怠ると、特例子会社の認定を取り消されるリスクもあるため、定期的な見直しとチーム体制の強化が不可欠です。
特に、制度変更や法改正に対応するには、社内に専門知識を持つ担当者の配置や、社会保険労務士・外部コンサルタントとの連携も重要になってきます。
特例子会社を作るメリットももちろんありますが、片手間で障害者雇用をスタートしようとしてもうまくいくことはありません。障害者雇用に本気で向き合う会社でないとうまくいかないのが現状です。ですから中途半端にスタートするよりも罰則を払ってしまった方が早いと判断する経営者が多いのも事実です。
特例子会社を活用した障害者雇用の戦略
法定雇用率の達成にどうつながるか
日本の企業には、障害者雇用促進法により、一定の割合(法定雇用率)で障害者を雇用する義務があります。2024年4月時点では、民間企業の法定雇用率は2.5%となっており、今後も段階的に引き上げが予定されています。
この基準を満たさない場合、企業には納付金の支払い義務や社名公表といったリスクが生じます。そこで有効なのが「特例子会社制度」です。
特例子会社を活用することで、グループ会社全体での障害者雇用率を一体的にカウントできるため、本社や事業所単体では難しかった目標を、戦略的に達成する道筋が描けるようになります。
全社的な雇用計画との連動
特例子会社は、障害者雇用の「受け皿」にとどまらず、企業全体の人材戦略の一部として設計することが重要です。
- 本社・各部署との連携による業務の切り出し・移管
- 人事部との協力による定期採用・配置転換の調整
- 管理職・現場リーダーの研修による理解促進と定着支援
このような体制を整えることで、「雇用率達成のための場」から一歩進んだ、企業文化としてのダイバーシティ推進へとつながります。
また、全社的な視点で計画を立てることで、人件費・支援コストの最適化にも貢献できる点が見逃せません。
グループ会社間の連携メリット
特例子会社を設立し、親会社・グループ各社との連携体制を構築することで、次のようなメリットが得られます。
- 業務の分担が柔軟になる(本社→特例子会社へ一部業務を移管)
- 障害者雇用のノウハウが蓄積し、グループ全体に展開できる
- 障害者本人のキャリアパスに多様性が生まれる(特例子会社→親会社へ異動など)
- 人材定着率が上がり、再採用・再教育コストが抑えられる
特例子会社が、単なる「隔離的な組織」ではなく、グループ全体の戦略的パートナーとして機能することで、より実効性の高い障害者雇用の仕組みがつくられます。
グループ内での相互研修や合同イベントなどを実施する企業もあり、全体でのエンゲージメントや企業価値の向上にもつながっています。
助成金や支援制度の活用方法
特例子会社対象の助成金一覧
特例子会社の設立や運営には、国からのさまざまな助成金制度を活用することができます。これらの制度を適切に利用することで、初期費用や継続運営の負担を大幅に軽減できます。
【助成金の一例】
- 障害者トライアル雇用助成金
試行的に障害者を雇用する企業に支給。雇用開始から最長3か月間、1人あたり月額最大4万円程度。 - 障害者職場定着支援助成金
定着支援のための支援員配置や環境整備に対して支給。 - 障害者雇用安定助成金(職場支援員等配置助成)
職業生活支援員やジョブコーチの人件費を一定割合補助。 - 障害者作業施設設置等助成金
バリアフリー化や作業設備の導入・改修に対する助成。 - 特例子会社等設立促進助成金
特例子会社の設立に対し、最大600万円程度の一時金が支給される制度(都道府県ごとに異なる)。
これらの助成金は主に独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口となっていますが上記などの助成金を把握するのだけもとってもハードルが高いです。
特例子会社を作ったり、運営していく場合は障害者雇用に強いコンサルなどに依頼するのも賢いすすめかたです。採用はもちろん、業務の切り出し、定着支援など今までの経験や実績でサポートしてくれますので大手企業などはコンサルティング会社を使用しながら運用しているケースが多いです。
自治体の支援策との併用
国の制度に加えて、地方自治体独自の支援制度を併用することで、より手厚い支援を受けられるケースもあります。
- 施設改修費や設備導入費への補助
- 就労支援員の派遣制度
- 地域密着型ジョブコーチ支援
- ハローワークと連携したマッチング支援
- 雇用後のフォローアップ面談支援
たとえば、東京都・大阪府・愛知県・福岡県などでは、特例子会社向けの独自補助金を設けており、国の助成金と併用可能な場合があります。
制度内容や申請タイミングは地域によって異なるため、設立予定地の自治体窓口(障害福祉課や産業振興課)に事前相談することをおすすめします。
申請時の注意点と事例
助成金を活用するには、要件に合った書類提出とスケジュール管理が不可欠です。よくある注意点は以下のとおりです。
- 申請前に計画書の提出が必要な制度がある
- 実績報告や経費明細の提出が期限付きで義務化されている
- 制度ごとに「対象経費の範囲」が厳密に決められている
- 雇用者数や継続雇用期間に対する要件未達成時は返還の可能性あり
また、申請に不慣れな場合は、社会保険労務士(社労士)や障害者雇用支援コンサルタントに依頼することで、申請ミスを防ぐことができます。
▼ 実例:
- 某製造業(従業員60人):特例子会社設立時に「特例子会社設立促進助成金」+自治体の「施設整備補助金」を併用し、合計約700万円の支援を受けた。
- 某IT企業:ソフトウェア検証業務に障害者を雇用し、「職場支援員等配置助成金」で支援員2名分の人件費を年間200万円以上カバー。
このように、国と自治体の制度を上手に組み合わせることで、初期投資を抑えつつ質の高い障害者雇用環境を整えることが可能です。
助成金だけでも特例子会社の担当者が把握するのは本当に大変です。外部のコンサルタントにうまく切り出して進めていくのが良いでしょう。
特例子会社と就労継続支援A型・B型の違い
障害のある方の働く場としては、特例子会社のほかに就労継続支援A型・B型といった福祉サービスもあります。名前は似ていますが、制度の目的・運営主体・雇用関係などが大きく異なります。
雇用契約の有無
最大の違いは雇用契約の有無です。
| 制度名 | 雇用契約 | 運営主体 |
|---|---|---|
| 特例子会社 | あり(正社員・契約社員・パートなど) | 民間企業(企業グループ) |
| A型事業所 | あり(パートタイム雇用が中心) | 福祉事業者(NPO・社会福祉法人など) |
| B型事業所 | なし(雇用契約を結ばない) | 福祉事業者 |
つまり、特例子会社は「企業による本格的な雇用」であるのに対し、A型は「雇用を前提とした福祉的就労」、B型は「雇用ではない支援付き作業」という位置づけです。
給与や待遇面の比較
給与や福利厚生なども制度によって大きく異なります。
- 特例子会社: 最低賃金以上が支払われ、雇用保険・厚生年金などの適用あり。正社員登用や賞与制度を導入している企業も多数。
- A型: 最低賃金以上の時給が義務付けられており、雇用保険の加入対象。ただし労働時間は短め(1日4時間程度)な場合が多い。
- B型: 工賃(1日数百円〜1,000円前後)が支払われるが、給与ではなく「成果報酬」に近い。雇用契約がないため社会保険は適用されない。
このように、特例子会社は企業の社員としての待遇を受けられるのに対し、A型・B型は福祉的支援の範囲内で働く形になります。
企業側が選ぶ基準の違い
企業が障害者雇用の手段として「特例子会社」と「福祉事業所との連携(A型・B型の利用)」を選ぶ際には、次のような判断基準があります。
- 長期的な雇用と戦力化を重視 → 特例子会社
- まずは軽作業から委託したい → A型・B型事業所との業務提携
- 地域貢献やCSRの一環として支援したい → B型との連携
- 法定雇用率を達成したい → 特例子会社(※雇用契約が必要なため)
なお、B型の作業は法定雇用率の対象にはカウントされません。一方、特例子会社やA型の雇用者は法定雇用率の算定対象になります。
そのため、法定雇用率達成を目的とする企業にとっては、特例子会社の設立やA型での雇用が現実的な選択肢となります。
これから特例子会社を考える企業へのアドバイス
自社に合う制度かの見極め方
特例子会社は非常に有効な制度ですが、すべての企業にとって最適とは限りません。まずは自社にとってこの制度が本当にフィットするかを見極めることが大切です。
- 障害者雇用の受け入れに前向きな企業文化があるか
- 障害のある方に任せられる業務を切り出せるか
- 雇用後に支援できる社内体制(人事・管理職など)があるか
- 特例子会社として独立運営できるだけの予算や人材があるか
これらの条件がある程度揃っている企業であれば、特例子会社を戦略的な雇用施策として導入する価値が高いと言えるでしょう。
まず何から始めるべきか
制度導入にあたって、まずは以下の3つのステップから着手することをおすすめします。
- 現状把握: 自社の障害者雇用率や雇用実績を確認
- 業務棚卸し: 障害者が対応できる業務の洗い出し
- 社内関係者との協議: 人事・総務・経営層を巻き込んだ初期検討
その後は、厚労省やハローワーク、JEEDなどの公的機関が提供するガイドラインを参考に、制度の詳細を理解しながら具体化を進めていきます。
また、他社の特例子会社を見学することで、運営実態や雰囲気を知ることができ、導入後のイメージが湧きやすくなります。
その他では、早めの段階からプロのコンサルタントに相談するのもありです。悩みの相談からできますし、実際に特例子会社を作る際もステップごとにサポートしてもらえます。
外部の専門家や支援団体の活用
特例子会社の設立・運営は、制度理解や支援体制の構築において専門的な知識が求められる場面が多くあります。そのため、外部の専門家との連携は非常に有効です。
- 社会保険労務士(社労士):制度設計・労務管理・助成金申請の支援
- 障害者雇用支援コンサルタント:職務設計や組織づくりの支援
- ハローワーク・就業・生活支援センター:人材紹介や定着支援
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED):制度説明・助成金・モデル事例の提供
- 地域の就労支援NPOや福祉団体:求人広報・マッチング支援・伴走支援
こうした外部リソースを早めに活用することで、社内の負担を減らしつつ、制度に合致した設立・運営が実現できます。また、第三者の視点からリスクや課題を指摘してもらえる点も、大きなメリットです。
よくある質問(FAQ)

Q1. 特例子会社にすると何が変わるの?
親会社と子会社の障害者雇用数を合算して法定雇用率の算定ができるようになります。また、障害者が働きやすい職場環境を特化して整備できるメリットもあります。
Q2. 誰でも特例子会社を設立できるの?
一定の条件を満たしていれば、企業規模に関係なく設立可能です。ただし、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
Q3. どれくらいの企業が導入しているの?
2024年時点で約530社以上の特例子会社が全国で運営されています主に大企業ですが、中小企業による設立事例も増えています。
Q4. 認定されないとどうなる?
認定を受けない場合は、障害者雇用数の合算ができず、通常の子会社として扱われます。法定雇用率を満たすためには、親会社単体での雇用が必要です。
Q5. 社会福祉法人との違いは?
特例子会社は営利企業であり、雇用契約を結んで働く職場です。一方、社会福祉法人は福祉サービスの提供主体であり、就労支援A型・B型などを運営します。
Q6. 就労継続支援A型・B型とは併用できる?
併用は可能ですが、法定雇用率の対象となるのは雇用契約を結んだA型までです。B型は雇用契約がないため、カウント対象にはなりません。
Q7. 一般企業との違いは?
特例子会社は障害者が働きやすい環境や支援体制が整っていることが前提です。業務内容も障害特性に応じて設計されており、一般企業より手厚い支援があります。
Q8. 認定を受けるのにどれくらい時間がかかる?
認定申請から承認までには、数か月程度(3~6か月)かかるケースが一般的です。事前準備や支援体制の整備がスムーズであれば短縮も可能です。
Q9. 助成金はどれくらいもらえるの?
助成金の種類によって異なりますが、特例子会社設立で最大600万円以上が支給されるケースもあります。その他、支援員配置・設備投資・定着支援なども対象です。
Q10. 障害者雇用数の「合算」とは?
親会社が設立した特例子会社の障害者雇用人数を、親会社の雇用率計算に含めることができます。これにより、親会社単体で雇用が難しい場合でも対応可能になります。
Q11. どんな人が働いているの?
身体障害・知的障害・精神障害など、さまざまな障害のある方が働いています。多くは事務補助・清掃・IT関連・軽作業などで活躍しています。
Q12. 従業員の割合に基準はあるの?
特例子会社は、全従業員の20%以上が障害者であることが原則です。また、重度障害者の割合なども考慮されます。
Q13. 本社とどのように連携するの?
多くの場合、業務の一部を本社から特例子会社に委託する形式が取られます。また、人事部門と協力しながら人材育成や評価制度も連携します。
Q14. 途中で取り消されることはある?
あります。認定後も、基準を満たさなくなった場合は認定が取り消される可能性があります。継続的な支援体制や報告義務を怠らないことが重要です。
Q15. 海外にも同じような制度はあるの?
国によって異なりますが、ドイツ・フランス・韓国などでも障害者雇用義務制度があります。ただし、「特例子会社」という制度は日本独自の枠組みです。
まとめ|特例子会社の活用で障害者雇用をもっと前向きに
この記事のおさらい
本記事では、障害者雇用の現実的な手段として注目されている特例子会社制度について、基本から実例、メリット・デメリットまで幅広く解説してきました。
ポイントをおさらいすると、以下のようになります。
- 特例子会社とは、障害者を雇用する目的で設立された、厚生労働省認定の子会社
- 親会社と雇用数を合算でき、法定雇用率の達成が現実的にしやすくなる
- 働きやすい環境整備、社会的評価の向上など多くのメリットがある
- 設立には要件と支援体制が必要で、外部の専門家と連携するのが有効
- 助成金や支援制度を活用すれば、導入コストを抑えられる
特例子会社は、単なる制度対応ではなく、企業の価値や社会的責任を高めるための戦略的な選択肢でもあります。
法定雇用率達成への現実的な選択肢として
2024年から段階的に法定雇用率の引き上げが進んでおり、すべての企業にとって障害者雇用は「避けられないテーマ」になりつつあります。
一方で、事業内容や人員体制の都合上、本社単体での対応が難しい企業も少なくありません。そうした中で特例子会社は、次のような理由から現実的かつ前向きな選択肢となります。
- 障害者が働きやすい環境を集中整備できる
- グループ全体で雇用を分担できる
- 支援体制やキャリア形成を専門的に設計できる
持続可能な障害者雇用体制を築く上で、特例子会社は「単なる法対応」ではなく、未来の企業づくりに向けた投資とも言えるでしょう。
次の一歩へ|相談窓口や資料請求リンクも紹介
特例子会社の設立や活用に関心がある場合は、まず以下のような専門機関や相談窓口で相談してみるのが良いでしょう。
- 厚生労働省 障害者雇用対策課
公式ページはこちら - 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
障害者雇用総合支援サイト - 都道府県の障害者雇用窓口・ハローワーク
- 社会保険労務士・就労支援コンサルタント
また、他社事例の資料請求やオンラインセミナーに参加することで、導入のリアルなイメージを掴むことも可能です。