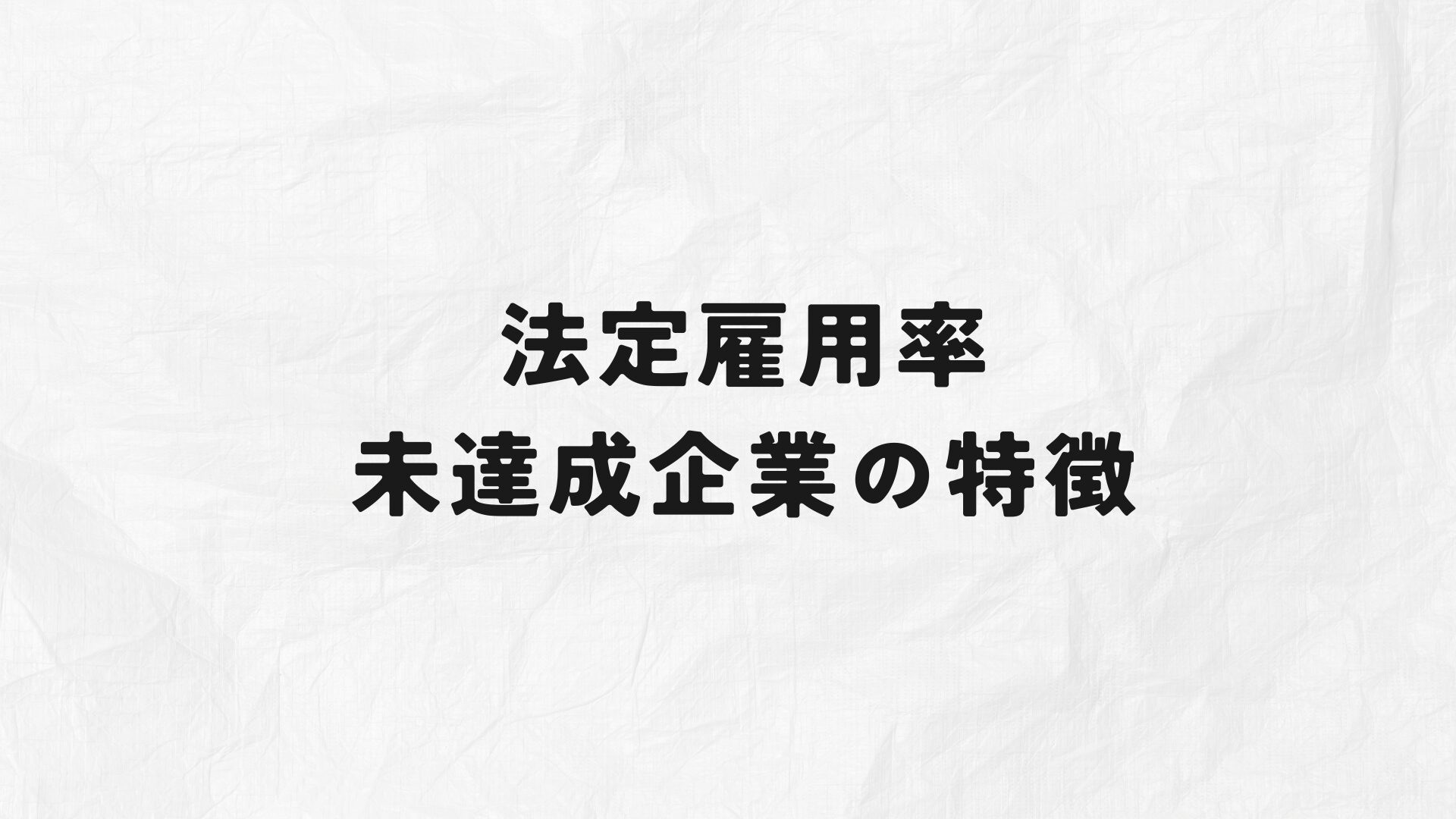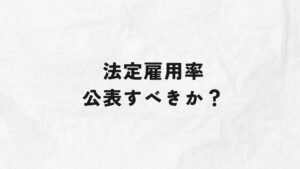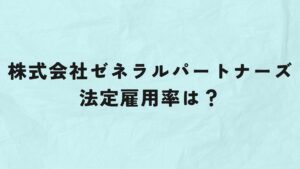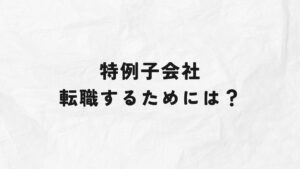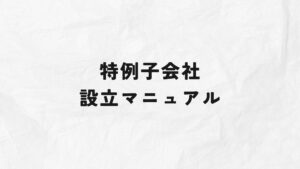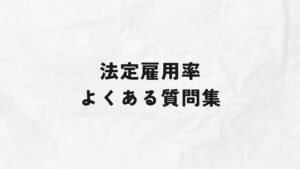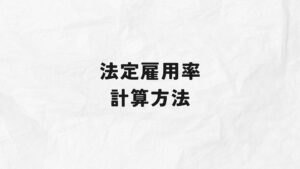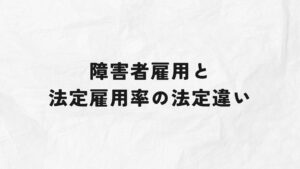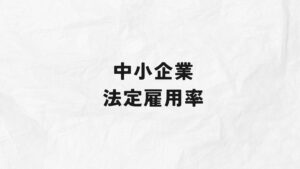法定雇用率を達成していない企業が増えている中で、「自社は大丈夫?」と不安を感じている担当者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、法定雇用率が未達成の企業に共通する特徴や、よくある課題、達成に向けた具体策をわかりやすく解説します。
法定雇用率の基礎から、実際に未達成の企業がどのような状況にあるのかまで、初心者の方でも理解しやすい内容になっています。
法定雇用率とは?初心者でもわかる基礎知識
まず、法定雇用率とは何か?を押さえておきましょう。
法定雇用率の概要
「法定雇用率(ほうていこようりつ)」とは、企業が一定の割合で障害者を雇用することを法律で義務づけられている制度のことです。これは障害のある人が社会の一員として働きやすい環境をつくるために、企業が担うべき役割として定められています。
たとえば、従業員が100人いる企業であれば、2.5人(=2.5%)以上の障害者を雇用する必要があります。この「何%雇えばよいか」の割合が「法定雇用率」です。
企業には、障害者が働きやすい職場を用意することが求められており、同時に、障害者の能力を活かせるような業務を切り出す工夫も重要です。
どの企業が対象になるのか
すべての企業が法定雇用率の対象になるわけではありません。基本的には、常時雇用する労働者が43.5人以上いる企業が対象となります。
「常時雇用」とは、パートやアルバイトを含めた労働者のうち、週20時間以上勤務している人のことです。そのため、社員数が少なくても、パートや契約社員を含めて43.5人を超える場合は対象になります。
逆に、それ未満の規模の事業所では法定雇用率の義務はありませんが、障害者雇用に取り組むこと自体は自由ですし、実際に取り組む企業も増えています。
2024年の改正ポイント
2024年には、法定雇用率に関して大きな変更がありました。具体的には、2024年4月から法定雇用率が「2.3%」から「2.5%」に引き上げられました。さらに、2026年7月には「2.7%」へ引き上げられる予定です。
これは、障害者の就労支援をより一層進めるために政府が打ち出した施策のひとつです。対象となる企業数も増え、採用や社内体制の見直しを迫られる企業も少なくありません。
今後は企業としても、単に「義務だからやる」のではなく、多様性を活かした職場づくりや、人手不足への対応として障害者雇用を捉える視点が求められています。
法定雇用率未達成の企業はどれくらいある?
厚労省の統計にみる未達成割合
法定雇用率は企業にとって義務とはいえ、すべての企業が達成できているわけではありません。厚生労働省の「障害者雇用状況報告(令和5年〈2023年〉)」によると、民間企業全体の達成率は全体の約50%台にとどまっています。
たとえば、2023年6月時点のデータでは、報告義務のある約11万社のうち、法定雇用率を達成していたのはおよそ5.4万社(達成率:48.3%)でした。つまり、半数以上の企業が未達成の状態であることがわかります。
これは決して他人事ではなく、多くの企業が「達成したいけれど、どうしたらいいかわからない」と感じているのが現状です。
業種・企業規模別の傾向
未達成企業の割合は、業種や企業規模によって大きく異なります。厚労省の統計から、特に未達成が多い業種・規模には以下のような傾向が見られます。
- 情報通信業・建設業・運輸業:体力仕事や専門職が多く、障害者雇用のハードルが高いと感じている傾向あり
- 従業員100~300人規模の企業:制度や採用ノウハウの不足が課題になりやすい
- サービス業(特に宿泊・飲食など):雇用の流動性が高く、定着が難しい傾向がある
一方で、製造業や金融・保険業などでは雇用の安定性や職種の多様性から比較的達成率が高くなっています。とはいえ、どの業種にも「工夫すれば実現可能な業務」は存在するため、業務の見直しや支援制度の活用がカギになります。
最新データをかみ砕いて解説
2023年の報告では、障害者の実雇用率は2.33%で、前年(2.25%)よりわずかに上昇しました。しかし、2024年4月から法定雇用率が「2.5%」へ引き上げられたため、現在の水準では依然として達成企業が少ない状況が続くと予想されます。
さらに、2026年7月には「2.7%」にまで引き上げが決まっており、今後ますます未達成企業の割合が増える可能性もあります。
このような背景から、今のうちに採用体制を整えておくことが将来的なリスク回避にもつながります。特に、障害者雇用を社内での「仕組み」として定着させることが、今後ますます重要になるでしょう。
法定雇用率未達成企業の特徴7選
未達成の企業の特徴はいかになります。達成していない企業は当てはまる項目が多いのではないでしょうか?
1. 障害者雇用に関する知識・経験がない
法定雇用率を達成できていない企業の多くは、障害者雇用に関する基本的な知識や経験が不足しています。「どんな業務を任せたらいいのかわからない」「配慮すべき点がわからない」といった不安から、一歩を踏み出せずにいるケースが多いです。
特に、過去に障害者を雇用したことがない企業では、「なんとなく難しそう」というイメージだけで判断してしまう傾向があります。
2. 採用や定着に対する不安が強い
「雇ったはいいけれど、続けてもらえるだろうか?」「社内の対応がちゃんとできるか心配」このように、採用後の定着やトラブルを懸念する企業も少なくありません。
定着支援を行ってくれる外部機関(就労移行支援事業所やジョブコーチなど)と連携すれば、これらの不安は大きく軽減できます。
3. 業務の切り出しができていない
障害のある方が無理なく働けるようにするには、作業内容を細かく分けて「この部分だけお願いする」という工夫が必要です。未達成の企業では「任せられる仕事がない」と判断してしまい、採用のチャンスを自ら狭めていることがあります。
実際には、資料整理、軽作業、データ入力など、任せられる仕事は社内に意外と多くあります。まずは、既存の業務を洗い出し、どこを切り出せるかを考えるところから始めましょう。
4. 採用コストや効率ばかりに目がいく
「求人広告費がかかる」「サポートが必要で非効率では?」このように、コストや効率性だけを基準にしてしまう企業も、障害者雇用が進みにくい傾向にあります。
助成金を活用することでコストを軽減できる場合もありますし、定着すれば長期的な戦力として活躍してくれることも多くあります。
5. 義務感だけで動いている
「法律で決まっているから仕方なく雇う」というスタンスでは、社内の受け入れ体制が整わず、職場に居づらさを感じる原因になってしまいます。
障害者雇用を「義務」ではなく、多様性を活かした職場づくりの一環として捉えることが、長く続く雇用関係の土台になります。
6. 助成金や支援制度の情報不足
国や自治体には多くの支援制度や助成金が用意されていますが、それを知らない・調べていない企業は少なくありません。結果として、「障害者を雇うとコストばかりかかる」という誤解が生まれ、雇用が進まない状態になりがちです。
専門家(社労士や支援機関)と連携すれば、活用できる制度を整理し、申請までスムーズに進められます。
7. 経営層や人事の意識が低い
最も根本的な問題のひとつが、経営層や人事部門における障害者雇用への関心・意識の低さです。「優先順位が低い」「ほかにやることがある」と後回しにされがちですが、そうした企業は当然ながら雇用率も上がりません。
トップの理解と推進力があるかどうかは、障害者雇用の成功を左右する大きなポイントです。経営層が方針を明確に示すことで、社内全体の意識も変わっていきます。
未達成企業のリアルな声と課題
「対象企業だと知らなかった」という声
法定雇用率の対象になるかどうかは、「常時雇用する労働者が43.5人以上」かどうかで判断されますが、その条件を正しく把握していない企業は意外と多く存在します。
実際に中小企業の担当者からは、
「パートや契約社員もカウントするなんて知らなかった」
「グループ会社との合計で対象になるとは思わなかった」
といった声が聞かれます。
このように、制度の基本を誤解していたり、「自社は関係ない」と思い込んでいたりするケースが、未達成の背景にあることも少なくありません。
「業務がない」「定着しない」という悩み
次に多いのが、「そもそも任せられる仕事がない」「雇っても長続きしない」という悩みです。
たとえば、建設業や小売業では、現場中心の仕事が多く「障害者ができる仕事がない」と感じてしまいがちです。また、「配慮しすぎて逆に気を使わせてしまった」「人間関係がうまくいかずに辞めてしまった」など、定着に関する悩みも多く聞かれます。
こうした課題の多くは、ジョブコーチや支援機関の力を借りることで改善が可能です。特に「業務の切り出し」や「社内の理解促進」に外部の専門家を活用することで、環境整備がスムーズになります。
採用活動がうまく進まない現実
「求人を出しても応募が来ない」「マッチする人材が見つからない」このように、採用段階でつまずいてしまう企業も多く存在します。
これは、情報発信の方法や募集内容に原因がある場合が少なくありません。たとえば、仕事内容が抽象的だったり、配慮内容が具体的に書かれていなかったりすると、応募者側も「ここで働けるだろうか」と不安に感じます。
また、ハローワークだけに頼らず、就労移行支援事業所などとの連携を活用することで、職場に合う人材と出会える可能性も高まります。採用活動を「待ちの姿勢」ではなく、「連携と工夫」で進めることが、法定雇用率達成の第一歩になります。
未達成を放置するとどうなる?
未達成の場合、罰則などのデメリットがあるため注意が必要です!
障害者雇用納付金制度とは
法定雇用率を達成していない企業には、「障害者雇用納付金制度」という制度が適用される場合があります。これは、一定規模以上の企業が障害者を法定人数よりも下回って雇用している場合、その不足人数に応じて納付金を支払う制度です。
たとえば、常時雇用する労働者が101人以上の企業が対象となり、1人あたり月額5万円(年額60万円)を納める必要があります(※金額は変更される場合あり)。
つまり、法定雇用率を満たさないままでいると、経済的な負担が長期的に続く可能性があるということです。一方で、雇用すれば納付金の支払いは不要になり、さらに助成金を受け取れる場合もあるため、対応を先送りするのは損になりかねません。
企業名の公表・行政指導の可能性
法定雇用率未達成の状態が続き、改善の姿勢が見られない企業には、行政からの指導や勧告が行われることがあります。さらに、改善が見られない場合は、企業名が公表されることもあります。
厚労省では、毎年「障害者雇用の取組が不十分な企業」として一定の条件に該当する企業をリスト化し、公表しています。これは法的な制裁というよりも、「社会的責任を果たしていない企業である」と世間に示す意味合いが強く、企業イメージに大きな影響を与える可能性があります。
企業イメージや信頼性への影響
障害者雇用の取り組みは、近年ではCSR(企業の社会的責任)やESG経営の観点からも注目されています。そのため、未達成のまま放置していると、次のような信頼低下リスクが発生します。
- 求職者から「働きたい」と思われにくくなる
- 取引先や株主からの評価が下がる
- 学生や若手の就職人気ランキングに影響
反対に、障害者雇用に積極的な企業は「多様性を尊重する企業」として社会的評価が高まり、人材獲得にもプラスに働く傾向があります。法定雇用率の達成は、単なる義務ではなく、企業価値を守り・高める重要な戦略でもあるのです。
業界別に見る達成率と課題
IT・建設・製造など業界ごとの傾向
障害者雇用の状況は、業界によって大きく異なります。ここでは、厚労省の報告書や現場の声をもとに、主な業界の傾向を見ていきましょう。
- IT業界:
テレワークやフレックス制度など柔軟な働き方が可能な一方で、「高度なスキルが必要」「職務が専門的すぎる」と感じられる傾向があり、実際の雇用率は他業種に比べてやや低めです。 - 建設業:
屋外作業や重作業が多く、身体への負担が大きいことから、「障害者に任せられる業務がない」と判断されやすく、用が進みにくい傾向があります。 - 製造業:
工場内での軽作業や検品など、障害者が担当できる業務が豊富なため、比較的雇用が進んでおり、法定雇用率を達成している企業も多い業界です。 - サービス業(宿泊・飲食など):
雇用の流動性が高く、短時間勤務やシフト制などに対応しきれず、定着が課題になるケースが多く見られます。
このように、業種ごとに事情が異なるため、一律の対策ではなく、業界の特性に応じたアプローチが重要です。
業界ごとの課題と「できない理由」
なぜ特定の業界では法定雇用率を達成しづらいのか。その背景には、業界ごとの「構造的な課題」や「誤解」が存在しています。
- IT業界の課題:
「スキルが高くないと務まらない」という先入観が障害者の選考を狭めています。しかし、実際にはテスターやデータ入力、社内のサポート業務など、スキルに応じた業務の切り出しは可能です。 - 建設業の課題:
現場作業以外の事務・資材管理・安全管理サポートなど、内勤的な業務への切り出しがまだ進んでいません。「全員が現場に出る」という固定観念を外すことが鍵となります。 - サービス業の課題:
勤務時間の柔軟性や、職場のコミュニケーションスタイルへの配慮が必要ですが、教育・フォロー体制が整っていないことが多く、短期離職につながりやすい現状があります。
どの業界にも「できない理由」は存在しますが、見方を変えると「できる方法」も必ず存在します。社内の業務を見直し、障害のある方が無理なく活躍できる環境づくりに取り組むことが、結果として企業全体の生産性向上にもつながります。
法定雇用率を上げるための具体策
業務の切り出しとマニュアル化
障害のある方が無理なく働ける環境をつくる第一歩は、社内の業務を見直し、「どの作業を任せられるか」を整理することです。これを「業務の切り出し」と呼びます。
たとえば、以下のような作業は多くの職場で切り出し可能です。
- 書類のファイリングやスキャン
- データ入力や照合
- 備品管理や清掃、郵便物の仕分け
さらに、業務内容をマニュアル化(手順書化)しておくことで、障害のある方が戸惑わずに作業を進められ、業務の属人化を防ぐ効果もあります。「特別な仕事を用意しなければ」と構えすぎず、既存の業務を分解して考えることで、雇用の可能性は大きく広がります。
短時間勤務や在宅ワークの活用
障害のある方の中には、体調管理や通院の関係でフルタイム勤務が難しいというケースもあります。そこで活用したいのが、短時間勤務制度や在宅勤務(テレワーク)です。
実際、週20時間以上の勤務であれば、雇用率にカウントすることが可能です。たとえば「1日4時間、週5日勤務」など柔軟なシフトを組むことで、雇用の幅が大きく広がります。
特にIT系業務や事務系作業は、在宅勤務と相性が良いため、コロナ禍以降は導入事例が急増しています。すべてを整えてから」ではなく、できる範囲から柔軟に雇用を始めてみる姿勢が重要です。
職場環境の見直しと配慮
障害のある方が安心して働ける環境を整えるためには、物理的・心理的な配慮の両方が求められます。
【物理的な配慮の例】
- 段差解消やスロープ設置
- 机やイスの高さ調整
- 視覚障害者向けの案内表示
【心理的な配慮の例】
- 理解ある上司・同僚の存在
- 体調や特性に応じたコミュニケーション方法
- 定期的な面談やフォローアップ
また、社内に向けて障害理解研修を実施することで、社員全体の意識改革にもつながります。「共に働く」という意識を持つことで、職場の雰囲気も大きく変わります。
支援制度・助成金をうまく使うには
使いやすい主な助成金一覧
障害者雇用を進める企業に向けて、国や自治体からさまざまな助成金や支援制度が用意されています。ここでは、特に活用されやすい代表的な助成金をご紹介します。
- 特定求職者雇用開発助成金
障害者を新たに雇い入れた企業に対して支給される助成金。雇用形態や障害の程度に応じて、最大240万円(中小企業)が支給されます。 - 障害者トライアル雇用奨励金
一定期間試行雇用(3か月)を行った場合に支給。本採用前に職場とのマッチングを確認できる制度です。 - 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援
職場での定着支援を行うジョブコーチの費用の一部が助成されます。 - 障害者作業施設設置等助成金
スロープ設置や設備改修など、職場の環境整備にかかる費用が対象です。
これらの制度は、組み合わせて活用することも可能です。最初からすべてを整える必要はなく、「活用できるものから始める」ことがポイントです。
専門家(社労士等)との連携がカギ
助成金制度には要件や申請期限、提出書類など細かいルールがあるため、専門家との連携が成功のカギとなります。
特におすすめなのが、社会保険労務士(社労士)や障害者雇用に詳しい支援機関との連携です。彼らは申請手続きのサポートだけでなく、「この制度が使えますよ」という提案もしてくれる心強いパートナーです。
また、就労移行支援事業所やハローワークの「障害者職業相談窓口」なども、企業側の支援に力を入れています。ひとりで悩まず、外部の力を借りることが成功への近道です。
助成金申請のポイントと注意点
助成金を確実に受け取るためには、以下のような申請時の注意点を押さえておく必要があります。
- 事前に計画を立てておくこと(採用後では遅い場合もある)
- 労働条件通知書や契約書類を整備しておくこと
- 助成対象となる障害者手帳の確認(精神・身体・知的の種別も影響)
- 書類の提出期限・手続きの正確さが重要
また、「助成金ありき」で採用を考えると本末転倒になることもあります。大切なのは、助成金を「障害者雇用を進めるための後押し」として活用することです。うまく制度を使いこなせば、コスト負担を抑えつつ、持続可能な雇用の仕組みづくりにつなげることができます。
障害者雇用がうまくいっている会社の特徴は、「すべて自社でやらない」という選択肢を取っている会社が多いです。障害者雇用は一般的な雇用と違い配慮する点も多くあります。これが同じ人事担当者がすべてやろうとするとパンクしてしまいますし、「面倒だから取り組みたくない」と考える会社も多くいます。
まずは、切り出せるところは外部に切り出し社内できるところからスタートしていくという形がよいでしょう。
雇用率を達成した企業の成功事例
中小企業の取り組み事例
障害者雇用は大企業だけの取り組みではありません。工夫と継続的な取り組みで、雇用率を達成している中小企業も全国に数多くあります。
たとえば、ある従業員80名規模の製造業では、作業工程の一部(検品・梱包)を切り出してマニュアル化し、週20時間の短時間勤務で2名の障害者を雇用。はじめは業務設計に苦労したものの、外部支援機関のアドバイスを受けながら体制を整え、現在は雇用率2.5%を安定的に維持しています。
「最初の1人を雇うまでが一番大変だった」という声が多く、一歩踏み出すことが大きな転機になることがわかります。
実際に定着率が上がった企業の声
障害者雇用の成否を分けるカギのひとつが「定着」です。成功している企業の多くは、定期的な面談やサポート体制の強化に取り組んでいます。
ある小売業では、入社後のフォロー面談を月1回実施し、本人の体調や業務の不安を早期にキャッチ。さらに、配属先の上司にも障害理解の研修を実施することで、職場内のコミュニケーションも円滑になりました。
結果として、1年以内の離職率が30%→10%以下に改善。「フォロー体制を整えることで、障害の有無に関係なく働きやすい職場になった」と社内でも好評です。
社内の意識や文化の変化
雇用率の達成は、単なる「数値目標のクリア」ではありません。障害のある方と共に働くことで、社内の意識や文化が大きく変わったという声も数多く聞かれます。
あるIT企業では、障害者雇用をきっかけに業務のマニュアル化が進み、全社的な生産性向上にもつながったといいます。また、「誰もが働きやすい職場とは何か?」を考える風土が根づき、ダイバーシティ推進の第一歩となったケースもあります。
このように、障害者雇用は単なる義務ではなく、組織の柔軟性や人材力を高めるチャンスにもなるのです。
よくある質問(FAQ)
Q. パートタイム勤務でもカウントされる?
はい、週20時間以上働いていればパートタイムの方でも雇用率にカウントされます。雇用契約書や出勤実績などで勤務時間を証明できることが重要です。
Q. 在宅勤務の障害者も雇用率に含まれる?
在宅勤務でも、勤務実態があり、条件を満たしていれば雇用率に含めることができます。特にIT系などで在宅ワークの導入が進んでおり、柔軟な働き方として注目されています。
Q. 雇用率を超えて雇用した場合のメリットは?
法定雇用率を超えて雇用した企業には、調整金や報奨金が支給されることがあります。また、企業イメージの向上やCSR(社会的責任)としての評価も高まります。
Q. 精神障害者も法定雇用率の対象になりますか?
はい。身体・知的・精神障害のいずれも法定雇用率の対象となります。ただし、精神障害者保健福祉手帳の所持が必要です。
Q. 障害者手帳がない場合でもカウントできますか?
原則として、障害者手帳の交付を受けていることが必要です。手帳がない場合、法定雇用率にはカウントされません。
Q. 障害者が退職したら雇用率はすぐに下がりますか?
はい。障害者が退職した時点で、その人数分のカウントは除外されます。そのため、定着支援が非常に重要になります。
Q. 雇用率は毎月チェックされるのですか?
雇用率の報告は年1回(6月1日時点)で行いますが、企業側は常にその水準を維持する努力が求められます。
Q. 雇用率の対象となる「労働者数」の定義は?
常時雇用する労働者(正社員・パート・契約社員など)で、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある方が対象となります。
Q. 自社が法定雇用率の対象企業かどうか確認するには?
「常時雇用する労働者」が43.5人以上いるかどうかで判断します。対象か不明な場合は、労働局やハローワークに相談すると正確に教えてもらえます。
Q. 助成金はすぐにもらえるのですか?
申請から支給までは数か月程度かかることが多いです。また、雇用前の申請が必要な制度もあるため、事前準備が重要です。
Q. 障害者雇用に対応した求人方法には何がありますか?
ハローワークをはじめ、障害者専用の求人サイトや、就労移行支援事業所との連携など、さまざまな方法があります。
Q. ハローワーク以外に相談できる機関はありますか?
はい。就労移行支援事業所、地域障害者職業センター、社会保険労務士なども相談先として活用できます。
Q. 障害者雇用で注意すべき労働条件のポイントは?
他の労働者と同様に、労働条件通知書の明示が必要です。また、本人の体調や特性に配慮した柔軟な勤務体系や業務内容の調整が求められます。
Q. 社内の受け入れ体制が整っていない場合はどうすれば?
無理に単独で取り組むのではなく、ジョブコーチや就労支援機関と連携して準備を進めるのが効果的です。社内研修の実施や配属部署の事前調整も有効です。
Q. 納付金を払っていれば雇用しなくてもいいのですか?
納付金を支払うことで法的には義務を果たしている形にはなりますが、企業名の公表やCSRの観点からも雇用推進が望ましいとされています。また、助成金などの支援を受けるメリットもあるため、雇用した方が中長期的にはプラスになることが多いです。
まとめ|まずは一歩踏み出すことが大事
- 未達成企業には共通した特徴がある
- リスクを放置せず、早めの対策が重要
- 支援制度や助成金をうまく活用することがカギ
法定雇用率の未達は、放置すれば納付金や企業イメージの低下など、さまざまなリスクにつながります。しかし、原因を見直し、対策を講じることで、確実に改善は可能です。
「何をすればいいかわからない」という方でも、業務の切り出しや短時間勤務、支援機関との連携など、今すぐ始められることはたくさんあります。
まずは現状把握と社内の意識改革から
障害者雇用は「義務」であると同時に、企業の価値を高める重要な経営戦略でもあります。採用・定着・社内体制づくりは一朝一夕ではありませんが、一歩踏み出すことで道は開けます。
この記事をきっかけに、ぜひ「自社にできること」から取り組んでみてください。