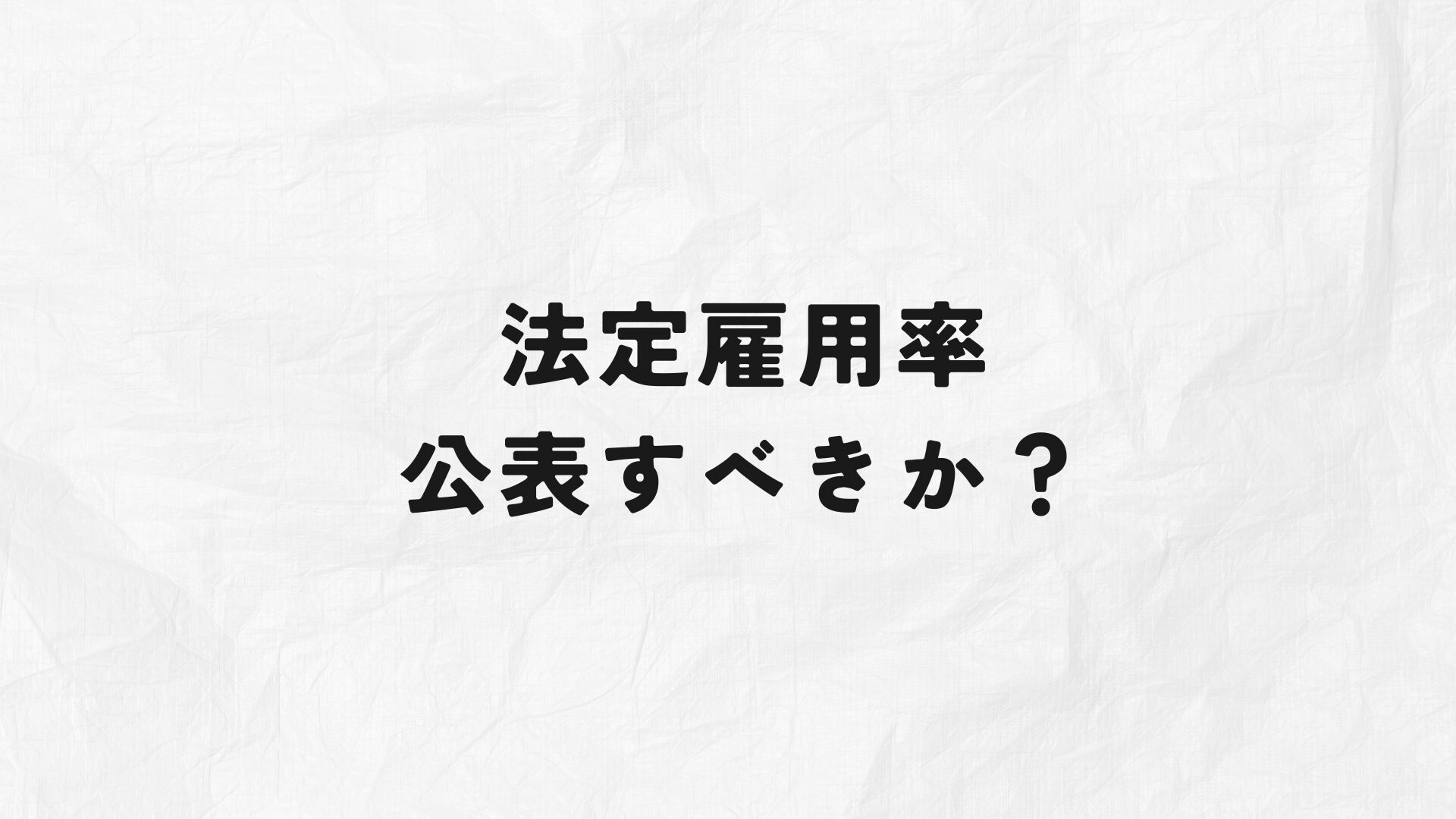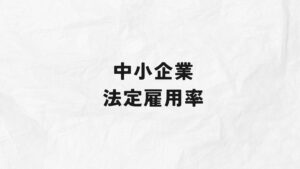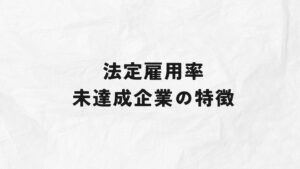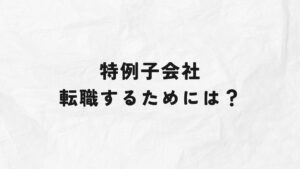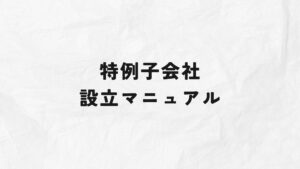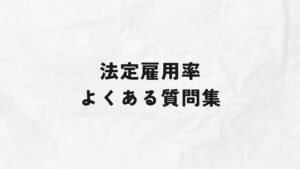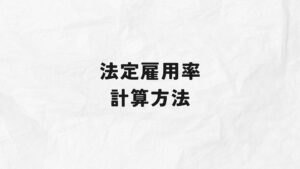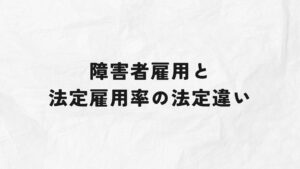「法定雇用率達成しているけど、世の中にアピールした方がいいの?」「法定雇用率って達成しても特にメリット感じない」この記事は、そんな疑問を持つ企業担当者の方に向けた内容になります。
最近では障害者雇用への取り組みが社会から注目される中で、企業の情報開示はほぼされていません。「公表すべきかどうか?」という問いに、具体的なメリット・デメリット・事例を交えてわかりやすく解説します。
法定雇用率とは?初心者にもわかる基本知識
まずは法定雇用率の基礎知識から。
法定雇用率の定義と対象企業
法定雇用率とは、企業が雇用する労働者のうち、一定割合以上の障害のある方を雇用することが義務づけられている制度です。この制度は「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づいて定められており、一定以上の規模の企業は法定雇用率を満たすことが求められます。
たとえば、従業員が40人以上いる民間企業では、一定の割合(%)で障害のある方を雇用しなければならないというルールです。この割合こそが「法定雇用率」と呼ばれています。
なぜ障害者雇用に「率」があるのか
障害のある方が、当たり前に働ける社会をつくるためには、雇用の場が必要です。しかし、実際には企業側が積極的に雇用に踏み出せないケースも多く、国として数値目標を定めることで雇用を後押ししています。
また、「率」として明確に定めることで、企業ごとの規模に応じた負担のバランスが取れるようになっているのも特徴です。
2024年の最新の雇用率と変更点
2024年4月の法改正により、民間企業の法定雇用率は 2.5% に引き上げられました。さらに、2026年4月には 2.7% まで引き上げられる予定となっています。
つまり、従業員が40人以上いる企業では、2024年時点で「1人以上」の障害者雇用が義務となり、今後さらにその基準が高くなるということです。
計算方法は細かい部分もあるので一概には言えませんが、100名の従業員がいる会社であれば、2.5%なので3名(切り上げ)の障害者雇用が必要になってきます。
対象となる企業の規模や業種
原則として、従業員数が43.5人以上(実質は常時雇用40人以上)の企業は、障害者を雇用する義務が生じます。業種にかかわらず、製造業・サービス業・IT企業などすべての民間企業が対象です。
また、従業員規模が基準を下回っていても、自主的に障害者雇用に取り組む中小企業も増えており、社会的な評価にもつながっています。
公表する義務ってあるの?
法定雇用率を公開しなければいけない決まりはあるのかをみていきましょう。
法的義務はある?
実は、法定雇用率を「公表する義務」は現時点の法律上ありません。つまり、企業が自発的に開示するかどうかは、あくまで任意です。
ただし、法定雇用率を達成していない場合には、「障害者雇用納付金制度」など、法的なペナルティが科されることがあります。また、一部の企業(特に上場企業)では、CSR(企業の社会的責任)や統合報告書などで「障害者雇用の状況」を公表しているケースが増えています。
企業が公表する背景と意図
法定雇用率の達成状況を公表する企業が増えている理由には、いくつかの背景があります。
- 企業の透明性向上:ステークホルダー(投資家・顧客・社員)からの信頼を得たい
- 採用ブランディング:障害者を含めた求職者に対して好印象を与えたい
- ESG(環境・社会・ガバナンス)経営の一環:社会的責任を果たす姿勢のアピール
これらは、企業の「義務」ではなく「選択」としての姿勢です。特に採用ページや会社案内などで「ダイバーシティへの取り組み」として掲載されることが増えています。
未達成の場合はどう扱われるの?
法定雇用率を達成していないからといって、それを公表してはいけないわけではありません。むしろ、「未達成だが、現在こうした取り組みを進めている」と正直に伝える企業も増えています。
公表することで「誠実な姿勢」や「改善意欲」が伝わり、かえってプラスの印象を与えるケースもあります。一方で、未達成の事実を単純に数値だけで示すと、誤解を生む恐れもあるため、文脈を添えて丁寧に説明することが重要です。
企業にとって「公表すべきか?」と迷うのは自然なことですが、その迷いの裏には“どう見られたいか”という経営姿勢が問われているとも言えるでしょう。
法定雇用率を公表する企業が増えている理由
公表義務はないのですが、法定雇用率を公表する企業は増えているのも事実です。どういう理由からでしょうか?
ESG・SDGsといった時代背景
近年、企業には「利益を出す」だけでなく、社会や環境にどのように貢献しているかも求められるようになってきました。特に注目されているのが、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)といった考え方です。
法定雇用率の達成・公表は、「社会(S)」への責任を果たしている証として評価されやすく、企業のサステナビリティ活動の一環として位置づけられるようになってきています。
特に大企業やグローバル企業では、こうした観点から障害者雇用の数値を開示するケースが増えており、今後は中小企業にもその波が広がっていくと予想されます。
透明性が重視される今の企業評価
従来の企業評価は「業績」や「ブランド力」が中心でしたが、最近では企業の姿勢や透明性が重視される傾向にあります。
「どんな会社か分からない」よりも、良い面も課題もオープンにしている企業のほうが、信頼されやすいのが今の時代。害者雇用に関する情報も例外ではなく、公表することが「誠実さ」や「社会への貢献姿勢」として評価されるのです。
特に採用・広報活動においては、発信している情報の量や質が、企業イメージを左右する大きな要素になっています。
投資家・求職者への影響
法定雇用率の公表は、投資家や求職者に対するメッセージにもなります。
投資家は、企業がどれだけ持続可能な経営をしているか、社会課題にどう向き合っているかを重視する傾向があり、その判断材料として障害者雇用の実績や開示状況が活用されることもあります。
また、障害のある求職者にとって、法定雇用率を公表している企業は「安心して応募できる企業」としての大きな指標になります。「どんな制度があるのか」「どんな職場か」という情報とあわせて、雇用状況を開示することは、採用面でもプラスに働くのです。
結果として、法定雇用率の公表は採用力や企業価値の向上につながるという好循環が生まれています。
あまり良い表現ではないかもしれませんが、法定雇用率が達成していることを公表すると社会的なイメージは上がります。採用・サービスに対する信頼感・株主と会社を運営していくうえでプラスになることが多いと言えます。しかもまだ公表している企業が少ないので、「法定雇用率達成している」というだけで目立つことができるのも事実です。
公表すべきか迷ったときの3つの視点
公表を迷ったときは下記の3つのポイントを考えてみてください。
① 社会的責任(CSR)の観点
まず考えたいのが、企業としての社会的責任(CSR)です。CSRとは、企業が利益を追求するだけでなく、社会や地域に対しても責任を持つべきという考え方です。
障害者雇用に関する情報を公表することは、誰もが働きやすい社会を目指す姿勢の表明につながります。特に、地域密着型の中小企業では、地域の雇用に対する誠実な取り組みとして評価されることもあります。
「うちはまだ達成していないから出せない…」と感じる必要はありません。むしろ、現在の取り組みや今後の目標を発信すること自体が、CSRの一部として意味を持つのです。
② 採用・広報効果の観点
2つ目の視点は、採用・広報への効果です。法定雇用率の達成状況を明らかにすることは、企業の姿勢を示す重要な材料となります。
たとえば、障害のある求職者にとっては、「障害者雇用に積極的な企業かどうか」を判断する一つの手がかりになります。また、企業説明会や採用ページでの開示は、ダイバーシティを重視する企業としての魅力向上にもつながります。
さらに、学生や若手人材が企業を選ぶ基準として“社会貢献性”を重視する傾向もあるため、障害者雇用に関する取り組みを伝えることは、採用活動においても大きな意味を持ちます。
③ 社内文化・理念との整合性
3つ目は、社内文化や企業理念との整合性という観点です。もし「多様性の尊重」「誰もが活躍できる職場づくり」を掲げているなら、その理念を行動として示すことが大切です。
法定雇用率の公表は、その理念を社内外に「見える化」する手段の一つです。特に、社内の社員に向けて「私たちはこういう姿勢で障害者雇用に取り組んでいます」と共有することで、社内一体感や誇りの醸成にもつながります。
また、理念とのギャップを感じた場合は、「理想と現実の差を埋めるためのステップ」としての公表も有効です。
このように、単なる数値の開示ではなく、会社としてどう向き合っているかを語ることが、信頼される企業づくりにつながります。
障害者雇用をまったくやっていない企業がわざわざ公表する必要性はありませんが、取り組みはやったが達成まであと一歩だった企業などは公表するメリットも大きいです。「こんな取り組みをして前年度より伸びた」「来年度は達成の見込みがみえた」など取り組みを公表するのもよいでしょう。
法定雇用率を公表するメリット
公表したときのメリットをみていきましょう。
企業イメージ・信頼性の向上
法定雇用率の公表は、企業の誠実さや社会への責任感を示すものとして高く評価されます。特に、ESGやSDGsなどの観点から「透明性のある企業姿勢」が求められる今、積極的に情報を開示することが信頼獲得につながります。
また、法定雇用率の達成状況だけでなく、現在の課題や改善努力まで伝えることで、「数値」以上の価値が生まれます。社会に対して“隠さない姿勢”を見せることで、企業ブランディングにも良い影響をもたらします。
障害のある求職者への安心感
障害のある求職者にとって、就職活動は大きな不安が伴います。「この会社は本当に自分を受け入れてくれるのか?」という不安を和らげるためには、事前に得られる情報の質がとても重要です。
法定雇用率の公表は、障害者雇用に前向きであることを客観的に示す手段となります。また、実雇用率に加えて、働いている障害者の人数や、職種・サポート体制なども公開することで、安心感はさらに高まります。
結果として、障害のある人材からの応募数が増加したという企業も少なくありません。
従業員のエンゲージメント強化
意外かもしれませんが、法定雇用率の公表は社内の従業員にも良い影響を与えることがあります。「自分の会社が、社会に貢献している」「多様性を大切にしている」という実感が、働くモチベーションや誇りにつながるのです。
また、障害者雇用の取り組みを社内で共有することで、部門を超えたコミュニケーションや協力体制が生まれ、組織全体の一体感が高まるという効果もあります。
事例:中小企業での成功例
ある地方の製造業A社では、障害者雇用の取り組みを自社ホームページで公表したところ、地域の障害者就労支援機関からの紹介が増加。さらに、求職者からの応募も増え、結果として採用活動の効率化にもつながったといいます。
また、従業員からも「会社の姿勢に誇りを感じた」「家族に安心して話せるようになった」という声があり、社内の雰囲気もポジティブに変化しました。
このように、法定雇用率の公表は単なる数字の開示にとどまらず、社外・社内両面に良い影響を与える可能性があるのです。
今回上げたメリットの中で現時点で一番影響力があるのは「企業イメージと採用」といえるでしょう。現在は公表の義務はありませんから、公表しているだけで目立つことができますし、会社のイメージがよくなります。これが公表が義務化の時代がきてしまったら、「達成するのが当たり前」という時代になるので、現時点で公表するメリットは大きいといえます。
法定雇用率を公表するデメリットやリスク
公表にはメリットもありますが、デメリットやリスクがないわけではありません。ここもしっかりチェックしておきましょう。
未達成の場合の風評リスク
法定雇用率を公表する際に最も多く聞かれる懸念が、「達成していないことを知られると、マイナスのイメージになるのでは?」という点です。
実際に、外部から「障害者雇用に消極的な会社なのか」と誤解されるリスクはゼロではありません。特に上場企業や採用活動を積極的に行っている企業では、数値がメディアやSNSで切り取られ、意図しない形で広がる可能性もあります。
しかし、達成していないこと自体よりも、何の説明もなく沈黙していることのほうが、かえって不信感を生む場合もあります。「取り組み中である」「今後こうしていく」といった前向きな説明を添えることがリスク軽減のポイントです。
誤解を招く可能性
法定雇用率という制度自体が一般にはあまり知られておらず、読み手によって誤解されるリスクもあります。
たとえば、「雇用率が低い=障害者を差別している」と受け取られてしまったり、「高い数値=環境が万全」と短絡的に評価されてしまうといった、不正確な認識のまま印象が形成されることもあります。
このような誤解を防ぐには、数値だけでなく、その背景や自社の取り組みをあわせて伝えることが大切です。
数値だけが独り歩きする懸念
法定雇用率はあくまで一つの指標にすぎません。しかし、数値を出すとそれが独り歩きし、「数値だけで評価されてしまう」という懸念もあります。
例えば、雇用率は高いがサポート体制が整っていない企業と、雇用率はまだ低いが丁寧な支援をしている企業では、実際の「働きやすさ」は大きく異なることがあります。
だからこそ、法定雇用率という数字とあわせて、「取り組みの質」や「社内体制」をしっかり伝えることが重要です。「数字を出したから終わり」ではなく、“その先”を丁寧に説明する姿勢が信頼につながります。
まだまだ「法定雇用率」「障害者雇用」というワードは浸透していませんから公表すると間違った認識をされてしまう可能性もありますがメリットも大きいです。今の会社で公表することはメリットが大きいか、リスクが大きいかはしっかり考える必要があります。
実際に公表している企業の事例紹介
上場企業の開示例
上場企業では、統合報告書やサステナビリティレポートなどで、法定雇用率に関する情報を積極的に開示する動きが進んでいます。
たとえば、某大手メーカーでは、自社の障害者雇用率を毎年レポートに掲載。雇用率に加えて、職場環境整備や人事制度、障害者社員の声などもあわせて紹介しており、“雇用の質”にも配慮している点が特徴です。
他にも、IT系上場企業ではコーポレートサイトの「ESG情報」ページで法定雇用率を数値で公開し、透明性の高さを対外的に示すとともに、求職者や投資家への信頼構築にも活用しています。
実際に公表している企業の事例紹介
ここでは、実際に法定雇用率を公表している企業をいくつかご紹介します。企業によって公表の理由や方法は異なりますが、共通しているのは「社会的責任」や「透明性」を重視しているという点です。
ゼネラルパートナーズ(障害者雇用特化)
障害者雇用支援サービスを展開するゼネラルパートナーズは、2023年度の障害者雇用率が15.55%と、法定雇用率(2.5%)の6倍以上を実現しています。自社Webサイトや報告資料で詳細な取り組み内容を公表しており、業界の先進事例としてもよく紹介されています。
エフピコ(食品容器メーカー)
大手食品容器メーカーのエフピコでは、障害者雇用率が2023年度時点で12.6%と非常に高く、特例子会社の活用も含めて積極的に取り組んでいます。年次報告書で雇用率の推移や雇用の工夫などを公開しており、ESG・CSRの視点からも注目されています。
ファーストリテイリング(ユニクロ)
ファーストリテイリングでは、2023年度で障害者雇用率4.60%と、法定雇用率を大きく上回っています。公式サイトで「ダイバーシティ&インクルージョン」ページを設け、障害者雇用の方針・実績・社員の声などを発信しています。
厚生労働省が社名公表した企業
一方で、法定雇用率を大きく下回り、改善指導にも応じず厚生労働省から社名を公表された企業もあります。
2023年3月時点では、不動産業や小売業など5社が対象となり、雇用率が0.4%〜0.8%程度と非常に低い水準でした。このように、公表には「積極的評価」と「行政による注意喚起」の2つの側面があることも押さえておきましょう。
中小企業での事例も多数
大企業だけでなく、中小企業でも雇用率や障害者支援の取り組みを公式サイトや採用ページで発信している事例が増えています。たとえば、介護事業所では、雇用率を公表しつつ、未達成である理由や現在の取り組みを丁寧に伝えており、地域の支援機関からの信頼にもつながっています。
公表方法に正解はありませんが、企業の姿勢を伝える手段として「事実+背景説明」をセットにすることが、信頼獲得のカギとなります。]
例えば、株式会社manabyは福祉系の会社ですが、取り組みを仙台市が公表しています。(記事はこちら)このように第三者が公表してもらえるとさらに信ぴょう性が増し、効果が出ると考えられています。
中小企業での工夫された公表方法
中小企業では、上場企業のような大規模な報告書は用意できなくても、身の丈にあった形で工夫して発信している事例が多数あります。
たとえば、ある介護事業所では、社内報や公式サイトで「障害者雇用の取り組み」を写真付きで紹介。「雇用率」そのものは未達成であることも正直に伝えつつ、現在取り組んでいる研修制度や今後の目標を丁寧に説明しており、地元自治体や支援機関からも高い評価を受けています。
別の飲食チェーンでは、店舗単位で障害者スタッフの紹介を行い、スタッフの得意なこと・工夫していることなどを紹介することで、地域とのつながり強化にもつながっています。
採用サイト・CSR報告書での活用事例
採用活動において、法定雇用率を採用サイトに掲載する企業も増えてきています。
たとえば、「ダイバーシティ採用」ページの中で、障害者雇用の現状・支援制度・キャリア支援の具体策などとあわせて、実雇用率を明記するスタイルです。数値だけでなく、「働いている人の声」「上司の声」「1日の流れ」なども併記することで、安心感と現実的なイメージを提供しています。
また、CSR報告書(企業の社会的責任に関する報告書)でも、法定雇用率や障害者雇用方針を盛り込む企業が増えており、これは社外への信頼だけでなく、社内の意識醸成にもつながっています。
このように、企業規模や業種にかかわらず、「伝え方を工夫すれば、自社の姿勢をきちんと伝えることができる」というのが現在のトレンドです。
公表する際に注意すべきポイント
情報の見せ方と説明文の工夫
法定雇用率をただ「数値」で表記するだけでは、読み手に誤解や先入観を与えてしまう恐れがあります。そのため、数値だけでなく背景や補足説明を加えることで、企業の真意や姿勢がより伝わりやすくなります。
例えば、「現在の雇用率は〇%です」と示すだけでなく、以下のような情報もあわせて掲載すると効果的です。
- 障害のある社員が活躍している業務内容
- 今後の雇用計画や目標
- 職場環境の整備・合理的配慮の具体例
また、文章トーンも「前向きさ」「誠実さ」を意識しましょう。たとえば、「まだ目標には届いていませんが、こうした取り組みを進めています」という表現であれば、未達成でも好印象につながります。
定期的な更新と誠実な発信
法定雇用率の情報は、一度出して終わりではなく、継続的に更新することが重要です。年度ごとに雇用状況を見直すだけでなく、進捗や改善への取り組み状況も伝えていくことで、企業の誠実さや本気度が伝わります。
また、更新の頻度や方法についてもルール化しておくと安心です。たとえば、「毎年6月に前年実績を公開する」など、発信のタイミングを定めておくことで、情報の信頼性が増します。
公表するからには「言いっぱなし」にならないよう、社内外から信頼される継続的な発信を心がけましょう。
社内説明と理解の徹底
外部に公表する前に、社内での情報共有と意識統一を行うことも忘れてはいけません。「うちは障害者雇用率を公開することになった」と突然通達するのではなく、なぜ公開するのか、どんな意味があるのかを丁寧に説明することが大切です。
特に、現場の社員やマネージャー層には、「これは企業の方針であり、職場づくりの一環である」ことを共有することで、納得感と一体感が生まれやすくなります。
また、社内での理解が進んでいない状態で外部に情報を出してしまうと、ギャップによる不信感が生まれる可能性もあるため注意が必要です。
公表は「社内外の信頼を築く行為」でもあるため、まずは社内の土台づくりからしっかりと整えることがポイントです。
公表に使えるフォーマット・テンプレート
数値と取り組みの併記例
法定雇用率の公表は、単に「〇%です」と数字を出すだけでなく、あわせて取り組みや背景を説明することで信頼性が高まります。以下はそのテンプレート例です。
【例文】
当社の障害者雇用率(2023年度実績):2.4%
法定雇用率:2.5%(2024年4月現在)
当社では、障害のある方が安心して働ける環境づくりに注力しています。
現在は法定雇用率にわずかに届いていない状況ですが、
今後の採用活動・職場改善を通じて達成を目指していきます。
このように、「数値+現状説明+今後の方針」をセットにすると、読み手に安心感を与えることができます。
社外資料・社内報での掲載例
法定雇用率の情報は、以下のような媒体での掲載が一般的です。
- 採用ページ(ダイバーシティ・インクルージョン紹介)
- 会社案内パンフレット
- 統合報告書・CSRレポート
- 社内報やイントラネット
特に社内向けでは、「自分たちの職場がどのような方を受け入れているのか」「どういう支援体制があるのか」などを伝える内容が好まれます。
【社内報のテンプレート例】
◎特集:当社の障害者雇用の現状
・現在の雇用率:2.6%
・活躍している職種:バックオフィス・製造補助・広報など
・制度:定着面談・職場支援スタッフ配置 など
このように、身近な言葉で取り組みを紹介することで、社内理解も深まりやすくなります。
問い合わせ対応のQ&A例
法定雇用率を公表すると、社外から質問や問い合わせを受けることもあります。事前に想定問答集(FAQ)を用意しておくとスムーズな対応が可能です。
【よくある質問と回答例】 Q. 雇用率が未達成なのはなぜですか? A. 求人への応募状況や業務マッチングの課題があり、現在も採用活動と職場改善を継続しています。 Q. 障害者が実際にどのように働いているか知りたいです。 A. 業務内容や支援体制については採用サイト・CSRレポートに掲載しています。見学も可能です。 Q. 今後の雇用計画はどうなっていますか? A. 中長期的に雇用を拡大する方針です。毎年雇用率を見直し、継続的な取り組みを行ってまいります。
このようなQ&Aは、ホームページのお問い合わせページや社内研修資料にも活用可能です。
あえて公表しない選択肢もある
公表するだけが正解ではありません。
なぜ非公表にする企業があるのか
法定雇用率を公表する企業が増えている一方で、あえて非公表のままにしている企業も一定数存在します。その理由はさまざまですが、主に以下のような背景があります。
- 雇用率が未達成であり、誤解や風評リスクを懸念している
- 一部業種では障害者雇用の適職が限られており、説明が難しい
- 公表によって「数値だけで判断される」ことを避けたい
このように、非公表は消極的な姿勢ではなく、戦略的な選択であることも少なくありません。むしろ、「今は出さない」ことを選んだ上で、他の形で企業姿勢を示すことが重要です。
代わりに発信すべき情報とは
法定雇用率を公開しない場合でも、企業として取り組んでいることは何らかの形で発信すべきです。たとえば、以下のような内容を採用ページや社内報、広報資料で伝えることができます。
- 障害のある方が活躍している事例紹介
- 社内での支援体制(ジョブコーチ、面談制度など)
- 今後の採用方針や多様性推進の取り組み
「数字」ではなく「人」や「姿勢」にフォーカスすることで、数字を出さなくても伝わる信頼を築くことができます。
目標と姿勢を明確にする方法
非公表であっても、「法定雇用率の達成を目指している」ことや「企業としての方針」は発信しておくと良いでしょう。これは採用・支援機関・投資家などに対しての誠意あるメッセージになります。
【例文】 当社では、現在の雇用率は法定基準に達していないものの、 多様な人材が活躍できる職場づくりに取り組んでいます。 今後も職務開発や支援体制の整備を通じて、雇用拡大を進めてまいります。
このように、数値の代わりに「意志」を示すことで、対外的な信頼は十分築くことができます。大切なのは、「公表するかしないか」ではなく、企業として何を大切にしているかを明確に伝えることです。
現時点では公表する義務はありませんから多くの法定雇用率未達成企業は「公表しない」選択肢をとっています。公表すればすべてよいことだけではありませんし、誤解されてしまう可能性もあります。ただ、公表していない企業が少ないために目立つことも間違いありません。会社としてどう判断をするかが大切になってきます。
よくある質問
法定雇用率ってそもそも何ですか?
法定雇用率とは、企業に対して一定割合以上の障害者を雇用することを義務づけた制度です。2024年4月現在、民間企業の法定雇用率は2.5%に設定されています。
法定雇用率を公表することは法律で義務づけられていますか?
いいえ、公表は義務ではなく任意です。企業の判断に委ねられています。
公表するときは具体的にどこに掲載すればいいですか?
採用ページ、会社案内、CSR報告書、統合報告書、社内報、公式ブログなどが主な掲載先です。
公表することで何かメリットはありますか?
企業の透明性・信頼性の向上、障害のある求職者からの応募増加、社員の誇り・エンゲージメント向上などが期待できます。
公表すると、未達成だと批判されませんか?
単に数字だけを出すのではなく、取り組みの背景や今後の方針を丁寧に説明することで、誠実な企業姿勢として評価されるケースが増えています。
法定雇用率を達成していないけど、正直に出してもいいの?
はい。現状と課題、今後の計画をあわせて伝えることで、信頼性を損なわずに公表できます。
中小企業でも公表した方がいいのでしょうか?
義務ではありませんが、地域や求職者との信頼構築のために公表する中小企業も増えています。
公表する場合、数値以外に何を伝えるべきですか?
職場での支援体制、障害者社員の業務内容、定着のための取り組み、今後のビジョンなども含めると効果的です。
公表のタイミングや頻度は決まっていますか?
法的な決まりはありませんが、年度末または採用ページの更新時に年1回程度の更新が一般的です。
公表しないことは悪いことですか?
いいえ。公表しないのも正当な選択です。ただし、代わりに取り組み姿勢や考え方を発信することが望ましいです。
他社はどれくらい公表しているんですか?
大手企業では統合報告書やESGページでの公表が進んでいますが、中小企業でも工夫して発信している例があります。
公表後に問い合わせが来たら、どう対応すればいいですか?
事前にFAQを用意し、担当窓口を明確にしておくとスムーズです。問い合わせ内容に対する誠実な対応が信頼につながります。
社員に公表内容をどう説明したらいいですか?
公表の目的・背景・内容を丁寧に説明し、誤解や不安を防ぐようにします。説明会や社内報での共有も有効です。
数値が一時的に下がった場合も更新すべきですか?
はい。正直に伝えた上で、その理由や改善の取り組みを説明することで、誠実な姿勢として受け止められます。
公表に向けてまず何から始めればいいですか?
まずは現在の障害者雇用状況を正確に把握しましょう。その上で、社内の方針確認・掲載場所の選定・原稿作成へ進むとスムーズです。
法定雇用率の公表は「企業の姿勢」を表す
企業価値・社会的評価との関係
近年、企業は「何をしているか」だけでなく、「どんな姿勢で社会と向き合っているか」が強く問われるようになっています。法定雇用率の公表は、まさにその企業のスタンス=社会への責任感を示す一つの指標です。
特にESG投資やSDGsへの取り組みが重視される中、障害者雇用の実績や方針の透明性は企業評価に直結する要素になりつつあります。単なる“法令順守”を超えて、社会との共生をどう実現しているかが注目されているのです。
社内・社外の信頼づくりにどう活かすか
法定雇用率を公表することは、社外への信頼発信だけでなく、社内へのメッセージとしても非常に効果的です。
たとえば、「会社が障害のある社員も大切にしている」という姿勢が明確に伝われば、社員のエンゲージメントやモチベーションが向上します。また、障害者雇用に直接関わらない部署にとっても、多様性への理解が深まるきっかけになります。
社外においては、求職者・取引先・地域住民など、さまざまなステークホルダーに対し、「信頼できる企業」としての印象を与えることができます。公表の内容とトーンが適切であれば、企業ブランド全体の価値向上にもつながります。
誠実な姿勢が選ばれる時代へ
「法定雇用率を達成しているから公表する」「未達成だから公表しない」という単純な話ではありません。今の社会では、どれだけ誠実に取り組んでいるか・その姿勢をどう伝えているかが評価の基準となっています。
たとえ雇用率が未達成であっても、「努力していること」「今後の方向性」をしっかりと発信すれば、多くの人にその思いは伝わります。逆に、達成していても何も発信しなければ、「何を大事にしている会社なのか」が見えづらくなります。
法定雇用率の公表は、「数値を開示すること」だけが目的ではありません。それを通じて、企業が社会とどう向き合っているかを示す“メッセージ”なのです。
これからの時代、選ばれる企業とは、実績とともに姿勢を語れる企業であることが求められています。
まとめ|法定雇用率の公表、すべきかどうかの最終判断
公表は義務ではないが、信頼づくりのチャンス
法定雇用率の公表は、現時点では法律上の義務ではなく、あくまで任意の取り組みです。しかし、企業の透明性・社会的責任が強く求められる今、公表することは信頼を得るための有効な手段となりつつあります。
数値だけでなく、背景や思い、今後の方針を丁寧に発信することで、社会からも社内からも評価される企業姿勢を築くことができます。
「何をどう伝えるか」で印象は大きく変わる
法定雇用率を達成しているかどうかよりも、「どのように伝えるか」が信頼性を大きく左右します。未達成であっても、真摯に取り組んでいる姿勢が伝われば、ポジティブに受け止められることが多いです。
逆に、達成していても発信がない・表面的すぎると、評価にはつながりません。数値+文脈+取り組み内容をバランスよく伝えることで、読者やステークホルダーに誠実さが伝わります。
まずは自社の現状を正しく把握しよう
公表するかどうかを判断するには、まず自社の障害者雇用の現状を把握することが第一歩です。現在の雇用率、制度、職場の環境整備状況を明確にすることで、「何を出すべきか」「どう伝えるか」が見えてきます。
そのうえで、会社の文化・理念・将来の方向性と照らし合わせて、公表の有無や内容を決めることが大切です。
法定雇用率の公表は、単なる広報活動ではなく、企業の信頼・価値・誠実さを社会に届ける選択肢のひとつです。一歩踏み出してみることで、新たなつながりやチャンスが広がるかもしれません。