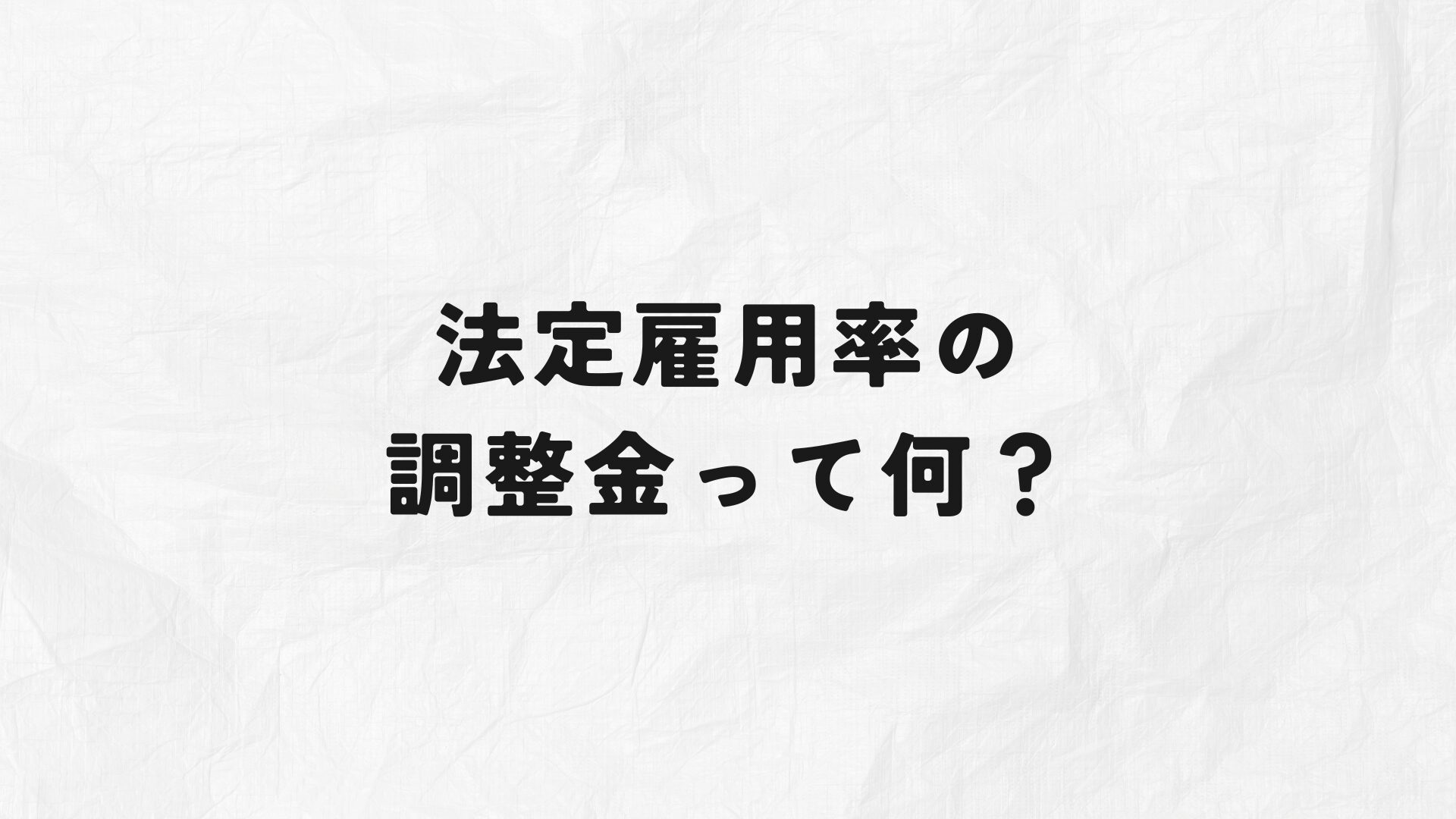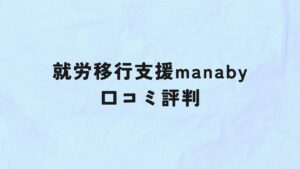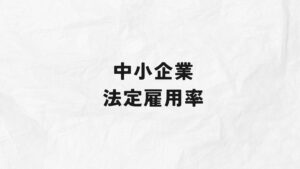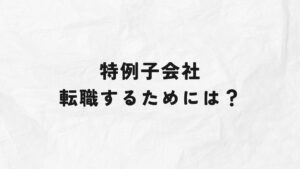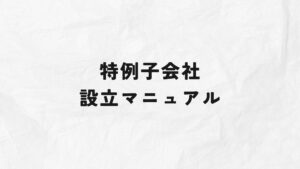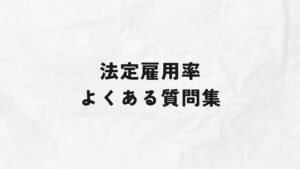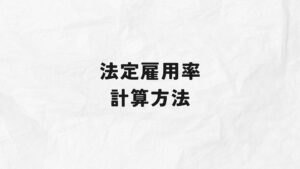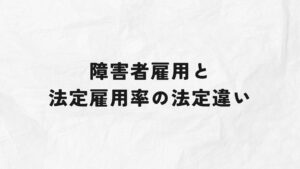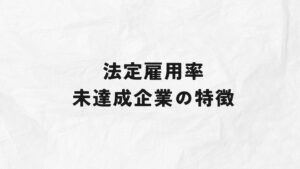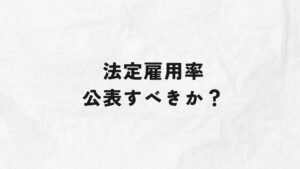法定雇用率という言葉は聞いたことがあっても、「調整金」まで詳しく知っている方は少ないかもしれません。この記事では、企業の障害者雇用に大きく関わる「調整金制度」について、初心者の方でもわかるように丁寧に解説します。
「どんな企業が対象?」「どうやって計算するの?」「納付金・報奨金と何が違うの?」そんな疑問に、実例も交えてお答えします。
法定雇用率と調整金の関係とは?
まずは法定雇用率の基礎知識から確認していきましょう!
法定雇用率とは何か?
法定雇用率とは、企業が雇うべき障害者の割合を法律で定めたものです。現在(2025年7月時点)の法定雇用率は、民間企業で2.5%。つまり、従業員が100人いる企業であれば、3人以上(小数点は切り上げのため)の障害者を雇用する義務があるということです。
この制度の背景には、「障害のある人も、社会の一員として働く機会を得るべきだ」という考え方があります。障害者の就労支援と、企業の社会的責任(CSR)を両立させる仕組みとして、法定雇用率が設けられています。
障害者雇用の基本ルール
法定雇用率制度の下では、企業は次のようなルールを守る必要があります。
- 常用労働者が43.5人以上の企業に、障害者の雇用義務が発生
- 雇用義務を果たしていない場合、納付金(ペナルティ)の支払いが必要
- 反対に、法定雇用率を超えて雇用した企業には、調整金や報奨金が支給されることがある
つまり、法定雇用率は「義務」として設定される一方で、それを超えて努力した企業には「報酬」があるという形になっています。これが「調整金」と言われているものになります。
調整金制度の全体像
調整金制度とは、法定雇用率を上回って障害者を雇用した企業に対して支給される、国の支援金制度です。企業の障害者雇用を促進するために設けられています。
調整金が支給されるのは、常用労働者100人超の企業が、法定雇用率を上回る人数の障害者を雇用した場合になります。支給額は、超過1人あたり月額27,000円(年間最大324,000円)と、企業にとっては人件費の補填として非常にありがたい金額です。
このように、調整金は「義務を超えて努力した企業」に対する報奨であり、障害者雇用の質と量を両立させる重要な制度として注目されています。
調整金とは?制度の概要をやさしく解説
調整金をさらに詳しくみていきましょう。
調整金の定義
調整金とは、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業に対して、国から支給される奨励的な給付金です。この制度は、障害者の雇用を積極的に行っている企業を支援し、社会全体で障害者雇用を推進することを目的としています。
企業が法定雇用率を達成するだけでなく、それを上回る人数の障害者を継続的に雇用している場合に、その努力を評価し金銭的な支援が行われるのが「調整金制度」です。
支給対象になる条件
調整金が支給されるためには、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 常用労働者が100人を超える企業であること
- 法定雇用率を上回って障害者を雇用していること
- 対象となる障害者がハローワークを通じて雇用されていること
- 週所定労働時間が20時間以上の雇用であること
これらの条件を満たしていれば、1人あたり月額27,000円(年間最大324,000円)の調整金が支給されます(2025年現在)。企業にとっては、人件費の一部補填として非常に大きなメリットがあります。
他の制度(納付金・報奨金)との違い
障害者雇用に関連する給付制度は「調整金」以外にも、「納付金制度」や「報奨金制度」があります。これらは似たような名前ですが、対象となる企業や目的が大きく異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
調整金と納付金の違い
納付金制度は、法定雇用率を満たしていない企業が、未達成分に応じて支払う義務のある金銭です。常用労働者が100人を超える企業が対象で、1人あたり月額50,000円(年間60万円)の納付が必要になります。
一方で調整金法定雇用率を超えて障害者を雇用した企業に対して支払われる奨励金です。つまり、納付金は「罰金」的な意味合いがあり、調整金は「報酬」的な意味合いを持つ制度です。
調整金と報奨金の違い
報奨金100人以下の企業が、法定雇用率を達成または超えた場合に支給されます。
支給額は調整金と同様に月額27,000円(1人あたり)ですが、報奨金は企業規模が小さいほど活用しやすい制度と言えます。対して調整金は100人超の企業限定という点で、対象範囲に違いがあります。
| 制度名 | 対象企業 | 雇用率の状態 | 支給・納付額 |
|---|---|---|---|
| 調整金 | 常用労働者100人超 | 法定雇用率を上回っている | 月額27,000円支給 |
| 納付金(罰金) | 常用労働者100人超 | 法定雇用率未達成 | 月額50,000円納付 |
| 報奨金 | 常用労働者100人以下 | 法定雇用率を超えている | 月額27,000円支給 |
このように、調整金は「大企業向けの報酬制度」として設けられている制度です。報奨金や納付金制度との違いを理解しておくことで、自社に合った雇用戦略が立てやすくなります。
調整金の支給対象企業と条件
常用労働者数が100人超の企業
調整金制度の対象となる企業は、常用労働者が100人を超える企業です。ここでいう「常用労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間の定めがない労働者、もしくは1年以上継続して雇用されている有期契約社員などを指します。
たとえば、パートや契約社員でも週20時間以上働いていれば、常用労働者としてカウントされる場合があります。逆に、100人以下の企業は調整金の対象外ですが、報奨金制度の対象となる可能性があります(詳しくは前の章をみてください)。
法定雇用率を上回って雇用している企業
調整金は、「義務を超えて障害者を雇用している企業」が対象です。つまり、法定雇用率(2025年時点で2.5%)を上回っていることが条件です。
例えば…常用労働者が200人いる企業の法定雇用数は、2.5%×200人=5人です。
この企業が6人の障害者を雇用している場合、1人分が法定雇用率を超えており、その超過分に対して調整金が支給されます。ポイントは「常に超えていること」。短期間だけでなく、年間を通じて安定的に雇用されているかが重要になります。
公共職業安定所(ハローワーク)との連携が必要
調整金を受け取るためには、雇用している障害者が、原則としてハローワークなどの公共職業安定所を通じて紹介された人材である必要があります。
これは、国が障害者の職業紹介を通じて雇用を管理・支援しているからです。企業が独自に採用した場合でも、条件次第では対象となることがありますが、基本はハローワークを通じた雇用であることが安全です。
さらに、調整金の申請時には、ハローワークが発行する「雇用状況報告書」や「実雇用率算定資料」などを基に審査が行われます。そのため、日頃からハローワークとの連携を密にし、障害者雇用に関する記録や書類をきちんと整備しておくことが求められます。
調整金の金額と計算方法
1人あたりの支給額
調整金は、法定雇用率を上回って雇用した障害者1人あたりに支給される給付金です。2025年度の支給額は、以下のとおりです。
- 1人あたり月額:27,000円
- 1人あたり年額:324,000円(※月額×12ヶ月)
これは対象となる障害者を継続的に雇用している企業にとって、実質的な人件費の支援となる大きな金額です。たとえば、調整対象者が5人いる企業では、年額で1,620,000円の調整金を受け取ることが可能になります。
調整金の支給人数の算出方法
では、調整金の「支給対象人数」はどのように決まるのでしょうか?その基本的な考え方を解説します。
- 企業の常用労働者数から、法定雇用義務数を計算
- 実際に雇用している障害者数と比較
- その超過分が調整金の支給対象になる
法定雇用義務数の計算は、常用労働者数 × 法定雇用率(現在は2.5%)で求めます。この義務数を超えた分が「超過雇用者数」となり、調整金の対象となります。
端数処理に注意
法定雇用義務数の計算で発生する小数点以下の端数には注意が必要です。制度上、義務雇用数は「小数点第2位を四捨五入」して算出されます。
たとえば、以下のようになります。
- 150人 × 2.5% = 3.75 → 義務数は3.8人 → 四捨五入で4人
- 189人 × 2.5% = 4.725 → 義務数は4.7人 → 四捨五入で5人
この「四捨五入」のルールによって、思わぬ差が出ることがあるため、正確な計算が非常に重要です。
実際の計算例
ここで、調整金の仕組みを具体的なケースで見てみましょう。
A社の場合
A社は、以下のような条件の企業です。
- 常用労働者数:200人
- 実際に雇用している障害者:7人
まず、法定雇用義務数を計算します。
200人 × 2.5% = 5.0人
→ 義務雇用数は「5人」となります。
実際の雇用が7人ですので、
7人 − 5人 = 2人分が調整金の対象になります。
支給額は以下の通りです。
- 月額:27,000円 × 2人 = 54,000円
- 年額:54,000円 × 12ヶ月 = 648,000円
つまり、A社は年額で約65万円の調整金を受け取ることができるというわけです。この金額は、障害者雇用にかかるコストの一部をしっかり補填してくれるでしょう。
調整金の申請方法と必要書類
ここまできたら次は申請の方法です。
どこに申請する?
調整金の申請先は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)です。正式には「障害者雇用納付金制度」を所管する機関であり、調整金の審査・支給もJEEDが担当します。
ただし、申請手続きの受付・書類提出窓口は都道府県単位で分かれており、企業の所在地にあるJEED支部または委託を受けた機関へ提出します。詳しくは、JEED公式サイトで該当エリアを確認してください。
毎年必要な提出書類
調整金の申請には、以下のような書類の提出が求められます。
- 障害者雇用状況報告書(6月1日時点)
- 障害者雇用納付金申告書
- 調整金・報奨金の支給申請書
- 障害者の雇用契約書・出勤簿・賃金台帳の写し
- 実雇用率算定に必要な書類(JEED指定)
とくに「障害者雇用状況報告書」は、毎年6月1日時点の雇用状況を記録したもので、法定提出義務がある重要書類です。これを提出していない場合、調整金の申請は受け付けられません。
申請スケジュールと期限
調整金の申請スケジュールは、以下のような年間サイクルで行われます。
- 対象期間:4月1日〜翌年3月31日
- 報告基準日:6月1日時点の雇用状況
- 申告・申請時期:翌年4月〜5月にかけて
つまり、前年4月〜当年3月までの雇用状況をもとに、翌年度の春に申請する流れです。申請書類の提出は5月中旬頃が締切になることが多いため、早めの準備が欠かせません。
よくあるミスと注意点
調整金の申請では、以下のようなミスや見落としが毎年多く報告されています。
- 障害者雇用状況報告書を出していない
- ハローワークを通さずに雇用したため対象外になる
- 週所定労働時間が20時間未満で対象外になる
- 障害者手帳の写しが未提出、または有効期限切れ
- 書類の提出が遅れて期限に間に合わない
制度自体は手厚い支援ですが、実務レベルではミスが命取りになるケースもあります。必要に応じて、社会保険労務士や外部コンサルタントに相談するのも一つの方法です。
やはり国の調整金・助成金制度はルールや書類がかなり細かいのが特徴です。ですので人事担当者が1人でやろうとするとかなり大変ですし、ミスが起こってしまう可能性もありますから必要に応じて外部の力を借りることをオススメします。
実際の活用事例とインタビュー
調整金を活用して雇用を広げた事例
ここでは、調整金制度を上手に活用しながら障害者雇用を拡大した企業の事例をご紹介します。「制度があることは知っているけど、どう活かせばいいかわからない…」という方にとって、ヒントとなる内容です。
製造業での成功事例(A社)
A社(従業員数:350名)では、これまで法定雇用率を最低限満たす程度の障害者雇用にとどまっていました。しかし、人手不足と多様な人材活用の必要性から、障害者雇用を本格的に推進する方針へと転換しました。
具体的には、以下のような取り組みを行いました。
- 軽作業部門に専用チームを設置
- ハローワークと連携して継続的な採用活動を実施
- ジョブコーチ(職場適応援助者)の導入で定着支援を強化
その結果、法定雇用率を1.8人分上回る雇用を実現し、年間58万円以上の調整金を受給。この資金を活かして、作業環境の改善や研修費用の確保にも取り組むことができました。
人事担当者の声:
「制度を知ってからの動き出しでしたが、障害者雇用は会社にとってもプラスが多いと実感しています。調整金は心強いサポートです。」
IT企業での工夫と改善(B社)
B社(従業員数:180名)は、テレワーク制度を活かしながら障害者雇用を拡大し、調整金制度を活用した事例です。特にIT業界では視覚・聴覚・精神面など、様々な障害特性に合わせた柔軟な対応が求められます。
同社の主な取り組みは次の通り。
- フルリモート勤務体制の整備
- 業務マニュアルの視覚化・作業分担の細分化
- 1対1のメンター制度によるサポート体制の構築
その結果、4人の障害者雇用を実現し、法定雇用率を2人分超過。年間64万円の調整金を受け取りつつ、社内の働き方改革やダイバーシティ推進にもつながっています。
担当マネージャーの声:
「制度を知って動いたことで、人材の多様性と組織の柔軟性が高まりました。調整金はそのきっかけとして非常に有効でした。」
よくある質問(FAQ)
Q1. 調整金はすべての企業がもらえるの?
いいえ。調整金は常用労働者が100人を超える企業で、法定雇用率を上回って障害者を雇用している場合に支給される制度です。中小企業(100人以下)は対象外ですが、別途「報奨金」制度の対象になる場合があります。
Q2. 納付金と調整金は相殺されるの?
基本的には相殺されません。同じ企業内に法定雇用率未達成の事業所と、超過している事業所がある場合は、全体での調整(企業単位での通算)が行われることもありますが、納付金と調整金は別々に扱われます。
Q3. 申請しなかったらどうなる?
申請しなければ、当然ながら調整金を受け取ることはできません。制度は自動支給ではなく、毎年の申請が必須なので注意が必要です。
Q4. 中小企業も対象になるの?
調整金は対象外ですが、中小企業(常用労働者100人以下)には「報奨金」制度があります。こちらも法定雇用率を超えた雇用に対して、月額27,000円(1人あたり)が支給されます。
Q5. 障害者の雇用はどのようにカウントされるの?
基本的には週所定労働時間20時間以上の障害者が対象です。また、障害の種類によっては「重度障害者は1人=2人分」としてカウントされる特例もあります。
Q6. 支給される金額は毎年同じなの?
現行では月額27,000円が支給されていますが、制度改正により金額が変動する可能性があります。JEEDや厚生労働省の発表を毎年確認することをおすすめします。
Q7. 雇用形態に制限はある?
正社員に限らず、契約社員・パート・アルバイトでも週20時間以上であれば対象になります。ただし、雇用契約や出勤実績など、証明できる書類の提出が必須です。
Q8. 障害者手帳がなくても対象になる?
基本的には障害者手帳(身体・知的・精神)が必要です。ただし、特定の福祉サービスを利用していることで対象となるケースもありますので、詳細はハローワークに確認してください。
Q9. ハローワークを通さず採用した人は対象外?
原則としてハローワーク経由での雇用が条件ですが、特定の条件を満たせば例外的に対象となる場合もあります。判断に迷う場合は、事前にJEEDまたはハローワークへ相談するのが安全です。
Q10. 障害者を短期雇用した場合でも対象になる?
支給対象となるのは、継続的に雇用されていることが前提です。短期や一時的な雇用では調整金の対象とは認められない場合があります。
Q11. 申請は誰が行うの?
基本的には企業の人事・労務担当者が申請を行います。
社労士や外部コンサルに申請代行を依頼する企業も増えています。
Q12. いつ申請すればいいの?
申請時期は毎年4月〜5月です。対象となる雇用期間は前年4月〜当年3月なので、年度末に向けて準備を進めておくとスムーズです。
Q13. どのくらいの期間で支給される?
申請書類の審査完了後、6月〜8月頃を目処に支給されることが多いです。審査に時間がかかる場合は、それ以降になることもあります。
Q14. 申請に費用はかかる?
申請自体に費用はかかりません。ただし、社労士や外部支援機関に申請を依頼する場合は、手数料が発生することがあります。
Q15. 他の助成金と併用できる?
はい、他の雇用関係助成金(特定求職者雇用開発助成金など)と併用可能です。ただし、同一の目的に対して二重で支給されないように注意が必要です。事前に制度の重複確認をしましょう。
障害者雇用に取り組むメリット
障害者雇用は、「法律で決まっているから仕方なくやるもの」ではありません。実際には、多くの企業が経営的にも社会的にも大きなメリット ここでは代表的な3つのメリットをご紹介します。
企業イメージの向上
障害者雇用に積極的な企業は、「社会貢献」や「ダイバーシティ推進」に力を入れている企業として、社外から高く評価される傾向があります。
特に最近では、投資家・取引先・求職者などが企業の「社会的責任(CSR)」や「ESG経営」を重視する時代です。そのため、障害者雇用への取り組みは、ブランド力の向上や人材採用のプラス要因にもつながります。
また、「障害者雇用優良企業」として厚生労働省や自治体から表彰される企業もあり、広報・PRの観点でも大きなメリットがあります。
人材多様性の強化
障害のある方の多くは、真面目で継続的な勤務に長けていたり、特定の業務に対して非常に高い集中力やこだわりを持つなど、ユニークな強みを持っています。
そうした個性を活かすことで、企業は業務の再構築(業務分解)や作業効率の見直しにもつながり、組織全体の生産性が向上するケースもあります。
さらに、多様な価値観や働き方が混ざり合うことで、「相手に配慮する文化」や「チームの柔軟性」が自然と育まれ、結果的に社員全体の定着率や満足度も向上する傾向があります。
助成金制度との併用も可能
障害者雇用に取り組む企業は、調整金だけでなく、以下のような複数の支援制度・助成金を活用できます。
- 特定求職者雇用開発助成金(障害者の新規雇用時に支給)
- 障害者職場定着支援助成金(一定期間の継続雇用で支給)
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業(専門家の派遣費用)
これらの制度は、併用可能な場合が多く、組み合わせ次第で最大数百万円規模の支援を受けることも可能です。
企業にとって、障害者雇用は「コストがかかる」というよりも、支援制度を使いこなすことで実質的なコスト削減につながる選択肢となります。
制度変更の履歴と今後の動向
近年の支給金額の変化
調整金の1人あたりの支給額は、2021年度までは月額27,000円で据え置かれており、2025年現在もこの水準が継続しています。ただし、納付金(未達成企業のペナルティ)については過去に段階的な引き上げが行われており、制度全体として「雇用達成への誘導」を重視した傾向が見られます。
▼過去の主な制度変遷の一例:
- 2021年度以前:納付金 1人あたり 月額50,000円
- 2023年度:納付金制度の厳格化(支払義務企業の対象拡大)
- 2024年度:法定雇用率が段階的に2.5%へ引き上げ
このように、政府は制度のインセンティブ構造を調整しながら、障害者雇用の全体底上げを目指している状況です。
制度改正の背景と理由
調整金を含む障害者雇用納付金制度の改正には、いくつかの社会的背景があります。
- 障害者の労働参加率が依然として低い
- 企業間の雇用格差が大きい(雇用している企業が偏っている)
- 高齢化と並行して精神・発達障害の就職支援ニーズが増加
- 多様性・包摂性(インクルージョン)を重視する国際的潮流
これらを踏まえて、国は「障害者が安心して働ける社会」の実現と、企業の自主的な雇用努力を促すために制度設計を見直してきました。調整金はその中で、雇用達成企業を支援する“プラスの報酬”としての位置づけを担っています。
2026年以降の制度見通し
2026年度以降も、障害者雇用制度は以下のような方向での見直しが予想されています(※現時点では正式発表なし)。
- 法定雇用率のさらなる引き上げ(2.7%〜3.0%)の可能性
- 精神障害・発達障害者向け支援の充実
- テレワーク雇用の評価方法の見直し
- 中小企業への新たな報奨金制度の検討
また、企業の障害者雇用に関する情報開示(見える化)義務の拡大など、透明性と社会的責任を高める方向に制度が進むと見られています。
今後の制度変更に備えるためにも、最新の政府発表や厚生労働省・JEEDの公式情報を定期的にチェックしておくことが重要です。
まとめ|調整金制度を理解して賢く活用しよう
この記事のポイントおさらい
調整金制度は、障害者雇用に積極的に取り組む企業にとって金銭的支援と社会的評価の両方が得られる非常に有効な制度です。本記事の内容を振り返ると、以下のようなポイントがありました。
- 調整金は法定雇用率を上回った障害者雇用に対して支給される
- 対象は常用労働者100人超の企業で、月額27,000円/人が支給される
- 申請には書類の整備とスケジュール管理が不可欠
- 納付金・報奨金制度との違いを正しく理解することが重要
- 調整金を活かして雇用の安定・多様性推進・助成金併用が実現可能
制度を正しく理解すれば、単なる義務ではなく、会社の成長と社会貢献を同時に実現する手段として活用できます。
今すぐできる社内チェックリスト
調整金の申請に向けて、以下のチェック項目を社内で確認してみましょう。
- 常用労働者数が100人を超えている
- 障害者の雇用人数が法定雇用率を超えている
- 障害者雇用状況報告書を毎年6月に提出している
- ハローワークを通じた雇用を行っている
- 雇用契約書・賃金台帳・出勤簿などの証明書類が保管されている
- 前年4月〜当年3月までの雇用実績を把握している
上記の条件を満たしていれば、調整金の対象となる可能性が高いです。社内で定期的にチェックする仕組みを作ると、申請忘れやミスも防げます。
社労士や専門家への無料相談も視野に
調整金制度はメリットが大きい反面、制度や書類の仕組みが複雑な部分もあります。特に初めて申請する企業にとっては、不安や疑問も多いのが実情です。
そんな時は、社会保険労務士(社労士)や障害者雇用に詳しい専門家への無料相談を活用しましょう。地域のハローワークや独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)も、相談窓口を設けています。
障害者雇用は、企業にとって「義務」ではなく「未来への投資」です。申請の遅れや記載ミスでせっかくの調整金を逃してしまわないよう、早めの準備とプロの知見をうまく活かすことが成功のカギです。