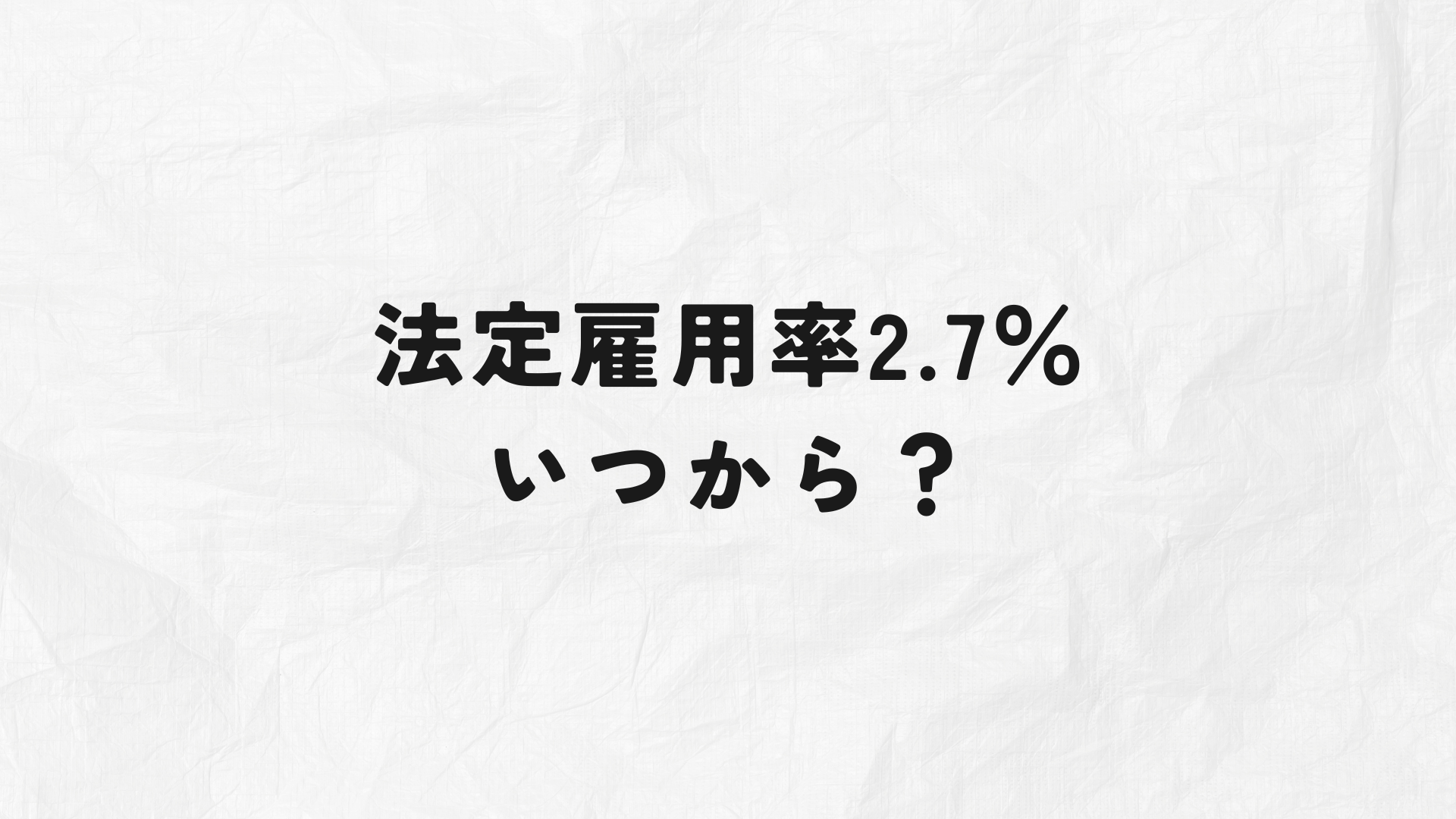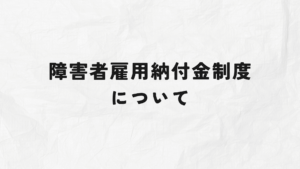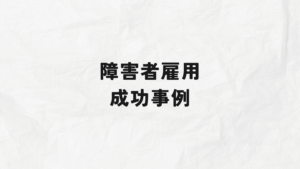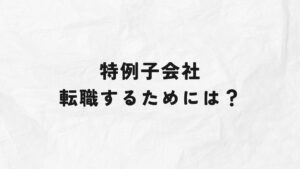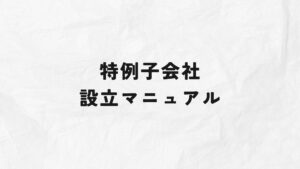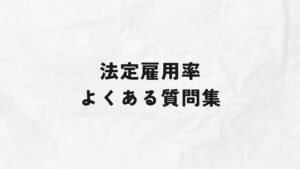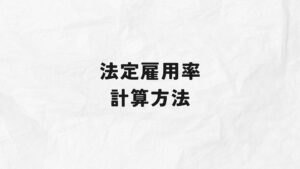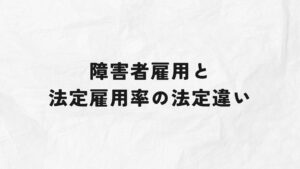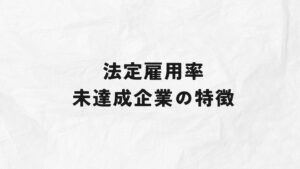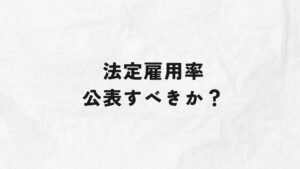「法定雇用率2.7%っていつから変わるの?」「そもそも法定雇用率って何?」そんな疑問を持っている担当者の方も多くいます。
この記事では、法定雇用率2.7%がいつから適用されるのか、背景や影響、対応策まで初心者でもわかりやすく解説します。
法定雇用率2.7%はいつから?
最新改定の適用日
2026年7月1日から施行予定
法定雇用率が2.7%へ引き上げられるのは、2026年7月1日からと厚生労働省より発表されています。現在(2025年7月時点)の法定雇用率は2.5%で、これは2024年4月1日に改定された数値です。
つまり、企業としては2024年に2.5%へ対応したばかりですが、2年後の2026年にはさらに2.7%へ引き上げられるため、今から採用計画や体制整備を進めておく必要があります。
例えば従業員が100人の企業の場合、2.5%では2.5人(切り上げ3人)、2.7%になると2.7人(切り上げ3人)と変わらないように見えますが、従業員規模が大きくなるほど必要人数も増えるため注意が必要です。
従業員1000人の会社は25名から27名へ、従業員10000人の会社は250人から270人に増やさなければいけません。
具体的に誰が対象?
民間企業と国・自治体の違い
法定雇用率は民間企業、国や地方公共団体、都道府県教育委員会に適用されますが、それぞれ数値が異なります。
- 民間企業:現在2.5%(2024年4月〜) → 2.7%(2026年7月〜予定)
- 国、地方公共団体、都道府県教育委員会:現在2.8% → 3.0%(2026年7月〜予定)
また、従業員43.5人以上の民間企業は法定雇用率適用対象となり、障害者の雇用が義務付けられます。
例えば、正社員30人+パート20人(週30時間以上勤務)など、全従業員が43.5人を超える場合には法定雇用率を達成する必要があります。
国や自治体で雇用率が高く設定されているのは、公的機関が率先して障害者雇用を推進する目的があるためです。
そもそも法定雇用率とは?
法定雇用率の定義と意味
法定雇用率とは、企業や国・自治体が雇用すべき障害者の割合を法律で定めた基準のことです。正式には「障害者雇用促進法」に基づいて定められています。
例えば民間企業では、従業員数に対して一定割合以上の障害者を雇用する義務があり、この割合が法定雇用率です。企業規模が大きくなるほど必要な雇用人数も増えるため、人事部門にとって重要な数値指標の一つと言えます。
なお、障害者雇用促進法では、企業に対して単に雇用するだけではなく、職場環境の整備や合理的配慮を行うことも求められています。
現在の法定雇用率の推移
過去10年間の推移表
ここ10年間で、法定雇用率は段階的に引き上げられてきました。以下の表がその推移です。
| 施行日 | 民間企業 | 国・地方公共団体 |
|---|---|---|
| 2013年4月1日 | 2.0% | 2.3% |
| 2018年4月1日 | 2.2% | 2.5% |
| 2021年3月1日 | 2.3% | 2.6% |
| 2024年4月1日 | 2.5% | 2.8% |
| 2026年7月1日(予定) | 2.7% | 3.0% |
このように法定雇用率は約5年ごとに引き上げられてきたことがわかります。しかし、近年引き上げられるスパンが短くなっており、次回は約2年で0.2%上がることが予想されています。その理由として、日本国内における障害者雇用の問題や関心度が高まっているといえます。
引き上げの背景
法定雇用率が引き上げられる背景には、以下のような理由があります。
- 障害者の就業機会拡大
障害者が働く場を確保し、経済的自立を支援するため。 - 障害者雇用促進法の理念実現
障害の有無に関わらず活躍できる共生社会の実現。 - 社会全体の意識改革
雇用を通じて障害理解を深め、企業文化を変革する狙い。
特に近年では精神障害者の雇用義務化や合理的配慮の法制化など、「雇うだけ」から「活躍してもらう」ことへ制度が進化しているのが特徴です。
今までの障害者雇用の仕事内容は「単純作業」「切り分ける」など比較的簡単な仕事が多かったのですが、ここから先、労働者不足になることは明らかです。『雇うだけから活躍してもらう』という考えが強まっていくため、障害者雇用の方に活躍してもらうためにはどうしたらいいか?ということがテーマになってきます。
なぜ2.7%に引き上げられたのか?
改定の背景と目的
法定雇用率が2.7%に引き上げられる背景には、社会的・法律的な流れがあります。その最大の目的は、障害者の就業機会を広げ、経済的自立を支援することです。
現在でも、障害者の就業率は全国平均と比べると低い状況が続いています。厚生労働省の発表によると、障害者雇用は増加傾向にありますが、まだまだ十分とはいえないため、法定雇用率を段階的に引き上げる政策が進められています。
障害者雇用促進法の改正内容
今回の引き上げは障害者雇用促進法の改正に基づいて行われています。具体的には、以下のようなポイントがあります。
- 法定雇用率の段階的引き上げ
2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%へと引き上げる計画。 - 精神障害者の雇用義務化
2018年から精神障害者も法定雇用率算定対象となり、企業には採用体制整備が求められる。 - 合理的配慮の提供義務
障害者が働きやすい環境を整備するための配慮が法的義務化。
このように、単に雇用数を増やすだけでなく、企業が障害者を雇用しやすくする制度整備も同時に進められています。
国が目指す障害者雇用の現状改善
法定雇用率引き上げの背景には、国が目指す障害者雇用政策の方向性があります。その目標は、障害の有無に関わらず誰もが活躍できる共生社会を実現することです。
例えば、厚生労働省は以下のような課題解決を掲げています。
- 障害者の就業機会不足解消
雇用率を引き上げることで企業の採用数を増やす。 - 精神障害者の雇用促進
近年精神障害者の雇用者数が増加しているものの、依然として雇用割合が低いため。 - 企業内定着支援
採用だけでなく、長く安心して働ける職場づくりを促進。
このように、2.7%への引き上げは単なる数字の変更ではなく、障害者が安心して働ける社会づくりの一歩として位置づけられています。
法定雇用率2.7%引き上げによる企業への影響
企業が抱える課題
法定雇用率が2.7%に引き上げられることで、多くの企業には様々な課題が生じます。特に人事担当者や経営層は、早めに影響を把握して対策を立てる必要があります。
採用難と人材確保
最も大きな課題は採用難です。近年、障害者雇用市場は人材不足傾向にあり、各社が法定雇用率を達成するために採用活動を強化しています。
例えば以下のような課題が発生しています。
- 応募者が少ない
特に地方や特定業種では求人を出しても応募がほとんど来ないケースが多い。 - ミスマッチが起きやすい
障害特性や希望業務と、企業側が求める業務内容が合わない。 - 採用コストの増加
外部支援サービス利用や募集媒体の出稿費用がかさむ。
このため、今後は求人手法の多様化や、業務内容を見直して障害者が活躍できるポジションを増やす工夫が求められます。
納付金制度との関係
法定雇用率の達成状況は障害者雇用納付金制度と密接に関係しています。この制度は、一定規模以上の企業で雇用率を達成できない場合に納付金を支払う仕組みです。
未達成の場合の負担増
法定雇用率が2.7%に引き上げられると、達成基準も上がるため、未達成企業の負担はさらに大きくなります。
例えば、従業員100人規模の企業が1人不足している場合、現在は月額5万円(年間60万円)の納付金を支払う必要があります。法定雇用率が上がり不足人数が増えれば、納付金総額も増えるため、経営への影響は決して小さくありません。
1名で年間60万円の納付金になるため10名だと年間600万円、100名だと年間6000万円の納付金が必要になってくるために企業にとっては、障害者雇用できないと負担が大きくなるといえます。
逆に、法定雇用率を上回って障害者を雇用している企業には調整金や報奨金が支給されるため、早めに採用計画を進めることが重要です。
業種別の影響度
小規模事業所への影響
法定雇用率2.7%への引き上げは、小規模事業所にも大きな影響を与えます。特に、従業員数が43.5人以上の事業所は法定雇用率の適用対象となるため注意が必要です。
例えば従業員が50人の企業では、2.5%の場合1.25人(切り上げ2人)、2.7%になると1.35人(切り上げ2人)で、雇用義務人数自体は変わらない場合がありますが、今後従業員数が増加した際には不足する可能性があります。
また、小規模事業所では
- 障害者雇用に適した業務が少ない
- 専任担当者がいないため対応が後回しになりやすい
- 納付金支払いの負担が経営に直結しやすい
という課題があり、引き上げを機に早めの体制整備や業務切り出しの検討が求められます。
大企業・上場企業への影響
一方で大企業や上場企業にとっても今回の法定雇用率引き上げは無視できない問題です。
特に以下のような影響があります。
- 必要雇用人数の増加
従業員数が数千人規模になると、2.7%への引き上げで必要人数が10人単位で増加することもある。 - 採用競争の激化
障害者雇用市場での人材獲得競争がさらに厳しくなる。 - CSR(企業の社会的責任)や評価への影響
未達成の場合、株主や取引先からの評価低下につながるリスクがある。
特に上場企業では障害者雇用率の達成状況がCSRレポートや統合報告書で公開されるため、採用戦略と職域開発を同時に進める必要があります。
また、納付金支払い総額が数百万円〜数千万円規模になることも珍しくなく、経営上の重要課題として位置付ける企業が増えています。
企業が取るべき対応策
社内体制の見直し
法定雇用率2.7%への引き上げに備えるためには、まず社内体制の見直しが重要です。具体的には以下のようなポイントが挙げられます。
- 障害者雇用担当者の明確化
人事部門内で障害者採用・定着支援を担当するメンバーを決める。 - 受け入れ部署の理解促進
配属先の上司や同僚へ、障害特性や配慮事項に関する研修を実施する。 - 業務切り出しの検討
障害者が活躍できる業務内容を明確化し、雇用創出につなげる。
特に業務切り出しは、これまで障害者採用が進まなかった企業にとって最初のハードルとなるため、社内業務フローを細かく見直すことが重要です。
採用チャネルの拡大
人材不足が続く障害者雇用市場では、採用チャネルの拡大が成功のカギとなります。ハローワークだけに頼るのではなく、複数のチャネルを活用することで採用確率を高められます。
ハローワーク以外の採用方法
具体的には以下のような採用方法があります。
- 障害者雇用専門の人材紹介会社
求職者の障害特性や希望条件を把握した上で紹介してくれるため、マッチング率が高い。 - 障害者就労支援事業所との連携
就労移行支援事業所や就労継続支援事業所からの紹介で、職業訓練を受けた人材を採用できる。 - 自社採用サイトでの募集
障害者雇用枠での募集ページを設置し、応募しやすい環境を整備する。 - 合同面接会・就職イベント
地域の障害者就職面接会や合同説明会への出展。
これらのチャネルを組み合わせることで、安定した採用活動が可能になります。
障害者雇用支援サービスの活用
自社だけで採用から定着支援まで行うのが難しい場合は、障害者雇用支援サービスの活用も検討しましょう。例えば、
- 障害者雇用コンサルティング
法定雇用率対応から職域開発、合理的配慮整備までを総合的に支援。 - 特例子会社設立支援
大企業が特例子会社を設立して雇用率を達成するモデル構築。 - アウトソーシング型雇用支援
障害者雇用に適した業務を外部施設に委託するスキーム。
これらのサービスを活用することで、採用リスクや運営負担を軽減しつつ、法定雇用率の達成と障害者の安定就労を同時に実現できます。
また引き上げになるタイミングでどうしようと考えても遅い可能性があります。ある程度余裕をもって今のうちから採用計画などを練るのが良いでしょう。
障害者雇用に役立つ助成金・支援制度
障害者雇用を進める際には、国や自治体の助成金・補助金を活用することで、採用コストや定着支援費用の負担を軽減できます。ここでは特に活用される制度を紹介します。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、障害者など就職が困難な人をハローワーク経由で雇用した場合に受給できる助成金です。
【ポイント】
- 支給額(例):重度障害者・45歳以上の障害者を常用雇用した場合、
中小企業で1人当たり120万円(半年ごと60万円×2回) - 対象:ハローワーク等の紹介で、継続雇用を前提に採用した場合
特定求職者雇用開発助成金は比較的受給ハードルが低く、障害者雇用の初期費用補填として多くの企業が利用しています。
障害者トライアル雇用奨励金
障害者トライアル雇用奨励金は、障害者を一定期間試行雇用した場合に支給される制度です。
【ポイント】
- 支給額:対象者1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
- 目的:採用前に就業適性や業務マッチングを確認できる
採用後すぐに長期雇用するのが不安な場合、トライアル雇用を活用することで、企業・本人双方にとってミスマッチを防ぐことができます。
その他活用できる補助金
その他にも障害者雇用を支援する補助金・助成金は多数あります。
- 障害者職場定着支援助成金
雇用した障害者が職場定着できるよう支援計画を実施した場合に支給。 - 障害者雇用安定助成金
職場適応援助者(ジョブコーチ)の配置や作業施設の改善費用を助成。 - 障害者作業施設設置等助成金
障害者が働きやすいように職場環境を整備する場合の設備投資費用を助成。
これらの助成金を組み合わせることで、採用から定着までの費用負担を大きく軽減できます。最新情報は厚生労働省や地域の労働局ホームページで必ず確認しましょう。
また、補助金などの専門的な話は理解するのが難しいので、障害者雇用のプロに依頼をするのも1つの手法です。障害者雇用のコンサルティングを行っている会社では、業務の切り出し、採用サポート、働き始めてからのサポートなど幅広く対応してくれます。
そういったサービスをうまく利用すると比較的スムーズに進められるでしょう。
法定雇用率未達成企業への罰則やペナルティ
法定雇用率を達成できなかった場合、企業には罰則やペナルティが課される仕組みがあります。ここでは、特に重要な「納付金制度」と「企業名公表制度」について解説します。
納付金制度の詳細
障害者雇用納付金制度とは、法定雇用率を未達成の企業に対して納付金の支払いを義務付ける制度です。
【ポイント】
- 対象企業:常用労働者数が100人超の民間企業
- 納付金額:不足1人につき月額50,000円(年間60万円)
- 納付時期:毎年度の障害者雇用状況報告に基づき算定
例えば、従業員200人の企業で障害者雇用が3人不足している場合、年間で180万円(60万円×3人)の納付金負担が発生します。
一方で、法定雇用率を上回って雇用している企業には調整金(雇用調整金)や報奨金が支給される仕組みもあり、積極的に雇用する企業へのインセンティブとなっています。
企業名公表制度について
企業名公表制度とは、法定雇用率を著しく達成していない企業に対し、厚生労働省が企業名を公表する制度です。
【ポイント】
- 公表対象:雇用率未達成が続き、行政指導にも従わない企業
- 影響:企業イメージの低下、採用活動や取引への悪影響
実際に企業名が公表された場合、社会的信用失墜や採用ブランド低下など、大きなダメージを受ける可能性があります。こうしたリスクを避けるためにも、早めに法定雇用率を達成するための計画を立て、継続的に実行していくことが重要です。
また、ここまで法定雇用率の%が上がるとどこかのタイミングで「法定雇用率の提示」が義務付けられる可能性も高まってきます。まだ先の話かもしれませんが、十二分に可能性があるため、罰則の納付金だけ払ってればよいという考えは持たない方がいいでしょう。
仮に法定雇用率の提示が義務付けられたら、採用活動へのダメージも大きくなるため、対策は今のタイミングからスタートしておくべきといえます。
今後の法定雇用率の見通し
更なる引き上げの可能性
法定雇用率はここ10年で段階的に引き上げられており、2026年7月には民間企業で2.7%、国・自治体で3.0%となる予定です。
厚生労働省は今後も「障害者の就業機会確保」「精神障害者の雇用促進」「合理的配慮の徹底」を政策目標として掲げており、将来的にさらに引き上げられる可能性があります。
例えば欧米諸国では、雇用率制度ではなく障害者の雇用義務を課さずとも一定数雇用されている国もありますが、日本では制度的支援と義務化を両輪で進める傾向にあり、今後も段階的引き上げが続くと予想されます。
企業としての長期的対応策
法定雇用率の更なる引き上げに備え、企業は短期的な採用対策だけでなく、長期的な障害者雇用戦略を構築する必要があります。
具体的には以下のような取り組みが求められます。
- 職域開発
障害者が活躍できる業務を新たに創出し、社内定着率を高める。 - 合理的配慮と環境整備
バリアフリー化、ICTツール活用、勤務時間柔軟化など、働きやすい職場環境を整備する。 - パートナー企業・支援機関との連携
就労移行支援事業所、特例子会社、障害者雇用支援サービスを活用し採用チャネルを拡大。 - 障害者雇用に関する社内教育
管理職・現場社員への研修を通じ、障害理解と共生意識を浸透させる。
これらを継続することで、単なる「法定雇用率達成」ではなく、障害者が戦力として活躍できる企業づくりが可能になります。今後の社会情勢や法改正を見据え、早めに対応策を検討していくことが重要です。
よくある質問(FAQ)
法定雇用率は今後も上がるの?
はい。ここ10年で段階的に引き上げられており、2026年には2.7%になります。将来的にも障害者雇用促進のため、さらなる引き上げが検討される可能性があります。
達成できない場合の納付金額は?
常用労働者100人超の企業で、法定雇用率を未達成の場合、不足1人につき月額5万円(年間60万円)の納付金を支払う必要があります。
何人雇えば2.7%になる?
従業員数 × 2.7% で計算します。例えば従業員200人の場合、200×0.027=5.4人。切り上げで6人の雇用が必要です。
精神障害者は法定雇用率にカウントできる?
はい。2018年から精神障害者も法定雇用率の算定対象となりました。診断書や障害者手帳の確認が必要です。
パートや契約社員もカウントできる?
週30時間以上勤務の場合、常用労働者として1人カウントされます。週20時間以上30時間未満は0.5人としてカウント可能です。
短時間勤務者のカウント方法は?
週20時間以上30時間未満の障害者は0.5人、週30時間以上勤務であれば1人としてカウントします。
障害者雇用枠で採用する際の注意点は?
障害特性や配慮事項を正確に把握すること、業務内容とマッチするか確認することが重要です。また職場環境や受け入れ体制も整備しましょう。
障害者雇用支援サービスの選び方は?
実績や専門性、サポート範囲(採用〜定着支援)、料金体系を確認し、自社の課題に合うサービスを選ぶことが大切です。
雇用率達成企業へのインセンティブは?
法定雇用率を上回って障害者を雇用している場合、調整金(1人あたり月額27,000円)や報奨金(年間50,000円)を受け取れることがあります。
納付金免除や減額の条件はある?
納付金は原則として免除されませんが、特例子会社を活用した場合や、一定条件で減額が認められるケースもあります。詳細は労働局へ確認しましょう。
法定雇用率の算定方法は?
常用労働者数(週30時間以上勤務者+短時間勤務者×0.5)の合計に法定雇用率を掛け算し、切り上げた人数が必要雇用数となります。
企業規模による対象人数の違いは?
従業員43.5人以上の企業は法定雇用率適用対象となります。従業員規模が大きくなるほど、必要雇用人数も増加します。
合理的配慮とは何?
障害者が働く上で不利にならないよう、業務内容の調整、設備改修、柔軟な勤務時間設定などを行うことを指します。提供は法律上の義務です。
雇用率未達成で行政指導を受けたら?
まずは指導内容を確認し、改善計画を作成・提出する必要があります。改善が見られない場合、企業名公表などのペナルティが課されることもあります。
障害者雇用で活用できる外部サービスは?
就労移行支援事業所、特例子会社、障害者雇用専門の人材紹介会社、アウトソーシング型雇用支援サービスなどがあります。
まとめ|法定雇用率2.7%を正しく理解し、早めの対応を
2026年7月から法定雇用率は2.7%に引き上げられる予定です。これにより、全ての企業は障害者雇用に対してより一層の取り組みが求められます。
企業が今すぐ取り組むべきこと
今後の法定雇用率引き上げに備え、企業が今すぐ取り組むべきことは以下の通りです。
- 自社の法定雇用率達成状況の確認
- 障害者雇用計画の見直し
- 受け入れ体制や職域開発の検討
- 助成金・支援制度の活用準備
- 採用チャネル拡大や外部サービス活用
特に、採用活動と同時に社内理解と合理的配慮の整備を進めることが、障害者が定着・活躍できる職場づくりにつながります。
専門家への相談も視野に
障害者雇用には、法改正や助成金、合理的配慮など専門的知識が必要な分野が多くあります。対応に不安がある場合は、社会保険労務士や障害者雇用コンサルタントなど専門家への相談も視野に入れましょう。
早めの準備が、企業のリスク回避だけでなく、障害者が安心して働ける環境づくりと社会的評価向上につながります。ぜひ今回の記事を参考に、法定雇用率2.7%への対応を進めてみてください。