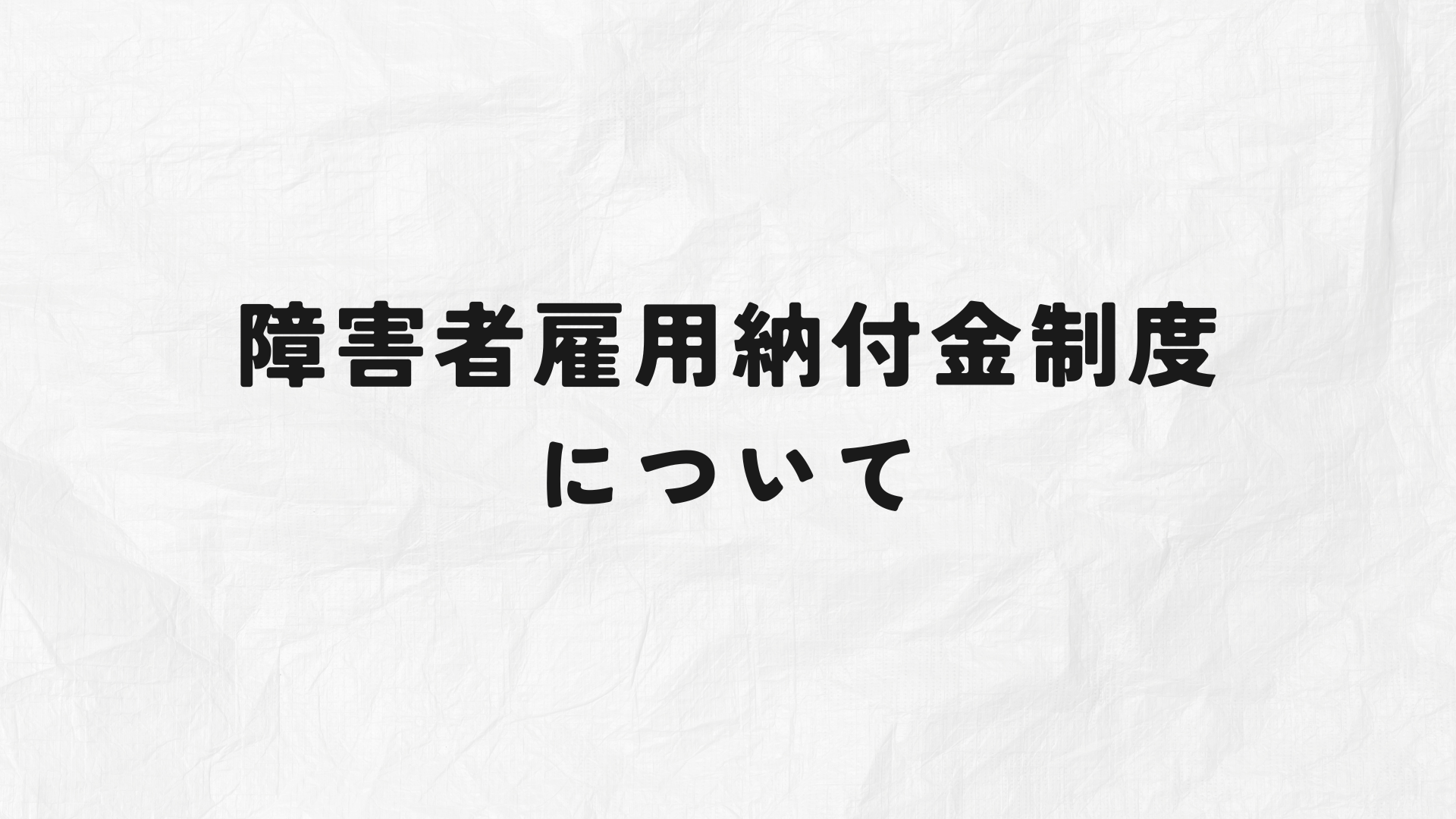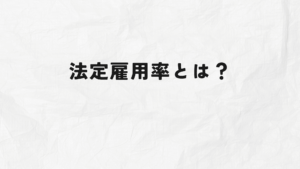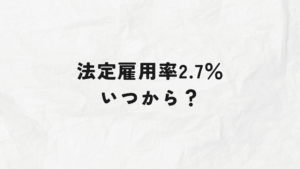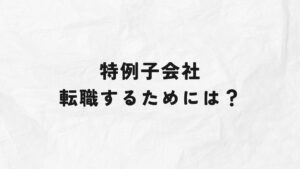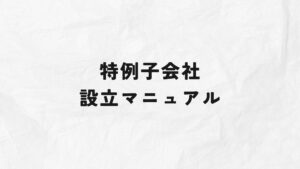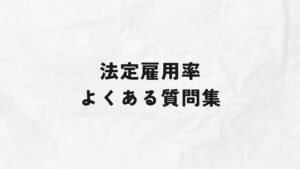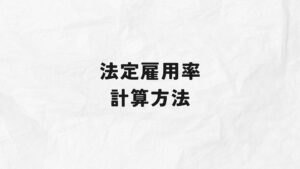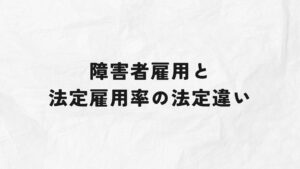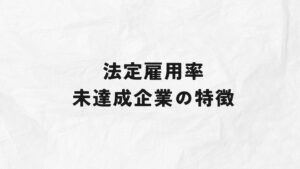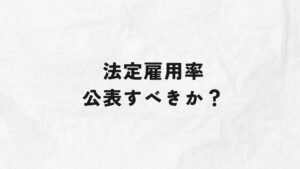障害者雇用納付金制度とは?
障害者雇用納付金制度の定義
障害者雇用納付金制度とは、一定規模以上の企業に対して、障害者の雇用人数が法定雇用率に達していない場合に納付金を徴収する制度です。これは、障害者を雇用している企業と雇用していない企業の間で経済的負担を調整し、障害者雇用を社会全体で支える仕組みになっています。
簡単にいうと、「障害者を雇わない場合、その分の納付金を払う」という制度です。逆に、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業には調整金や報奨金が支給されることもあります。
制度の目的と背景
この制度ができた背景には、「障害者の雇用機会を増やす」という国の目的があります。
障害者は、働きたいと思っても一般企業での雇用が進まない現状がありました。そこで、法律(障害者雇用促進法)に基づき、企業の社会的責任として雇用を促進するために納付金制度が設けられたのです。
納付金を徴収することで、障害者を雇用しない企業にも一定の負担を求め、そのお金を活用して障害者雇用に積極的な企業を支援する仕組みになっています。
障害者雇用率制度との違い
障害者雇用率制度と納付金制度はセットで語られることが多いですが、役割が異なります。
- 障害者雇用率制度:企業が雇用すべき障害者の割合(法定雇用率)を定めたもの
- 障害者雇用納付金制度:法定雇用率を達成できなかった場合にお金を納める仕組み
つまり、雇用率制度は「雇ってください」というルール、納付金制度は「雇わなかった場合にお金を納めてください」という経済的ルールと言えます。
この二つの制度により、企業は障害者雇用を進めるインセンティブを持ち、社会全体で障害者の雇用機会を確保できるようになっています。
どんな企業が対象になるの?
対象企業の規模
障害者雇用納付金制度の対象となるのは、常用労働者が100人を超える企業です。
「常用労働者」とは、パートやアルバイトも含め、1週間の所定労働時間が短い場合でも一定の計算方法で換算されます。
例えば、週20時間以上働くパートさんは0.5人としてカウントされるため、パート・アルバイトが多い事業所でも対象企業になる可能性があります。
なお、中小企業(100人以下)は納付金が免除されていますが、法定雇用率の適用は50人以上の企業から義務付けられているため注意が必要です。
業種ごとの注意点
基本的には業種を問わず、従業員数で対象が決まりますが、一部の業種では特例措置が認められています。
例えば、建設業や警備業など、就労環境的に障害者雇用が難しいと判断される場合、一定の軽減措置が適用されることがあります。
また、「特例子会社制度」を活用すると、親会社の障害者雇用率算定に含められるため、グループ全体で雇用率をクリアしやすくなるという仕組みもあります。
法定雇用率未達成の場合の影響
法定雇用率を達成できなかった場合、対象企業は不足1人につき月額5万円(年間60万円)の納付金を支払う必要があります。
例えば、法定雇用人数が3人の企業で1人しか雇用していない場合、不足2人 × 5万円 × 12ヶ月 = 年間120万円の納付金が発生します。
さらに、雇用率未達成が続くと、厚生労働省からの指導・勧告や企業名公表といった措置を受ける可能性もあります。このため、納付金を単なる「罰金」と捉えるのではなく、企業の社会的責任として障害者雇用を進めるきっかけにすることが大切です。
納付金の計算方法
納付金額はいくら?
障害者雇用納付金は、不足している障害者1人あたり月額5万円と定められています。
つまり、年間では60万円の納付金が発生します。
なお、この納付金額は企業規模や法改正により変動する可能性があるため、最新情報は厚生労働省や高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式発表で確認しましょう。
具体的な計算例
例えば、常用労働者が200人の企業で、法定雇用率2.5%の場合、雇用義務人数は5人となります。もし実際の雇用人数が3人だった場合、不足人数は2人です。この場合の納付金額は、
2人 × 5万円 × 12ヶ月 = 年間120万円
となります。1人60万ですから10人だと年間600万など不足人数が多いほど納付金総額も増えるため、経営上の負担が大きくなる点に注意が必要です。
減額・免除の条件
障害者雇用納付金には、一定条件で減額や免除される制度があります。
例えば、災害などで事業経営が著しく困難になった場合や、経済的理由で納付が難しい場合には、納付金減免申請を行うことができます。
ただし、減免が認められるには詳細な書類提出と審査が必要であり、免除は簡単には認められないため、早めに管轄の労働局や社会保険労務士などの専門家へ相談することが重要です。
納付金の徴収と支払い方法
納付時期
障害者雇用納付金は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況に基づいて計算されます。
企業は、毎年6月末までに障害者雇用状況報告書を提出し、報告内容をもとに高齢・障害・求職者雇用支援機構から納付金の納付通知が送付されます。
納付通知は、通常7月から9月頃に届き、通知書に記載されている期限までに支払う必要があります。
納付方法
納付金は、納付通知書に記載された金額を指定口座へ銀行振込で納付します。
振込先は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の指定口座となっており、振込手数料は企業負担です。
支払いを忘れないよう、納付期限を確認し、経理部門や財務担当者と共有しておきましょう。
未納付の場合の罰則
もし納付金を期限までに納めない場合は、延滞金が加算されることになります。
さらに、障害者雇用率未達成が長期化し、行政からの指導や勧告にも従わない場合は、企業名が公表される可能性があります。
企業名公表は社会的信用に大きな影響を与えるため、納付金だけでなく障害者雇用率の達成も含め、法令遵守を徹底することが重要です。
調整金・報奨金制度とは?
調整金の仕組み
調整金とは、障害者を法定雇用率以上に雇用している企業に対して支給されるお金です。
具体的には、常用労働者100人以上の企業が、法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合、超過1人あたり月額27,000円が支給されます(令和6年度時点)。
例えば、法定雇用人数より2人多く障害者を雇用している場合、
2人 × 27,000円 × 12ヶ月 = 年間約64万円
が調整金として支給されます。
これは、障害者雇用を積極的に進める企業へのインセンティブとして設けられています。
報奨金の仕組み
報奨金は、主に中小企業(常用労働者100人以下)が対象です。
中小企業が法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合、超過人数に応じて年額21,000円が支給されます。
調整金と比べ金額は少ないですが、障害者雇用を行う中小企業への支援策として重要な制度です。
なお、調整金と報奨金は重複して受給することはできず、企業規模に応じてどちらかが適用されます。
納付金との関係性
障害者雇用納付金制度は、納付金・調整金・報奨金が一体となって運用されています。
不足している企業から納付金を徴収し、その資金を超過雇用している企業に調整金や報奨金として分配することで、障害者雇用の経済的負担を社会全体で分担する仕組みです。
つまり、納付金は「罰金」ではなく、調整金・報奨金と合わせて障害者雇用を支える財源として位置づけられています。
障害者雇用納付金制度のメリット・デメリット
企業側のメリット
障害者雇用納付金制度には、企業側にとって以下のようなメリットがあります。
- 障害者雇用を推進するインセンティブになる
- 障害者を雇用することで、調整金や報奨金を受け取れる可能性がある
- 企業の社会的信用やブランドイメージ向上につながる
- 障害者雇用を通じて、社内のダイバーシティ推進が進む
特に、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業は調整金や報奨金を受け取れるため、経済的にもプラスになります。
デメリットと負担感
一方で、障害者雇用納付金制度には以下のようなデメリットや負担感があります。
- 法定雇用率を達成できない場合、納付金の負担が大きい
- 雇用人数が多いほど納付金額も増え、経営コストとして無視できない
- 障害者雇用を進めるための社内体制整備や業務調整が必要
- 職域開発や職場環境改善に時間とコストがかかる
特に、障害者雇用経験の少ない企業にとっては、受け入れ体制を整えるまでの初期負担感が大きいという声もあります。
制度を上手に活用するコツ
障害者雇用納付金制度を上手に活用するためには、以下のポイントが重要です。
- 自社の雇用義務人数を正確に把握する
- 納付金を支払うよりも、障害者を雇用するメリットを検討する
- 特例子会社設立など、グループ全体で雇用率達成を目指す
- 外部コンサルタントや社会保険労務士の支援を活用する
納付金を「罰金」と捉えるのではなく、障害者雇用を推進するきっかけとして考えることが、企業にとっても社会にとってもプラスになります。
実際の企業事例
納付金を支払っている企業例
A社(従業員数約300人)は、これまで障害者雇用を積極的に進めていませんでした。
その結果、法定雇用率未達成により、年間で180万円の納付金を支払っています。
経営陣からは「納付金が固定費としてかかるくらいなら、雇用して社内に貢献してもらいたい」という声が上がり、現在は雇用計画を策定中です。
納付金を回避するために行っている取り組み例
B社(従業員数約120人)は、納付金発生を避けるため、障害者の職域開発を行いました。
具体的には、オフィス内の清掃、書類のスキャン・ファイリング業務、備品管理などを切り出し、障害者が無理なくできる業務内容を整備しました。
その結果、納付金が発生しないだけでなく、従業員全体の業務効率化にもつながり、社内からは好評です。
障害者雇用推進の成功事例
C社(従業員数約500人)は、特例子会社を設立し、障害者雇用をグループ全体で進めています。
特例子会社では、軽作業やデータ入力、事務補助業務などを中心に配置し、障害者本人の適性に合わせた育成プログラムも導入。
結果として、法定雇用率を大幅に上回るだけでなく、調整金の受給も得られ、障害者雇用が企業ブランド向上の一助となっています。
よくある質問(FAQ)
Q. 障害者雇用納付金制度とは何ですか?
障害者を法定雇用率以上に雇用していない企業が納めるお金で、雇用促進のために使われる制度です。
Q. 障害者雇用率とは何ですか?
企業が雇用すべき障害者の割合を示した基準で、法令で定められています。
Q. どんな企業が納付金の対象ですか?
常用労働者が100人を超える企業が対象です。
Q. パートやアルバイトも対象人数に含まれますか?
はい。週20時間以上勤務する場合は0.5人など、換算して含まれます。
Q. 障害者を1人も雇っていない場合、どうなりますか?
雇用義務人数分×5万円×12ヶ月の納付金を支払う必要があります。
Q. 納付金は経費として計上できますか?
はい、損金算入が可能です。
Q. 障害者を雇った場合でも納付金が発生することはありますか?
はい。法定雇用率に満たない場合は不足人数分の納付金が必要です。
Q. 調整金と報奨金の違いは何ですか?
調整金は100人以上の企業、報奨金は100人以下の企業が対象です。
Q. 納付金を支払わないとどうなりますか?
延滞金が加算され、最終的には企業名公表などの罰則を受ける可能性があります。
Q. 特例子会社とは何ですか?
障害者雇用を目的とした子会社で、親会社の雇用率算定に含めることができます。
Q. 障害者手帳がない場合、カウントできますか?
原則として、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持が必要です。
Q. 精神障害者は雇用率計算でどう扱われますか?
平成30年から法定雇用率の対象に正式追加されています。
Q. 障害者雇用納付金は毎年変わりますか?
納付金額は法改正により変動する可能性があります。
Q. 障害者雇用の助成金制度はありますか?
はい。特定求職者雇用開発助成金や職場適応援助(ジョブコーチ)など複数あります。
Q. 法定雇用率が変わった場合、いつから適用されますか?
法改正によって適用開始時期が告知されるため、厚生労働省の最新情報を確認してください。
Q. 納付金を減額・免除してもらうにはどうしたらいいですか?
災害や経営悪化など正当な理由がある場合、労働局へ減免申請が可能です。
Q. 障害者雇用納付金と調整金を同時に受けることはできますか?
いいえ。不足している場合は納付金、超過している場合は調整金を受け取る仕組みで、同時には適用されません。
Q. 障害者雇用率の計算に派遣社員は含まれますか?
原則として派遣元が雇用率計算対象になりますが、一定条件で派遣先計上も可能です。
Q. 短時間労働の障害者はどのように計算されますか?
週20~30時間未満の場合は0.5人、30時間以上は1人としてカウントされます。
障害者雇用納付金制度と今後の法改正動向
直近の改正ポイント
障害者雇用納付金制度は、障害者雇用率の引き上げや制度運用の見直しに伴い、定期的に改正されています。
2024年度からは、法定雇用率が2.5%へ引き上げられ、2026年度には2.7%になる予定です。
これにより、企業の障害者雇用義務人数が増加するため、納付金の負担額が増える可能性があります。
今後予想される変更点
今後は以下のような変更が予想されています。
- 法定雇用率のさらなる引き上げ
- 精神障害者雇用の拡大に伴う助成制度の見直し
- 特例子会社制度の柔軟化や支援強化
- 納付金・調整金・報奨金額の改定
特に、労働人口減少の中で障害者雇用が重要政策と位置づけられているため、雇用義務の強化が続くと考えられます。
企業が準備しておくべきこと
企業としては、今後の改正に備えて以下のポイントを準備することが重要です。
- 自社の障害者雇用状況を正確に把握する
- 障害者雇用の受け入れ体制や業務内容を見直す
- 特例子会社設立や外部支援機関活用の可能性を検討する
- 最新の法改正情報を定期的に確認し、社内で共有する
特に、障害者雇用を進めることは単なる法令遵守にとどまらず、企業価値向上や社内ダイバーシティ推進にも直結します。
法改正を「負担」と考えるのではなく、経営戦略の一環として捉えることが今後ますます求められるでしょう。
他サイトにはない差別化ポイント
専門家からのアドバイス
障害者雇用納付金制度は法令で決まっているため、表面的な解説はどのサイトでもほぼ同じ内容になります。
しかし、実務上重要なのは「どう対応するか」という点です。
社会保険労務士や障害者雇用コンサルタントに取材したところ、「納付金はコストと考えるのではなく、雇用を進めることで社内活性化やダイバーシティ推進に繋がる。最終的には経営面でもプラスになる企業が多い。」
という意見がありました。
障害者雇用コンサルタントの視点
現場で支援しているコンサルタントは、次のような取り組みを推奨しています。
- 業務切り出し:既存社員の負担軽減業務を障害者雇用枠に置き換える
- ジョブコーチ活用:職場適応援助者のサポートで定着率向上
- 社内啓発:従業員向け障害者理解研修を行い受け入れ体制を作る
これらを実施することで、障害者雇用率達成だけでなく、組織全体の効率化や雰囲気改善にも繋がります。
中小企業でもできる具体的取り組み例
「うちは中小企業だから無理…」と思う方もいるかもしれませんが、実際には予算ゼロでも始められる取り組みがあります。
- 障害者就業・生活支援センターに相談し、雇用計画を一緒に作成する
- ハローワークの専門援助部門から人材紹介を受ける
- 清掃や軽作業など、一部業務を分けて職域開発する
これらは、専門家のサポートを受ければ初期費用をかけずに進められるケースが多く、障害者雇用納付金の負担軽減だけでなく、助成金受給にも繋がります。
まとめ|障害者雇用納付金制度を正しく理解して自社に活かそう
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を達成していない企業から納付金を徴収し、障害者を積極的に雇用する企業へ調整金や報奨金として分配する制度です。
制度の目的は、企業間で経済的負担を調整し、障害者雇用を社会全体で支えることにあります。
本記事では、納付金額の計算方法や具体例、減免条件、納付方法、罰則、調整金・報奨金制度、そして企業事例まで詳しく解説しました。
今後の行動ポイント
- 自社の法定雇用率達成状況を確認する
- 納付金が発生している場合、雇用推進と費用比較を行う
- 障害者雇用の受け入れ体制を整えるため、社内で担当者を決める
- 特例子会社や助成金、外部支援の活用を検討する
- 最新の法改正情報を定期的にチェックする
障害者雇用納付金制度は、単なる罰金制度ではなく、障害者雇用を進めるチャンスでもあります。
この制度を正しく理解し、企業価値向上やダイバーシティ推進に役立てていきましょう。