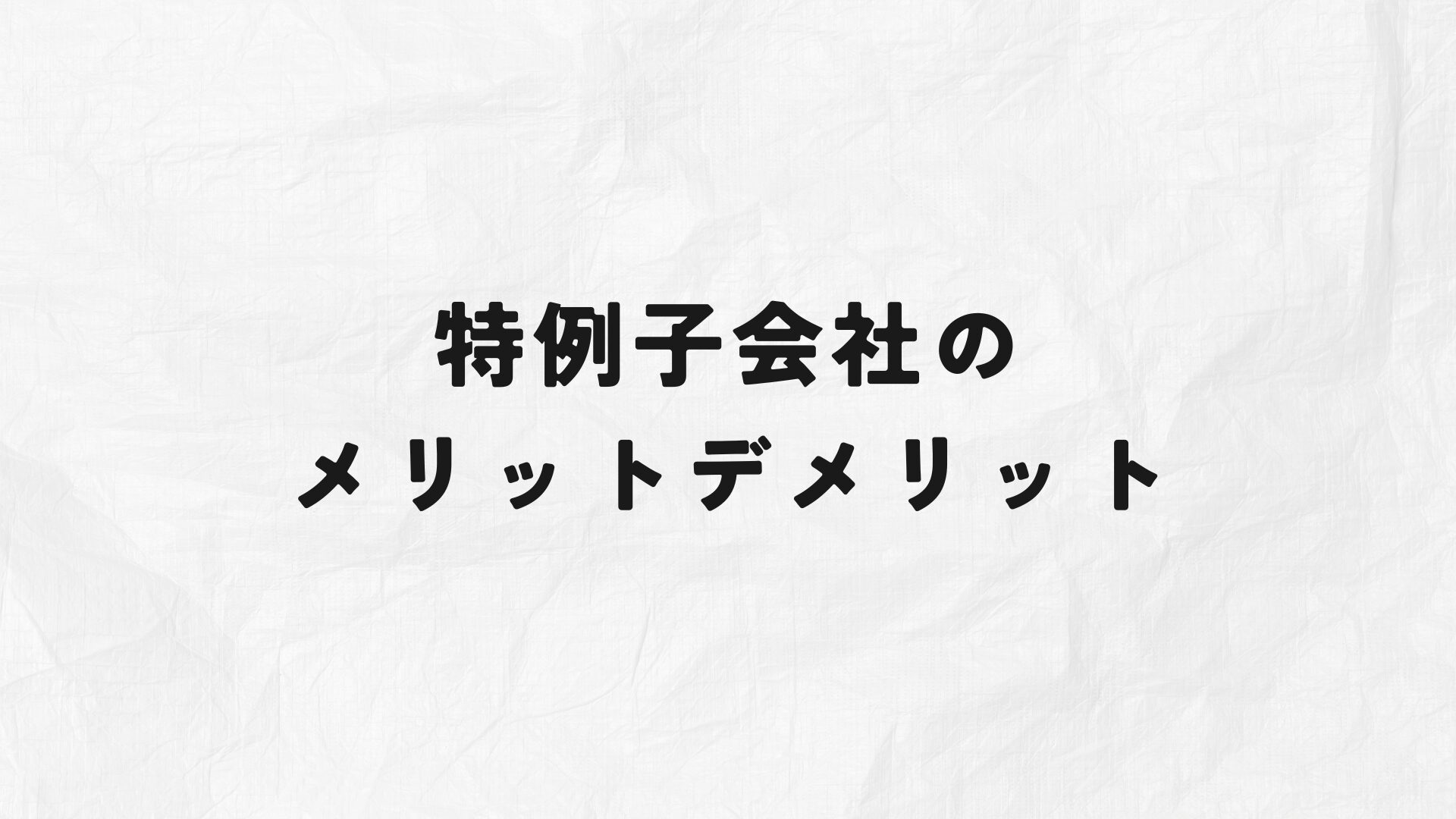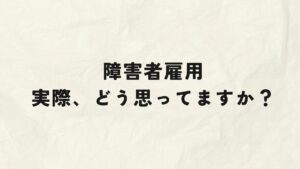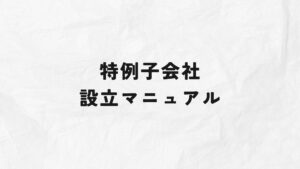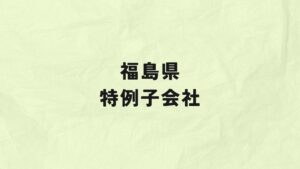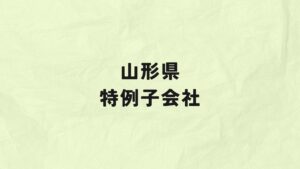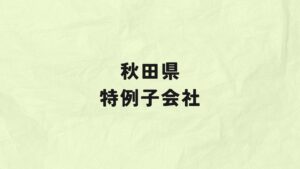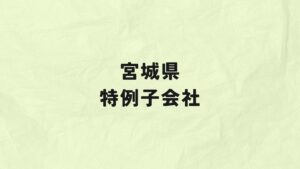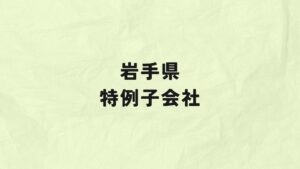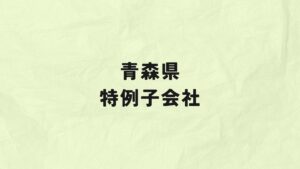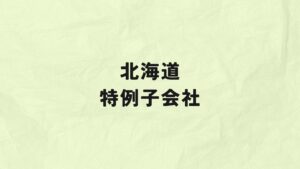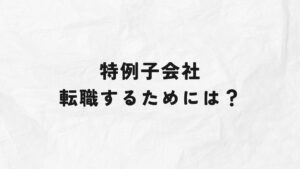「特例子会社(とくれいこがいしゃ)」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、障害のある人が働きやすいように作られた、グループ会社の一つです。親会社のサポートのもと、障害者の雇用に特化した会社として運営されています。
企業が法律で決められた「障害者の雇用人数」を守るために、特例子会社を作ることで、グループ全体で雇用率を達成しやすくなるという仕組みです。
でも、良いことばかりではありません。コストがかかったり、思ったようにうまくいかないこともあります。この記事では、特例子会社のメリットとデメリットをわかりやすく解説し、「自社に合っているのかどうか?」を考える材料をお届けします。
特例子会社とは?基本的な仕組み

特例子会社ってどんな会社?
特例子会社は、障害のある人をたくさん雇うために作られた子会社です。親会社が中心となって設立し、特別なルールに沿って運営されます。
たとえば、大きな会社が障害者を雇うのが難しいと感じたときに、別会社を作って、そこで働きやすい環境を用意するという形です。
この特例子会社で働く障害者は、親会社の「障害者雇用率」にカウントされるというメリットがあります。
この仕組みは、どんな法律に関係してるの?
特例子会社は、「障害者雇用促進法(しょうがいしゃ こよう そくしんほう)」という法律に関係しています。
この法律では、ある程度の人数の会社には「障害者を○%以上雇ってくださいね」というルール(法定雇用率)があります。でも、実際には「自社では雇うのが難しい」「環境が整っていない」という企業も多いのが現実です。
そこで作られたのがこの特例子会社制度です。グループ会社の中で障害者をまとめて雇っても、親会社の雇用人数としてカウントできるという仕組みなのです。
特例子会社になるための条件
どんな会社でも特例子会社になれるわけではありません。いくつかの条件をクリアしないといけません。
- 親会社から50%以上の出資があること(=しっかりつながっている会社)
- 社員の20%以上が障害のある人であること
- 障害のある人が安心して働ける環境があること(たとえばバリアフリーや支援体制)
- しっかりとした支援やサポート体制があること(面談や相談窓口など)
これらの条件を満たしているかどうかをチェックして、都道府県の労働局を通じて国に申請します。認定されると、晴れて「特例子会社」と名乗ることができます。
なぜ、こんな仕組みが作られたの?
昔から、「障害のある人がなかなか仕事を見つけられない」という問題がありました。特に、大きな企業でも「うちの仕事には合わない」「配慮が難しい」といった理由で、雇用が進みにくいケースがあったのです。
でも、だからといって雇わないのではなく、「障害者が働きやすい会社を別に作ろう」という考えで生まれたのが特例子会社です。
これにより、
- 障害のある人が無理なく働ける
- 企業は法律のルール(法定雇用率)を守りやすくなる
- 障害者の働く場が広がる
といった、企業と障害者、どちらにとっても良いことがある仕組みとなっています。
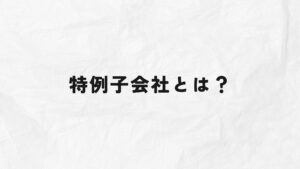
特例子会社制度が生まれた経緯
障害者雇用率制度っていつからあるの?
障害のある人が安心して働ける社会を作るために、日本では「障害者雇用率制度(しょうがいしゃ こようりつ せいど)」というルールが作られました。この制度は1976年(昭和51年)にスタートしました。
「ある程度の人数がいる会社は、決められた割合で障害者を雇いましょうね」という仕組みです。
たとえば、社員が40人以上の会社なら「全体の2.5%は障害者を雇ってくださいね」といったルールです(※数字は時期により変わります)。このルールがあることで、障害のある人がもっと働けるように、という思いが込められています。
なぜ、ふつうの会社だけではうまくいかなかったの?
でも実際には、「雇いたいけど難しい」という会社がたくさんありました。
- 工場やオフィスが障害のある人にとって使いにくい
- サポートできる社員がいない
- スピードや体力が必要な仕事が多くて合わない
- どうやって接したらいいのか分からない
このような理由で、「雇用したくても、どうしたらいいのか分からない」という声が多かったのです。
また、ひとりふたりだけ雇っても、まわりの社員がサポートできず、働く人もつらくなって辞めてしまうこともありました。そこで国は、「障害者が働きやすい会社を別に作って、そこでまとめて雇ってもいいですよ」という仕組みを用意しました。
制度が企業や社会にもたらしたよい変化
この「特例子会社制度」ができたことで、企業や社会にいろいろな良い変化がありました。
- 障害者が安心して長く働ける会社が増えた
- 企業が法律(障害者雇用率)を守りやすくなった
- 雇用された人の「働く喜び」や「自信」が大きくなった
- 障害者雇用の専門スタッフやノウハウが生まれた
また、最近ではSDGs(持続可能な開発目標)やダイバーシティ経営という考え方も広がっていて、「誰もが働きやすい会社をつくろう」という動きが強まっています。
特例子会社は、そうした時代の流れにもぴったり合った制度となっています。
特例子会社を作るメリット
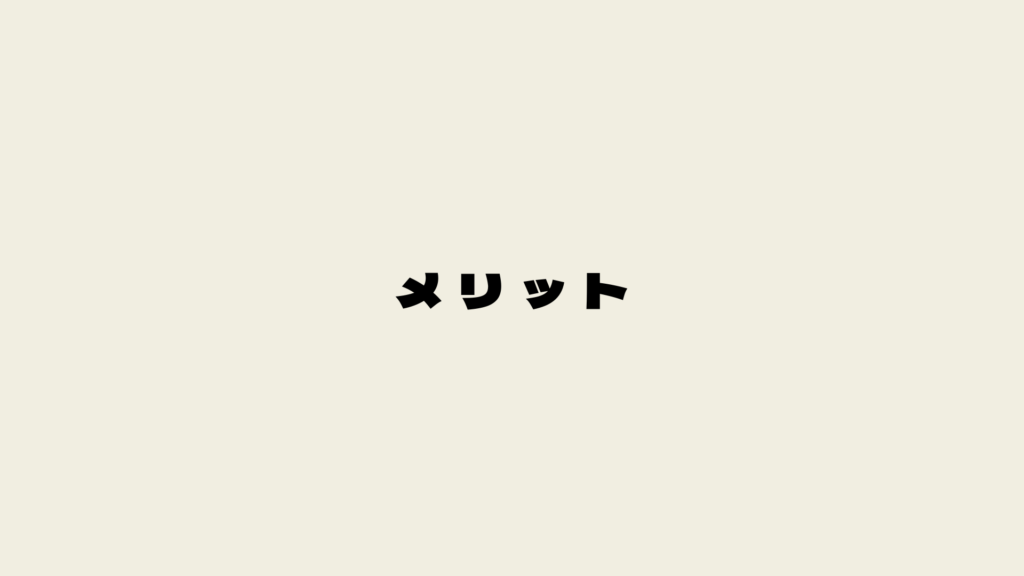
ここでは、企業が特例子会社を作ることでどんな良いこと(=メリット)があるのかを紹介します。
1. 障害者雇用率をクリアしやすくなる
日本では「障害者雇用促進法」という法律により、企業には一定の割合で障害のある人を雇うことが義務づけられています。
この割合のことを「法定雇用率(ほうていこようりつ)」といいます。たとえば、現在の法定雇用率は2.5%(令和7年4月からは2.7%)とされており、従業員が40人以上の会社は、少なくとも1人以上の障害者を雇う必要があります。
しかし、実際には「どんな仕事をお願いしたらいいか分からない」「配慮が難しい」などの理由で、法定雇用率を達成できない企業もたくさんあります。
そこで役立つのが「特例子会社」という選択肢です。
特例子会社で雇った障害のある人は、親会社の雇用人数としてカウントされるため、グループ全体で雇用率を達成しやすくなります。
たとえば、親会社A社が100人の社員を持っていて、障害者を2.5人(2.5%)雇わないといけないとします。でもA社では対応が難しい。
そこでA社は特例子会社B社を作り、障害のある人を3人雇いました。この場合、A社の雇用率にその3人がそのまま加算されるため、法定雇用率をクリアできるのです。
| 会社 | 社員数 | 障害者雇用人数 | 雇用率クリア? |
|---|---|---|---|
| 親会社A社(特例子会社なし) | 100人 | 0人 | ❌ |
| 親会社A社+特例子会社B社(3人雇用) | 100人 | 3人(カウント可能) | ✅ |
このように、特例子会社を活用することで、
- 自社だけでは難しかった障害者雇用を実現しやすくなる
- グループ全体で「まとめて」雇用率をクリアできる
- 国の調査や監査にもきちんと対応できる
という大きなメリットがあります。
特に、複数のグループ会社を持つ大企業にとっては、効率よく法律を守るための有力な手段として多く活用されています。
2. 障害のある人が働きやすい環境を作りやすい
特例子会社は、もともと障害のある人が働くことを前提に作られる会社です。そのため、働く人に合わせた職場環境の工夫がしやすくなっています。
- 車いすでも通れるように通路を広くする
- まぶしすぎない照明にする
- 話し声が気にならないように仕切りをつける
- 疲れたら休める「静養室」をつくる
また、知的障害や精神障害のある方にとっては、落ち着いた空気の中で、ゆっくり丁寧に仕事ができる環境がとても大切です。
一般の職場ではなかなか実現しにくいことも、特例子会社なら最初から働きやすい職場を作れるので、結果的に定着率も高くなる傾向があります。
3. 専門的なサポート体制が作れる
特例子会社では、障害者雇用に詳しいスタッフを配置したり、外部の支援機関と連携したりして、働く人をサポートする体制を整えやすくなります。
- 職場定着をサポートする「ジョブコーチ」の配置
- 困ったときに話を聞いてくれる「相談窓口」
- 週1回の「個別面談」や、本人と家族との「三者面談」
こうした支援があることで、「職場で孤立しない」「困ってもすぐ相談できる」環境が整い、安心して長く働けるようになります。
一般の職場だとサポートの手が足りなかったり、忙しくて対応できないこともありますが、特例子会社は“支援ありき”で作られているため、しっかりフォローができるのが強みです。
4. 会社のイメージアップや社会貢献につながる
特例子会社を作って障害のある人を雇っている企業は、「社会に貢献している会社」として良いイメージを持たれやすくなります。
- ニュース番組や新聞で取り上げられる
- 採用ページに障害者雇用の取り組みを載せる
- 投資家や取引先から高い評価を受ける
といった形で、障害者雇用が企業ブランディングに役立つようになってきています。
また、SDGs(持続可能な開発目標)の流れの中でも、「すべての人に働く機会を」という目標に取り組んでいる姿勢は、企業価値を高める要素になります。
つまり、特例子会社を作ることはビジネスの成長にもつながる社会貢献になるのです。
5. 親会社とは違う仕事ができる
特例子会社は、親会社と同じ仕事をしなくてもOKです。むしろ、障害のある人が自分のペースで取り組める、シンプルな仕事を中心にするほうがうまくいくことが多いです。
- 名刺や書類の印刷、封入
- 社内の郵便物の仕分け・配送
- おしぼり・タオルのクリーニング
- 観葉植物の水やり・手入れ
- パソコンを使ったデータ入力やラベル作成
このような「特例子会社向けの仕事」を用意することで、誰かに無理をさせることなく、自然な雇用をつくることができます。また、本社ではできない軽作業や手作業を分担してもらうことで、業務全体の効率が上がるというメリットもあります。
6. 国の助成金が使えることがある
特例子会社を作る際には、国や自治体から「助成金」を受けられることがあります。次のような費用に対してサポートが出ることがあります:
- 建物のバリアフリー工事
- 作業に使う道具や機械の購入費
- 職場支援員(サポートスタッフ)の人件費
- 職場実習やトライアル雇用にかかる経費
また、障害者を雇った人数に応じて、1人あたりいくら、という形で給付される助成金もあります。助成金をうまく活用することで、会社の負担を減らしながら、より良い職場づくりができるのも大きな魅力です。
ただし、助成金には条件や申請期限があるので、事前にハローワークや専門機関に相談すると安心です。
特例子会社のデメリット・課題
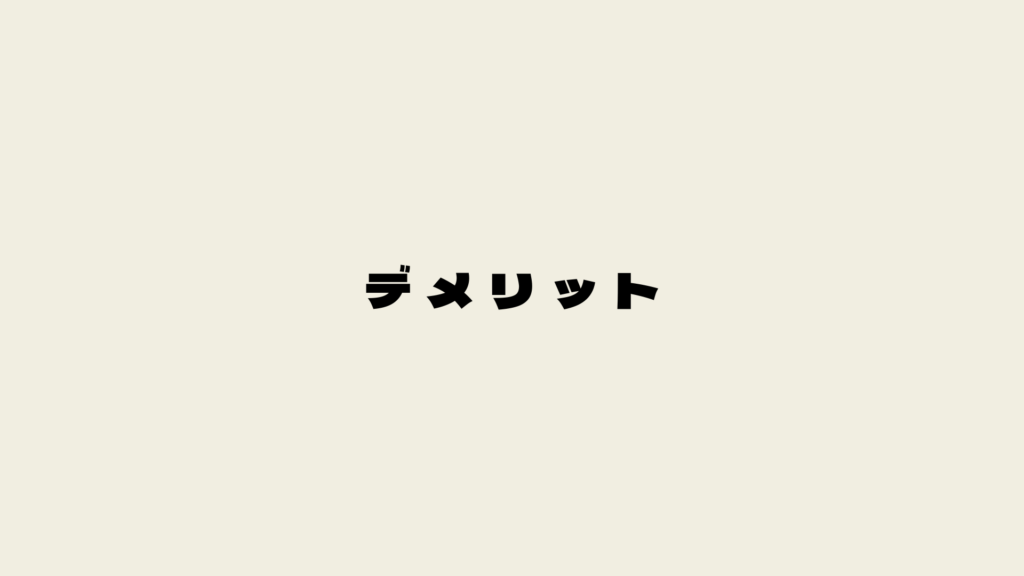
特例子会社には多くのメリットがありますが、注意しておきたい点やデメリットもあります。
この章では、企業が特例子会社をつくる際に、あらかじめ理解しておいた方がいい5つの課題を、できるだけ具体例も交えながら紹介していきます。
1. 設立や運営にお金がかかる
特例子会社を作るには、新しく会社を立ち上げる手続きが必要です。
- 法人設立の登記費用(20万円前後)
- 事務所や作業場の賃貸・工事代
- バリアフリーの改修(スロープ・手すり・エレベーターの設置など)
- 支援員やジョブコーチの人件費
- 仕事で使う道具や機械の購入
たとえば「パソコン作業が中心の特例子会社」を作るなら、パソコンやソフトの準備・操作研修・セキュリティ対策なども必要になります。もちろん、国の助成金で一部をカバーできる場合もありますが、最初にある程度のお金と準備期間が必要です。
今までにあった例、とある中小企業は、クリーニング工場をリフォームして、障害者向けのタオルたたみ・袋詰めの仕事を行う特例子会社を作りました。初期費用は約800万円でしたが、そのうち300万円を助成金でまかなうことができました。
2. 本社との交流が少なくなることがある
特例子会社は、本社とは別の場所に設けられるケースが多いです。別々になってしまうと障害のある社員と、親会社の社員との間で、普段の接点が少なくなることもあります。
結果として、「あの会社、障害者雇用してるって言ってるけど、社内ではまったく見かけないな」といったように、社員の中でも意識の差が生まれてしまうことがあります。
- 月に1回、特例子会社の社員が本社を訪問する
- お互いの仕事を知る「社内見学ツアー」を実施
- 運動会や納会などのイベントを合同で行う
大手飲料メーカーの特例子会社では、本社の社員が交代で“職場体験”を行っています。特例子会社の清掃チームと一緒に作業することで、「こんなに丁寧に働いてくれているんだ」と実感でき、職場のつながりも深まったそうです。
3. 本社の障害者雇用が進みにくくなることも
「うちには特例子会社があるから、本社ではもう雇わなくていいよね」そんな考えが強くなると、本社での障害者雇用が後回しになることがあります。本来、特例子会社はグループ全体で障害者雇用を進めるための“パートナー”です。
たとえば、事務補助・社内美化・郵便物の仕分けなど、本社でも受け入れられる業務は意外と多いものです。
「できるところは本社でも受け入れる」「特例子会社は、より配慮が必要な人向け」というように、バランスよく雇用を広げていく意識が大切です。
厚生労働省や支援団体からは、「特例子会社に偏りすぎず、本社にも障害者雇用の意識を広げていくことが望ましい」とされています。
4. 収益を出すのが難しいこともある
特例子会社の仕事は、障害のある方に合わせた内容になるため、
- 作業スピードがゆっくりになる
- サポートのための人手が必要になる
- 専門性の高い仕事が難しい
といった事情から、収益を上げにくい構造になってしまうこともあります。そのため、「利益よりも、社会的な役割を重視する」という考え方で取り組んでいる企業も多いです。
例えば、一般社員が行っているルーティン業務を切り出して、障害者雇用の方に対応してもらうなどが考えられます。その方の障害特性によるので一概にはいえませんが、障害者雇用で働く方は決まった作業を繰り返すのが得意な方が多くいます。
一般社員の方が面倒だと思う作業を切り出して、障害者雇用の方に依頼をするケースは非常に多く、上手く回っている例としてもあげられます。
営業など直接利益を出す業務はあまり向いていませんが、サポート業務等は向いている傾向にあるため、どんな業務をやってもらうかがとても重要になってきます。
5. 制度の変更に影響されるリスクがある
特例子会社は法律で認められた制度ですが、時代に合わせて制度やルールが変わることもあります。
- 法定雇用率が2.3% → 2.5% → 2.7%と段階的に上昇
- 助成金の対象や金額が見直される
- 認定基準が厳しくなる
といった変化が今後も起こりうるため、常に最新情報にアンテナを張ることが大切です。厚生労働省のWebサイトや、地域の労働局、障害者就業・生活支援センターなどを活用して、「制度を知る→対応する」サイクルを続けていくことが、安定した運営につながります。
特例子会社のメリット・デメリットの比較まとめ
ここまで、特例子会社についてのメリットとデメリットを紹介してきました。
| メリット | デメリット・課題 |
|---|---|
| 障害者雇用率をグループ全体で達成しやすい | 会社の設立・運営にコストと時間がかかる |
| 障害のある人に合った職場を作りやすい | 本社と特例子会社の社員との交流が減りやすい |
| 専門のサポート体制(ジョブコーチ等)を作れる | 本社での障害者雇用が進みにくくなることがある |
| 企業イメージの向上、CSR・SDGsへの貢献 | 仕事の内容が限られ、収益化が難しい場合がある |
| 本社と違う業務を設定でき、柔軟な運営が可能 | 制度の変更(助成金見直しなど)の影響を受けやすい |
| 条件に合えば助成金を活用できる | 助成金には期限や申請条件があるため注意が必要 |
このように、特例子会社にはたくさんのメリットがありますが、事前に準備すべき点やリスクもいくつか存在します。大切なのは、「メリットだけでなく、課題もふまえて総合的に判断する」ということです。
また、「うちの会社では本当に合うのか?」「本社での雇用とどう組み合わせるか?」といった社内でのすり合わせや計画づくりも欠かせません。
次の章では、特例子会社と一般の障害者雇用(本社など)との違いを、より具体的に比べていきます。
特例子会社と一般雇用の違いとは?

障害のある人を雇う方法には、大きく分けて2つのパターンがあります。
- 本社や支店などで直接雇用する「一般雇用」
- 障害者専用の会社として設立する「特例子会社での雇用」
では、この2つにはどんな違いがあるのか?ここでは「雇用のスタイル」「支援体制」「働く環境」などの面から、やさしく比較してみましょう。
1. 雇用する場所・会社の形がちがう
まず、「一般雇用」と「特例子会社での雇用」は、どこで働くのか?どんな形の会社なのか?という点が大きくちがいます。
● 一般雇用とは?
これは、障害のある方を本社や支店など、親会社の通常の職場に直接雇うスタイルです。
たとえば、A株式会社が東京に本社を持ち、営業部や総務部などで一般社員が働いているとします。そこに、障害のある方も同じ職場・同じチームの一員として加わるのが「一般雇用」です。
日常的に健常者の社員と一緒に仕事をしたり、雑談をしたり、同じ休憩室を使ったりと、自然な関わりの中で働くことができます。
ただし、業務内容が難しい、スピードが速い、職場に配慮が少ないといった場合、長く働き続けるのが大変になってしまうこともあります。
● 特例子会社での雇用とは?
一方、特例子会社とは、障害のある人が働きやすいように設計された「別会社」です。
親会社が出資して、新しく会社を作り、そこで障害者の雇用に特化して運営します。
たとえば、A株式会社が「Aサポート株式会社」という特例子会社を作り、そこで10名の障害のある方を雇用するといった形です。
この特例子会社は、業務内容も働く環境も、障害者に合うように最初から整えてあるため、無理なく仕事を続けやすいというメリットがあります。
- 名刺の印刷や封入作業
- データの入力
- 清掃やタオルのたたみ
など、その人の得意や特性に合わせたシンプルな仕事が中心になります。特例子会社の社員は基本的に障害のある方が多く、支援員やジョブコーチがそばでサポートしてくれるのも特徴です。
★ イメージで比べると:
- 一般雇用:本社でみんなと一緒に働く。自然な関わりがあるけど、配慮が難しい場面も。
- 特例子会社:別の場所で、障害者に合った環境で働く。支援が多くて安心だが、他の社員との交流は少なめ。
どちらにも良さがあるので、自社の体制や障害者本人の希望に合わせて、適した雇用形態を選ぶことが大切です。
2. 障害者雇用率のカウント方法がちがう
会社は法律で、「障害のある人を何人かは雇わないといけませんよ」というルールがあります。このルールのことを「法定雇用率」といいます。
たとえば、法定雇用率が2.5%の場合、
- 従業員が100人いれば、障害者を2.5人以上(=2人以上)雇う必要があります。
- この人数の「カウントの仕方」に、一般雇用と特例子会社で違いがあるのです。
● 一般雇用の場合
たとえば、A株式会社が障害のある人を本社で直接雇った場合、その人はA株式会社の社員としてカウントされます。
つまり、
- 本社で雇えば → そのまま本社の雇用率に加算
です。これはわかりやすいですね。
● 特例子会社の場合
一方で、A株式会社が「Aサポート株式会社」という特例子会社を作り、そこで障害のある人を雇用した場合、
その人数は親会社(A株式会社)の雇用率に合算してもOKという特別ルールがあります。
たとえば、A株式会社が100人の従業員を抱えていて、
- 本社で障害者を1人雇っていて
- 特例子会社で2人雇っている
という場合でも、
1人(本社)+ 2人(特例子会社)= 3人
とカウントされ、雇用率2.5%を達成したとみなされます。
● なぜ特例子会社では合算できるの?
これは、特例子会社が「障害者の雇用を本気で支援している会社」として、厚生労働省から特別に認められた会社だからです。ただし、認定を受けていない普通の子会社で雇っても、親会社の雇用率にはカウントされません。
つまり、
- 普通の子会社 → 親会社のカウント対象にはならない
- 特例子会社 → 親会社の雇用率に合算できる!
● 企業にとってのメリット
この仕組みによって、
- 「本社では対応が難しいけど、特例子会社なら雇える」
- 「グループ全体で効率よく雇用率を達成したい」
という企業にとってはとても大きなメリットになります。
実際に、大手企業を中心に、グループの中に障害者雇用の受け皿として特例子会社を設けているケースがたくさんあります。
(ポイントまとめ)
- 一般雇用 → その会社での雇用率にカウント
- 特例子会社 → 親会社の雇用率に合算OK(認定されていれば)
このルールを活用すれば、企業グループとして柔軟に障害者雇用を進めることができます。
3. 支援体制がちがう
特例子会社は、障害者が働くことを前提に作られているので、
- ジョブコーチの配置
- 相談員の常駐
- 個別面談や就業サポートの仕組み
など、専門的な支援体制が整っているケースが多いです。
一方、一般雇用の場合は、本来の業務がある中でサポートを行うため、支援の人手や時間が足りないと感じることもあります。
4. 周囲の社員との関わり方がちがう
一般雇用では、健常者の社員と同じ空間・チームで働くことが多く、
・日々のコミュニケーション
・ランチや休憩などの交流
・一緒にプロジェクトを進める経験
などが自然に生まれます。
一方で、特例子会社は障害のある人が中心の職場になるため、社外や親会社との接点が少なくなりがちです。
その分、安心して働ける環境にはなりますが、「多様な人と働く経験が減る」という面もあるので、両方のバランスが大切です。
5. 働く仕事の内容がちがう
一般雇用では、企業の通常業務(営業・事務・現場作業など)の中に障害者を受け入れます。そのため、業務の難易度やスピードに慣れるのが大変なこともあります。
一方、特例子会社では、
- 簡単な軽作業
- ゆっくり進められる作業
- 単純だけど正確さが求められる仕事
など、その人の能力に合わせた仕事を設計しやすいのが特徴です。
6. 制度的な要件・認定があるのは特例子会社
一般雇用は、特別な認定などは必要ありません。
でも、特例子会社になるには、
- 出資関係が明確(親会社が50%以上出資)
- 従業員のうち20%以上が障害者
- 支援体制や職場環境が整っている
など、厚生労働省の認定条件をクリアする必要があります。その分、メリットも大きいですが、つくるまでの手間や準備は多いのが特徴です。
まとめ
どちらが「良い・悪い」ではなく、自社に合った方法を選ぶことが大切です。
たとえば:
- 「少人数の雇用なら、まずは一般雇用から」
- 「本社では難しいから、特例子会社で集中して支援」
- 「両方組み合わせて、選べる働き方を用意する」
というように、バランスよく活用する企業も増えています。次の章では、特例子会社を実際に作るときの流れや条件について、わかりやすく紹介していきます。
特例子会社を作るには?設立の条件と手順
「特例子会社っていいかも!」と思っても、すぐに作れるわけではありません。国(厚生労働省)から「特例子会社」として認めてもらうための条件があります。
この章では、特例子会社を作るために必要な3つの条件と、5つのステップでできる設立の流れを、わかりやすく解説します。
特例子会社になるための3つの条件
まずは、特例子会社と認められるために、次の3つの条件をクリアする必要があります。
① 親会社とのつながり(出資比率)がある
特例子会社は、親会社が50%以上出資している会社であることが基本です。つまり、まったく別の会社や、資本関係があいまいな子会社では認定されません。
例)A株式会社が「Aサポート株式会社」に60%出資している → OK!
例)A株式会社が「Aサポート株式会社」に40%出資している → NG!
② 全従業員のうち、20%以上が障害者である
「障害者の雇用に特化している会社」であることが前提です。そのため、社員全体のうち20%以上が障害者であることが求められます。
たとえば、社員が20人いるなら、そのうち4人以上が障害者であればOKです。
③ 障害者が安心して働ける体制・設備がある
バリアフリーや支援体制が整っていないと、認定は難しいです。
たとえば:
- 車いすや視覚障害に対応した作業場
- 支援員(ジョブコーチ)などのフォロー体制
- 定期面談や相談窓口の設置
こうした「働きやすい職場環境」が整っているかどうかも、重要なポイントです。
特例子会社の設立ステップ(5ステップ)
条件を満たしたら、いよいよ設立に向けての準備です。実際の流れは、次のようなステップになります。
STEP1:計画づくり
まずは、
- どんな仕事をする会社にするか
- どこに作るか(場所)
- 何人ぐらい雇用するか
などを整理して、全体の事業計画を作ります。この段階で、社会保険労務士(社労士)や就労支援センターなどの専門家に相談する企業も多いです。
STEP2:会社を設立する(法人登記)
法務局で、会社として法人登記を行います。
このとき、
- 会社名・住所
- 出資割合
- 事業内容
などをきちんと整理して書類を提出します。
STEP3:職場環境を整える
作業スペースや休憩室、トイレなどを、障害者が安心して使えるように整備します。バリアフリーの改修工事、静養室の設置などが必要になることもあります。また、どんな仕事をするかに合わせて機械やパソコンの準備も行います。
STEP4:障害者の採用と支援体制の準備
ハローワークや支援機関と連携して、障害者の採用活動を行います。また、入社後の支援のために、
- 支援員やジョブコーチを配置する
- 研修や慣らし勤務の仕組みを用意する
といった準備も進めます。
STEP5:労働局へ「特例子会社」の認定申請
会社の準備が整ったら、厚生労働省(都道府県労働局)に申請書を提出します。内容に問題がなければ、数週間〜2か月程度で認定され、「特例子会社」として正式に認められます。
まとめ:準備すれば、しっかり活用できる制度
特例子会社を作るには、
- 事業計画を立てる
- 会社を登記する
- 職場や支援体制を整える
- 障害者を採用して、認定申請を出す
という手順が必要です。
簡単ではありませんが、しっかり準備すれば、企業にとっても働く人にとっても大きなプラスになります。次の章では、実際に特例子会社を作ってうまく活用している企業の事例をご紹介します。
どんな会社が特例子会社を作ってるの?規模や特徴を紹介

特例子会社というと、「大企業だけの制度なのでは?」と思われることがあります。でも実際には、いろいろな業種・いろいろな規模の会社が特例子会社を作っているんです。
ここでは、どんな会社が特例子会社を作っているのか、傾向をわかりやすくご紹介します。
大企業が中心だけど、中小企業グループも増えている
たしかに、特例子会社の多くは大手企業(従業員1000人以上)のグループ会社です。
- トヨタグループ(トヨタループス株式会社)
- ソニーグループ(ソニー希望・光株式会社)
- NTTグループ(NTTクラルティ株式会社)
こうした大企業では、「雇用率を達成しつつ、専門的な支援が必要な社員をしっかりサポートする場所」として特例子会社が活用されています。
一方、最近では中堅企業や中小企業グループでも特例子会社を作る例が出てきています。
- 社員数200〜500人規模の建設会社が、清掃業務の特例子会社を設立
- 地方の印刷会社が、簡易封入・梱包作業に特化した子会社を設立
グループ内に複数の法人がある企業であれば、工夫次第で特例子会社の設立は可能です。
いろいろな業種で活用されている
特例子会社が多い業種としては:
- メーカー(製造・組立・検品作業)
- IT・通信(データ入力・PC業務)
- 印刷・出版(名刺・封筒・書類の印刷・製本)
- 飲料・食品(サンプル詰め・出荷)
- 金融・保険(社内資料の管理・清掃)
といった企業が多いですが、最近では
- 建設業の現場サポート
- 農業法人による就農支援型の特例子会社
- コールセンター業務に特化した例
など、アイデアと工夫次第でさまざまな業種に広がっています。
従業員数は10〜100名規模が多い
特例子会社の規模は、
- 大手の場合は100人以上
- 中小企業グループでは10〜30人前後
という会社が多いです。
障害のある社員が5〜20名、支援員や事務スタッフを含めても全体で30人未満の会社もたくさんあります。大きな会社でなくても、「働きやすい小さな職場」をつくって安定運営している企業は多く存在します。
地方でも特例子会社は増えている
以前は東京・大阪など都市部が中心でしたが、今では
- 地方の県庁所在地
- 工業団地内
- 農村部や郊外
などでも地域に根ざした特例子会社が増えています。
地域密着型の清掃、内職、農業、IT軽作業など、地元で長く働きたいというニーズにも応えられる点が注目されています。
まとめ:大企業だけじゃない。工夫次第でどんな会社でも
特例子会社というと、「大手企業だけが使える制度」というイメージを持たれがちですが、
- 社員数が少ない中小企業グループ
- 地方の会社
- 非営利法人(社会福祉法人・医療法人など)
でも、制度を理解し、支援機関と連携することで設立が可能です。「自社には無理かも」とあきらめる前に、一度、労働局や専門家に相談してみるのがおすすめです。
特例子会社の成功事例
ここでは、実際に特例子会社を設立し、障害者雇用に成功している企業の事例を紹介します。大手企業を中心に、さまざまな工夫や取り組みがされており、これから設立を考えている企業にとっても参考になるはずです。
事例①:ソニー希望・光株式会社(ソニーグループ)
ソニーグループが1998年に設立した特例子会社で、約100名以上の障害者が在籍しています。
主な業務は、
- 印刷・製本
- データ入力
- 名刺・封筒の作成
など、社内で必要な業務を一手に担っています。
【特徴】
- 社員一人ひとりの特性に合わせた作業指示・工程を用意
- 定期的な社内イベントやレクリエーションで定着率UP
- ジョブコーチや心理士が在籍し、きめ細かい支援体制を整備
結果として、高い定着率と企業内評価を両立しており、他社からの見学も多数受け入れています。
事例②:トヨタループス株式会社(トヨタ自動車グループ)
トヨタ自動車が設立した特例子会社で、全国に拠点を持つ大規模な組織です。
主な業務は、
- 社内の清掃・リサイクル活動
- 印刷・製品のラベル貼り
- 自動車部品の簡易検査
障害のある社員は、500名以上在籍しており、多様な障害特性に対応できる支援体制が整っています。
【特徴】
- 職場ごとにジョブコーチ・支援担当を配置
- 社内評価制度や表彰制度がある
- 一人ひとりの「働きがい」に焦点を当てた人材育成
トヨタらしい“カイゼン”の仕組みを取り入れており、障害者の成長と会社の成果が両立しています。
事例③:サントリービジネスシステム株式会社(サントリーグループ)
飲料メーカーであるサントリーが設立した特例子会社で、障害者雇用の質にこだわった運営を行っています。
主な業務は、
- オフィス内清掃
- 事務補助(書類のデータ入力・封入など)
- 商品サンプルの管理・発送
【特徴】
- 「無理なく、長く働ける職場づくり」がモットー
- 精神障害・発達障害の社員向けに静養室や面談制度を充実
- 一般社員との合同研修も実施し、社内の理解を深めている
社内外からの評価も高く、CSR報告書などでも積極的に情報公開されています。
事例④:NTTクラルティ株式会社(NTTグループ)
NTTが設立した特例子会社で、全国で700人以上の障害者を雇用している日本有数の規模を誇ります。
主な業務:
- 文書のデジタル化
- 印刷・発送業務
- 名刺・封筒の制作
【特徴】
- 在宅勤務やテレワーク制度も導入
- 就業支援スタッフが常駐し、相談体制を徹底
- 全国で複数の拠点を展開し、地域雇用にも貢献
働きやすさを追求し、障害者の「自立と成長」を応援する企業文化が根づいています。
まとめ:成功事例に共通するポイント
紹介した企業の成功事例には、次のような共通点があります。
- 1人ひとりの特性に合った仕事・環境づくり
- 支援員・ジョブコーチなど専門スタッフの配置
- 職場の雰囲気や人間関係にも配慮
- 障害者本人の「働く喜び」や「成長」に目を向けた運営
「特例子会社=雇用率を満たすための制度」ではなく、会社の一員として“いきいき働ける場所”にしていることが、長く続けられるポイントです。
エリア別特例子会社記事一覧

法定雇用率ナビに掲載をしているエリア別の特例子会社記事になります。ぜひ参考にしてください。
- 北海道エリア・東北エリアの特例子会社一覧
- 関東エリアの特例子会社一覧
- 中部エリアの特例子会社一覧
- 近畿エリアの特例子会社一覧
- 中国エリアの特例子会社一覧
- 四国エリアの特例子会社一覧
- 九州エリア・沖縄エリアの特例子会社一覧
特例子会社の失敗例・注意点
特例子会社は、うまく運営できれば障害者と企業の両方にとってメリットが大きい仕組みです。でも実際には、うまくいかなかった例や、思ったような成果が出なかった会社もあります。
この章では、よくある失敗例や注意点を紹介しながら、どうすれば回避できるのかもわかりやすく解説します。
目的が「雇用率を満たすこと」だけになっていた
失敗例:ある企業は「法定雇用率をクリアしなきゃ」と焦って、短期間で特例子会社を立ち上げました。
しかし、現場で働く人のことをあまり考えずに進めてしまったため、
- 仕事が単調すぎてモチベーションが続かない
- 本人の得意・不得意が考慮されていなかった
結果的に、1年以内に退職者が続出し、再び雇用率を割り込んでしまいました。数字だけでなく、「働く人の視点」を大切にした計画を立てることが成功のカギです。
雇用率を満たすためだけに特例子会社を作ると、その後苦戦してしまうケースが多いです、。
2. 適した業務がなかった
失敗例:ある会社は特例子会社を立ち上げたものの、
- グループ会社内で任せられる仕事がなかった
- 軽作業を外注化していて、戻すことが難しかった
結果として、仕事が少なく、社員が暇を持て余す状態に。働く人のやりがいも感じられず、「いるだけ」状態になってしまいました。
これは今でも起こっている現象です。「この業務を切り出してお願いしよう」と計画したものの、実際に働いてもらうと、「業務が難しすぎてできない」「用意された仕事が終わってしまって何もすることがない」など実際に起こっているケースです。
ここを最初からうまくいかせることはなかなか難しいですが、意外と障害者雇用の方の仕事を作るのは難しいと知っておくことは重要です。障害者コンサルのようなプロにお願いをしてスタートするのもオススメです。
3. サポート体制が不十分だった
失敗例:精神障害や発達障害のある社員が多かったが、
- 支援員やジョブコーチの配置がなかった
- 面談や相談の時間が取れていなかった
その結果、体調を崩してしまう人が多く、定着率が低くなってしまったという例もあります。
「サポートする人の配置と育成」も、障害者雇用の成功には欠かせません。専門職の採用や、外部支援機関との連携もとても大切になってきます。今いる社員さんだけでサポートを考えると、今までやってこなかった分野の仕事でストレスが溜まってしまうことも多くありますので、どこまでを外部に依頼をするかなど決めることも重要になってきます。
4. 親会社との連携がうまくいかなかった
失敗例:親会社の理解が浅く、
- 「特例子会社に任せたから、本社では関係ない」と考えていた
- 特例子会社の存在が社内で知られていなかった
その結果、
- 仕事の依頼がこない
- 本社との交流もなく孤立する
など、グループ内でうまく連携できずに閉鎖になったケースもあります。特例子会社は「グループ全体の障害者雇用を支える役割」。本社とのコミュニケーションや業務連携の仕組みづくりが重要です。
5. そもそも認定されなかった
失敗例:会社を作ったものの、
- 親会社の出資比率が足りていない
- 障害者の割合が20%に届いていない
- 支援体制・環境が十分でない
などの理由で、「特例子会社として認定されなかった」ケースも実際にあります。設立前に労働局や社労士に相談し、要件をしっかり確認しましょう。
まとめ:成功のカギは「準備・支援・社内連携」
特例子会社で失敗しないためには、
- 数字だけでなく「働く人のこと」を考える
- どんな仕事をするか、前もって決めておく
- しっかりした支援体制を整える
- 親会社やグループ全体と連携する
という4つのポイントがとても大切です。
事前にきちんと準備をしていれば、特例子会社は大きな力になる制度です。
特例子会社とSDGs・ダイバーシティの関係
最近では「SDGs」や「ダイバーシティ経営」といった言葉をよく聞くようになりました。特例子会社の取り組みは、これらの考え方ととても深い関係があります。
ここでは、特例子会社が社会や企業にとってどんな意味を持つのか、SDGsやダイバーシティの視点から紹介します。
SDGsとは?
SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは、国連が決めた「持続可能な開発目標」のことです。
2030年までに世界が目指す17の目標があり、企業にもその達成が求められています。
特に特例子会社に関係するのは、この3つです:
- 目標8: 働きがいも 経済成長も
- 目標10: 人や国の不平等をなくそう
- 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう
障害のある人も、やりがいをもって働ける会社を作ることは、まさにSDGsの実践です。
ダイバーシティ経営とは?
ダイバーシティとは「多様性」という意味です。
ダイバーシティ経営とは、性別・年齢・国籍・障害の有無に関わらず、いろいろな人が活躍できる会社を目指す経営スタイルのことです。
障害のある人が安心して働ける特例子会社は、企業の多様性・包摂性を高める取り組みの一つです。最近では、投資家や取引先が「ダイバーシティを重視する企業か?」を見ているというケースも増えています。
社会から信頼される企業になる
特例子会社を設立して、障害のある人が長く働ける環境をつくることは、
- 社会課題に取り組んでいる
- 地域と連携している
- 誰もが安心して働ける職場を目指している
というポジティブなメッセージを社会に発信することにもなります。これは、社員・取引先・地域・求職者などあらゆるステークホルダーからの信頼を得ることにもつながります。
企業ブランディングや採用にも効果がある
特例子会社を作って障害者雇用に積極的に取り組むことで、
- 「この会社、応援したいな」と思われる
- 就職希望者から「安心して働けそう」と選ばれる
- SDGsやESG対応企業として評価される
といった企業ブランディングの向上にもつながります。
実際に、大手企業ではホームページや採用パンフレットに特例子会社の取り組みを掲載し、「働く人の多様性」をアピールしている例が増えています。
特例子会社は、単なる「雇用率達成のための仕組み」ではありません。障害者雇用を通じて、社会・地域・社員・会社のすべてに良い影響をもたらす仕組みです。
SDGsやダイバーシティといった言葉が注目される今こそ、「どんな人も働ける会社」を目指す姿勢が、企業の未来に大きな価値をもたらします。
特例子会社に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、特例子会社についてよくいただく質問を15個にまとめました。「そもそもどんな制度?」「中小企業でもできる?」「助成金は?」など、気になる疑問をやさしく解説します。
Q1. 特例子会社って何ですか?
A. 障害のある人が働きやすいように、企業がグループ内に作る“別の会社”です。この会社で雇った障害者の人数は、親会社の雇用率にカウントできます。
Q2. どんな会社でも特例子会社を作れますか?
A. 基本的にはどの会社でも可能ですが、親会社との資本関係・障害者の割合・支援体制などの条件をクリアする必要があります。
Q3. 中小企業でも作れますか?
A. はい、可能です。最近は従業員数100〜200人規模の企業でも、特例子会社を設立する例が増えています。
Q4. 特例子会社にするには、何が必要ですか?
A. 主に以下の3点です:
・親会社が50%以上出資していること
・従業員のうち20%以上が障害者であること
・職場環境や支援体制が整っていること
Q5. どんな仕事を任せればいいですか?
A. 一人ひとりの特性に合わせて、軽作業・印刷・清掃・データ入力・ラベル貼りなどがよくあります。最近はIT業務や在宅ワークも増えています。
Q6. 障害の種類に制限はありますか?
A. 制限はありません。身体・知的・精神・発達など、すべての障害種別に対応可能です。ただし、支援体制をしっかり整えることが大切です。
Q7. 認定されるまでどのくらいかかりますか?
A. 書類の準備や相談も含めて、3か月〜半年程度が目安です。事前に労働局に相談しておくとスムーズです。
Q8. 認定を受けなかったらどうなりますか?
A. 認定されないと、特例子会社としてのカウント対象になりません。必要条件を満たしてから再申請することは可能です。
Q9. 助成金は使えますか?
A. はい。設備費・人件費・バリアフリー工事などに対して、国や自治体の助成金が使える場合があります。条件やタイミングにより異なるので、専門家に相談しましょう。
Q10. 特例子会社で雇った人は親会社の雇用率にどうカウントされるの?
A. 特例子会社が厚労省に認定されていれば、そこで働く障害者は親会社の雇用率に合算できます。これは特例子会社だけの特別な仕組みです。
Q11. 在宅勤務でも特例子会社で働けますか?
A. はい、業務内容によっては在宅ワークやテレワークを取り入れている特例子会社もあります。データ入力や封入業務の一部などが対応しています。
Q12. 本社の人と交流はありますか?
A. 企業によってさまざまですが、定期的な合同研修やイベントを通じて、親会社の社員との交流を行っている例もあります。
Q13. 社会的な評価は高いの?
A. はい。特例子会社を持つ企業は「障害者雇用に積極的な会社」「SDGs・ダイバーシティに配慮した企業」として評価されることが多いです。
Q14. 親会社が倒産したらどうなりますか?
A. 原則として特例子会社の認定が取り消される可能性があります。新たな出資者・親会社を確保できれば、継続できることもあります。
Q15. 将来的に本社でも雇用を広げていくことはできますか?
A. もちろん可能です。特例子会社で働いた実績やノウハウを活かして、本社での受け入れに広げていく企業もたくさんあります。
まとめ:特例子会社は、企業と社会をつなぐ“やさしい選択肢”
ここまで、特例子会社の仕組みやメリット・デメリット、成功例や失敗例などをわかりやすく紹介してきました。
あらためて、特例子会社の大きなポイントをまとめると、次の通りです。
- 障害のある人が安心して働ける環境を企業グループの中に作れる
- 親会社の雇用率としてカウントできる制度がある
- SDGs・ダイバーシティなど社会的価値を高める活動にもつながる
もちろん、設立や運営には課題もありますが、
「数字のため」ではなく「人のため」に向き合うことで、企業としても社会としても得られるものはたくさんあります。特例子会社は、単なる制度ではなく、
「誰もが自分らしく働ける社会」を形にする、企業のやさしい選択肢です。もし今、障害者雇用のあり方に悩んでいるなら、一度、特例子会社という仕組みを検討してみるのも良いかもしれません。