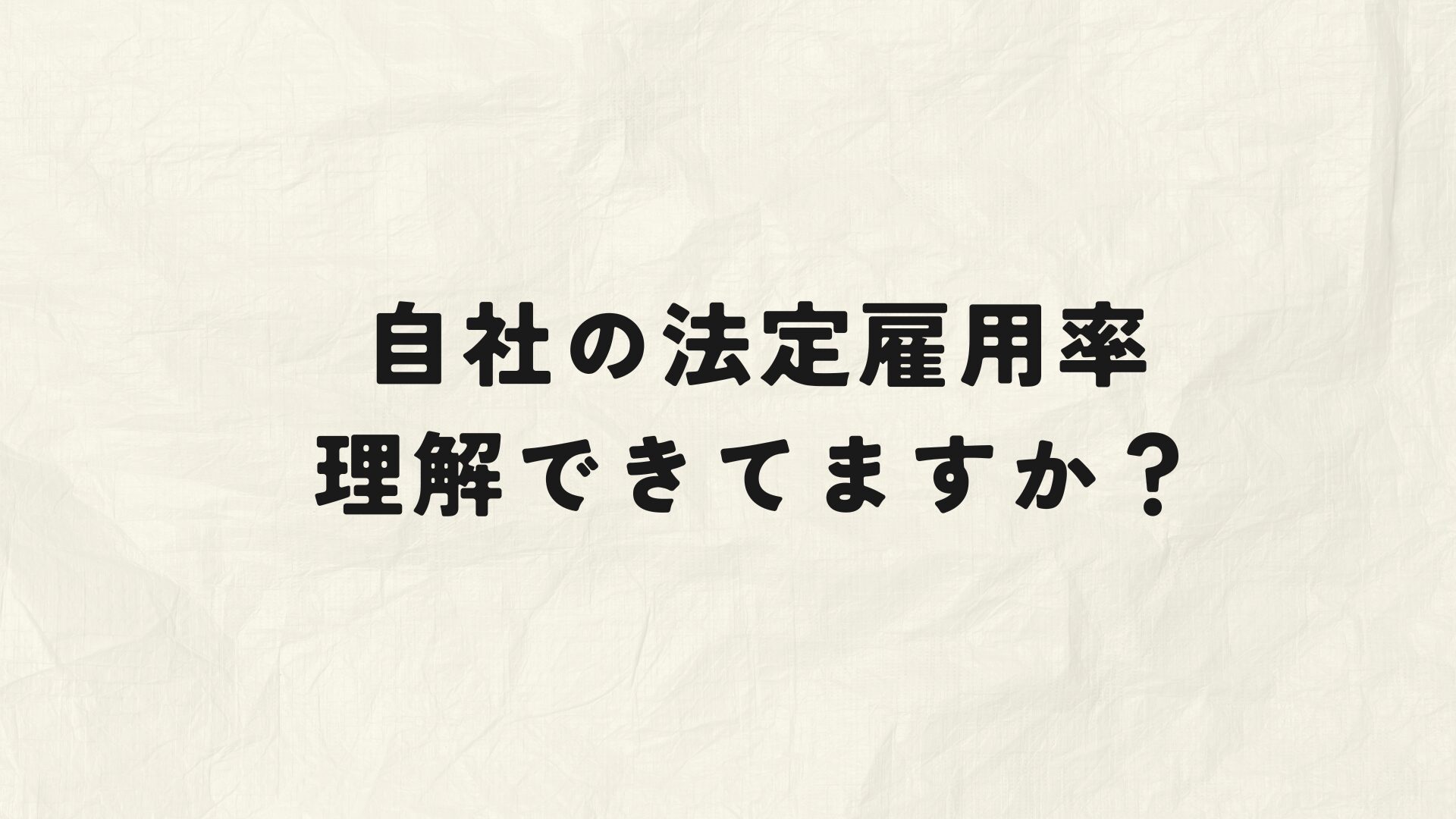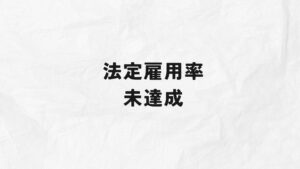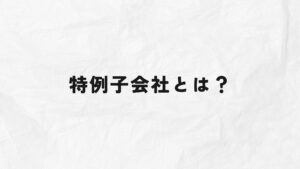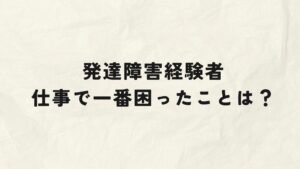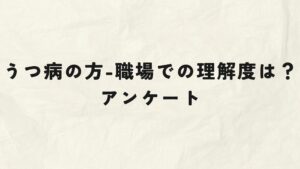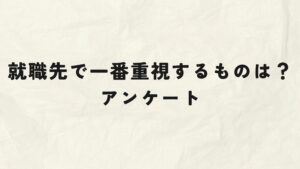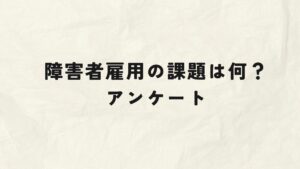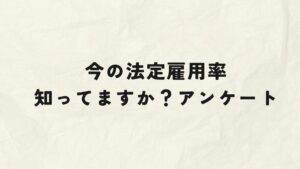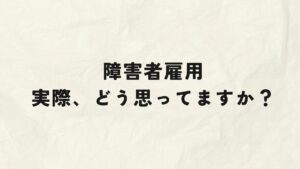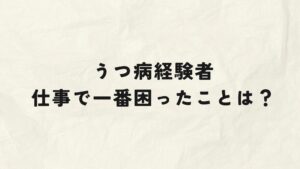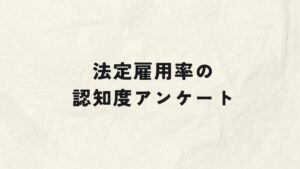「自分の会社の障害者雇用のこと、知っていますか?」
企業が障害者を雇用する割合には法律で定められた基準があります。ですが、その内容を正確に理解している人はどれほどいるのでしょうか?
今回、「法定雇用率ナビ」では、企業に勤める方々を対象にした簡単なアンケートを実施し、その結果から現場の実態を探りました。
アンケート概要
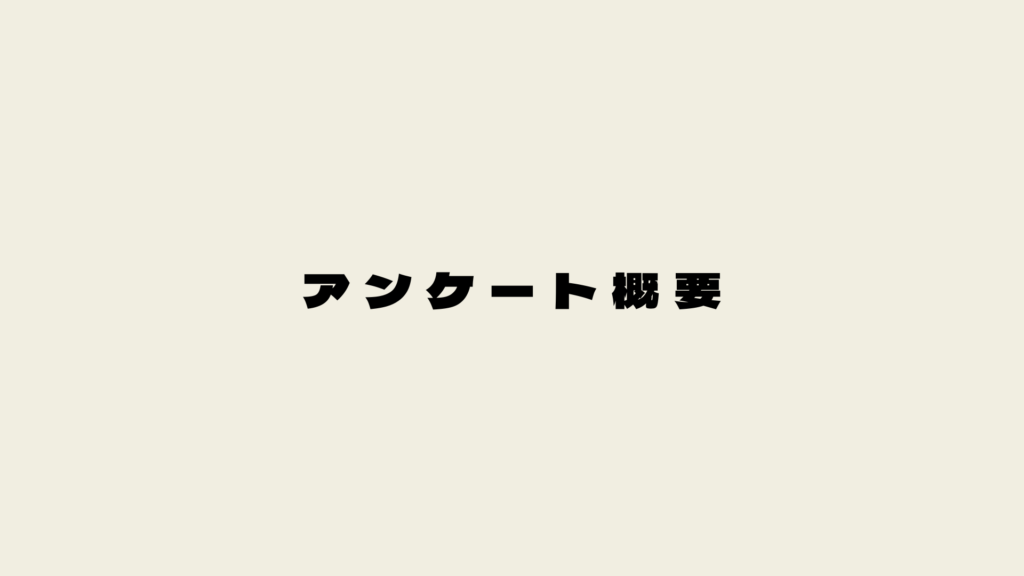
- 調査対象:50名以上の従業員がを会社に勤めている方
- 回答件数:256件
- 実施時期:2025年7月14日~2025年7月14日
- 主な質問内容:
・自社(働いている会社)の法定雇用率(障害者雇用の人数)知ってますか?
・自社(働いている会社)は法定雇用率に達していると思いますか?
・障害者雇用に関して思うことがあれば書いてください。(自由記述)
コチラに関してのアンケートをとってみました。
アンケート結果

自社(働いている会社)の法定雇用率(障害者雇用の人数)知ってますか?
- 知っている:30.1%(77件)
- 知らない:67.2%(172件)
- 何を指しているのかわからない:2.7%(7件)
7割近くの人が「知らない」または「理解していない」と回答しており、企業内での制度周知がまだまだ進んでいないことが明らかになりました。
自社(働いている会社)は法定雇用率に達していると思いますか?
- はい:29.7%(76件)
- いいえ:32.4%(83件)
- わからない:37.9%(97件)
「わからない」と答えた人が最多となり、自社の状況を把握していない社員が多数存在する実態が浮き彫りになりました。「達成している」と答えた人は3割未満で、「いいえ」も3割超。企業全体での制度運用や共有が不十分である可能性もあります。
実際に障害者雇用に関してはどんなことを考えているのでしょうか。自由記述で聞いてみました。
障害者雇用に関して思うこと(自由記述)

アンケートには自由記述もあり、多くのリアルな声が寄せられました。ポジティブ、ネガティブ、実際の経験に分けて紹介します。
ポジティブなコメント
- 「出来れば採用したいが、なかなか出会う機会がないので採用に繋がらないのが気になっています。」
- 「障害者にもできる業務が会社にはあると思うので、負担のない範囲で障害者雇用をするのはいいことだと思います。」
- 「障害者雇用は、個々の特性を理解して、適切な配慮のもとで能力を活かす仕組みがあれば、企業にとっても有益だと思います。」
- 「障害者の方でも働きたいと思う方はいっぱいいらっしゃいますし、人手不足な会社も多いことから障害者雇用は社会的にも意義があると思います。」
- 「障害者雇用は社会的に非常に大切な取り組みだと思います。企業が協力して取り組めば、きっとより良い社会になると感じます。」
- 「出来る仕事はあるので、企業が少しずつ柔軟な環境を整えることが大事だと思います。」
- 「社内で障害者を戦力として受け入れる文化が育ってきていると感じています。」
- 「採用後も支援員や上司がフォローしていくことで、働き続けやすい環境が作れます。」
- 「障害のある方の仕事ぶりに感動した経験があります。むしろ模範的な存在として職場を引っ張ってくれています。」
- 「制度をうまく使えば、企業にも障害者にもメリットがあるはずです。」
多くの回答者が「前向きに雇用したい」「働ける環境を整えれば活躍できる」といった前向きな姿勢を示しています。制度面だけでなく、職場づくりや意識改革が鍵になることがうかがえます。
ネガティブなコメント
- 「障害者にもできる業務が会社にはあると思うので、負担のない範囲で 障害者雇用をするのはいいことだと思います。」(一方で“負担”が前提になっている声も)
- 「大企業等は法定雇用率を満たすためにグレーなことをしている。ただ雇用すればいいという問題ではないと思う。」
- 「何人いらっしゃるかわからないが、積極的に採用していることは知っている。」(情報の共有が不十分な様子)
- 「障害者雇用は社会的に非常に大切な取り組みだと思いますが、表面的に人数だけを満たすような形で行われることもあり、違和感があります。」
- 「障害のレベルによっては、雇用がなかなか難しいと思う。結局他の方に負担がいく場合もあるので、国全体での支援が必要。」
- 「制度の存在は知っているが、実際にどう配慮すればよいのか社内でも決まっていない。」
- 「精神障害のある方の対応が難しく、現場が混乱することもある。」
- 「法定雇用率だけを目標にしていると、本質的な雇用にならないと思う。」
- 「障害者本人に合う業務が社内に少なく、長く続けてもらうのが難しい。」
- 「実際に雇用しているが、現場の理解が浅く、受け入れが難航している。」
現場の実態を反映した声には制度と現場のギャップや、サポート体制の不足が浮き彫りになっています。制度の達成だけでなく、職場全体での理解促進・環境整備の重要性があらためて問われています。
実際に経験してみてのコメント
- 「障害者雇用は社会的に非常に大切な取り組みだと思いますが、表面的に人数だけを満たすような形で行われることもあり、違和感があります。」
- 「実際に障害者雇用を進めているが、現場の職員の障害者に対する理解が浅く、なかなか受け入れできる環境が整わないのが現実です。」
、「制度の大切さ」を理解しながらも、「現場での運用には課題が多い」というリアルな状況が伝わってきます。単に制度を導入するだけでなく、現場の理解促進や支援体制の整備が不可欠です。
なぜ法定雇用率の理解が必要なのか?
法定雇用率とは、障害者雇用促進法に基づき、企業に対して一定割合の障害者を雇用することを義務付けた制度です。2024年度以降、法定雇用率の引き上げも段階的に進められており、企業側の対応もますます重要になっています。
この制度を理解せずにいると、以下のようなリスクが生じます。
- 納付金制度の対象になる:法定雇用率を満たしていない企業は、障害者雇用納付金(月額5万円/人〜)の支払い対象となる。
- 行政指導や勧告:未達成が続く場合、ハローワークなどから指導や改善命令を受ける可能性。
- 企業名の公表:障害者雇用への取組みが著しく不十分な企業は厚労省のWebサイト等で企業名が公表され、企業イメージの悪化に繋がる恐れがある。
つまり、法定雇用率の理解は「コンプライアンス」の問題であると同時に、「企業の信頼性」「社会的責任」「職場の多様性」に直結する重要テーマで、今後も重要同はさらに増していくと考えられています。
さらに、法定雇用率の達成は「障害者の雇用創出」にとどまらず、社内の風通しや、企業文化の健全化にもつながる可能性があります。だからこそ、まずは制度の基本を知り、現場の実態を把握し、全社的に理解を深めることが求められています。
アンケート結果まとめ

今回のアンケートを通じて、企業における法定雇用率(障害者雇用)に関する意識や実態が明らかになりました。以下に主なポイントをまとめます。
- 法定雇用率の認知度はまだ低い: 回答者の約7割が「知らない」または「何を指しているのかわからない」と回答。
- 自社の達成状況を把握していない人が多い:「わからない」と答えた人が約4割で最多。
自由記述でも
- 現場には前向きな声も多数:「できれば雇用したい」「業務がある」「活躍してほしい」といったコメントが多く寄せられた。
- 一方で、制度運用や現場体制には課題も:「現場の理解不足」「対応が難しい」「形だけの雇用」など、制度と実態のギャップを指摘する声も多く見られました。
- 実体験に基づくコメントは少数ながら説得力あり: 実際に障害者雇用を経験した人からは、制度の意義と同時に、受け入れ体制の整備の必要性が語られています。
このアンケート結果が、制度を“義務”としてだけでなく、“職場の可能性を広げるチャンス”として見直すきっかけとなれば幸いです。
法定雇用率ナビの独自アンケート一覧

法定雇用率ナビでは独自のアンケート調査を実施しています。企業側目線、障害者雇用側目線など様々なアンケート調査をしていますので是非参考にしてください。(アンケート一覧はこちら)