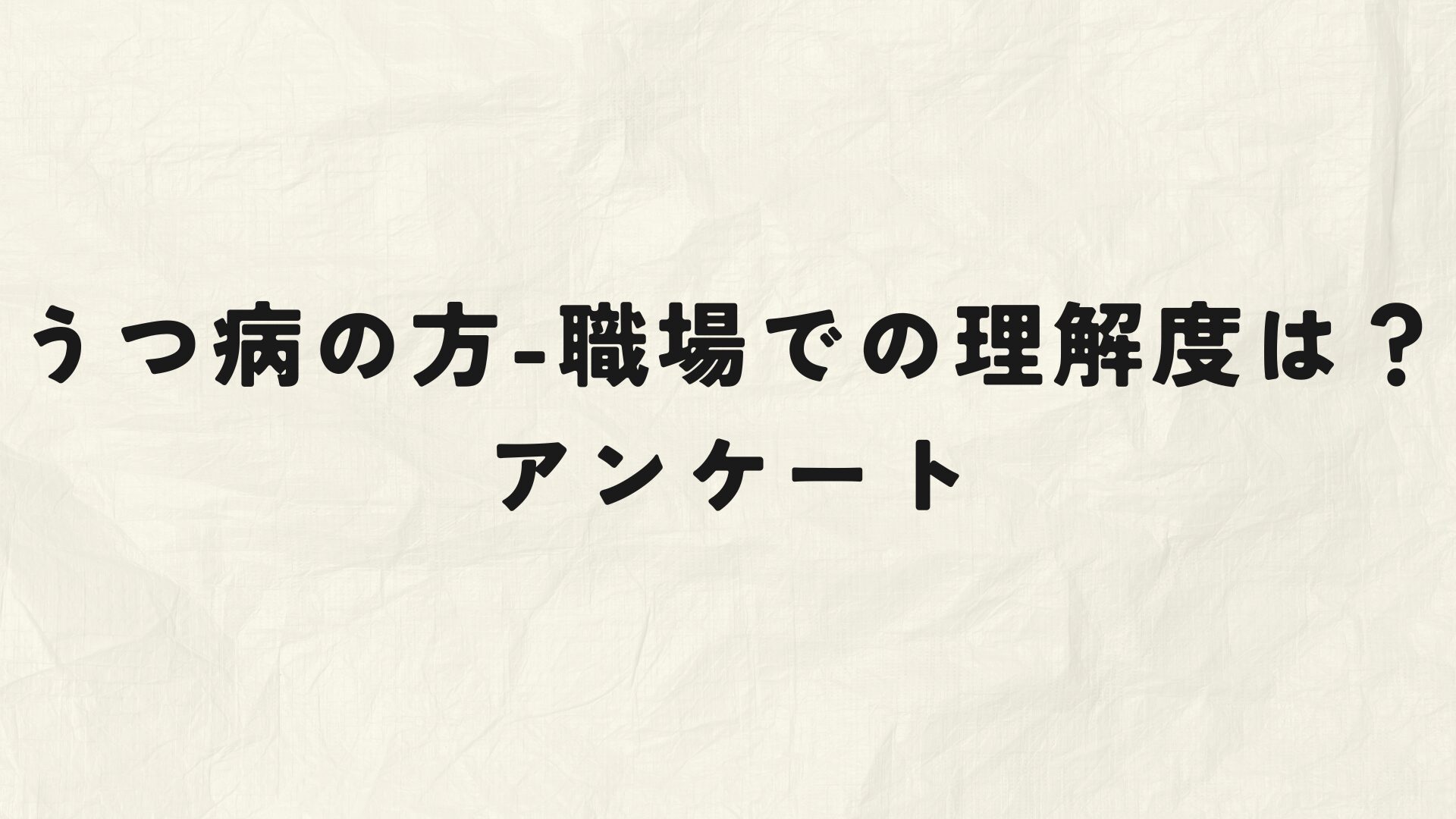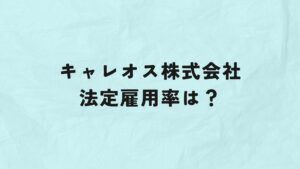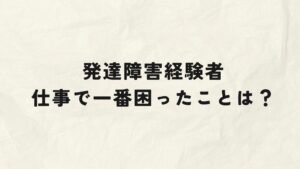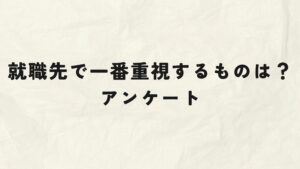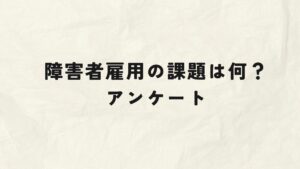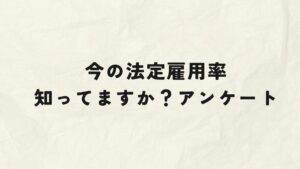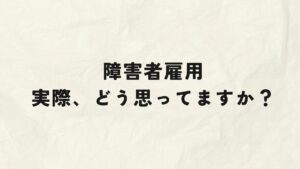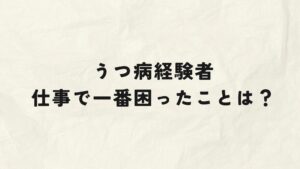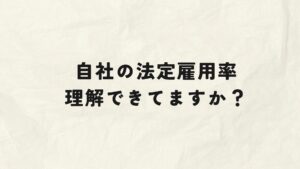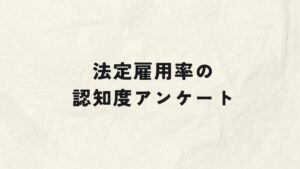うつ病を経験し、職場に病気を伝えている方は、実際にどの程度理解を得られているのでしょうか?今回、うつ病経験者175名にアンケートを実施し、職場の理解度を調査しました。
アンケート概要
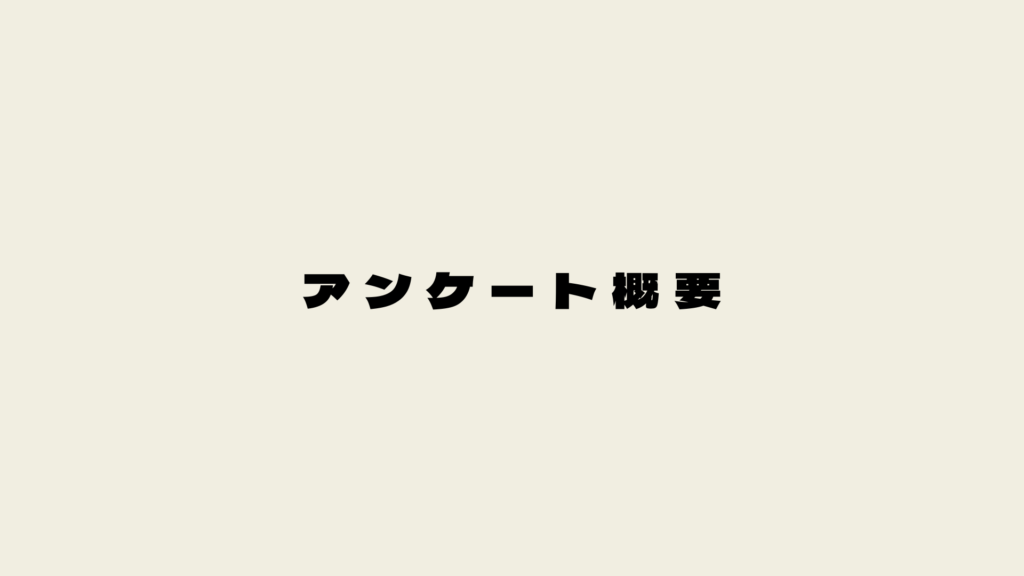
- 調査方法:インターネット調査
- 対象:うつ病の方・うつ病経験がある方
- 回答者数:175人
- 調査期間:2025年8月14日~2025年8月15日

質問項目
- 性別
- 年齢
- 職場での理解度はありますか?(選択式)
- 何か思うことがあれな書いてください。(自由記述)
アンケート結果

性別
| 性別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 女性 | 101人 | 57.7% |
| 男性 | 74人 | 42.3% |
年代
| 年代 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 1人 | 0.6% |
| 20代 | 38人 | 21.7% |
| 30代 | 72人 | 41.1% |
| 40代 | 43人 | 24.6% |
| 50代 | 18人 | 10.3% |
| 60代以上 | 3人 | 1.7% |
職場の理解度
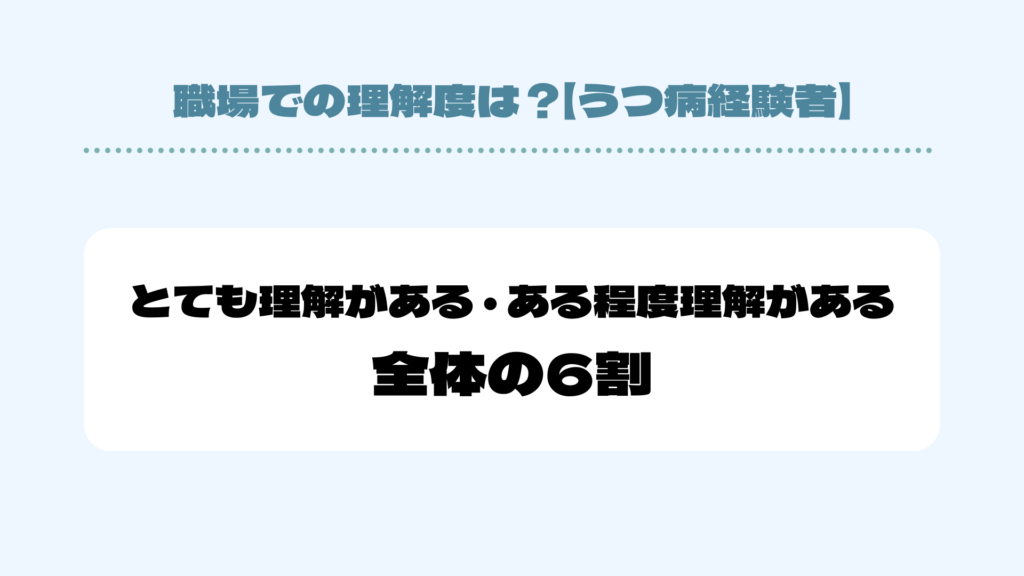
| 理解度 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| とても理解がある | 32人 | 18.3% |
| ある程度理解がある | 73人 | 41.7% |
| あまり理解がない | 50人 | 28.6% |
| 全く理解がない | 20人 | 11.4% |
アンケート結果から、「理解がある」と感じている方は全体の約60%でした。半数以上が職場からの配慮を実感している一方で、約40%は理解不足を感じています。特に「あまり理解がない」「全く理解がない」という回答は、業務負担や人間関係、復職サポートの不十分さなどが背景にある可能性があります。
うつ病は見えにくい症状も多く、周囲からの理解を得にくいことがあります。そのため、上司や同僚への正しい知識の共有、柔軟な勤務制度、相談しやすい環境づくりが重要です。企業にとっても、従業員のメンタルヘルスを守ることは生産性向上や離職防止につながります。
「理解がある」と感じる割合を増やすには、制度面だけでなく、日常の声かけやちょっとした配慮といった“職場の文化”を育てることが欠かせません。
みんなの口コミ

『とても理解がある』と回答した方の口コミ
 男性(30代)
男性(30代)人によって仕事や悩み事を抱えやすいという個人的な問題と職場が繁忙でコミュニケーションが減少したタイミングが重なった時に発生した。
しかし、基本的にチーム内で顔色を見るクセを付けているため、すぐに上位者へ報告して、仕事の調整やフォロー体制を組むといった対策に迅速に取り組んだ。



約5年前に仕事の関係でうつを発症しました。
それからずっと病院に通い続けているのですが、前の職場の労働環境のせいでうつを再発しました。精神科の先生と相談しながら、「職場を帰れば仕事はできる」との結論になり、今の職場に転職することになりました。
今の職場には、自分がうつを発症し、今も継続して通院していることは面接時に打ち明けています。採用担当の方はそれを分かった上で採用してくださり、今でも仕事をしていると、「仕事量は多くないですか?しんどいと感じることはないですか?」と気を使って声をかけて頂いています。
また、職場の方々にも、うつについては話してあるので、繁忙期なんかは仕事を手伝ってくださる様なサポートをしてくださいます。転職してからもう1年ほどになりますが、今では症状も落ち着いて、楽しく仕事が出来ています。



症状が出たり調子が悪い時は、仕事量や勤務時間を調整してもらえている。



休職者の多い職場のため、偏見等はない。しんどくなっちゃったんだな、くらいの認識で復職も他の人がしているのでしやすい。また感情労働なのでなりやすいことも皆さん理解されている。復帰してもうつ病を理由に不当に扱われることもなく、営業職ではあるもののノルマ達成について細かく言われることもないので、むしろ配慮いただける環境である。業務量については自身の裁量に任せられているので、会社から何か言われることはなく自分で体調と相談しながらノルマ達成のために調整して行く形。



中途で障害者枠で働いてます。入社時に合理的配慮として、通院時に休みを頂けますかと面談時、要望出した所、承諾はもらってます。また、定期的上司とは面談を行いまして、相談しやすい、環境だと思います。また特例子会社ですが、福祉資格もってる、定着支援のスタッフと定期的に相談してる状況です
今回寄せられたエピソードを見ると、「無理な出社を求めず休養や在宅勤務を認めてくれる」「負担の少ない部署に異動してくれる」「通院や療養のための休暇や時短勤務を承認してくれる」といった、制度面での配慮が多く挙がっていました。中には、傷病手当や手続きの案内までスムーズにしてくれたという声もありました。
また、「体調や気持ちを気にかけて声をかけてくれる」「困ったときに代わりに仕事を引き受けてくれる」など、人間関係のあたたかさを感じる体験談も多く見られました。形式的な対応だけでなく、日常の小さな気遣いが、うつ病経験者にとって大きな安心感につながっているようです。
こうしたエピソードからもわかるように、「理解がある」と感じられる職場には、制度と人の両方からのサポートがそろっています。数字だけでは見えない、現場ならではのやさしさが垣間見える結果でした。
『ある程度理解がある』と回答した方の口コミ



上司にうつ病のことを伝えたところ、急ぎでない業務は他のメンバーに振ってくれたり、会議の出席を調整してくれました。また、症状が強い日は在宅勤務に切り替えることを提案してくれ、休憩時間も多めに取れるよう配慮してもらえました。特に、体調が悪くて言葉が出づらかったときも、責めるのではなく「今日は無理せず早めに帰って」と優しく声をかけてもらい、安心して働き続けられました。



メンタル面の問題で体調が崩しがちのところがあり、タスクについてメンタルが落ちてるときは重要性が低いものを優先してくれる。



うつ病になったことで業務内容の負担を少なくしてくれたり、気にかけてくれたりしていました。
でもそれは最初だけだったな…とも感じてきています。



現在32歳で介護施設勤務です。20代の頃から精神的な不調がありました。当時は、軽い息苦しさを感じる程度だったのですが、約2年前に強い息苦しさに加えて、無気力感、悲しくないのに涙が止まらないというような症状が現れ、仕事にも行けなくなってしまいました。調子が良いと思って仕事に行っても数時間したら前述の症状が出てきてしまい、帰社する。というような状況が続いていました。その中で、介護施設勤務で人員も足りていない中、私の状態をみて会社の方から「リモートワーク」を提案していただきました。「落ち着くまでは自宅で仕事してくれていいから、よくなったらまた現場に復帰してね」といっていただき約3ヶ月程リモートワークで仕事をさせていただきました。その間に、病院受診などして現在は服薬で体調も落ち着き、現場復帰できました。



体調の変化や状態に大変理解があり、無理をしないで働ける環境を提供してくれる
寄せられた体験談をみると、職場がうつ病に対して理解を示す行動にはいくつかの共通点がありました。多くの方が挙げたのは、業務量や勤務時間の柔軟な調整や在宅勤務・休職などの制度面での配慮です。症状が悪化した際には急な欠勤や遅刻を許容してくれたり、段階的な復職スケジュールを組んでくれた事例も多く見られました。
また、制度だけでなく上司や同僚からの温かい声かけやフォローが印象的でした。会議や業務を代わってくれる、休憩を促してくれる、話を最後まで聞いてくれる――こうした日常の小さな行動が、当事者にとって大きな安心感につながっています。一方で、部署異動や人の入れ替わりなどで理解が薄れるケースや、一部の同僚からの偏見を感じるケースもあり、職場全体での継続的な理解醸成が必要だといえます。
総じて、うつ病経験者が「理解がある」と感じる職場は、制度面の支えと人間関係の温かさの両方が備わっている傾向があります。数字の結果だけでは見えない、こうした現場での配慮が、働き続けるための大きな支えになっていることがわかります。
『あまり理解がない』と回答した方の口コミ



休職期間などはとても長く理解あると思っていたが、復帰するときのフローや説明など人事の対応が不十分だった。



上司や人事にうつ病のことを伝え、しばらく休職することにはなりましたが、その話し合いの場で上司は
「そんなに大変な思いをしていたのは知らなかった」「業務量を少し減らせば大丈夫では」など軽く考えていることばかり言い、
大ごとにしないようにこちらにも釘を刺してきたので、全く理解がないのだと思った。



なんで鬱病気なんてならんやろと言われて、自分には理解出来んと言われた



人間関係が理由でうつ病と診断されました。看護師をしており病院に伝えたところ「辛いときは休んでよい。」と言われましたが、朝に体調を崩して休みたい旨を伝えても一度仕事場まで来てほしい。と言われることが多かったです。辛くて行けそうにない旨を伝えて後日謝罪しても嫌な顔されることが多かったです。
身体の調子を整えるのも看護師の仕事みたいな感じに言われたので理解はないと思っています。同僚はとても心配してくれましたがトップは理解がなかったので余計に体調を崩すことばかりでした。



任せていただける仕事が増えて、担当業務のキャパシティオーバーが原因でうつ病を発病。4ヶ月の休職を経て復職しました。
休職中は医師の指示で生活リズムを整えることを意識して取り組み、朝に活動が出来るように取り組んでいました。
復職面談を実施した際に、その生活リズムを継続したくてシフト制の職場でしたが、「早番の時間帯で働かせてください」と依頼をしたところ
上長の顔色が変わり「誰がそうしろって言ったの?医者が言ったの?あなたの意思じゃなくて?」と詰められました。
医師からも通常のサラリーマンが働く時間でと言われていたので「医師からの指示です」と答えて3ヶ月はその時間で勤務してました。
その後の面談にて「今の早番のポジションだとあなたが働けるポジションなんてないです。遅番になってください。」と言われてしまい、容認したところ
休職前のように23時近くまで働く毎日が戻ってきてしまい体調を崩すようになってきてしまいました。休み明けに謝罪をすると「あなたがコントロール出来ていないせいだ」と言われるばかりであったため再休職ののち退職をしました。
職場は働ける人を駒としか見ていないし精神疾患についてもなったことないからの一点張りでした。
「あまり理解がない」口コミを読むと、制度や表面的な配慮はあっても、当事者が本当に必要としているサポートや寄り添いが不足しているケースが多いと感じます。
- 業務量や配置の調整が形だけで、根本的な負担は変わらない
- 上司や同僚に知識がなく、根性論や誤解が残っている
- 情報共有不足で、異動や上司交代のたびに配慮が消える
- 腫れ物扱い、もしくは無関心で関わりを避ける態度
こうした状況は、本人に「言っても変わらない」という諦めや孤立感を与え、結果的に症状の悪化や退職につながりやすくなります。
『全く理解がない』と回答した方の口コミ



上司に、寝たら治る、気持ちの問題、休みを多く入れられると困る、本当にしんどいのか、と言われた。



うつ病イコール甘えとか怠けとか思われて、体調が悪くて休む時など、気合いが足りないからだと怒られる。
更に、うつ病だから近づくな、うつ病は詰めないと治らない、甘えるな、優しくするとうつ病が悪化するぞとわざと業務を押し付けたり、休みを入れてくれないと言ったことも多く、辛い。



うつ病になったと総務に相談しましたが、話を聞くだけで対応はなにもなしで、むしろ私の仕事のやり方がよくないみたいに言われました。



鬱病で休養が必要という診断書を職場に提出したところ、本当かお前が医者に書かせたのではないかと言われた。



残業・ストレスが多い会社で心療内科の先生からうつ病の診断書を書いていただいたのですが、上司から「耐性が足りない」とか「仕事に慣れれば自然と回復する」と言われ一蹴されました。



職場の人事に、病院へ行った結果うつ病だったことを伝えても、何の配慮もなかったので理解はないです。
この「あまり理解がない」エピソードを見ると、制度や仕組みよりも、周りの人の言葉や態度が当事者をさらに苦しめていることがわかります。
- 「気の持ちよう」「甘えるな」などの否定的な言葉
- 医師の診断や診断書を信じない、疑う態度
- 本人や医師の希望と真逆の部署異動や仕事の割り当て
- デリケートなことをからかう、腫れ物のように避ける
- 配慮をしないどころか、不利な配置や解雇を迫る
こうした対応は、症状を悪化させたり、孤立感を強めたりします。職場の「理解」は制度よりも日常のちょっとした言葉や行動で決まるものです。
改善のためには、「上司や同僚が病気について正しい知識を持つこと」が大切です。たった一言や態度で、職場の印象は「理解がある」か「ない」かに大きく分かれてしまいます。
まとめ


今回のアンケートから、うつ病を職場に伝えている人の中でも「とても理解がある」「ある程度理解がある」と感じている人は約6割でしたが、残りの4割は「あまり理解がない」「全く理解がない」と答えています。
理解がある職場では、休養や在宅勤務の許可、業務量や勤務時間の調整、日常的な声かけやフォローなど、制度と人の両面で支えられている事例が多く見られました。一方、理解が乏しい職場では、根性論や否定的な発言、医師の診断を軽視する態度、希望と真逆の配置などがあり、症状悪化や孤立感につながっていました。
今回の結果から、「職場の理解」は制度の有無だけでなく、日々の言葉や態度が大きく左右することが明らかです。うつ病経験者が安心して働き続けるためには、正しい知識の共有、本人の希望の尊重、そして小さな気遣いの積み重ねが欠かせません。
法定雇用率ナビの独自アンケート一覧


法定雇用率ナビでは独自のアンケート調査を実施しています。企業側目線、障害者雇用側目線など様々なアンケート調査をしていますので是非参考にしてください。(アンケート一覧はこちら)