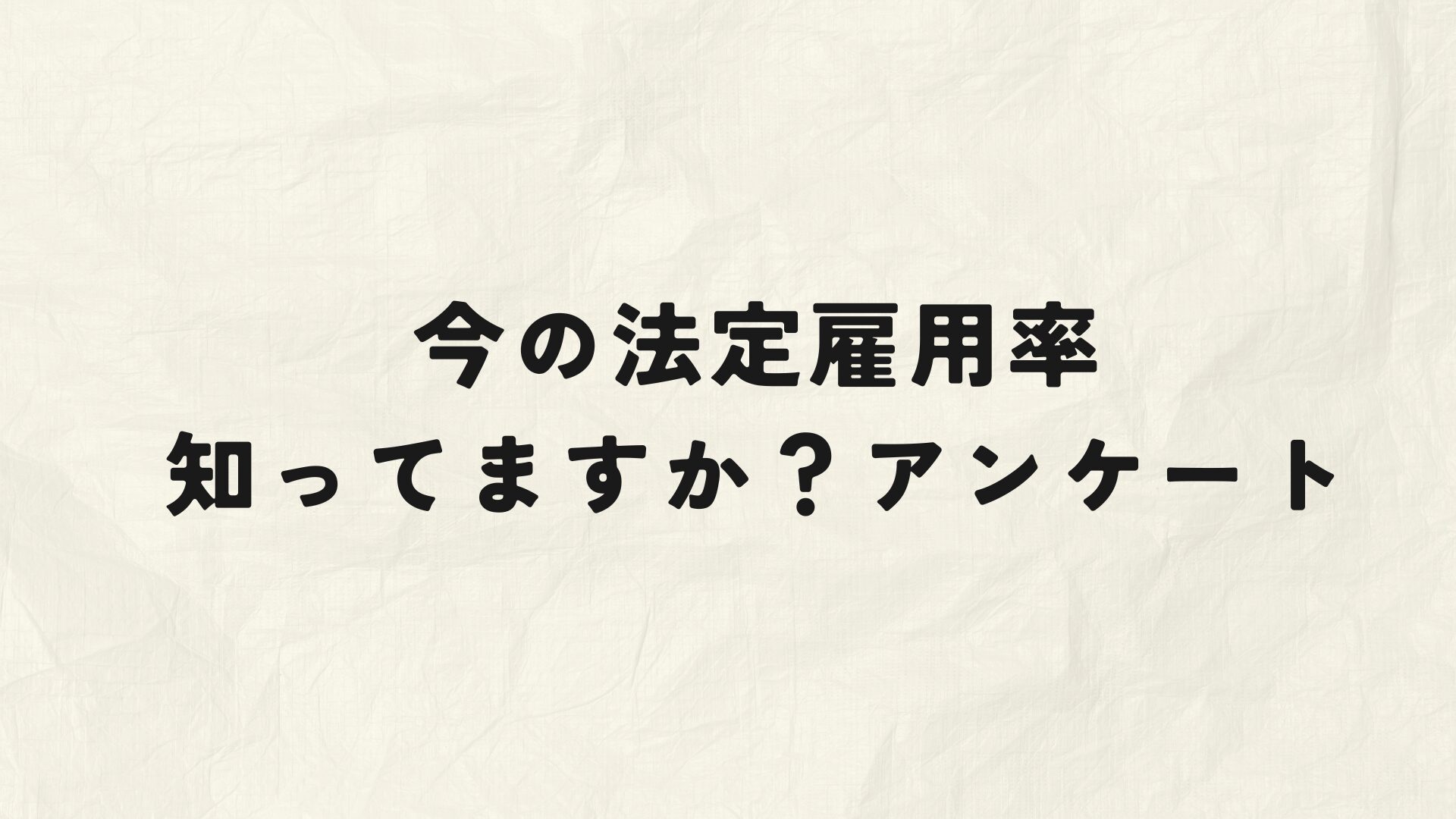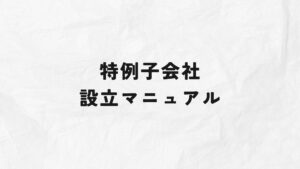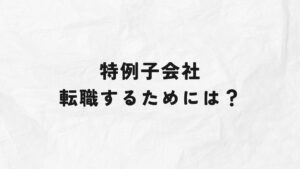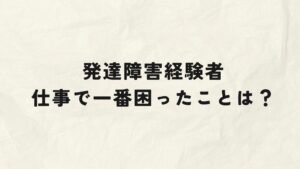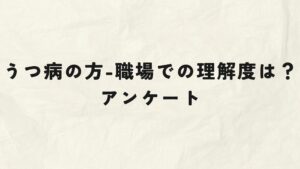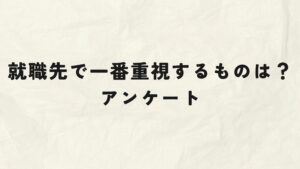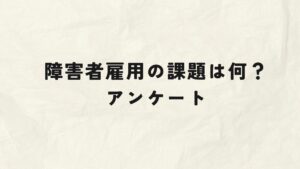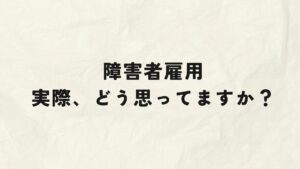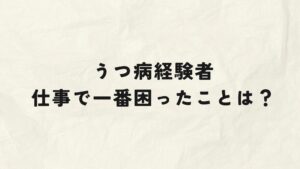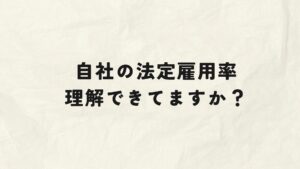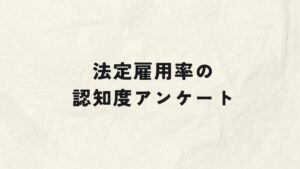「法定雇用率」って聞いたことありますか?
企業に義務付けられている“障害者雇用の割合”のことですが、実際に「今の法定雇用率が何%か」答えられる人はどのくらいいるのでしょうか?
今回は320名の方に聞いてみました。
アンケートの概要
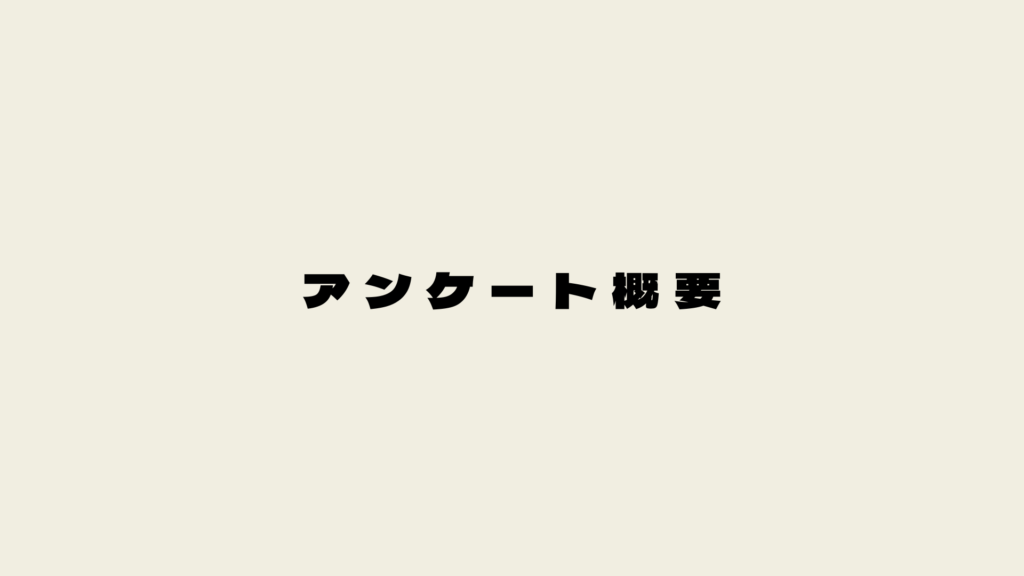
- 調査方法:インターネット調査
- 対象:全国の男女(職業問わず)
- 回答者数:320人
- 調査期間:2025年8月8日~2025年8月8日
質問内容
- ①今の法定雇用率知ってますか?(調べないで直感で答えてください)
- ②2025年7月から何%になるか知ってますか?(調べないで直感で答えてください)
- ③法定雇用率、障害者雇用について思うことがあれば書いてください。(自由記述)
アンケート結果

①今の法定雇用率知ってますか?(調べないで直感で答えてください)

正解率:29.6%(回答:320名)
| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1.80% | 44名 | 13.75% |
| 2.00% | 96名 | 30.00% |
| 2.30% | 56名 | 17.50% |
| 2.50% | 95名 | 29.69% |
| 2.70% | 12名 | 3.75% |
| 3.00% | 17名 | 5.31% |
- 正解は「2.5%」(2024年4月〜)ですが、正しく回答できたのはわずか29.69%でした。
- 最も多かった回答は「2.0%(30.00%)」で、過去の制度の印象が根強く残っていることがわかります。
- 「2.3%」「1.8%」「3.0%」といった選択肢も見られ、法定雇用率の数字そのものが正確に理解されていない傾向が明らかです。
- この結果から、「法定雇用率」という言葉は知っていても、具体的な数値を把握している人は少数派であることが浮き彫りになりました。
制度の名前や存在はなんとなく知っていても、「今、何%なのか?」という情報は意外と知られていないのが現実です。これは、制度の周知や情報発信のあり方に課題があるとも言えるでしょう。
②2025年7月から何%になるか知ってますか?(調べないで直感で答えてください)

正解率:22.5%(回答:320名)
| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2.00% | 24名 | 7.50% |
| 2.30% | 35名 | 10.94% |
| 2.50% | 77名 | 24.06% |
| 2.70% | 72名 | 22.50% |
| 3.00% | 84名 | 26.25% |
| 5.00% | 28名 | 8.75% |
- 来年度(2026年度)からの法定雇用率は「2.7%」へ引き上げ予定ですが、正解を選んだのは22.50%にとどまりました。
- 最も多かった回答は「3.0%(26.25%)」で、「上がることは知っているが正確な数字まではわからない」という傾向が見受けられます。
- 「2.5%(24.06%)」という現行制度の数字をそのまま選んだ人も多く、制度改正の情報が十分には届いていないことが伺えます。
- 「5%」という極端な選択肢も約9%存在し、障害者雇用に関する制度があいまいに理解されている層も一定数いると考えられます。
正解率が2割強という結果は、来年度の制度改定がまだまだ知られていないことを示しています。
法定雇用率、障害者雇用について思うこと(自由記述)

もう1つ、「法定雇用率、障害者雇用について思うことがあれば書いてください。(自由記述)」質問してみました。実際の口コミをみていきましょう。
前向きにとらえている人の口コミ

一定の枠は必要だと思うが、受け入れる企業もただ受け入れるだけでなく、しっかりと働きやすい体制を整えて準備して欲しい。



障がいをもつ方も、働く機会をつくることは大切だと思いますが、障がいをもつ方、その方と一緒にはたらくスタッフ達、双方のフォローが必要だと考えます。



障害者雇用は社会の多様性を尊重し、誰もが働きやすい環境を作るために重要だと思います。
ただし、仕事の内容や能力に応じた公正な評価や待遇も必要であり、一律の給与ではなく適切な役割分担と報酬体系が望ましいと考えます。
お互いが尊重される職場環境が理想です。



一定の枠は必要だと思うが、受け入れる企業もただ受け入れるだけでなく、しっかりと働きやすい体制を整えて準備して欲しい。



雇用率があがるのは良いことだと思うが、雇う側の負担、雇われる側の負担のどちらも軽減され、無理なく継続できるような政府の補助や考え方が広まればよいと思う。



一定の枠は必要だと思うが、受け入れる企業もただ受け入れるだけでなく、しっかりと働きやすい体制を整えて準備して欲しい。
前向きな口コミに対して
今回のアンケートでは、「障害者雇用をもっと進めてほしい」「雇用率が上がることは良いこと」といった前向きな声も数多く寄せられました
- 「個人的にはどんどん人を採用してほしい」
- 「障害があるなしにかかわらず、誰もが活躍できる社会が実現できれば」
- 「法定雇用率がきちんと定められているのは良いと思った」
など、制度そのものを肯定し、さらに広げていくべきという考えを持っている方が一定数いることがわかりました。
こうした意見は、企業や制度設計者にとっても大きな励みになる声であり、同時に「働きたい」という意志を持つ障害のある方々にとっても社会的な支援の広がりを感じられる貴重なメッセージです。
課題あるのでは?と感じている人の口コミ



一定の枠は必要だと思うが、受け入れる企業もただ受け入れるだけでなく、しっかりと働きやすい体制を整えて準備して欲しい。



障がいをもつ方も、働く機会をつくることは大切だと思いますが、障がいをもつ方、その方と一緒にはたらくスタッフ達、双方のフォローが必要だと考えます。



障害者雇用は社会の多様性を尊重し、誰もが働きやすい環境を作るために重要だと思います。
ただし、仕事の内容や能力に応じた公正な評価や待遇も必要であり、一律の給与ではなく適切な役割分担と報酬体系が望ましいと考えます。お互いが尊重される職場環境が理想です。



雇用率があがるのは良いことだと思うが、雇う側の負担、雇われる側の負担のどちらも軽減され、無理なく継続できるような政府の補助や考え方が広まればよいと思う。



障害者の雇用人数が増えることは働ける場面の少ない障碍者にとって良い事だと思います。人に頼ることの多い障害者は社会又人に貢献できることに喜びを感じる人が多いと思います。
その機会が増えることは健常者との関係が良くなる機会も増える事と思います。
懸念されるのは、企業側の体裁のために数合わせで雇われ何もホローされず飼い殺しのような状況にならない様に注意をしてもらうのは大切だと思います。
課題アリの口コミに対対して
アンケートの中には、「障害者雇用は重要」としながらも、現場で直面する課題や運用の難しさに言及する声も多く見られました。
- 「一定の枠は必要だと思うが、企業側も体制を整えてほしい」
- 「働く機会は大切だが、双方のフォローが必要」
- 「制度は良いが、飼い殺しのような雇用にならないよう注意すべき」
これらの口コミに共通するのは、制度そのものを否定していないという点です。むしろ、制度が本来の目的を果たすために、「環境整備」「教育」「支援体制の充実」などが欠かせないという建設的な視点が込められています。
法定雇用率という仕組みを“数字の達成”に終わらせないためにも、現場から上がるこうした声にこそ、社会や企業が耳を傾ける必要があると感じます。
ネガティブにとらえている人の口コミ



精神疾患になったとき、会社から障がい手帳の取得をお願いされた。もちろん、非課税とか交通運賃の割引率もあったが、法定雇用率のために障がい者にさせられたような気もしている。



障害者雇用と聞くと身体障害者のイメージがあるが精神系の障害者雇用のイメージはない
障害雇用はどこか、健常者の一人一人が我慢しているように思える。やはり大多数の人間は、障害者に対して迷惑だというような感情を持っているのでは?



雇用率が決まっていたら、それに満たないとペナルティがあるのだろうかと思った。それでは逆に、企業にとっても働く障害者にとっても良くない状況になってしまわないのだろうかと思った。



精神障害者の方はすぐ辞めるケースもあり、コミュニケーションが苦手な方には受電業務などもすべて免除し、大変簡単な作業をしていただいておりますので、上層部は数値を見ていい気になっていますが、現場は正直慈善事業をやらされている状態です。



雇用率が上がるほど、そうでない方々の雇用機会は少なくなり、すでに雇われている障碍者でない方々の負担は増加してしまうので複雑だなと思います。
制度に対するネガティブな意見にも耳を傾ける
アンケートには、「制度の理想」と「現場の現実」のギャップを指摘する厳しい声や疑問の声も少なからず寄せられました。
- 「法定雇用率のために障がい者にさせられたような気がする」
- 「現場は慈善事業をやらされているような状態」
- 「雇用率が上がると、他の人の雇用機会や負担に影響が出るのでは」
こうした声は一見ネガティブに映るかもしれませんが、制度の改善に向けた“リアルな課題提起”でもあります。
実際、制度が数字先行で進んでしまったり、企業が受け入れ体制を整えられていないまま雇用が進むことで、結果として障害者本人も、周囲の従業員も苦しい思いをしてしまうケースがあるのは事実です。
だからこそ、こうした「現場の声」から目を背けず、制度の理念と現実の橋渡しをしていくことが、これからの社会に求められると感じます。
制度運用や現場のリアルな課題に対しての口コミ



自分の職場は障害者を雇用するも、育成は現場に丸投げ。専門的な知識もない中、接客の部署にアスペや統合失調症といった、接客に全く向かない人を放り込まれてあとはヨロシク状態です。
せめて障害者のいる部署には1人、ケースワーカー的な専門家を配属して、彼らにどう伝えたらわかってもらえるのか、間をとりもってもらう役が必要じゃないかと思います。



数字上の達成が目的化されてしまっている現状に、少し違和感を覚えます。企業が義務として雇用することは制度上必要な仕組みだと思いますが、本来の目的は、誰もが自分らしく働ける社会の実現であるはずだと思ってしまいますが。



以前勤めていた企業(企業全体従業員は150名ほど)で3名の障害者雇用者がいました。お願いした仕事ができる方もいれば、できない方もいて、ルールを守れなかったり、見本通りにできなかったり、時間がかかったり、、、。
不良を出さないために二重の検品が必要となったり、やり直しになったり、正直なところ関連部署にいた者としては仕事が増えてしまったり、扱いにくい、内職に出した方が早くて安い、という現場の声もあり、関連部署内では苦労やトラブルが多かったです。
障碍者雇用はとてもいい制度のように思いますが、職種によっては扱いがとても難しく、法定雇用率が上がった場合、企業だけではなく一緒に働く人の強力・理解が必要不可欠だと感じます。



自分自身精神障害者ですが枠があっても入れないような壁を感じます。



以前、障害者採用に携わっていたことがあります。企業側は法定雇用率達成のため必死に採用活動を行いますが、実際に活躍が望める方ばかりでなく、企業側の期待とスキルのミスマッチで採用後にメンタル不調に陥る方もいました。何のための施策なのか、より納得出来る仕組みになればいいなと思っています。
制度をより良くする“ヒント”は、現場のリアルにある
アンケートの中には、前向きでもネガティブでもなく、制度の運用に関わる課題や気づきを冷静かつ具体的に伝えてくれる声も多数ありました。
- 「育成は現場任せで、専門的な支援が足りない」
- 「職種によっては扱いが難しく、周囲の理解が不可欠」
- 「スキルと役割のミスマッチが原因でメンタル不調になることもある」
これらの声は、現場で実際に障害者雇用に関わった方々だからこそ気づけたリアルな課題であり、制度の理想と実態との間にある“すき間”を浮き彫りにしています。
法定雇用率という仕組みが、単なる義務や数値の達成に終わらず、障害のある方が本当に働きやすい環境づくりに繋がるためには、こうした現場の声を丁寧に拾い上げ、制度側が柔軟にアップデートしていく必要があります。
制度は知っていても「数字」は覚えていない人が多数
- 「今の法定雇用率(2.5%)」の正答率は29.69%。
- 「来年度の法定雇用率(2.7%)」の正解率は22.50%。
- 多くの人が法定雇用率の存在は知っていても、具体的な数字までは把握していない
企業の人事担当者や管理職の方はもちろん、これから就職を目指す学生や求職者も、この機会に制度を正しく理解しておくことが大切です。
またアンケートの中には、前向きでもネガティブでもなく、制度の運用に関わる課題や気づきを冷静かつ具体的に伝えてくれる声も多数ありました。
- 「育成は現場任せで、専門的な支援が足りない」
- 「職種によっては扱いが難しく、周囲の理解が不可欠」
- 「スキルと役割のミスマッチが原因でメンタル不調になることもある」
これらの声は、現場で実際に障害者雇用に関わった方々だからこそ気づけたリアルな課題であり、制度の理想と実態との間にある“すき間”を浮き彫りにしています。
法定雇用率という仕組みが、単なる義務や数値の達成に終わらず、障害のある方が本当に働きやすい環境づくりに繋がるためには、こうした現場の声を丁寧に拾い上げ、制度側が柔軟にアップデートしていく必要があります。
法定雇用率ナビの独自アンケート一覧


法定雇用率ナビでは独自のアンケート調査を実施しています。企業側目線、障害者雇用側目線など様々なアンケート調査をしていますので是非参考にしてください。(アンケート一覧はこちら)