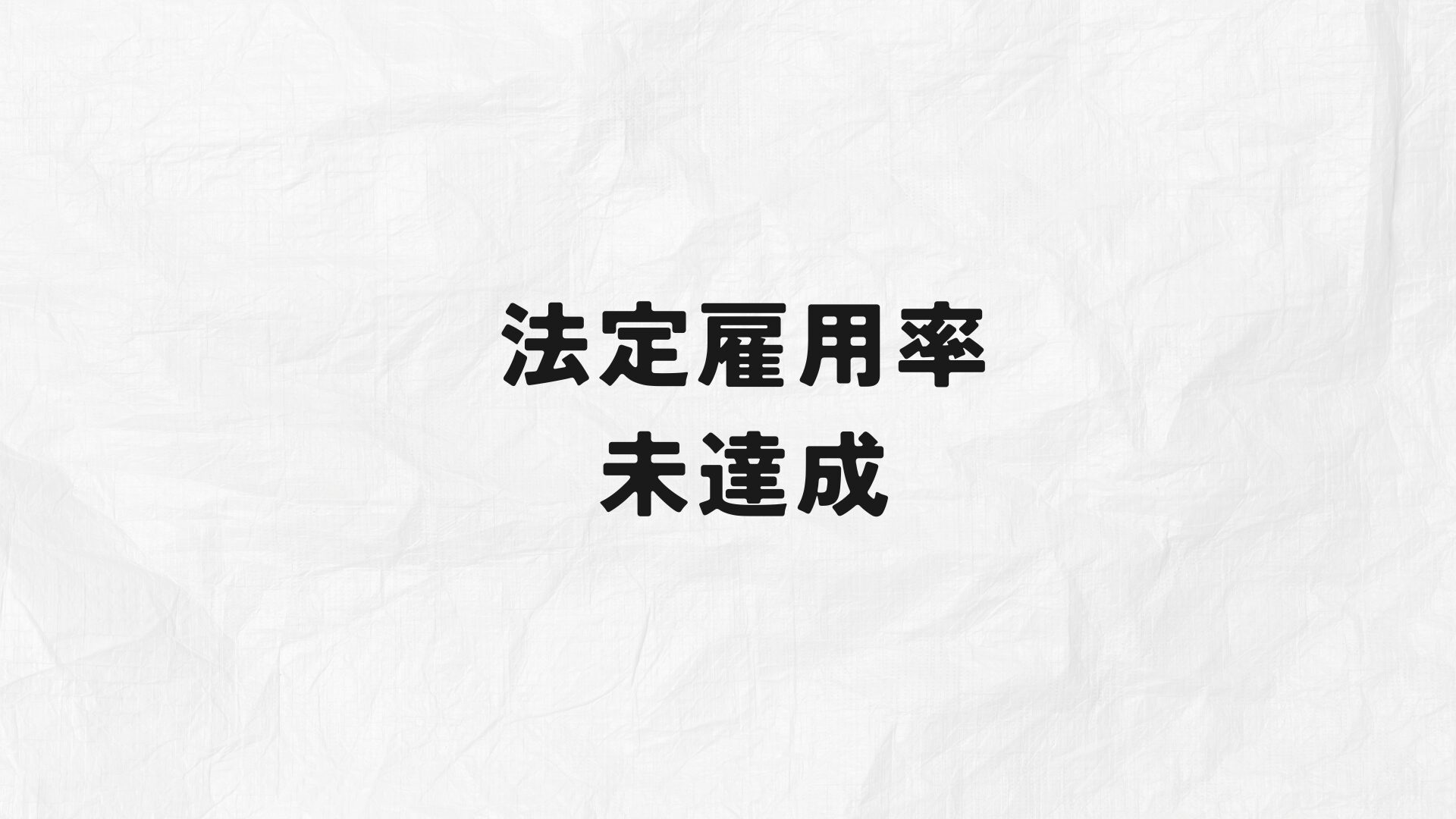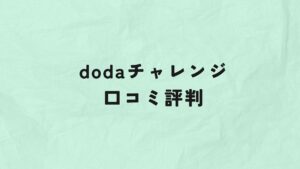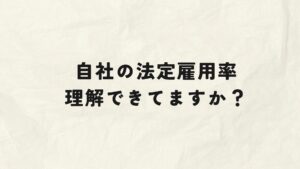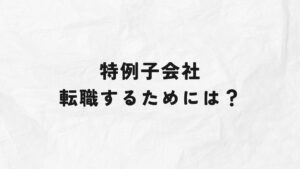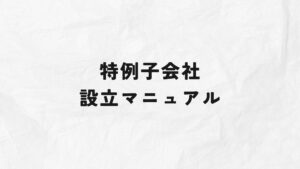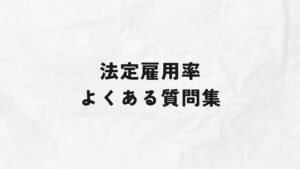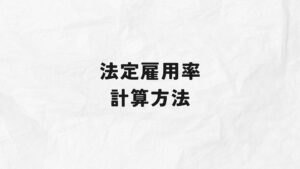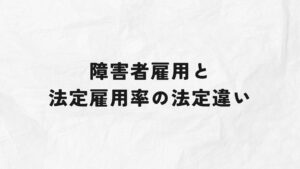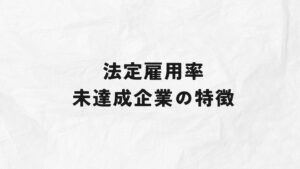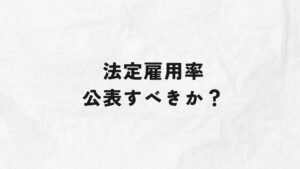「法定雇用率って達成しなければいけないの?」「うちは未達成だけど大丈夫なの?」「罰金があるって聞いたけど本当?いくらなの?」と意外に理解していない企業担当者も多くいます。
ここで「法定雇用率 未達成」の現状や影響、対策までをわかりやすく解説します。初心者でも理解できるよう、具体例を交えながら丁寧に紹介していきますので是非参考にしてくださいね。
法定雇用率とは?
法定雇用率の基本的な定義
法定雇用率とは、企業に対して「一定割合の障害者を雇用しなければならない」と法律で定められている割合のことです。この制度は、障害のある方も社会の一員として働きやすい環境をつくることを目的としています。
2025年7月時点では、従業員43.5人以上の企業は、従業員のうち2.5%以上を障害者として雇用することが義務づけられています。例えば、従業員が100人いる企業であれば、少なくとも3人の障害者を雇用していなければなりません。(2.5人などの端数は切り上げられるため3人となる。)
1000人の会社は25人、10000人の会社は250人の障害者雇用をしなければいけません。
なお、この割合(2.5%)は「法定雇用率」として厚生労働省により決められており、すべての企業に同じ基準が適用されます(業種や地域による例外はありません)。
なぜ法定雇用率が定められているのか
日本では、障害のある方の就職率が依然として低く、希望しても働く場所が見つからないという課題があります。そこで、企業が積極的に障害者の雇用機会を確保するよう、一定の割合を義務づけたのがこの「法定雇用率制度」です。
この制度の目的は、単なる数字合わせではなく、障害のある方の自立支援と社会参加の促進です。働くことを通じて得られる収入ややりがいは、障害の有無に関係なく、誰にとっても大切なものですよね。
また、企業にとっても障害者雇用は社会的責任を果たすだけでなく、ダイバーシティ(多様性)推進や企業価値の向上につながるという側面もあります。
2024年〜2026年の変更点(2.7%への推移)
これまでの法定雇用率は2.3% → 2.5%へ段階的に引き上げられ、さらに2026年には2.7%へと引き上げられる予定です。
- 2024年4月:2.5%(現在)
- 2026年7月:2.7%
つまり、企業は今後さらに多くの障害者を雇用する必要があります。
従業員100人の会社で考えると、今は2.5人(実質3人)が必要ですが、2026年には2.7人(実質3人、場合によっては4人)になります。
このように法定雇用率は年々引き上げられており、早めの準備がカギです。特に、採用や社内体制が整っていない企業にとっては、今のうちから対策を始めておくことが重要です。障害者の推移もみておきましょう。
障害者数の推移
障害者手帳の交付者数の増加傾向
日本における障害者数は年々増加傾向にあります。厚生労働省の「障害者白書」や「福祉行政報告例」によると、障害者手帳の交付を受けている人の数は、以下のように推移しています。
- 2011年:約743万人
- 2016年:約874万人
- 2021年:約967万人
この10年で200万人以上増えており、2025年には1,000万人を超えているとも言われています。これは高齢化や精神障害の認知拡大、診断制度の整備などが影響しています。
種類別に見る障害者の構成
障害者は主に以下の3つに分けられ、それぞれ就労の支援や雇用の状況にも違いがあります。
- 身体障害者:約436万人(約45%)
- 知的障害者:約110万人(約11%)
- 精神障害者:約420万人(約43%)
特に増加しているのが精神障害者です。うつ病や統合失調症などの精神疾患による障害者手帳の取得者が大きく伸びており、企業の受け入れ体制強化が求められています。
今までは言葉の定義がされていなかった障害名も今後も増えていく可能性はありますのでまだ増えると考えられています。
雇用の場における障害者数の増加
企業などで働いている障害者の数も年々増えています。以下は、民間企業における障害者の雇用者数の推移です。
- 2013年:約43万人
- 2018年:約53万人
- 2023年:約63万人(過去最多)
特に近年は精神障害者の雇用が伸びており、全体の20%以上を占めるようになっています。障害者雇用の支援制度や就労移行支援の普及が背景にありますし、受け入れる企業が増えてきたり、体制が整ってきているともいえます。
障害者数の増加が企業に与える意味
障害者数の増加は「企業が受け入れるべき対象が広がっている」ことを意味します。かつては身体障害者の雇用が中心でしたが、今は精神障害や発達障害を持つ人をどう受け入れるかが課題となっています。
企業にとっては、法定雇用率を達成するうえで対象者の幅が広がった一方で、配慮の仕方や就労サポートの在り方を工夫する必要が出てきました。
今後さらに法定雇用率が引き上げられることを見据えると、障害者雇用のあり方を根本から見直すことが重要になってきています。
法定雇用率 未達成の現状
達成企業の割合と推移(最新データ)
法定雇用率を達成している企業の割合は、少しずつ増えてはいるものの、依然として全体の約半数が未達成というのが現状です。
厚生労働省の「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業全体での達成率は48.3%にとどまっています。これは、企業の約半数が法定雇用率2.5%をクリアできていないことを示しています。
一方、障害者雇用者数自体は増加傾向にあり、2023年には過去最多の約63万人が民間企業で働いています。このことから、障害者を雇用しようとする動きは活発化しているものの、法定水準に届いていない企業が多い状況が読み取れます。
業種別・企業規模別に見た達成率の傾向
法定雇用率の達成率には、業種や企業規模によって明確な差があります。たとえば、以下のような傾向があります。
- 達成率が高い業種:製造業、金融・保険業、公務・公共関連
- 達成率が低い業種:飲食業、建設業、運輸業、小売業
サービス業や小売業などでは、現場業務が中心で「障害者が働ける仕事を用意しにくい」と感じている企業が多く、未達成率が高い傾向にあります。
また、企業規模が大きいほど達成率が高いという傾向もあります。従業員数が1,000人を超える大企業では、70〜80%が達成していますが、中小企業では40%未満のケースも珍しくありません。
中小企業は「採用リソースの不足」や「受け入れ体制の未整備」などの理由から、障害者雇用が進みにくい現実があります。
社会的な見え方もあります。有名な大企業が障害者雇用を達成していないと「あそこは障害者雇用、ちゃんとでいていないんだ」と思われてしまし、企業イメージや採用に直結するともいわれています。
よくある「未達成企業」の特徴
法定雇用率を達成できていない企業には、いくつか共通する傾向があります。
- 障害者の受け入れ経験がなく、何から始めていいか分からない
- 業務の切り出し(業務の分担・調整)がされていない
- 経営層が障害者雇用に関心を持っていない
- 職場の理解や支援体制が整っていない
- 「いい人がいれば雇いたい」という受け身の採用スタンス
これらの要因が重なり、結果として「求人を出しても応募がない」「採用しても定着しない」という問題につながってしまいます。逆にいえば、受け入れの仕組みや考え方を少し変えるだけで達成できる可能性があるということでもあります。
また人事などの担当者が障害について詳しくないということも理由に挙げられます。大手の場合は障害者雇用に強いコンサルを入れるなど費用をかけて解決に向かうこともありますが、中小企業はそこまでのコストも人手もないために、結果的に「罰則を払った方が安くすむ」という考えの企業も多くあるのが事実です。
法定雇用率 未達成によるペナルティ
障害者雇用納付金制度とは
法定雇用率を満たしていない企業は、「障害者雇用納付金」という形で金銭的なペナルティを支払う必要があります。これは、障害者を雇用していない分の社会的責任を、金銭で一部肩代わりする制度です。
対象となるのは、常用雇用労働者が101人以上いる企業です。100人以下の中小企業は原則として納付義務はありませんが、助成金の対象にもなりにくいため、結果的に対応が遅れる傾向があります。
未達成の場合に発生する金額とその算出方法
障害者雇用納付金は、1人不足するごとに月額5万円が課されます(年額60万円)。例として、2人分足りていない企業の場合は、年間120万円の納付金を負担することになります。
算出方法のイメージ:
- 基準雇用障害者数:企業規模 × 法定雇用率(例:200人 × 2.5% = 5人)
- 実際の雇用者数:2人
- 不足数:5人 − 2人 = 3人
- 納付金:3人 × 5万円 × 12ヶ月 = 年間180万円
なお、この納付金は雇用率を1人でも下回っていれば課されるため、「ほぼ達成しているから大丈夫」と油断するのは危険です。
実際の罰則の総額はいくらぐらい?
法定雇用率を達成できていない企業が支払っている障害者雇用納付金の総額は、年々増加傾向にあります。
厚生労働省が発表している「障害者雇用状況報告(令和5年)」によると、2022年度における納付金総額は約538億円にも上りました。これは、全国の企業が「障害者を雇用できていないことで発生した罰則の合計額」と言い換えることができます。
このうち多くを占めるのは、大企業や事業所数の多い法人です。企業ごとに見ると、年間数千万円単位の納付金を支払っている例もあります。例えば、
- 従業員数:2,000人
- 法定雇用率:2.5% → 必要雇用数50人
- 実際の雇用数:30人 → 不足数20人
- 納付金:20人 × 5万円 × 12ヶ月 = 年間1,200万円
上記の企業は年間に1200万円の罰則を支払わなければいけません。こうした企業が複数存在しているため、納付金制度全体で見ると数百億円規模の「見えないコスト」が発生していることがわかります。
逆に言えば、これだけの金額があれば、障害者雇用のための環境整備や専門人材の採用に充てた方が、企業の長期的利益につながるという見方もできます。
行政指導・企業名公表のリスク
納付金の負担だけでなく、継続的に未達成のままでいると、厚生労働省から行政指導を受ける可能性もあります。
改善が見られない場合には、企業名が公表されることもあります。これは「障害者雇用に非協力的な企業」と見なされたことを社会に知られるという、非常に大きなリスクです。
実際に、過去には大手企業が名指しで公表された事例もあり、報道やSNSで話題になることもありました。こうした情報は、取引先・採用応募者・株主などステークホルダーの信頼低下につながる可能性があります。
現在、法定雇用率の公開義務はありませんが、今後義務化されることは十二分に考えられます。そうなると未達成企業がすぐにわかってしまうために今のうちから準備をしておくのが賢いやり方といえます。
社内外に与えるイメージダウンの影響
法定雇用率を達成していないという事実は、企業イメージにも少なからず影響を及ぼします。
特に近年では、SDGs・ESG・ダイバーシティ経営といったキーワードが注目されており、「障害者雇用への取り組み」は企業の社会的評価に直結します。未達成状態が続くことで、以下のようなマイナス印象を与えるリスクがあります。
- 「社会貢献意識が低い企業だ」と見なされる
- 「時代の変化に対応していない」と受け取られる
- 採用活動で応募者の離脱が増える
- 社内の多様性・包摂性に欠けると認識される
これは外部だけでなく、社内のモチベーションや離職率にも影響を与える可能性があります。つまり、法定雇用率の未達成は、企業ブランドや組織力にも悪影響を及ぼしかねないのです。
法定雇用率を達成できない理由とは?
採用活動の難航
法定雇用率を達成できない理由の中で最も多く聞かれるのが、「障害者の応募自体が少ない」という採用活動の難しさです。特に中小企業や地方の企業では、そもそも応募者が集まらず、求人票を出しても「ゼロ件」が続くことも珍しくありません。
- 企業の知名度が低く、応募の母数が少ない
- 求人情報に「配慮内容」や「サポート体制」が書かれておらず、不安を与えている
- 障害者側も「自分にできる仕事があるか不安」と感じている
つまり、「来ない」のではなく、「来たくても来れない」「安心して応募できない」状態を企業が無意識に作ってしまっているケースが多いのです。
社内受け入れ体制の未整備
仮に採用できたとしても、受け入れ体制が整っていなければ定着しません。これは障害者雇用における“採用後の落とし穴”です。
- 受け入れる部署や上司がどう接していいか分からない
- 相談窓口がなく、本人が孤立してしまう
- 業務の調整や配慮が現場任せになっている
特別な設備を用意する必要はない場合が多いですが、「人の理解」と「仕組み」がないと、結果的に早期離職につながってしまいます。
むしろ、大変なのは採用前よりも採用後(いかに定着させるか)です。障害者雇用の方を一般職の方たちと同じように対応するとストレスに感じてしまい長く続かないケースもあり、いかに受け入れ態勢をしっかり準備するかが重要になってきます。
業務のマッチング不足
「障害者にお願いできる仕事がない」と感じている企業も少なくありません。しかしこれは、業務の切り出しや整理が不十分なだけというケースも多いです。たとえば、以下のような業務はマッチしやすいと言われています。
- 事務補助(データ入力、書類整理)
- バックヤード業務(備品管理、清掃など)
- 専門スキルが活かせるIT系(画像編集、簡単なコーディング)
「今ある仕事を少し分ける」意識で考えると、意外と多くの業務が障害者雇用に適していることに気づく企業も多くあります。
とある企業は「ルーティン業務」を切り出し、障害者雇用の方たちにお願いをしました。そうしたら、以前までのスピードの3倍で処理がでいるようになったそうです。障害者雇用の方はルーティン業務や決まった業務を得意としている方が多いために、一般社員が面倒だと思う作業を依頼することもできます。
経営層の関心の低さ
法定雇用率の未達成は、現場だけの問題ではなく、経営層の姿勢にも大きく関係しています。
- 納付金を払えばいいという考えにとどまっている
- 法定雇用率は「コスト」だと捉えている
- CSRやESGの重要性を十分に理解していない
一方で、経営層が主導して障害者雇用に取り組んでいる企業は、定着率も高く、社内の多様性推進が進んでいる傾向があります。つまり、障害者雇用は「人事部の仕事」ではなく、経営課題として本気で取り組むべきテーマであるということです。
今は会社の意識の低さが未達成企業が多くなってしまう大きな要因になっているといわれています。特に超大手企業はブランドイメージがあるのである程度は着手していますが、中小企業は経営者が危機意識をもっていない限りは達成するのは難しいといえます。
今後は、経営者がいかに「障害者雇用に真剣に取り組むか」ここが本当に重要になってくるでしょう。
未達成企業がとるべき対応策
短期的な対応策
法定雇用率を満たせていない企業が、まず取り組みやすいのが短期的に実行可能な外部連携や採用支援です。特に以下の2つの取り組みは、成果が出やすく導入のハードルも低いためおすすめです。
障害者雇用コンサルの活用
障害者雇用に特化したコンサルタントや支援団体の力を借りることで、「何から始めたら良いか分からない」状態を解消できます。具体的には、以下のようなサポートが受けられます。
- 雇用対象者の紹介(採用支援)
- 配慮事項や職場環境のアドバイス
- 定着支援やフォローアップ体制の構築
自社にノウハウがなくても、外部の専門家と伴走する形でスムーズに雇用体制を作ることが可能です。初めての雇用を成功させるためにも、早い段階での相談をおすすめします。
就労移行支援事業所との連携
全国にある「就労移行支援事業所」は、障害のある方が一般企業で働くためのスキルや社会性を学ぶ場です。ここで訓練を受けている利用者の中には、企業就職を目指して積極的に就職活動をしている方も多くいます。
事業所と直接連携することで:
- 事業所からの人材紹介
- 見学や実習の受け入れ
- 採用後の継続支援(定着支援)
といったサポートを受けることができ、ミスマッチの少ない採用が実現します。地元の事業所を探し、気軽に相談してみるのも大きな一歩です。
中長期的な体制整備
障害者雇用を「一時的な対応」に終わらせず、企業の仕組みとして継続・拡大していくためには中長期的な体制づくりが欠かせません。
社内教育・マニュアル整備
現場社員が障害者との接し方や配慮事項に戸惑う場面は少なくありません。そのため、「社員教育」や「障害者雇用マニュアル」の整備が重要で、以下のような教育が有効と考えられています。
- 障害の基礎知識(身体・知的・精神の違い)
- 対応の基本(言葉かけ・業務指示・困りごとへの気づき)
- 社内相談窓口や支援担当者の設置
また、トラブルが起きた時や体調に変化があった時に対応できるようなフローマニュアルや対応事例集も、実務上とても役立ちます。
業務の切り出し・可視化
「どんな仕事をお願いすればいいか分からない」という声は多いですが、既存業務を細分化・可視化することで対応可能な業務は見えてきます。業務の切り出しを進めるためのポイントは以下の通りです。
- 繰り返し発生する単純作業をリストアップする
- マニュアル化できる業務を選定する
- パソコンや軽作業など、特定スキルが不要な業務から始める
一度業務を切り出せば、今後の採用にも応用が利き、定型的な雇用がしやすくなります。また、特例子会社の設立や業務委託といった展開も視野に入るようになります。
実際に未達成から改善した企業事例
ここでは、法定雇用率を満たせていなかった企業が、実際にどのような取り組みを行い、改善へとつなげていったのかをご紹介します。業種や企業規模ごとの工夫が詰まった事例は、あなたの会社のヒントになるはずです。
事例①:中小製造業の取り組み
従業員120名の部品加工会社(地方・家族経営)では、長年法定雇用率を下回り、年額60万円の納付金を支払い続けていました。人手不足と「現場作業に障害者は難しいだろう」という固定観念が障壁となっていました。
しかし、地元の就労移行支援事業所と連携し、「軽作業の一部を切り出して委託実習」を実施。利用者と現場の相性が良かったことから採用に至りました。
その後、担当社員が支援員と協力しながら「工具の準備」「部品検品」「伝票整理」などを段階的に引き継ぎ、雇用から1年で定着・評価される戦力へと成長。
結果として現在は3名の障害者を雇用し、法定雇用率をクリア。納付金の支払いもなくなり、助成金も受給できるようになりました。
事例②:IT企業の在宅雇用活用例
従業員300名規模のWeb制作会社では、社内の人材不足もあり障害者雇用の採用に踏み切れない状態が続いていました。「コミュニケーションが不安」「体調変動に対応できるか心配」といった課題がありました。
そこで同社は、在宅での障害者雇用に挑戦。精神障害者保健福祉手帳を持つ人材に、週20時間のテレワークで「画像のトリミング」「Excelデータ処理」を依頼しました。
業務はマニュアル化されており、チャットでのやりとり中心とすることで、体調に配慮しながらスムーズに業務を進行。採用から半年後には、定着と成果を見て2名を追加雇用。現在は法定雇用率を安定的に達成しています。
事例③:流通業の社内ジョブコーチ制度
全国に店舗を持つ流通業(従業員800名)では、以前は障害者の早期離職が多く、雇用数が増えても法定雇用率を維持できませんでした。
そこで同社は、「社内ジョブコーチ制度」を導入。店舗スタッフの中から希望者を募り、障害者雇用サポートの研修を実施。障害者社員が配属された店舗には、必ずジョブコーチ役の社員を1人置く体制を整備しました。
この制度により、「ちょっと困った」「声をかけたいけど迷う」といった場面にすぐ対応できるようになり、離職率が大幅に改善。
結果として、数年にわたり定着率90%超を維持しながら、毎年着実に雇用数を拡大。グループ全体でも安定的に法定雇用率を達成しています。
法定雇用率を達成するメリット
「法定雇用率は守らないとペナルティがあるから仕方なく…」といったネガティブな動機になりがちですが、実は達成することで得られるメリットも多く存在します。ここでは、法定雇用率を達成した企業が得られる3つの主要な利点についてご紹介します。
助成金や報奨金の受給可能性
法定雇用率を達成している、または積極的に障害者雇用を行っている企業には、各種助成金や報奨金が支給される可能性があります。代表的な制度には以下のようなものがあります。
- 障害者雇用調整金:一定の雇用を超えて障害者を雇用している企業に支給
- 障害者雇用報奨金:特に高い水準の雇用を継続している企業に支給
- 特定求職者雇用開発助成金:障害者を新たに雇用した場合の費用補助
精神障害者や重度身体障害者を新規採用した場合、最大240万円程度(1人あたり)の助成を受けられるケースもあります。
納付金という「支払い」を回避するだけでなく、支援金という「収入」を得られる可能性があるのは、大きな財務上のメリットです。
企業イメージやESG評価の向上
近年、投資家や求職者が企業を評価する際に重視しているのが、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGsの観点です。障害者雇用の取り組みは「社会性(Social)」に直結しており、次のような評価向上につながります。
- 採用ブランディングの強化:多様性のある職場を求める若手人材に好印象
- 取引先・行政からの信頼性向上:コンプライアンス重視の姿勢をアピール
- IR(投資家向け情報)でのアピール材料:ESGスコアやレポートに記載可能
「障害者雇用に取り組んでいる企業です」と自信を持って言えることが、企業ブランドの信頼性を高める武器になります。
多様な人材による組織の活性化
障害者を雇用することで、職場に新たな視点やコミュニケーションが生まれ、組織全体の風土が変わるという効果も見逃せません。
- 社員が自然と「お互いを気にかける」ようになった
- 職場の雰囲気が穏やかになり、定着率が向上した
- 業務マニュアルや教育制度の見直しが進み、全体の効率がアップ
障害者雇用は、単に「雇って終わり」ではありません。そのプロセスで生まれる対話・配慮・仕組みづくりは、健常者の働きやすさにも直結します結果として、社内の多様性と心理的安全性が高まり、離職率の低下や業績向上に貢献するケースも多数報告されています。
障害者雇用に対する誤解と正しい理解
障害者雇用に対しては、まだまだ誤解や不安が根強く残っています。ここでは、企業担当者の方からよく聞かれる声を3つ取り上げ、正しい理解につながる情報をわかりやすく解説します。
「特別扱いしなければいけない?」
障害者を雇うと「毎日声をかけないといけないのでは?」「ずっと気を遣い続けなければいけないのでは?」という不安を感じる方もいます。
しかし、実際は必要以上の“特別扱い”は不要です。大切なのは、「一人ひとりに合わせた適切な配慮」を行うこと。
それは障害の有無にかかわらず、すべての社員にとっても必要な配慮のはずです。
- 業務手順を文書化して伝える
- 静かな作業環境を確保する
- 体調変化があったときに相談できる窓口を用意する
これらは特別なことではなく、「誰もが働きやすい環境づくり」の一環です。結果的に職場全体のコミュニケーションや生産性が向上することも多くあります。
「仕事が限定される?」
「障害があると、できる仕事が少ないのでは?」と思われることもありますが、それは大きな誤解です。確かに配慮が必要な場面はありますが、実際には多様な業務で活躍されている方がたくさんいます。
- 事務職(データ入力、備品管理、文書作成)
- IT系(プログラミング、Webデザイン、画像処理)
- 販売・サービス(バックヤード、商品の整理・管理)
- 製造業(検品、梱包、部品整理)
このような定型業務やルーティン業務は障害者雇用の方と相性がよく、一般社員よりもスピーディーに処理できることも多々あります。
また、精神・発達障害などの“見えにくい障害”を持つ方の能力を活かす事例も増えてきています。仕事の選択肢は思っているよりも広く、マッチング次第で戦力として活躍することが可能です。
「長く続けてもらえない?」
「障害があるとすぐに辞めてしまうのでは…」という声も聞かれますが、これも環境と対応次第で大きく変わります。
実際、厚生労働省のデータでは、定着率(就職後1年以上働いている割合)は年々上昇しており、精神障害者でも約50%以上が1年以上働いているという実績があります。
定着に成功している企業の共通点は、「入社前に実習や職場見学を行っている」「相談しやすい担当者や制度がある」「社内教育やサポート体制が整っている」などがあげられます。
つまり、採用の前後に「信頼関係を築く工夫」があるかどうかが、定着を大きく左右するのです。障害の有無に関係なく、誰でも安心して働ける職場づくりが、結果として長く働ける環境につながります。
まずは自社の現状把握から
法定雇用率の達成に向けて何より大切なのは、「自社の現状を正しく把握すること」です。ここでは、今すぐ確認できる簡易チェック方法や、必要な雇用人数の計算方法、カウント対象となる人の範囲をわかりやすく解説します。
雇用率の簡易チェック方法
法定雇用率の計算は、以下の数式で簡単に確認できます。
障害者雇用率(%)=(障害者の雇用人数 ÷ 常用雇用労働者数)× 100
例:従業員が200人の企業で、障害者を5人雇っている場合
- 障害者雇用率 =(5 ÷ 200)× 100 = 2.5%
このように、自社の常用雇用労働者数(フルタイム+一部のパート)と、障害者雇用数を照らし合わせることで、現時点の達成状況を把握できます。
厚生労働省の「障害者雇用状況報告システム」でも、毎年6月1日時点での雇用状況を報告する義務がありますので、社内に最新の数字があるかどうかを確認してみましょう。
何人雇えば2.7%になる?シミュレーション
2026年からは、民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられます。自社であと何人必要なのか、簡単にシミュレーションしてみましょう。
必要な障害者数=常用雇用労働者数 × 2.7%(0.027)
※小数点以下は四捨五入、または切り上げが適用されます。
| 常用雇用労働者数 | 必要な障害者数(2.7%) |
|---|---|
| 100人 | 3人 |
| 150人 | 4人 |
| 200人 | 6人 |
| 300人 | 9人 |
| 500人 | 14人 |
もし「あと◯人足りない」と判明した場合は、どの部署で受け入れられるか、短時間勤務や在宅など柔軟な雇用形態で対応できるかを検討するのがポイントです。
障害者の対象範囲とカウント方法(短時間労働者など)
「障害者」としてカウントされるためには、以下のいずれかの手帳を所持していることが必要です。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(知的障害)
- 精神障害者保健福祉手帳
さらに、雇用率の計算にあたっては雇用形態により換算数(カウントされる比率)が異なります。
| 雇用形態 | カウント方法 |
|---|---|
| 週30時間以上 | 1.0人としてカウント |
| 週20時間〜30時間未満 | 0.5人としてカウント |
| 短時間(週20時間未満) | 原則カウント対象外 |
例えば、週25時間働いている障害者を2名雇用している場合は、0.5人 × 2 = 1人分としてカウントされます。
また、重度障害者(身体・知的)は、特定の条件を満たすと「1人で2人分」としてカウントされるケースもあります。
正確な確認には、ハローワークや支援機関への相談がおすすめです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 法定雇用率はいつから2.7%?
2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は現在の2.5%から2.7%に引き上げられます。それに向けて、今から段階的に準備しておくことが大切です。
Q2. パートタイムでもカウントされる?
はい、週20時間以上勤務している場合は0.5人分としてカウントされます。ただし、週20時間未満の場合は原則カウント対象外となるので注意が必要です。
Q3. 達成できない期間が長くても問題ない?
達成できていない期間が長くなると、納付金の累積だけでなく、行政指導や企業名の公表といったリスクも高まります。早期に改善計画を立てて、段階的な対応を検討しましょう。
Q4. 納付金以外にどんなリスクがある?
金銭面だけでなく、企業イメージの低下、取引先や求職者からの評価悪化といったリスクがあります。また、SDGsやESG重視の流れの中で、社会的責任を果たしていないと見なされる可能性もあるので注意が必要です。
Q5. 障害者手帳があれば誰でもカウントできる?
基本的には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることが必要です。また、雇用保険加入が必要など、いくつかの条件があります。
Q6. 精神障害のある方でも雇用率にカウントできる?
はい、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は雇用率にカウントされます。現在、精神障害のある方の雇用は特に増加傾向にあります。
Q7. 重度障害者はどうカウントされる?
重度の身体・知的障害者を雇用した場合、原則2人分としてカウントできます。ただし、週30時間以上勤務していることなどの条件があります。
Q8. 在宅勤務でも対象になる?
はい、在宅勤務でも労働条件を満たしていれば対象としてカウントできます。近年はテレワークによる障害者雇用も拡大しています。
Q9. 障害の程度によって、採用が難しいのでは?
障害の程度に関わらず、業務内容とのマッチングを工夫すれば、多くの方が戦力として活躍できます。実習や事前面談を通じた相性確認がポイントです。
Q10. 障害者雇用の求人はどこに出せばいい?
ハローワーク、就労移行支援事業所、障害者専用求人サイト(例:atGP、BABナビ)などを活用できます。支援機関と連携することでスムーズな採用が可能です。
Q11. ハローワークへの報告義務とは?
毎年6月1日時点の障害者雇用状況を、6月1日〜7月15日までにハローワークへ報告する義務があります。報告は「障害者雇用状況報告書」にて行います。
Q12. 雇用した後の定着が不安です
定着率を高めるには、相談窓口の設置・ジョブコーチ制度・フォロー面談の実施などが効果的です。また、外部支援機関と連携することで、継続的なサポートを受けられます。
Q13. 納付金はいくらから発生する?
従業員が101人以上の企業で、法定雇用数に1人でも満たない場合、1人あたり月額5万円(年60万円)が発生します。
Q14. 中小企業にも義務はある?
常用雇用労働者が43.5人以上の企業は法定雇用率の対象となります。ただし、納付金の義務は101人以上の企業からです。
Q15. 法定雇用率はどのタイミングで見直される?
法定雇用率は、おおむね5年ごとに見直されますが近年はそのスパンが短くなっています。障害者の就業状況や社会環境の変化に応じて、今後も引き上げられる可能性があります。
まとめ|未達成でも諦めず、今できる対策を
法定雇用率の未達成は、多くの企業が抱えている共通の課題です。しかし、しっかりと現状を把握し、正しい知識と適切な支援を活用すれば、どの企業でも改善の道を歩むことができます。
この記事のポイント再確認
- 法定雇用率は2026年7月から2.7%に引き上げ予定
- 未達成のままでは納付金や企業名公表のリスクがある
- 受け身の採用ではなく、準備と体制づくりがカギ
- 在宅勤務や短時間勤務など柔軟な雇用方法も可能
- 助成金やイメージアップなど達成のメリットも大きい
今後の対応フロー例(チェックリスト)
以下のステップで、段階的に取り組んでみましょう。
- 現在の障害者雇用数と雇用率を確認する
- 必要な雇用人数を2.7%基準でシミュレーション
- 求人票の見直し・配慮事項の明記
- 就労移行支援事業所やハローワークと連携
- 受け入れ部署・担当者の決定
- 業務の切り出しとマニュアル整備
- 職場見学・実習などからスタート
- 採用後のフォロー体制(相談窓口・ジョブコーチなど)を確保
最初から完璧を目指す必要はありません。「できることから一歩ずつ」が、結果的に法定雇用率の達成につながっていきます。
無料で相談できる外部機関・サービス一覧
障害者雇用に関しては、以下のような無料相談窓口を活用することができます。
- ハローワーク:障害者求人の掲載、面接支援、職場実習など
- 障害者就業・生活支援センター:地域に密着した総合相談窓口
- 就労移行支援事業所:職業訓練を受けた利用者とマッチングが可能
- 地域障害者職業センター:職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援
- 都道府県の労働局・労働基準監督署:制度全般の説明や行政的支援
また、厚生労働省の公式サイトや、障害者雇用情報センターなどでも、最新の資料や支援制度情報が随時公開されています。「まずは話を聞いてみるだけ」でも十分な一歩です。気軽に活用してみてください。
障害者雇用は、企業の未来をつくる大切なテーマ。できる小さな行動が、やがて持続可能な組織づくりにつながります。