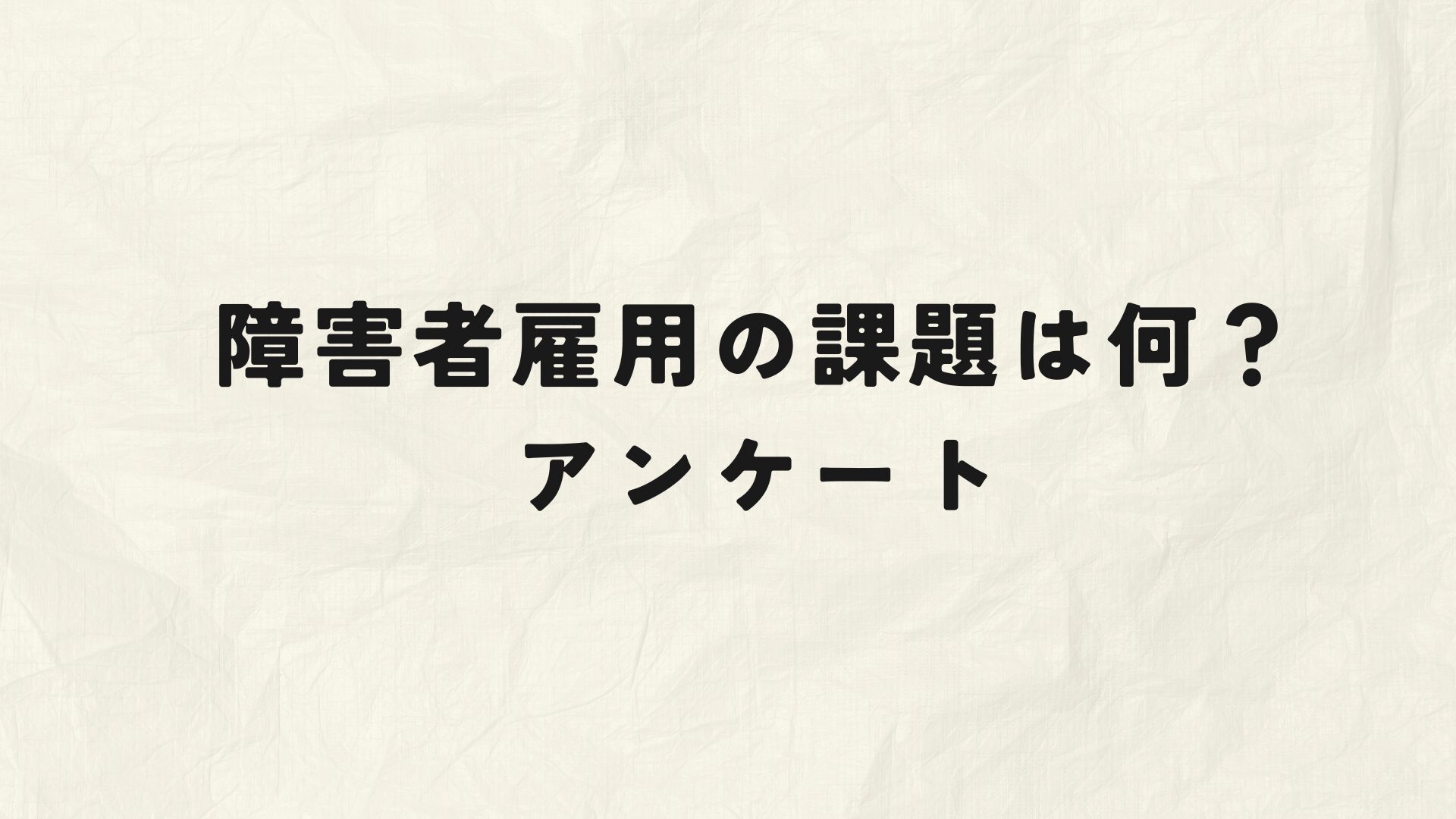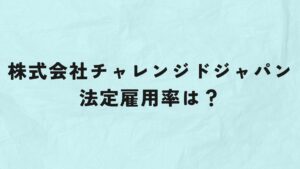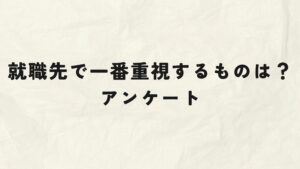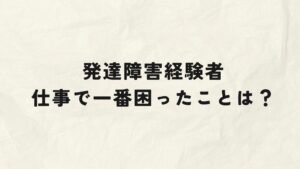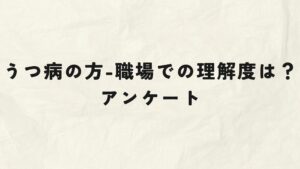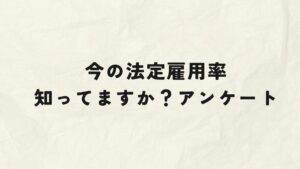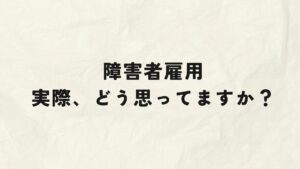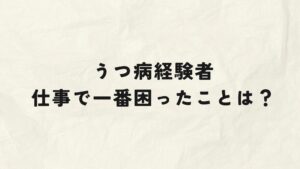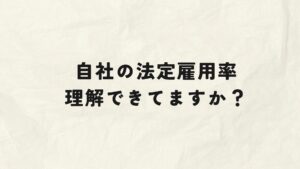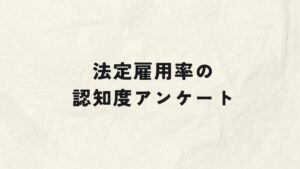本記事では、「障害者雇用に関して課題だと思うことは?」というテーマで実施したアンケート(有効回答:231件)の集計結果をまとめました。
調査概要
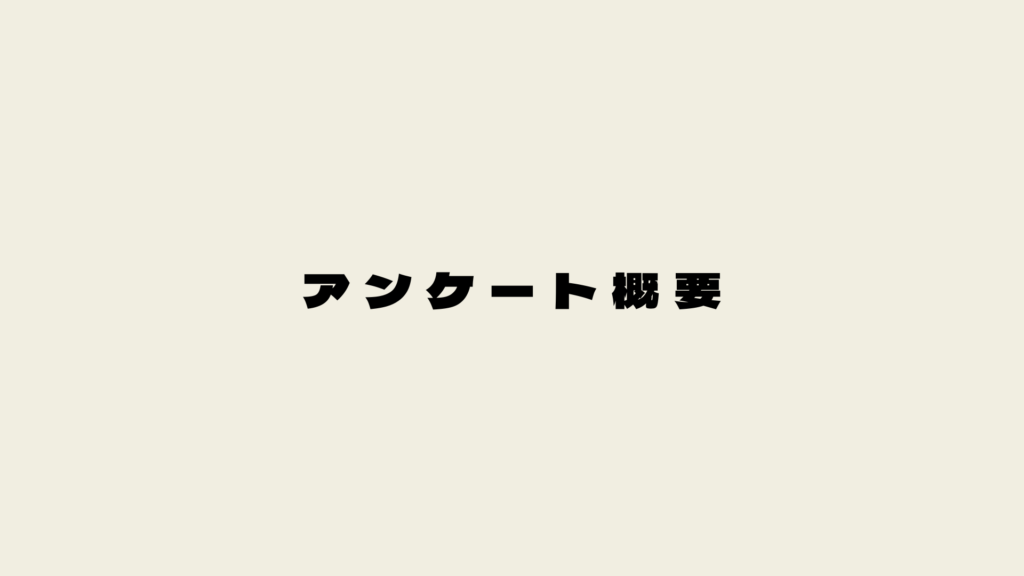
- 調査方法:インターネット調査
- 対象:全国の男女(職業問わず)
- 回答者数:231人
- 調査期間:2025年8月13日~2025年8月13日

質問内容
- 性別
- 年齢
- 障害者雇用に関して課題だと思うことは?
- 何か思うことがあれな書いてください。(自由記述)
集計結果

性別
| 性別 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 女性 | 139 | 60.2% |
| 男性 | 92 | 39.8% |
年代
| 年代 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 20代 | 47 | 20.3% |
| 30代 | 79 | 34.2% |
| 40代 | 66 | 28.6% |
| 50代 | 34 | 14.7% |
| 60代以降 | 5 | 2.2% |
障害者雇用に関して課題だと思うことは?

| 順位 | 課題項目 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サポート体制の不十分さ | 56 | 24.2% |
| 2位 | 職場の理解不足 | 54 | 23.4% |
| 3位 | 仕事内容のミスマッチ | 43 | 18.6% |
| 4位 | 給料の低さ | 19 | 8.2% |
| 5位 | 職場のバリアフリー環境が不十分 | 13 | 5.6% |
| 6位 | 採用枠や人数の不足 | 13 | 5.6% |
| 7位 | 精神的負担やストレスへの配慮不足 | 11 | 4.8% |
| 8位 | 制度そのもの認知度の低さ | 9 | 3.9% |
| 9位 | 昇進やキャリア形成の機会が少ない | 5 | 2.2% |
| 10位 | 勤務時間・勤務形態の柔軟性がない | 5 | 2.2% |
| — | その他 | 3 | 1.3% |
アンケートからわかること
今回の結果を見ると、大きく3つのタイプの課題があることがわかりました。
職場でのサポートや理解が足りない
「サポート体制が不十分」「職場の理解不足」「仕事内容のミスマッチ」が多くの声を占めました。制度として雇用していても、実際のサポートや周りの理解がないと働き続けるのは難しくなります。
お給料やキャリアの面での不満
「給料が低い」「採用枠が少ない」「キャリアアップの機会が少ない」といった声もありました。長く安心して働くためには、評価や処遇の見直しも大切です。
環境や制度の整備不足
「職場のバリアフリーが不十分」「勤務時間の柔軟性がない」など、物理的な環境や働き方の選択肢に関する課題も挙がりました。また、「制度自体の認知度が低い」という声もあり、もっと情報を広く伝える必要があります。
一番のポイントは、現場での受け入れ体制と職場の理解をしっかり作ることです。その上で、お給料やキャリアの制度、働く環境や制度の周知をセットで進めることが、より良い障害者雇用につながります。
みんなの口コミ

今回のアンケートでは「障害者雇用の課題に関して思うことがあれば自由に書いてください」と項目を設置したので投稿された口コミを紹介していきます。
『サポート体制の不十分さ』についての口コミ
 女性(30代)
女性(30代)受け入れる方も知識が足りず、障害の度合いに関わらず一定の仕事しか回せていないのが現状なように思う。



障害者雇用=足手まといという感覚が強いと双方にとって不利益にしかならないので、サポート体制を充実させた上で障害者の方の強み、できることに集中でき成果を出せる環境を作ることが必要だと感じました。



どのような障害なのかを理解して、周知とケアの徹底が必要であると感じる。また、職場や業務内容もそれに見合ったものを当てがうことが管理職の役目であると思う。と感じました。



以前働いていた職場で1人、障害者雇用で入社してきましたが、重度ではなかったので、軽作業ならなんとか出来るようにはなりましたが、それでも時々声かけやチェックをしなければなりません。
私がだいたいサポートしてたのですが、私自身の作業もあるし、プラスアシストは本当に大変でした。みんなで見守るはずだったのですが、結局面倒をみる人に押し付けがちなんですよね。お店の店長も彼の症状を全然理解していなかったし、ただ雇用しただけで、現場に丸投げみたいな感じでした。



どのような障害なのかを理解して、周知とケアの徹底が必要であると感じる。また、職場や業務内容もそれに見合ったものを当てがうことが管理職の役目であると思う。
これらの意見から、「サポート体制の不十分さ」が障害者雇用の現場で大きな課題になっていることがわかります。
単に人員を増やすだけではなく、正しいかかわり方を理解したうえで支援できる人材の育成や、サポートする人を支える仕組みまで必要だという声が目立ちます。
また、「現場に丸投げ」「一部の人に負担が集中」という指摘も多く、役割分担の明確化や、管理職が主体的に関わる体制づくりが欠かせません。
一方で、専門カウンセラーの配置や部署間の柔軟な異動など、すでに有効な取り組みを行っている事例もあり、こうした成功例を他社でも共有・導入することが改善の近道となるでしょう。
『職場の理解不足』についての口コミ



“障害者”というだけで偏見を持つ人が多い。
経営側が雇用することを決定し、現場に流してくるが研修等のサポートもなく、雇用された本人の”出来ること”が全くわからないまま。
現場でサポートしたいと思っても情報収集から入らなければならないため、現場を回しながらだとどうしてもサポートが薄くなる。きちんと体制を整えたいと思っても方法がわからない経営側が多すぎる。



たとえ時間がかかったとしても、熱心に取り組まれている人が多いです。柔軟性ある職場がこれから求められる事を望みます。



どのように接してよいのか一緒に働く人たちもわかっていない



心身に障害を持っている方がいると周りも過剰に気を遣ってしまうので、双方の理解を深めるために交流の機会を多く設けるべきだと思う。



心身に障害を持っている方がいると周りも過剰に気を遣ってしまうので、双方の理解を深めるために交流の機会を多く設けるべきだと思う。
障害者雇用の現場では「職場全体の理解不足」が根本的な課題であることがはっきりとわかります。
特に、障害の度合いや特性を把握しないまま業務を割り当ててしまうケースや、「見た目にはわからない障害」への配慮不足が繰り返し指摘されています。
また、「理解しているつもりでも実際には対応できていない」「経営層が雇用を決定しても現場に十分な情報や研修が届かない」など、情報共有・研修不足も大きな壁となっています。
一方で、「思いやりと助け合いの気持ちが必要」「交流の機会を増やすべき」といった前向きな意見もあり、制度面の見直しと合わせて現場での相互理解を深める取り組みが改善の鍵になると考えられます。
『仕事内容のミスマッチ』についての口コミ



障がい者であっても能力が高い人も多いのに、障がい者雇用だと単純作業など誰でもできる求人が大半で、自分の能力を生かしたい人が求める求人が少ない印象。



大企業では法令順守をしている事をアピールする為、とりあえず実施している感が強く、一般社員との意識の乖離も大きいように感じる。



業務・作業内容に得手不得手があるならば、本人のためにも周囲のためにも、特性を生かした配置にするべきと思います。



障害者の特性や希望と、実際の業務内容が合っていないと、働く意欲や能力が活かされず、早期離職に繋がると思います。企業側の理解不足や環境整備の遅れも原因で、もっと丁寧なマッチングと対話が必要だと感じます。
障害者雇用では「特性や能力に合った配置・業務設計」がいかに重要かが浮き彫りになっています。
特に、スキルや専門性が十分あっても、単純作業に限定されてしまう現状や、逆に能力に合わない仕事を任されることで本人・周囲双方に負担がかかるケースが繰り返し指摘されています。
また、在宅ワークの活用や柔軟な働き方の必要性、一律の雇用率制度の実情との乖離など、制度面の見直しを求める声も目立ちます。
一方で、「できること・できないこと」を正しく把握する難しさや、体調や薬の影響によるパフォーマンスの変動も考慮し、丁寧なマッチングと継続的な対話を行うことが、離職防止と定着率向上につながると考えられます。
『給料の低さ』についての口コミ



国の補助金・税制優遇などで、給料が上がればモチベーションも上がると思う



実際には想定以上の成果を上げていても、障害者と言う括りでなかなかプラス評価になりにくい、むしろマイナス評価につながりやすい状況はまだたくさんあります。もう少し、色眼鏡なしの評価があれば頑張れる人はたくさんいるはずです。



障害者だからと給料が安すぎるとモチベーションが維持できないので結果として仕事の効率が落ちると思います。
今回の意見からは、障害者雇用において給与水準と評価の在り方が大きな論点であることがわかります。
多くの人が「同一労働同一賃金」を理想としつつも、業務量や生産性の違いから一律化の難しさを指摘しています。一方で、最低賃金を下回るような不当な待遇や、成果を正当に評価しない風土はモチベーション低下や効率悪化につながるとの声が目立ちます。
また、ママ枠や主婦枠との比較からもわかるように、給与の低さは特定の属性に偏る傾向があり、不平等感や孤立感の原因となることもあります。そのため、直接的な賃金改善が難しい場合でも、福利厚生や評価制度での補完が重要との提案もありました。
総じて、金銭的な報酬だけでなく、働く環境や人間関係を含めた「総合的な満足度の向上」が、障害者雇用の定着と活躍に欠かせない視点だといえます。
その他の口コミ



障害者雇用の問題点としては、一般の求人に比べると求人や採用枠が少ないという点ではないでしょうか。特に地方や田舎は少ないと感じる方が多いと思います。障害があるけれど働きたい人が多いわりには、求人数が少ないのがネックになると思います。



バリアフリーの環境を作るにしてもスペースや費用面で余裕がない



サポートする人材の育成と人件費の増加



サポートする人材の育どのような障害なのかを理解して、周知とケアの徹底が必要であると感じる。また、職場や業務内容もそれに見合ったものを当てがうことが管理職の役目であると思う。



上記にもあるが、会社からの障害への理解も大切だと思う。障害者雇用がもっと増えてみんなが気持ちよく働ける世の中になればいいと思う。
まとめ|現場の声から見えたこと
今回の口コミを通して、障害者雇用には大きく4つの課題が見えてきました。
- サポート体制:知識不足や一部の人への負担集中をなくし、支える仕組みを整えること。
- 職場理解:障害への理解を深める研修や交流の場を増やすこと。
- 仕事内容のミスマッチ:スキルや特性に合った仕事を丁寧にマッチングすること。
- 給与・評価:成果を正しく評価し、納得できる待遇や福利厚生を用意すること。
障害者雇用は「法定雇用率を達成すること」が目的ではなく、「本人が能力を発揮し、安心して働き続けられる環境を整えること」が本質です。
そのためには、制度・職場環境・評価の三位一体での改善が必要であり、現場の声を反映した柔軟な運用こそが、雇用の質を高める近道といえるでしょう。
法定雇用率ナビの独自アンケート一覧


法定雇用率ナビでは独自のアンケート調査を実施しています。企業側目線、障害者雇用側目線など様々なアンケート調査をしていますので是非参考にしてください。(アンケート一覧はこちら)