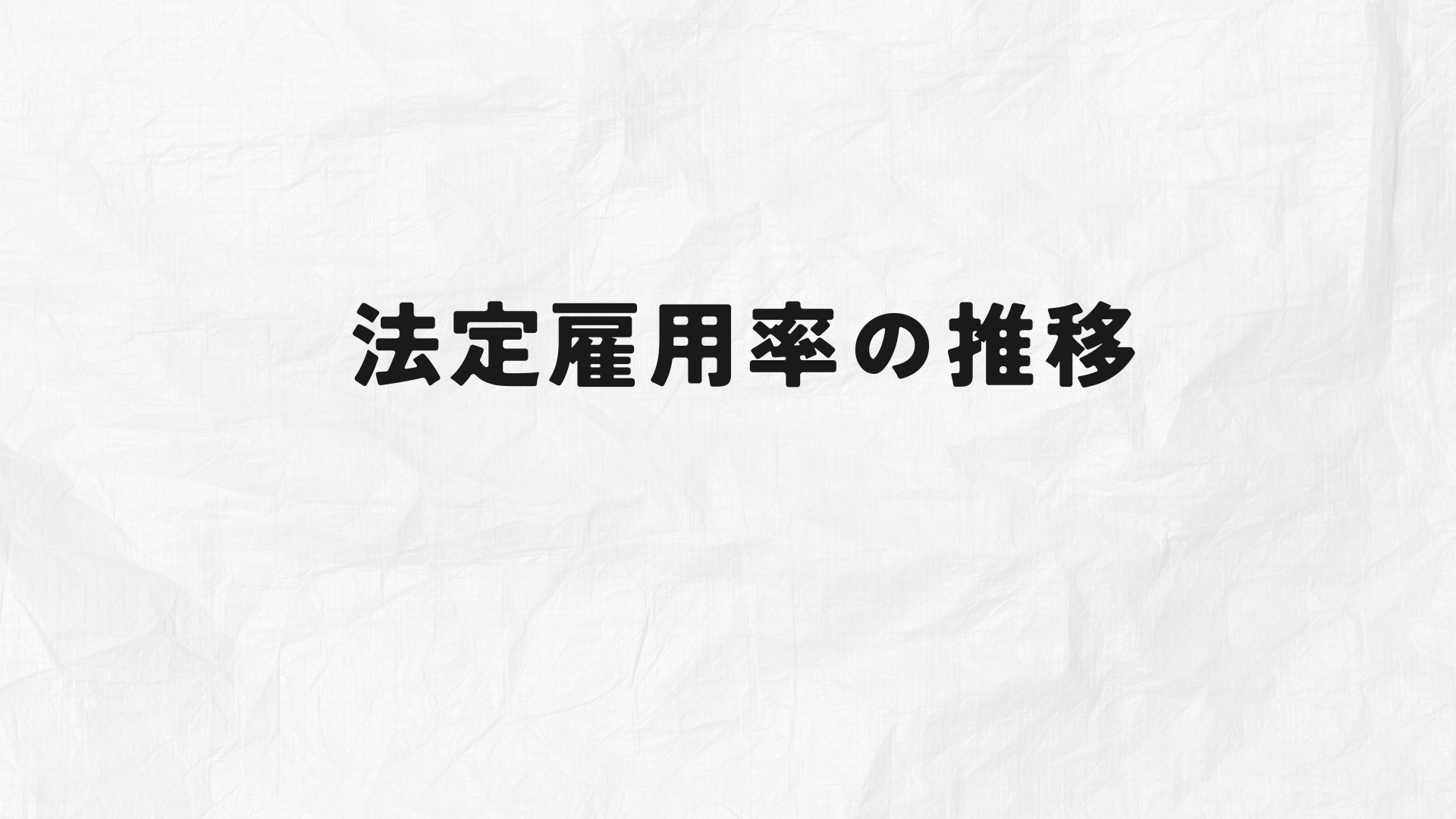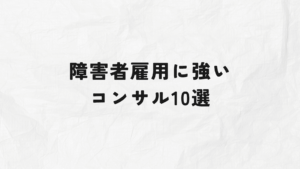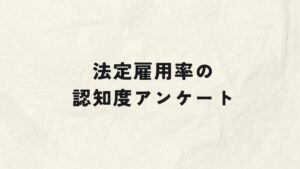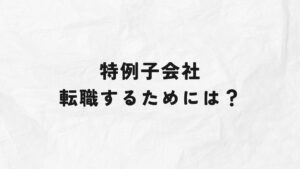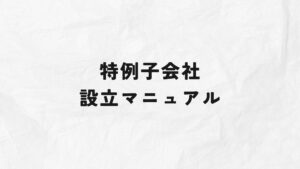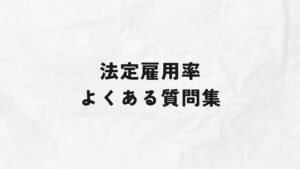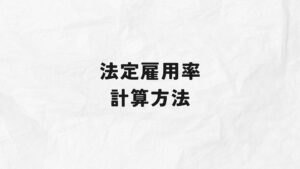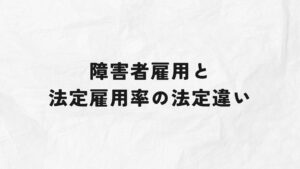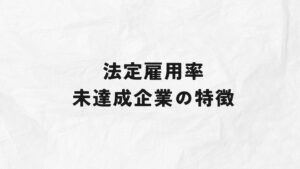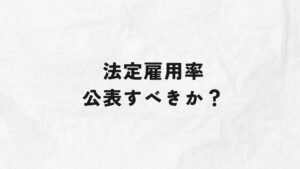「法定雇用率の推移ってどうなっているの?」「昔と比べて上がってるの?」そんな疑問を持つ方へ。
この記事では、初心者でもわかるように、法定雇用率の過去から現在までの推移、背景、今後の見通しまで解説していきます。
法定雇用率とは?
法定雇用率の定義
法定雇用率とは、企業や国・地方公共団体などが雇用しなければならない障害者の割合のことです。簡単にいうと「従業員のうち、これだけの割合で障害者を雇ってください」という国が決めたルールです。
例えば、民間企業の場合は従業員が43.5人以上いると、1人以上の障害者を雇用する義務があります。この割合が法定雇用率であり、数年ごとに見直されてきました。
障害者雇用促進法に基づく決まり
法定雇用率は障害者雇用促進法という法律に基づいて定められています。この法律は、障害のある人もない人も平等に働ける社会を作るために制定されたものです。
企業や自治体が法定雇用率を達成できない場合は、障害者雇用納付金を納める必要があります。一方で、達成している企業には調整金や報奨金が支給されるなど、雇用を後押しする仕組みが整えられています。
なぜ法定雇用率があるのか
「そもそもなぜ法定雇用率が必要なの?」と思う方もいるかもしれません。その理由は、障害がある方の就職がまだまだ難しい現状があるからです。
もし法定雇用率という制度がなければ、企業側が積極的に雇用しようとしない可能性もあります。そのため、国が法律でルールを作り、障害者雇用を促進しているのです。
障害者雇用促進の社会的背景
背景には、障害者も自立して生活できる社会を作るという国の方針があります。障害があってもスキルや能力を活かして働ける場を増やすことは、個人の自立だけでなく、企業にとっても多様性ある組織づくりにつながります。
また、少子高齢化で労働力人口が減る中で、障害者雇用は企業にとっても重要な人材確保策と位置づけられるようになっています。
法定雇用率の推移|全体の流れを解説
ここからは、法定雇用率がこれまでどのように変わってきたのか、全体の流れをわかりやすく解説します。法定雇用率は、障害者雇用を取り巻く社会状況の変化に合わせて、段階的に引き上げられてきました。
1976年の法制定当初
法定雇用率は1976年(昭和51年)に制度化されました。当時の障害者雇用促進法(旧・身体障害者雇用促進法)によって、民間企業の法定雇用率は1.5%と定められました。
これは、障害のある方が社会で働くための環境整備がまだ十分でなかった時代背景もあり、現在よりも低い水準でした。
1990年代の改正
1990年代に入ると、障害者雇用をめぐる社会の意識が高まり、1998年(平成10年)には法定雇用率が1.6%に引き上げられました。
また、1993年(平成5年)には障害者の範囲に知的障害者が含まれるようになり、雇用義務の対象が拡大されました。これにより企業は、身体障害者だけでなく知的障害者の雇用も進める必要が出てきました。
2000年代以降の推移
2000年代に入ると、法定雇用率は以下のように段階的に引き上げられてきました。
- 2002年(平成14年):1.8%
- 2013年(平成25年):2.0%
- 2018年(平成30年):2.2%
この背景には、障害者の就労支援体制の整備や、企業への雇用促進施策の強化がありました。
2018年 精神障害者の算定開始
2018年(平成30年)には、法定雇用率における算定対象に精神障害者が正式に加わりました。これまでは身体障害者、知的障害者のみが対象でしたが、精神障害者の雇用促進を進めるため、法律改正が行われたのです。
これにより、企業はより幅広い障害種別の方々を受け入れる体制づくりが求められるようになりました。
直近5年間の推移
直近5年間の民間企業の法定雇用率推移は以下の通りです。
| 年度 | 法定雇用率 |
|---|---|
| 2018年 | 2.2% |
| 2021年 | 2.3% |
| 2023年 | 2.3%(据え置き) |
| 2024年 | 2.5% |
| 2026年予定 | 2.7%(予定) |
2024年4月に2.5%に引き上げられ、さらに2026年には2.7%への引き上げが予定されています。今後も法定雇用率は上昇傾向にあり、企業としては早めの取り組みが重要です。
民間企業における法定雇用率の推移
ここでは、民間企業全体の法定雇用率達成状況の推移と、企業規模別の状況について解説します。
自社がどの位置にいるのかを把握することで、今後の取り組みを考える参考になるでしょう。
民間企業全体の推移表
まずは、厚生労働省が発表している民間企業全体の障害者雇用状況の推移表を確認しましょう。
| 年度 | 実雇用率 | 法定雇用率 | 達成企業割合 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2.05% | 2.2% | 48.0% |
| 2019年 | 2.11% | 2.2% | 50.0% |
| 2020年 | 2.15% | 2.2% | 51.6% |
| 2021年 | 2.20% | 2.3% | 43.5% |
| 2022年 | 2.25% | 2.3% | 46.0% |
| 2023年 | 2.31% | 2.3% | 50.1% |
| 2024年 | 2.41% | 2.5% | 46.0% |
このように、全体の実雇用率は少しずつ上昇していますが、法定雇用率を達成している企業は半数程度にとどまっているのが現状です。法定雇用率の引き上げに伴い、達成企業割合が一時的に下がる年もあることがわかります。
規模別(100人未満・100〜300人・300人以上)の推移
次に、企業規模別の法定雇用率達成状況を見ていきましょう。
| 企業規模 | 2022年度 実雇用率 | 達成企業割合 |
|---|---|---|
| 100人未満 | 1.86% | 34.2% |
| 100〜300人 | 2.14% | 46.8% |
| 300人以上 | 2.41% | 59.4% |
このように、企業規模が大きくなるほど実雇用率が高く、達成企業割合も増える傾向にあります。特に300人以上の企業では約6割が法定雇用率を達成しており、障害者雇用の受け入れ体制が比較的整っていることがわかります。
一方、100人未満の中小企業では達成割合が3割程度と低く、今後どのように雇用を進めるかが課題となっています。
国・地方公共団体における法定雇用率の推移
民間企業だけでなく、国の機関や地方公共団体にも法定雇用率が定められています。
ここでは、国・地方公共団体の雇用率推移と、教育委員会の推移について解説します。
国・地方公共団体の雇用率推移表
国や地方公共団体では、民間企業よりも少し高い法定雇用率が設定されています。
以下の表は、厚生労働省発表のデータに基づく近年の推移です。
| 年度 | 国・地方公共団体 法定雇用率 | 国の実雇用率 | 地方公共団体の実雇用率 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2.5% | 2.50% | 2.57% |
| 2020年 | 2.5% | 2.68% | 2.70% |
| 2021年 | 2.6% | 2.83% | 2.82% |
| 2023年 | 2.6% | 2.88% | 2.90% |
| 2024年 | 2.8% | 2.95% | 2.96% |
このように、国や地方公共団体では法定雇用率を上回る実雇用率を達成している傾向があります。特に2024年4月には、法定雇用率が2.8%へ引き上げられましたが、それでも実雇用率は2.95~2.96%と高水準です。
教育委員会の法定雇用率推移
教育委員会についても、独自に法定雇用率が設定されています。
過去からの推移は以下の通りです。
| 年度 | 教育委員会 法定雇用率 | 実雇用率 |
|---|---|---|
| 2018年 | 2.4% | 1.92% |
| 2020年 | 2.4% | 2.11% |
| 2021年 | 2.5% | 2.21% |
| 2023年 | 2.5% | 2.32% |
| 2024年 | 2.6% | 2.35% |
教育委員会では、徐々に実雇用率が上昇しているものの、法定雇用率を下回っている現状があります。特に教職員は専門職が多く、配置上の難しさもあるため、今後の取り組み強化が求められています。
法定雇用率が上がってきた理由
ここまで法定雇用率の推移を見てきましたが、そもそもなぜ法定雇用率は引き上げられてきたのでしょうか。ここでは、その背景にある理由を解説します。
障害者の就労環境整備
一つ目の理由は、障害者の就労環境が整備されてきたことです。かつては障害があることで働ける場が限られていましたが、近年は以下のような取り組みが進みました。
- 就労移行支援事業所の普及
- 特例子会社制度による雇用拡大
- ICTの発達による在宅勤務やテレワークの普及
このように、障害があっても働きやすい環境や制度が増えてきたことで、国としても雇用率を引き上げ、より多くの障害者が働ける社会を目指す方針が示されるようになったのです。
国際的な潮流と国内施策
二つ目の理由は、国際的な潮流と国内施策の影響です。日本は2006年に採択された「障害者権利条約」を2007年に署名、2014年に批准しています。
この条約では、障害者が差別されることなく平等に社会参加できる権利を保障しており、就労の機会確保も重要な柱のひとつです。
さらに国内では、
- 2013年:障害者雇用促進法改正(精神障害者の雇用義務化に向けた準備)
- 2018年:精神障害者を法定雇用率の算定対象に追加
- 2024年:法定雇用率を2.5%へ引き上げ
といったように、国際的な動きに合わせて法律や制度改正が進められてきました。これにより、企業には「障害者雇用は社会的責任である」という意識改革も求められるようになっています。
法定雇用率の今後の見通し
これまでの推移を踏まえ、ここでは法定雇用率の今後の改正予定について解説します。
企業にとっては、早めに情報を把握し準備しておくことが重要です。
2024年の改正内容
2024年4月1日から、民間企業の法定雇用率は2.3%から2.5%へ引き上げられました。この改正により、従業員数43.5人以上の企業は、これまでよりも障害者雇用義務人数が増加することになります。
例えば、従業員が200人の企業の場合、これまで4.6人(切り捨てで4人)必要だったものが、2.5%になると5人必要になります。わずかな増加に思えますが、全国的にみると新たに雇用義務が発生する企業や、不足人数が出る企業が増えるため、影響は大きいです。
また、法改正では雇用率引き上げだけでなく、
- 障害者雇用納付金制度の見直し
- 短時間労働者の雇用状況把握の厳格化
といった制度運用面での変更も行われており、企業の人事・総務部門は最新情報を継続的にチェックする必要があります。
2026年以降の予定
2026年7月1日からは、法定雇用率が2.7%へ引き上げられる予定です。2024年改正に続く大きな引き上げであり、企業にとっては更なる対応が求められます。
厚生労働省は、障害者雇用率の引き上げを段階的に行うことで、企業側に準備期間を与えつつ、障害者の就労機会拡大を目指しています。
2026年の法定雇用率2.7%引き上げにより、従業員数ごとの必要雇用人数も以下のように変わります。
| 従業員数 | 現在(2.5%) | 2026年以降(2.7%) |
|---|---|---|
| 100人 | 2.5人(切り捨てで2人) | 2.7人(切り捨てで2人) |
| 200人 | 5人 | 5.4人(切り捨てで5人) |
| 500人 | 12.5人(切り捨てで12人) | 13.5人(切り捨てで13人) |
このように、2026年の改正では必要雇用人数が1人増える企業が多くなるため、採用計画の見直しや、特例子会社設立を含めた対応が求められるでしょう。
法定雇用率推移から見る企業の課題
これまで見てきたように、法定雇用率は年々引き上げられていますが、実際に達成できている企業はどれくらいあるのでしょうか。ここでは、法定雇用率の推移から見える企業の課題を解説します。
達成企業と未達成企業の割合推移
厚生労働省の発表によると、民間企業全体で法定雇用率を達成している企業割合は約50%前後にとどまっています。
以下の表は、直近5年間の達成企業割合の推移です。
| 年度 | 法定雇用率 | 達成企業割合 |
|---|---|---|
| 2019年 | 2.2% | 50.0% |
| 2020年 | 2.2% | 51.6% |
| 2021年 | 2.3% | 43.5% |
| 2022年 | 2.3% | 46.0% |
| 2023年 | 2.3% | 50.1% |
| 2024年 | 2.5% | 46.0% |
このように、法定雇用率が引き上げられたタイミングで達成企業割合が一時的に低下する傾向があります。
達成できない原因としては、
- 障害者採用ルートの不足
- 社内受け入れ体制・業務設計が整っていない
- 短時間勤務や在宅勤務制度の未整備
などが挙げられます。
納付金制度の影響
法定雇用率を達成できない場合、企業には「障害者雇用納付金」が課されます。これは障害者雇用促進法に基づく制度で、現在の納付金額は不足1人あたり月額50,000円(年間60万円)です。
例えば、3人不足している場合は年間180万円の納付金を支払うことになります。一方、法定雇用率を超えて雇用している場合には、調整金や報奨金が支給される仕組みもあり、企業にとって雇用義務達成が経済的にもプラスになる制度設計となっています。
納付金制度は「ペナルティ」という側面だけでなく、調整金や助成金制度とあわせて企業全体で障害者雇用を支える仕組みです。しかし、雇用義務未達成が続けば納付金コストが累積するため、企業にとっては人材確保と合わせて重要な経営課題といえるでしょう。
納付金制度の影響|全国で年間どれくらい支払われている?
「納付金って実際にどれくらい払われているの?」と気になる方も多いかもしれません。ここでは、最新データをもとに全国の不足人数と納付金総額を試算してみました。
令和6年度(2024年)の民間企業における障害者雇用者数は677,461.5人で、実雇用率は2.41%でした。
不足人数の計算式
不足人数は、以下の計算式で求めることができます。
総従業員数 × 法定雇用率 - 実際の雇用者数 = 不足人数
実際に計算してみると、
- 総従業員数 =677,461.5÷0.0241=28,110,436人
- 必要雇用者数(法定雇用率2.5%適用時)= 28,110,436×0.025=702,761人
- 不足人数=702,761-677,461=約25,300人
この不足人数に対して、納付金は不足1人あたり年間60万円(月額5万円)課されます。つまり、全国で支払われている納付金総額は…
25,300人×60万円=年間約152億円
この年間152億円規模の納付金は、決して罰金ではなく、障害者雇用を達成している企業への調整金・報奨金や雇用支援助成金に再分配される仕組みになっています。
しかし、企業から見れば「納付金を支払うより、障害者を雇用した方が社会的にも経済的にもプラスになる」といえるでしょう。
実際、あと1~2名雇用すれば法定雇用率を達成できる企業も多いため、納付金負担を続けるよりも、採用計画や受け入れ体制を整えることが今後の重要な経営課題といえます。企業が今取り組むべきこと
法定雇用率が引き上げられる中で、企業としては「自社は今どの状況にあるのか」「これから何をすべきか」を明確にしておく必要があります。
ここでは、今すぐ取り組めるポイントを解説します。
自社雇用率の現状把握
まず最初に取り組むべきは、自社の障害者雇用率が現在どの水準にあるかを正確に把握することです。現状把握の際には、以下のポイントを確認しましょう。
- 自社の法定雇用率(民間企業は2024年現在2.5%、2026年以降は2.7%)
- 算定対象となる従業員数(週所定労働時間30時間以上/短時間雇用は0.5カウント)
- 現在雇用している障害者人数
- 法定雇用率達成までに必要な人数
この基本データを整理することで、あと何人雇用する必要があるのかが明確になり、次の施策計画が立てやすくなります。
達成に向けた具体的施策
自社の不足人数がわかったら、次は具体的な採用・受け入れ体制づくりです。
例えば、以下のような取り組みが有効です。
- ハローワークや障害者就業・生活支援センターとの連携
地域の支援機関に求人を出し、紹介を受ける。 - 特例子会社の設立検討
企業グループとして障害者雇用を進める場合に有効。 - 業務切り出しによる職域開発
既存業務を細分化し、障害者が取り組みやすい仕事を創出。 - 在宅勤務や短時間勤務制度の整備
特に精神障害者や身体障害者の通勤負担軽減につながる。 - 社内受け入れ体制の強化
上司や同僚への障害理解研修、サポーター配置など。
これらの取り組みを進めることで、単に法定雇用率を達成するだけでなく、障害者が長く安心して働ける職場環境づくりにもつながります。結果として、企業の社会的信用向上や、多様な人材活用による業務効率化・組織活性化にも寄与するでしょう。
法定雇用率推移に関するよくある質問(Q&A)

法定雇用率は毎年上がるの?
法定雇用率は毎年必ず上がるわけではありませんが、数年ごとに段階的に引き上げられる傾向があります。例えば2024年に2.5%、2026年には2.7%へ引き上げ予定です。
中小企業も対象になる?
はい、従業員43.5人以上(法定雇用率2.5%の場合)であれば、中小企業でも障害者雇用義務が発生します。規模が小さい場合でも対象外ではないため注意が必要です。
達成できないと罰則がある?
刑事罰などはありませんが、障害者雇用納付金(月額5万円×不足1人)が課されます。さらに厚生労働省からの指導や、達成状況が公表されることもあります。
精神障害者はいつから算定対象?
2018年(平成30年)4月から、精神障害者も法定雇用率の算定対象に含まれるようになりました。これにより雇用の幅が広がっています。
パートタイムでもカウントされる?
はい、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も0.5人分としてカウントされます。ただし短時間雇用者の条件を満たす必要があるため、詳細確認が重要です。
除外率って何?
除外率とは、業種ごとの障害者雇用が難しい事情を考慮し、算定対象人数から一定割合を除外できる仕組みです。医療や建設業など一部業種に適用されています。
特例子会社とは?
特例子会社とは、親会社が障害者雇用を進めるために設立する子会社で、親会社の雇用率に合算できる制度です。多くの大手企業が活用しています。
重度障害者はどうカウントされる?
重度障害者(身体障害1・2級、知的障害重度判定)は1人を2人分としてカウントされます。ただし短時間勤務の場合は0.5人分としての扱いになります。
法定雇用率は業種によって違う?
基本の法定雇用率は同じですが、除外率適用業種では実質的に必要雇用人数が軽減されます。ただし制度は複雑なので厚労省公表データでの確認が必須です。
障害者雇用を進めると助成金はもらえる?
はい、障害者雇用に取り組む企業には、施設設置や職場適応訓練、雇用調整などで様々な助成金が用意されています。用することで負担軽減につながるでしょう。
まとめ|法定雇用率推移を正しく理解し、早めの対策を
法定雇用率の定義から推移、今後の見通し、企業が取るべき対策まで詳しく解説してきました。この記事のポイントをおさらいし、企業としてどのように向き合うべきかをまとめます。
この記事のポイントおさらい
- 法定雇用率は数年ごとに引き上げられており、2024年に2.5%、2026年には2.7%となる予定
- 民間企業全体では約25,300人分の不足があり、年間約152億円の納付金が発生している可能性
- 精神障害者が2018年から算定対象となり、障害者雇用の幅が広がった
- 企業規模が大きいほど達成率は高いが、中小企業では対応が遅れている
- 納付金制度は罰金ではなく、達成企業への調整金や雇用助成金として再分配される仕組み
- 達成に向けては現状把握→採用計画→受け入れ体制整備が重要
企業としてどう向き合うか
法定雇用率の引き上げは、単なる義務ではなく、企業が多様な人材を活かすための社会的責任でもあります。そして、それは企業価値向上にもつながります。
まずは自社の雇用率を正確に把握し、不足している場合は採用計画を早急に見直すこと。その上で、障害者が安心して働ける環境づくりに取り組むことで、組織全体の活性化やイメージアップにもつながるでしょう。
今後も法定雇用率は上がる見通しです。「早めの準備」が、企業にとって大きな差別化ポイントとなるはずです。