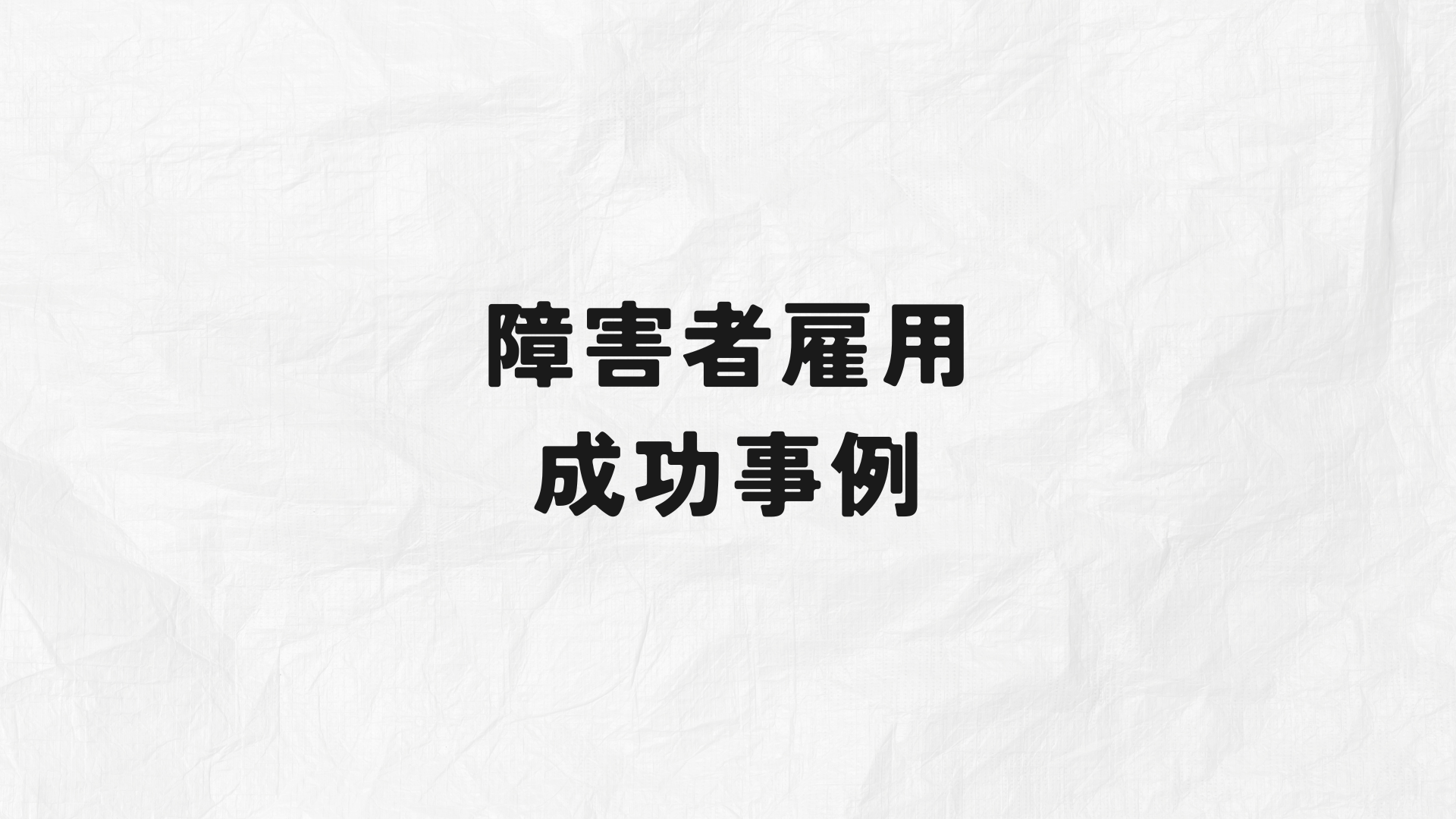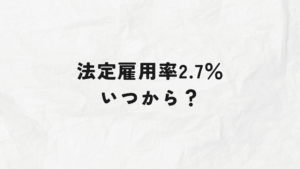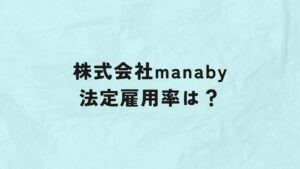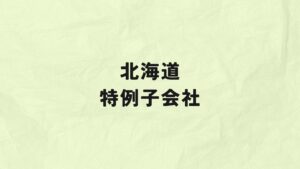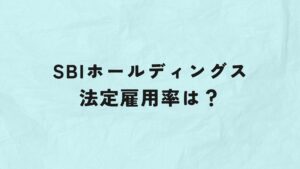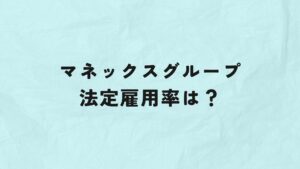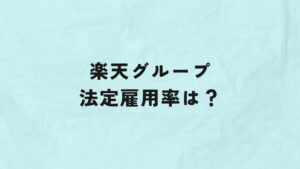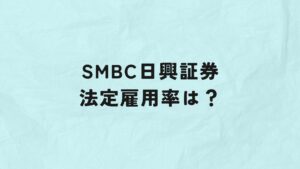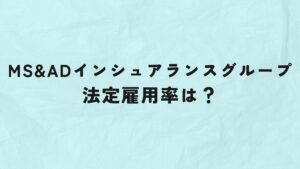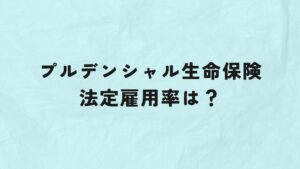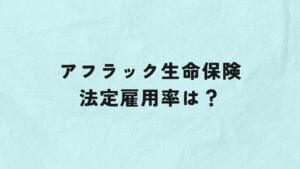「障害者雇用って本当にうまくいくの?」「自社で取り組んでも成功するか不安…」多くの企業の担当者が思っているポイントです。
この記事では、実際に障害者雇用に取り組み成果を出している企業の成功事例を中心に、取り組みのポイント、業種別の工夫、そして失敗を回避するためのコツまで、初心者にもわかりやすく解説していきます。
障害者雇用の現状と課題
法定雇用率とは?
法定雇用率の定義と仕組み
法定雇用率とは、企業が雇用しなければならない障害者の割合を定めたものです。
現在、従業員数が43.5人以上の企業には障害者を一定割合以上雇用する義務があり、これを満たさない場合は「障害者雇用納付金」を支払うことになります。
2024年度時点での民間企業の法定雇用率は2.5%で、2026年度には2.7%まで引き上げられる予定です。例えば、従業員が100人いる会社なら2~3人の障害者を雇用する必要があります。
この制度の背景には、障害者が社会で活躍する場を広げること、そして企業の多様性推進があります。しかし、「制度は知っているけど、どう取り組んで良いかわからない」という企業が多いのが現状です。
企業が抱える主な課題
採用難と定着率の低さ
障害者雇用に取り組む企業の多くが抱える課題は「採用」と「定着」です。
求人を出しても応募が少なく、仮に採用できたとしても数ヶ月以内に退職してしまうケースが少なくありません。
特に初めて障害者を雇用する企業は、業務内容の切り出しや指示方法、合理的配慮の仕方がわからず、結果として障害者本人が力を発揮できない状況に陥りがちです。また、社内の受け入れ体制が整っていないことで、周囲の理解不足やコミュニケーション不足がストレスとなり、早期離職に繋がることもあります。
しかし、実際には「障害者雇用 成功事例」として取り上げられる企業の多くは、最初から完璧だったわけではありません。試行錯誤を重ねながらも、少しずつ社内体制を整え、業務マニュアルを改善し、結果として戦力化に成功しています。
次章では、そうした成功事例を業種別に詳しく解説していきますので、自社での取り組みイメージを膨らませながら読み進めてみてください。
障害者雇用の成功事例|業種別解説
製造業の事例
単純作業から品質管理へステップアップ
製造業では、障害者雇用を成功させている企業が多く見られます。
例えば、某部品メーカーでは当初、製品の検品や梱包といった単純作業を任せていました。しかし、業務に慣れるにつれて品質管理の補助業務も担当するようになり、今では検査工程の一部を任されるまでに成長しています。
この企業が取り組んだポイントは「業務の切り出しとステップアップ設計」です。最初から難しい作業を任せるのではなく、習熟度に応じて役割を広げていくことで、本人のモチベーション向上にも繋がりました。
IT業界の事例
在宅勤務や合理的配慮の工夫
IT業界では、特に精神障害や発達障害のある方を在宅勤務で雇用する成功事例が増えています。
あるシステム開発会社では、障害特性に配慮して勤務時間を短縮し、チャットツールでコミュニケーションを完結させる体制を整備しました。
さらに、業務内容もコーディングやテスト作業など、集中力を活かせる分野に特化。これにより、通勤負担や対面コミュニケーションによるストレスを軽減し、安定して勤務できる環境を実現しています。
飲食業界の事例
接客補助や仕込み業務で活躍
飲食業界でも、障害者雇用の成功事例は少なくありません。
例えば、ある大手チェーンでは、開店前の仕込み作業や調理補助、食器洗浄などのバックヤード業務を中心に障害者を雇用しています。
また、比較的コミュニケーションが得意な方には、配膳補助やおしぼり提供など接客補助業務を任せることで、店舗全体の業務効率アップに繋がっています。
流通・小売業の事例
品出し・バックヤード業務で戦力化
流通・小売業界では、スーパーやドラッグストアでの品出し業務で障害者雇用に成功している事例が多くあります。
例えば、あるスーパーマーケットでは、曜日ごとに担当する棚を固定し、マニュアルを写真付きで作成することで作業効率が飛躍的に向上しました。
この工夫により、障害者雇用の成功事例として社内表彰も受けており、今では欠かせない戦力となっています。
福祉・介護業界の事例
同じ立場を活かした支援業務
福祉・介護業界では、障害当事者が相談支援員や補助スタッフとして活躍する事例も増えています。
ある障害者就労支援事業所では、過去に利用者として通っていた方を支援員として採用。利用者の気持ちを理解できる強みを活かし、利用者とのコミュニケーションや作業指導で大きな成果を上げています。
このように、自身の経験や立場を活かした支援業務は、他のスタッフにはない価値を生み出すため、障害者雇用の成功事例として注目されています。
障害別の雇用成功ポイント
各障害種別の注意すべきポイントをみていきましょう。
身体障害の場合
合理的配慮と作業環境調整
身体障害のある方を雇用する際は、最も重要なのが作業環境の整備です。
例えば車いす利用者の場合、作業台の高さ調整や通路幅の確保など物理的バリアフリーが必要となります。また、視覚障害がある方には音声読み上げソフトの導入、聴覚障害がある方には筆談やチャットツールでのコミュニケーションが効果的です。
合理的配慮は特別扱いではなく、誰もが働きやすくなる工夫です。ある製造業の事例では、車いす利用の社員が使いやすいよう作業台を電動昇降式に変更したことで、他の社員の腰痛予防にも繋がり、生産効率も向上しました。
知的障害の場合
業務マニュアル化と指示系統の明確化
知的障害のある方にとって重要なのは、「わかりやすい指示」と「業務手順の可視化」です。
例えば、小売業のある店舗では、作業工程を写真入りのマニュアルにまとめ、チェックリストを活用することで作業ミスが激減しました。
また、指示を出す人が日替わりだと混乱しやすいため、必ず決まった担当者が指示・相談窓口になる体制を整えることも成功ポイントです。
精神障害の場合
定期面談とメンタルサポート体制
精神障害のある方の雇用では、症状の変動やストレスコントロールが課題になることがあります。
そのため、あるIT企業では週1回の定期面談を実施し、業務負荷や体調変化を早めにキャッチできる体制を構築しています。
また、社内に相談窓口を設置したり、ジョブコーチと連携した支援体制を整えたりすることで、精神的な安定と定着率向上に繋がる成功事例が多く見られます。
発達障害の場合
タスク分解と視覚的支援の活用
発達障害のある方への成功ポイントは「タスクの分解」と「視覚的支援」です。
例えば、あるバックオフィス業務では、資料作成という曖昧な依頼を「1.資料内容確認 → 2.テンプレート作成 → 3.入力 → 4.見直し」など細かく工程化し、ToDoリストや進捗ボードで可視化しました。
また、マルチタスクが苦手な場合は、同時進行ではなく一つずつ終わらせる仕組みにすることが大切です。この取り組みにより、業務の正確性とスピードが上がり、会社にとっても大きな戦力となったという事例があります。
上記のポイントをおさえておけば必ずうまくいくわけではありませんが、障害者雇用といっても障害種別や各個人によって悩みや不得意なことは様々です。障害種別の大枠のポイントを押さえつつ、個人に合わせて配慮をしていくことがとっても重要になってきます。
障害者雇用の失敗事例とそこから学ぶこと|業界別
成功例もありますが、失敗例も数多くあります。
製造業の失敗事例
安全配慮不足で配置転換
ある製造業では、ライン作業に身体障害のある方を配置しましたが、作業台の高さが合わず、腰や肩に負担がかかり体調を崩してしまいました。結果として軽作業部署へ配置転換されましたが、本人は「戦力外通告を受けた」と感じてしまい、退職してしまいました。
この事例から学べることは、「安全配慮は配置前に徹底的に確認する」ことです。本人にヒアリングし、可能なら職場見学や実習を通じて、負担がない作業環境を用意することが大切です。
IT業界の失敗事例
在宅勤務時のコミュニケーション不足
あるIT企業では、発達障害のある方を在宅勤務で採用しましたが、チャットのみでのコミュニケーションに限界がありました。タスク指示が曖昧になり、納期遅延が続いたことで業務委託契約を終了する結果に。
この失敗事例からは、「在宅勤務こそコミュニケーションのルール整備が必要」だとわかります。具体的には、指示内容をテキスト化して残す、定期的にオンラインMTGを設定するなど、対面以上の配慮が欠かせません。
飲食業界の失敗事例
業務内容と障害特性のミスマッチ
ある飲食チェーンでは、精神障害のある方を接客業務へ配置しましたが、忙しい時間帯で緊張が高まり、パニック状態になることが続きました。最終的には体調を崩し、短期間で退職しています。
このケースの学びは、「障害特性と業務内容の適性確認を最優先する」こと。接客よりも仕込みや清掃など落ち着いた環境で力を発揮できる場合もあるため、面接段階で適性を見極める工夫が必要です。
流通・小売業の失敗事例
指示系統が不明確で混乱
あるスーパーマーケットでは、知的障害のある方が複数の担当者から異なる指示を受け、混乱してミスが続出。指摘を受けるたびに自信を失い、結局退職してしまいました。
この事例からの学びは、「指示系統を一本化する」ことです。担当者を決め、相談窓口も同じ人にすることで、本人が安心して働ける環境を作れます。
福祉・介護業界の失敗事例
過度な期待とプレッシャー
ある福祉施設では、障害当事者スタッフを雇用しましたが、「当事者だからこそ利用者の気持ちがわかるはず」と過度な期待をかけすぎてしまいました。相談が殺到し、心理的負担が大きくなった結果、体調を崩して退職しています。
この事例の学びは、「期待をかけすぎないこと」です。本人ができる範囲を見極め、無理なく業務を遂行できる体制を整えることが大切です。
ミスマッチによる早期離職
ある中小企業では、障害者雇用の法定雇用率を満たすために急いで採用を進めた結果、入社からわずか3ヶ月で退職という事態になりました。
原因は、採用時に仕事内容や求めるスキルの説明が不足していたことです。実際に入社してみると、障害特性上苦手な業務が多く、本人が大きなストレスを感じてしまったのです。
この事例から学べることは、「雇用率達成をゴールにしない」こと。
業務内容の切り出しとマッチングを丁寧に行い、障害特性や本人の希望を踏まえた業務設計が重要だとわかります。
配慮不足によるトラブル
また、ある飲食業の店舗では、聴覚障害のある方を採用しましたが、筆談やチャットでの指示体制が整っておらず、コミュニケーションエラーが続出。
最終的に、指示漏れによる作業ミスが原因で職場内の人間関係が悪化し、本人も「ここでは働けない」と退職してしまいました。
この失敗事例から学ぶべきは、「合理的配慮は採用後すぐに整備する必要がある」ということです。本人に「この職場なら働ける」と思ってもらえる環境づくりが、定着率アップの鍵になります。
特性を理解することが重要
障害者雇用を成功させるために最も重要なのは、「障害特性を正しく理解すること」です。障害と一言で言っても、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など様々で、その特性や困りごとは一人ひとり異なります。
例えば、発達障害のある方はマルチタスクが苦手な場合があり、複数業務を同時進行させるとパニックになってしまうことがあります。また、精神障害のある方は、業務負荷や人間関係のストレスによって体調が変動しやすいこともあります。
こうした特性を理解せずに「みんなと同じようにできるはず」と思ってしまうと、本人にとっても企業にとっても大きな負担になります。逆に、特性を理解し、合理的配慮や業務の切り出し、指示方法を工夫することで、障害者雇用は確実に成功へと繋がります。
「特性を理解することは、特別扱いではなく、その人が持つ力を最大限に活かすための第一歩」なのです。
障害者雇用成功企業インタビュー
A社の場合(業務内容の細分化)
雇用から定着までの取り組み
A社は従業員300名規模の製造業企業です。
以前は障害者雇用に消極的でしたが、法定雇用率達成をきっかけに採用活動を開始。現在では4名の障害者スタッフが品質管理や検品業務で活躍しています。
採用当初は、業務内容を一律に割り当てていたため、覚えるのが難しい作業もありました。しかし、ジョブコーチのアドバイスを受けて「業務内容を細分化」「習熟度に合わせたステップアップ」を導入。
例えば、最初は検品業務の一部分だけを担当してもらい、慣れてきたら数量確認や梱包工程まで業務範囲を広げました。
担当社員は次のように話しています。「最初はどこまで任せていいか不安でしたが、細かく業務を区切ることでミスも減り、本人も達成感を持って働いてくれています。」
現在では定着率も向上し、障害者雇用成功事例として地域の産業支援センターから表彰されるまでになりました。
B社の場合(在宅・メンター制度)
経営層の意識改革が鍵
B社はITサービスを提供する企業です。以前は「精神障害のある方は在宅勤務でも管理が難しいのではないか」という先入観がありましたが、障害者雇用コンサルタントを招いて社内研修を実施。経営層の意識改革が進みました。
その後、発達障害と精神障害のある方2名を在宅勤務で採用。タスク管理ツールを活用し、1日のタスクを細分化して明確化する取り組みを実施しました。
また、メンター制度を導入し、業務上の相談だけでなく日常のちょっとした不安も気軽に話せる環境を整備。これにより、勤怠安定率は95%以上を維持しています。
人事責任者はこう話します。「経営層が『障害者雇用=CSR』ではなく『戦力化への投資』と考えるようになったことで、社内全体の雰囲気も変わりました。多様性がある職場の方が、アイデアも増えている実感があります。」
このように、障害者雇用の成功には経営層の理解と仕組み作りが欠かせないことがわかります。
C社の場合(完全在宅)
通勤をなくすという決断
C社は福祉系のサービスを提供する企業です。以前は「出社できる人のみを採用」していましたが、マーケティングの部署で完全在宅の仕事を任せることにしました。
最初は、コミュニケーションやスキルアップの観点からうまくいくかは不明でしたが、2年間で5名の採用に成功。入社後も精神的な理由の体調不良などはほぼなく安定して勤務してもらうことに成功しています。
また、障害特性に合わせた業務を準備することによって「一般社員よりも処理スピードが早い」業務なども出てきており、今では欠かせないメンバーになっています。
担当者曰く、「大切にしたのはいかに楽しんで仕事に取り組んでもらうかです。通勤にストレスを感じているメンバーが多かったので完全在宅に切り替え、業務内容も得意なことを伸ばすような業務を切り出しています」
このように障害者の方がストレスに感じやすい部分をいかに取り除けるかも成功するかどうかのポイントになってきます。
障害者雇用を成功させるポイント
採用時の工夫
ジョブコーチ活用と求人票の書き方
障害者雇用を成功させるためには、採用段階から工夫することが重要です。
まず、求人票には具体的な業務内容を明記しましょう。「軽作業」など曖昧な表現ではなく、「商品の袋詰め作業(1日○件程度)」など具体的に記載することで、応募者と企業双方のミスマッチを防げます。
また、採用活動にはジョブコーチの活用も効果的です。ジョブコーチとは、障害のある方が職場に定着できるよう支援する専門家で、業務指導や職場環境調整、上司・同僚への配慮方法のアドバイスまで行ってくれます。
ハローワークや地域障害者職業センターで相談できるので、ぜひ活用してみましょう。
配属・教育の工夫
OJTと外部研修の活用
配属後の教育では、通常のOJTだけでなく、外部研修を組み合わせることが効果的です。
例えば、障害特性理解や合理的配慮に関する外部研修を定期的に実施すると、現場の受け入れ体制が格段に強化されます。
また、OJTでは作業内容を細分化し、進捗ごとにフィードバックを行うことが重要です。「できている部分」を必ず褒めることで本人の自信に繋がり、モチベーションアップにもなります。
職場環境づくり
バリアフリーだけでなく人間関係も重要
職場環境づくりというとバリアフリー設備ばかりが注目されがちですが、実際には人間関係のバリアフリーが最も重要です。
障害者雇用に成功している企業は、設備面の配慮だけでなく「声かけしやすい雰囲気」や「誰に相談すればいいかが明確」など、心理的安全性を高める取り組みを行っています。
例えば、あるIT企業では、障害者スタッフとメンター社員が週1回面談する機会を設けています。この取り組みにより、小さな不安や業務上の困りごとを早期に解消でき、定着率が大きく向上しました。
このように、物理的環境だけでなく、人間関係面の配慮こそが障害者雇用成功の鍵になります。
助成金・支援制度の活用方法
障害者雇用には様々な助成金や支援制度がありますので理解しておくと、負担軽減にもつながります。
障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度とは、従業員43.5人以上の企業が法定雇用率未達成の場合、納付金を納める必要がある制度です。1人につき月額5万円の支払いになるため年間60万円の納付金になります。
逆に、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業には、調整金や報奨金が支給される仕組みになっています。
例えば、法定雇用率を超過して雇用している場合、1人あたり月額27,000円(2024年度時点)の調整金が受け取れます。(年間324,000円)
この制度をうまく活用することで、障害者雇用を進めながら経営面での負担軽減にも繋がります。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)は、障害者を試行雇用する企業に対して支給される助成金です。
最長3ヶ月間の試行雇用期間を設け、その間に雇用継続の可否を判断できる仕組みで、受給額は対象者1人につき月額最大4万円程度(上限あり)。
採用前に実際の業務適性を確認でき、かつ企業側もリスクを抑えながら雇用できるため、初めて障害者雇用に取り組む企業にもおすすめの制度です。
その他地域の助成金
地域によっては、独自の障害者雇用助成金や支援制度を設けている自治体もあります。
例えば、東京都では「障害者雇用奨励金」として、一定期間以上雇用を継続した場合に一人当たり最大50万円が支給される制度があります。
こうした地域独自の制度は自治体のホームページや、最寄りのハローワーク、地域障害者職業センターで確認できます。助成金を上手に活用することで、障害者雇用の経済的負担を大幅に軽減できるため、必ず最新情報をチェックしておきましょう。
また、ご自身の会社が何に該当するかわからない場合は、障害者雇用のコンサルなどプロに相談してみるのも良いでしょう。
障害者雇用を進めるための社内体制構築
障害者雇用をするにあたって「採用するだけ」ではうまくいかない可能性があります。
経営層の理解とビジョン共有
障害者雇用を成功させるためには、経営層の理解とビジョン共有が不可欠です。
「法定雇用率を満たすためだけの採用」ではなく、経営戦略の一環として障害者雇用を位置付けることで、現場の受け入れ意識も大きく変わります。
例えば、あるIT企業では、社長自らが障害者雇用の重要性について社内説明会で語り、理念に組み込んだ結果、社員全体の理解が深まりました。経営層がビジョンを示すことで、「誰かがやる仕事」ではなく「全員で取り組む会社の課題」という意識づけができるのです。
担当部署と連携体制
障害者雇用を推進するには、人事部だけでなく各部署との連携体制も重要です。
採用や配属決定は人事部主導でも、実際の受け入れは配属先の現場が担うため、日頃から情報共有や相談体制を構築しておく必要があります。
例えば、週1回の定例ミーティングを設け、業務上の課題や本人の様子を関係部署で共有する取り組みをしている企業もあります。また、障害者雇用担当者を1名専任配置し、現場からの相談窓口を一本化することで、問題解決がスムーズになったという事例もあります。
このように、経営層のビジョンと現場の連携体制が整うことで、障害者雇用は単なるCSRではなく、組織全体の強化に繋がる取り組みとなります。
障害者雇用コンサルの活用
障害者雇用コンサルに依頼するメリット
障害者雇用コンサルタントに依頼する最大のメリットは、専門的な知識と経験を活かした支援が受けられることです。
初めて障害者雇用に取り組む企業では、業務の切り出し方、合理的配慮の内容、助成金申請方法など、何から手を付ければよいかわからないことが多くあります。
コンサルタントは、これまでの支援実績から、
・どの業務が切り出しやすいか
・障害特性に合わせた指示方法
・職場内研修の進め方
など具体的に提案してくれます。
また、ジョブコーチや支援機関とのネットワークがあるコンサルタントも多く、採用から定着までワンストップで支援を受けられる点も大きな魅力です。
障害者雇用コンサルに依頼するデメリット
一方で、コンサルタントに依頼するデメリットもあります。
第一に費用負担です。障害者雇用コンサルティングは数万円~数十万円単位の費用がかかる場合があり、予算に限りがある中小企業にとっては負担になることがあります。
また、コンサルタントに頼りきりになることで、社内で障害者雇用に関するノウハウが蓄積されにくいという側面もあります。外部依存ではなく、最終的には自社内で体制を構築できるよう、コンサルタントを活用しつつ学びを深める姿勢が重要です。
障害者雇用コンサルを選ぶときのポイント
障害者雇用コンサルタントを選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 障害者雇用支援の実績が豊富か
- 対象業界・職種に応じた具体的提案が可能か
- ジョブコーチや支援機関とのネットワークがあるか
- 費用体系が明確で、成果目標や支援範囲が契約書で定められているか
特に重要なのは、単に法定雇用率を満たすためだけではなく、雇用後の定着や戦力化まで支援してくれるかという点です。
面談時に過去事例や支援内容を詳しく質問し、自社に合うかどうかを見極めましょう。
よくある質問(FAQ)
障害者雇用はコストがかかる?
確かに採用時に設備改修や合理的配慮でコストがかかる場合もありますが、助成金や調整金を活用することで負担を軽減できます。また、業務効率化や離職率低下など、長期的には企業にとってプラスになるケースが多いです。
採用後にトラブルがあった場合は?
まずは本人と面談し、原因を一緒に整理することが大切です。それでも解決が難しい場合は、ハローワークやジョブコーチ、地域障害者職業センターに相談してみましょう。
精神障害の方の勤務時間は?
体調変動に合わせ、最初は短時間勤務から始める企業が多いです。徐々に勤務時間を延ばすことで、無理なく安定して働けるようになります。
どの業種でも雇用できる?
基本的にはどの業種でも雇用可能です。ただし、業務内容によっては合理的配慮が必要な場合もあるため、採用前に特性と業務の適性を確認しましょう。
助成金の申請方法は?
ハローワークや地域障害者職業センターで申請可能です。申請書類の書き方や必要書類も丁寧に教えてもらえるため、まずは相談してみるとよいでしょう。
障害者雇用は何人から必要?
従業員43.5人以上の企業に法定雇用率が適用されます。2024年度は2.5%、2026年度には2.7%に引き上げ予定です。
定着率を上げるにはどうすればいい?
特性理解・合理的配慮・定期面談・相談体制の4つがポイントです。特に「誰に相談すればいいか」を明確化することが定着率向上に繋がります。
合理的配慮ってどこまで必要?
本人が業務を遂行するために必要最低限の配慮を行う義務がありますが、過重な負担となる場合は調整可能です。本人やジョブコーチと相談し、実現可能な範囲で決定します。
ジョブコーチはどこに依頼する?
ハローワークや地域障害者職業センターで派遣申請が可能です。民間のジョブコーチ事業所に依頼する方法もあります。
採用面接では何を聞いてはいけない?
障害名や診断内容を強制的に聞くことはできません。ただし、業務上必要な配慮を確認するための質問は可能です。
障害者雇用に向いている業務は?
製造業なら検品・梱包、IT業界ならデータ入力やテスト業務、小売業なら品出しなど、業務を細分化しやすい作業が向いています。
知的障害の方に指示を出すコツは?
短く具体的に、1つずつ伝えることが大切です。写真入りマニュアルやチェックリストを活用すると理解度が高まります。
精神障害の方に多い離職理由は?
人間関係によるストレスや、業務量の変動による体調悪化が多い傾向にあります。定期面談と業務負荷管理で予防できます。
障害者雇用コンサルタントって何をしてくれる?
業務切り出しや配慮方法の提案、助成金活用アドバイス、定着支援など幅広く対応してくれます。
複数名雇用するときの注意点は?
障害特性は一人ひとり異なるため、同じ配慮で全員に対応できるとは限りません。それぞれに合わせた業務設計と支援が必要です。
まとめ|障害者雇用は特性の理解から
障害者雇用を成功させるためには、まず「障害特性の理解」から始めることが大切です。
制度上の義務感だけでなく、一人ひとりの特性に合わせた業務設計や配慮を行うことで、障害のある方も会社も互いにプラスになる関係を築くことができます。
また、社内体制づくりも重要です。経営層がビジョンを示し、現場と連携して受け入れ体制を整えることで、採用から定着までの成功率は格段に上がります。
専門家への相談も検討を
「何から始めたらいいかわからない」という場合は、ハローワークや地域障害者職業センター、ジョブコーチ、障害者雇用コンサルタントなど専門家に相談することを検討してみてください。
専門家の支援を受けながら進めることで、失敗リスクを減らし、結果として時間もコストも最小限に抑えることが可能です。
障害者雇用は、企業にとって新たな戦力確保の機会であり、多様性を活かした組織づくりへの第一歩です。
ぜひ、今回の記事を参考に、できることから取り組んでみてください。